こんにちは。ジェネレーションB、運営者の「TAKU」です。
「Sonics バンド」と検索すると、なんだかすごいバンドだってことは分かるんですけど、情報が古かったり、Nirvanaとの関係がよく分からなかったりしますよね。
私ものめり込むまで、The Sonicsの正しい読み方や、一体いつ活動してたバンドなのか、よく知らなかったんです。
彼らの代表曲や必聴のアルバム、そして現在のメンバーがどうなっているのか、気になっている人も多いんじゃないかなと思います。
この記事では、ガレージロックの伝説と呼ばれるThe Sonicsの基本情報から、なぜ彼らが後世のアーティストに多大な影響を与えたのか、その魅力の核心に迫っていきますね。
この記事でわかること
- The Sonicsの基本的なプロフィールと音楽性
- ガレージロックの「祖」と呼ばれる理由
- Nirvanaやジャック・ホワイトなど後世への影響
- 現在の活動状況とメンバー構成
1. Sonicsというバンドとは?基本情報を解説
まずは「The Sonics」がどんなバンドなのか、基本的なところから押さえていきましょう。
彼らを知ることが、後のパンク・ロックやグランジといった音楽のルーツを知ることにも直結しますからね。
1-1. The Sonicsの読み方と活動時期

まず、バンド名の読み方ですが、これは「The Sonics(ザ・ソニックス)」 が正しい読み方です。
「Sonics」という名前から、80年代以降に活躍した「Sonic Youth(ソニック・ユース)」 と混同してしまう人もいるかもしれませんが、名前は似ていても活動時期も音楽性もまったく異なるバンドですね。
The Sonicsが結成されたのは、なんと1960年 (または1961年 )。
アメリカ合衆国のワシントン州タコマ出身のバンドです 。
この「ワシントン州タコマ」という出身地が、音楽史的にすごく重要で。後のグランジ・ムーブメントの中心地となるシアトルの近郊 なんですね。
この地理的な背景もあって、彼らは後に「グランジの祖父(Grandfathers of Grunge)」 と呼ばれることになります。
バンド名の由来も、彼らのサウンドを象徴していて面白いですよ。
近隣の米空軍基地から鳴り響く「耳をつんざくようなソニックブーム (sonic booms)」 から名付けられたそうです。
「音速」 という名前自体が、彼らが目指したラウドな音楽性を予言していたかのようですよね。
活動期間は、大きく分けて以下の三期として捉えられています 。
The Sonicsの主な活動時期
- 第一期(1960年~1968年): 「プロトパンク」と呼ばれる伝説的なアルバム群を残した全盛期。
- 散発的な再結成期(1972年, 1980年): シアトルでの一度きりの再結成ライブ や、ボーカルのジェリー・ロスリー主導での変則的な再結成 など、一時的な活動。
- 第二期(2007年~現在): 本格的な再結成を果たし、フェスへの出演や新作アルバムのリリース 、現在に至るまでのツアー活動を行う時期。
60年代にこれほど過激な音楽をやっていたバンドが、半世紀以上の時を経て今も現役で活動している という事実だけでも、彼らのすごさが伝わってくるかなと思います。
1-2. ガレージロックの祖、その音楽的特徴

The Sonicsがなぜ「伝説」と呼ばれるのか。
それは、彼らの音楽が「ガレージロック」 や「プロトパンク(パンク以前のパンク)」 と呼ばれるジャンルの、まさに「祖」 と見なされているからです。
彼らのサウンドを一言でいうと、「攻撃的」「生々しい」「ラウド」。
1960年代当時、彼ら以上にワイルドで、激しいサウンドを鳴らしていたバンドは他にいなかったと断言されています 。
そして、この衝撃的なサウンドは、偶然の産物ではなく、彼らが意図的に作り出したものでした。
意図的に作られた「歪み」と「反響」
彼らのサウンドメイクに関する逸話は、彼らの革新性をよく表しています。
- スタジオの改造: 2ndアルバム『Boom』のレコーディング時、より「ライブ感」のある反響を得るために、スタジオの防音材を剥がしたとされています 。
- 常識外れの録音: ドラムの録音を、わずかオーバーヘッドマイク1本だけで行ったという逸話もあります。
- 歪みの追求: エンジニアのKearney Bartonは、バンドが機材の限界を超えるようなディストーション(歪み)を求めても、文句を言うどころか、その要求に従って協力したと記録されています 。
- 特異な音響効果: あの特徴的なサックスの反響音を得るために、なんとサックス奏者のロブ・リンドを(録音スタジオの)バスルームに配置して演奏させたそうです。
このサウンドの中核を担ったのが、リードシンガーのジェリー・ロスリー (Gerry Roslie) です。
彼のボーカルは「熱狂的な遠吠え (fevered howls)」 や「痛ましいソウル・スクリーム (harrowing soul-screams)」 と評され、「白人のリトル・リチャード」 という異名を持っていました。
さらに、ロブ・リンド (Rob Lind) による荒々しいサックスも特徴的で、しばしばファズ(エフェクター)をかけたギターの音と間違われるほど強烈に歪んでいました 。
ただ、彼らが単なるノイジーなバンドと一線を画すのは、「凶暴性」と「ポップ」の二面性を意図的に使い分けていた点です。
例えば、1945年のブルースバラード「Since I Fell for You」のカバーでは、驚くほど「大人しく丁寧にやっている」 のに対し、リトル・リチャード や「Louie, Louie」 のカバーでは「結構凶悪なサウンド」 を追求しています。
つまり、彼らはR&Bスタンダードを演奏できる技術を持ちながら、あえてそれを破壊し、歪ませるという「制御されたカオス」を選択していたわけです。
これこそが、彼らを「プロトパンク」の始祖たらしめている核心的な理由だと私は思いますね。
1-3. 代表曲の歌詞に込められた意味
The Sonicsの革新性は、サウンドだけじゃありません。歌詞のテーマも、1965年当時としては極めて異端でした。
彼らの代表曲といえば、「The Witch」(魔女)、「Psycho」(サイコ)、そして「Strychnine」(ストリキニーネ、猛毒) といったあたり。
もうタイトルからして、普通のポップソングじゃないことが分かりますよね。
1960年代のポップソングが「素敵な恋愛」や「かっこいい車」について歌っていた時代に、彼らが選んだテーマは「魔女」「サイコ」「毒」です。
反社会的とみなされた歌詞
例えば「Strychnine」は、その歌詞が「人々に毒を飲むことを奨励している」 とも解釈できる内容でした。
ラリー・パリーパ(ギター)自身も、後年「まるで悪魔的なもの(satanic kind of thing)のようだった」 と回想しているほどです。
また、「The Witch」は、その歌詞(「彼女は魔女だ」)が不適切とみなされ、「主婦の時間帯 (housewives’ time slot)」のラジオでは放送を拒否された という逸話も残っています。
こうした暗く、反社会的で、非道徳的とも取れるテーマを、ジェリー・ロスリーの「動物的な叫び」 でシャウトするスタイルは、10年以上後のパンク・ロック の歌詞の世界を明確に先取りしていたと言えるんじゃないでしょうか。
1-4. 初心者におすすめの入門アルバム
じゃあ、どこからThe Sonicsを聴き始めればいいの? と思いますよね。
私も最初は迷いましたが、彼らの本質に触れるなら、まずはこの3枚から入るのが間違いないかなと思います。
1. 『Here Are the Sonics!!!』 (1965年)
まず絶対に外せないのが、この1stアルバム。ロック史における金字塔的な作品です 。
「ガレージパンクの産みの親」 とも呼ばれる、彼らの溢れんばかりの初期衝動が詰まった一枚 です。
この強烈なサウンドが、後世のミュージシャンたちに「カルト的な人気 」 を博すことになりました。
2. 『Boom』 (1966年)
2ndアルバムですね 。1stと同じクラシック・ラインナップによる作品で 、あの攻撃的な勢いとサウンドを継承した重要作です。
まずは1stと2ndをセットで聴くことで、60年代のThe Sonicsがどれだけ飛び抜けていたかが分かると思います。
3. 『This Is The Sonics』 (2015年)
そして、驚きなのがこの2015年のアルバム。2007年の再結成後、実に48年ぶり (または49年ぶり )にリリースされた、スタジオ録音による「新曲」アルバムです 。
これが単なる同窓会的なアルバムじゃなくて、めちゃくちゃカッコいいんですよ。
「レイドバックなんかどこ吹く風」「年齢不詳のギラギラしたサウンド」 と評される通り、サウンドは全く衰えていません。
それもそのはず、このアルバムのエンジニアを務めたのは、NirvanaやMudhoneyを手掛けたシアトル・サウンドの重鎮、ジャック・エンディノ (Jack Endino) なんです。
この人選も、彼らの歴史的な繋がりを感じさせますよね。
聴く順番としては、まず『Here Are…』で衝撃を受け、次に『Boom』でその世界を深め、最後に『This Is The Sonics』を聴いて、彼らのサウンドが半世紀を経ても全く色褪せない「現在進行形」 のロックンロールであることを確認するのがおすすめです。
1-5. クラシック・ラインナップのメンバー紹介

あの強烈なサウンドを生み出していた、全盛期(1963年~1966年頃) の「クラシック・ラインナップ」と呼ばれるメンバーは、以下の5人です 。
| メンバー | 担当 | 補足 |
|---|---|---|
| ジェリー・ロスリー (Gerry Roslie) |
リードボーカル、オルガン、ピアノ | ー |
| ラリー・パリーパ (Larry Parypa) |
リードギター、ボーカル | バンドの創設者 |
| アンディ・パリーパ (Andy Parypa) |
ベースギター、ボーカル | ラリーの兄 |
| ロブ・リンド (Rob Lind) |
サックス、ボーカル、ハーモニカ | ー |
| ボブ・ベネット (Bob Bennett) |
ドラムス | ー |
このラインナップは、ジェリー・ロスリー、ロブ・リンド、ボブ・ベネットの3人が、元々「The Searchers」(※英国の同名バンドとは別)というバンドにおり、パリーパ兄弟のThe Sonicsに合流する形で1963年に固まりました 。
やはり、バンドの「顔」であるジェリー・ロスリーの絶叫ボーカル と、ロブ・リンドの歪んだサックス が、The Sonicsのサウンドを決定づけていたと言えますね。
2. 伝説のSonics バンドと後世への影響
60年代に活躍したThe Sonicsが、なぜ今も「伝説」として語り継がれるのか。
その理由は、彼らが活動当時に商業的な成功を収めなかった にもかかわらず、後世の音楽シーンに絶大な影響を与え続けた からです。
ここでは、Nirvanaをはじめとする後世のバンドとの関係性について、深く掘り下げてみましょう。
2-1. 2007年の再結成と現在のメンバー
数十年にわたるカルト的な人気 と、NirvanaやMudhoneyといったグランジバンドからのリスペクト を受け、The Sonicsは2007年にニューヨークのガレージロック・フェスティバル「Cavestomp」で本格的に再結成を果たします 。
この時の再結成メンバーは、オリジナルメンバーのうち3人、ジェリー・ロスリー(ボーカル/キーボード)、ラリー・パリーパ(ギター)、ロブ・リンド(サックス)でした 。
ちなみに、アンディ・パリーパ(ベース)とボブ・ベネット(ドラムス)は、遠征を望まなかったため参加しなかったそうです 。サポートメンバーとして、ドラムはRicky Lynn Johnson、ベースはDon Wilhelmが務めました 。
その後、メンバーチェンジを経て、ベースがFreddie Dennis 、ドラムがDusty Watson に交代。この5人編成が、2015年の復活アルバム『This Is The Sonics』 をレコーディングしたラインナップです。
ただ、現在の活動をチェックする上で、2016年が大きな転換点になります。
2016年の発表:オリジナルメンバーのツアー離脱
2016年5月、バンドの「声」であったボーカルのジェリー・ロスリーと、創設者のラリー・パリーパが、ツアーメンバーとしては今後継続しないことが発表されました 。ただし、両名ともレコーディングには引き続き参加する とされています。
この発表のため、2018年以降、そして2024年現在 のツアーは、以下のメンバーで行われています 。(詳細はバンドの公式サイト The Sonics Official Website も参照してください)
- ロブ・リンド (Rob Lind): サックス、ボーカル、ハーモニカ(唯一のクラシック・ラインナップメンバー)
- フレディ・デニス (Freddie Dennis): ベース、ボーカル
- ダスティー・ワトソン (Dusty Watson): ドラムス
- ジェイク・キャヴァリエ (Jake Cavaliere): キーボード、ボーカル (Gerry Roslieの代役)
- エヴァン・フォスター (Evan Foster): ギター (Larry Parypaの代役)
ジェリー・ロスリーの代役を務めるジェイク・キャヴァリエは、Lords of Altamontといったガレージバンドでのキャリアがあり 、若い頃にピアノの先生に「The Sonicsのレコードみたいに弾きたい!」と言っていたほど、彼らに憧れていたミュージシャンだそうです 。
2024年時点で「The Sonics」としてツアーを行っているバンドは、クラシック・ラインナップのメンバーがロブ・リンド1人です。
バンドのサウンドを定義づけたジェリー・ロスリーとラリー・パリーパはステージにいません。
したがって、現在のバンドは、オリジナルメンバー(リンド)の監修のもと、次世代のガレージロック専門家(キャヴァリエら)がそのサウンドを忠実に継承し、演奏する「生きたレガシー・アクト(音楽的継承機関)」と呼ぶべき形態に変容している、と私は捉えています。
2-2. Nirvanaとの複雑な関係を分析

「The Sonics バンド」と検索する人の多くが、Nirvana(ニルヴァーナ)との関係に興味があるんじゃないかと思います。私もそうでした。
音楽史的には、「The SonicsがいなければNirvanaもいなかった」 と断言されるほど、The SonicsはNirvanaに「多大な影響を与えた (major influence)」 とされています。
これは間違いない事実だと思います。
…なんですが、ここでちょっと複雑な話が出てくるんです。
当のカート・コバーン本人の発言や記録を見ると、「あれ?」と思うような「矛盾」が出てきます。
1. カート・コバーンの「お気に入りアルバム50」にThe Sonicsは無い
カート・コバーンが彼の日記(『Journals』)に残した、「お気に入りのアルバム トップ50」の手書きリスト があります。ファンにとっては有名なリストですよね。
驚くことに、このリストに、The Sonicsのアルバムは含まれていないんです 。
リストには、Sonic Youth や Mudhoney 、そして同じくPNW(太平洋岸北西部)の先輩である The Wipers(ワイパーズ)に至っては3枚もリスト入り しているにもかかわらず、です。
2. カート・コバーンは「ソニックスなんて大嫌いだ」と発言
さらに衝撃的なのが、ジャーナリストのNardwuar(ナードウォー)とのインタビュー での発言です。
NardwuarがPNWの先輩(The Sonics, The Wailers)について尋ねたところ、カート・コバーンはこう言い放っています。
「I hate the Sonics. They’re stupid.(ソニックスなんて大嫌いだ。馬鹿げてる)」
ちなみに、この直後、隣にいた妻のコートニー・ラブが「No they’re not.(そんなことないわ)」 と即座に否定しているのが、また面白いところです。
この「矛盾」はどう解釈すればいい?
「Nirvanaに影響を与えた」 という事実と、「カート本人は『嫌い』と言い、リストにも入れていない」 という事実は、一見すると真っ向から矛盾します。この矛盾をどう解釈すればいいんでしょうか。
専門家の分析や当時の状況を考えると、この「大嫌いだ」という発言は、彼の本心からの嫌悪というより、彼特有の皮肉(サーカズム)であった可能性が非常に高いようです。
当時、カート・コバーンは、Nirvanaと過去のシアトルの先輩バンドとを安易に結びつけるメディアの論調にウンザリしていました。だから、あえて天邪鬼な態度をとって、単純な比較への「抵抗」として「嫌いだ」と言ってみせた、というわけですね 。コートニーが即座に否定している ことからも、それが彼の本心ではないことが伺えます。
また、「Top 50 Albums」リストは、あくまで彼個人のお気に入りであり、彼が受けたすべての影響 のリストではありません 。彼はThe Sonicsよりも、同じPNWの先輩でありながら、よりダークで内省的な The Wipers を(リストに3枚も入れている ことから)個人的には偏愛していた可能性が高いです。
結論としては、「バンドとしてのNirvana」および「グランジ・シーン全体」は、The Sonicsの「音の設計図 」 なしには成立し得なかった(=影響は事実)。
一方で、「個人としてのカート・コバーン」は、メディアが作り上げた単純な「シアトル・サウンドの系譜」という物語 に、彼特有の皮肉な反発をしていた、と理解するのが最も自然かなと思います。
2-3. ジャック・ホワイトが語る魅力

The White Stripesのジャック・ホワイトも、The Sonicsの熱心な信奉者として知られています 。
彼はThe Sonicsのサウンドを「本物」だと見抜き、惜しみない賛辞を送っています。
ジャック・ホワイトによるThe Sonicsへの賛辞
「1960年代のパンクの縮図 (the epitome of 1960s punk) だ」
「キンクスよりもハードで、パンクが登場するずっと前にパンクだった (harder than The Kinks, and punk long before punk)」
「60年代半ばの退屈したティーンエイジャーの根源的な思考を意味する、動物的な叫び (animalistic screams signifying the base thoughts of mid-’60s bored teens)」
「Sonicsのレコードを買うと、人生がより良くなる (Life becomes better after buying a Sonics record)」
ジャック・ホワイトの音楽的特徴である、ブルースの原始的な解体と生々しい攻撃性は、まさにThe Sonicsが提示した「設計図」 と酷似していますよね。
彼にとってThe Sonicsが、ロックンロールの根源的な衝動の純粋な結晶であることがよくわかります。
2-4. ブルース・スプリングスティーンのカバー

The Sonicsの影響の広範性を示す、ちょっと意外なエピソードがあります。あの「ボス」こと、ブルース・スプリングスティーン も彼らの曲をカバーしているんです。
スプリングスティーンは、1988年の「Tunnel Of Love Express Tour」のライブで、「Have Love, Will Travel」を定期的に演奏していました 。
ここで重要なのは、彼がカバーしたのはリチャード・ベリーによる1959年のオリジナル版 ではなく、The Sonicsによる攻撃的なアレンジ・バージョン だったという点です。
The Sonicsのバージョンは、キーを変更し、リフをボーカルからインスト(歪んだサックス )に変えるなど、原曲を完全に解体・再構築したものでした 。
そして、このThe Sonicsのバージョンこそが「事実上、他のすべてのパフォーマーがコピーした」決定版 となっていたのです。
アメリカン・ロックの頂点に立つスプリングスティーンが、1988年という時点で、カルト的なガレージバンドのバージョン を選んでカバーしたという事実からも、The Sonicsの影響がパンクやグランジといった特定のサブカルチャーに留まらず、アメリカン・ロックの主流にまで認められていたことがわかりますね。
2-5. Sonics バンドの魅力を再確認

ここまで見てきたように、The Sonicsは、単なる「60年代のバンド」ではありません。
私が思う彼らの最も興味深い点は、彼らが活動当時に商業的成功は収められなかった というパラドックスにあります。
彼らはあくまでワシントン州のローカルスター であり、メジャーレーベルと契約することなく解散し、メンバーは「普通の男としてのキャリアを築くため」 に音楽界を去りました。
しかし、逆説的ですが、「売れなかった」からこそ、彼らのサウンドはメジャーレーベルの意向によって「希釈 」されることがなかった んです。
その「希釈されていない」純粋な暴力性と原始的な衝動 がレコードに刻まれた からこそ、何十年も経った後、Nirvana やジャック・ホワイト といった後世のアーティストたちが彼らを「再発見」し、自分たちの音楽の「設計図」 として崇拝することになりました。
時代を先取りしすぎた、ラウドで、生々しいロックンロール。
それこそが、今も私たちがThe Sonicsの音楽に惹かれる理由なんだと思います。

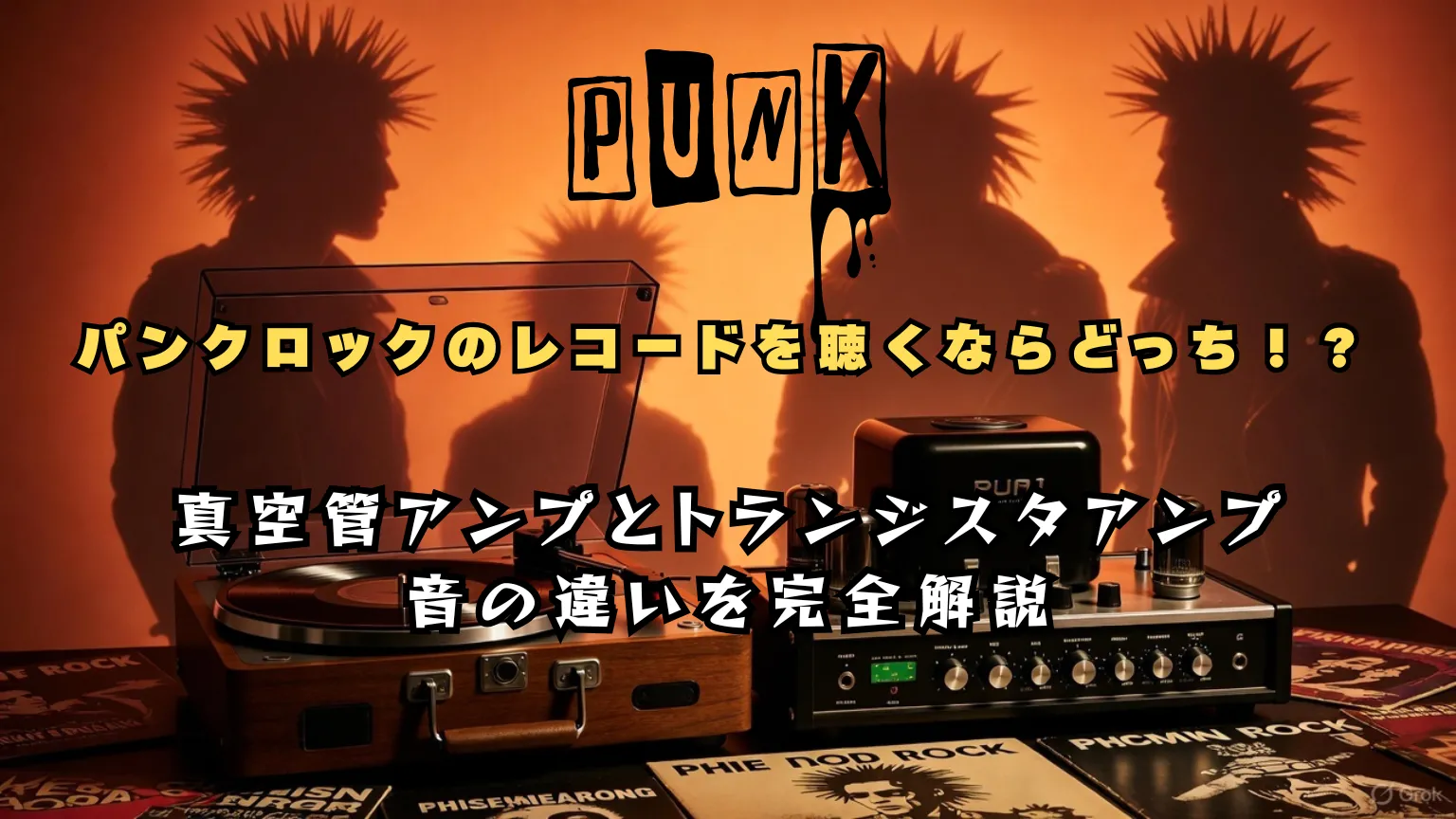

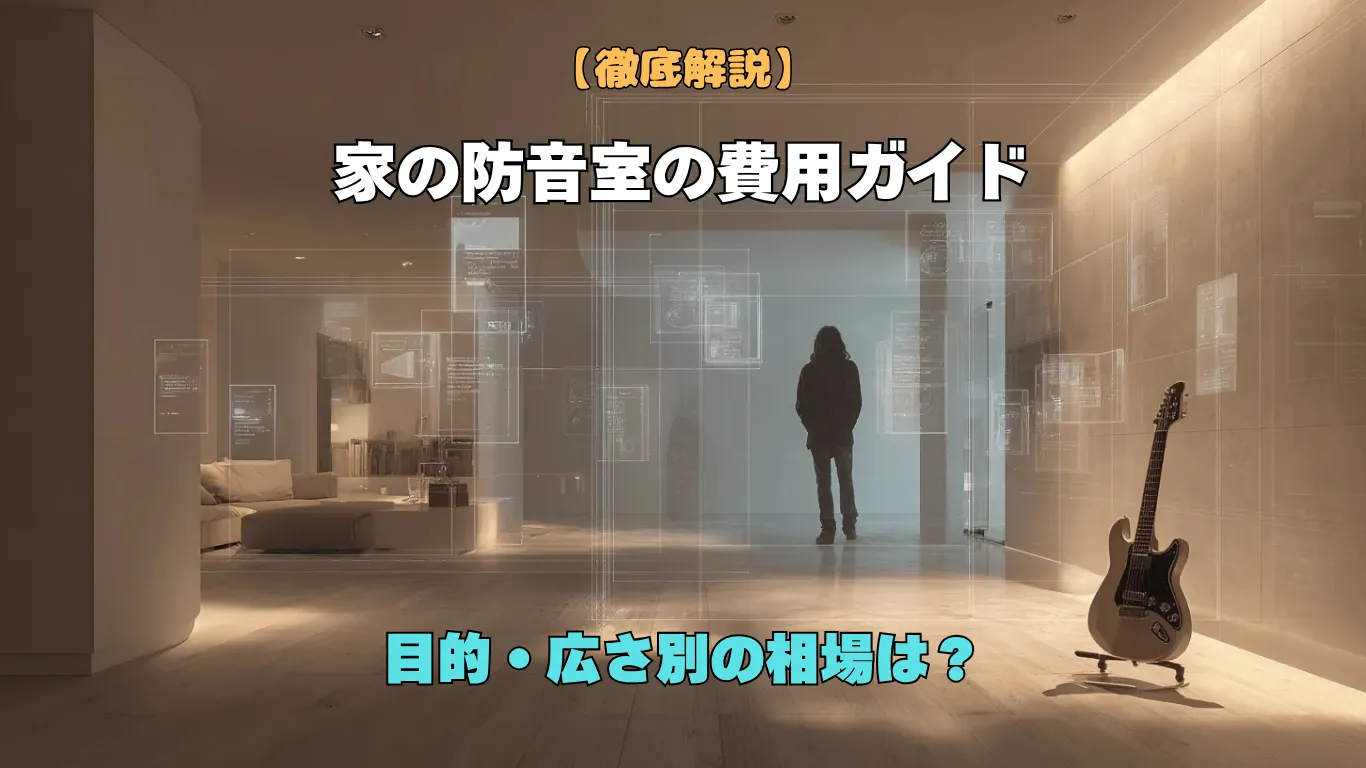
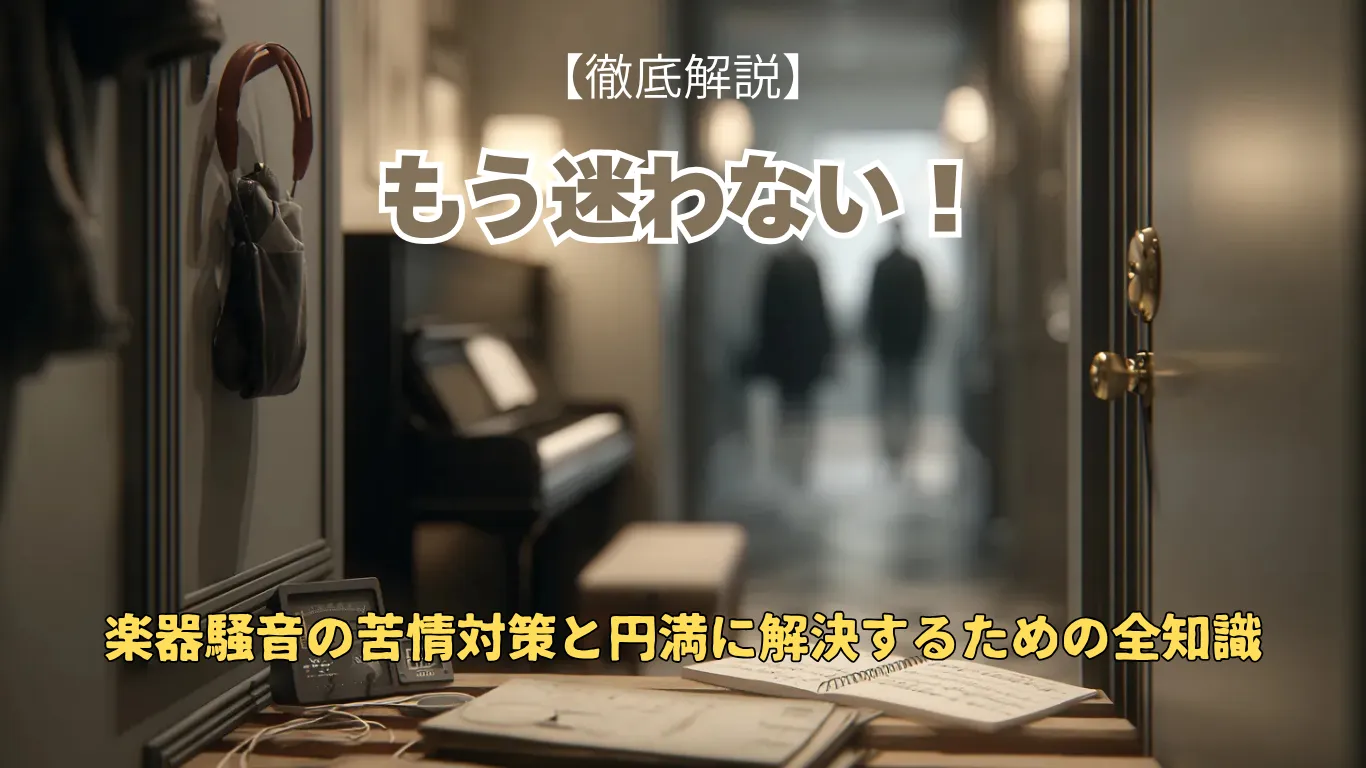
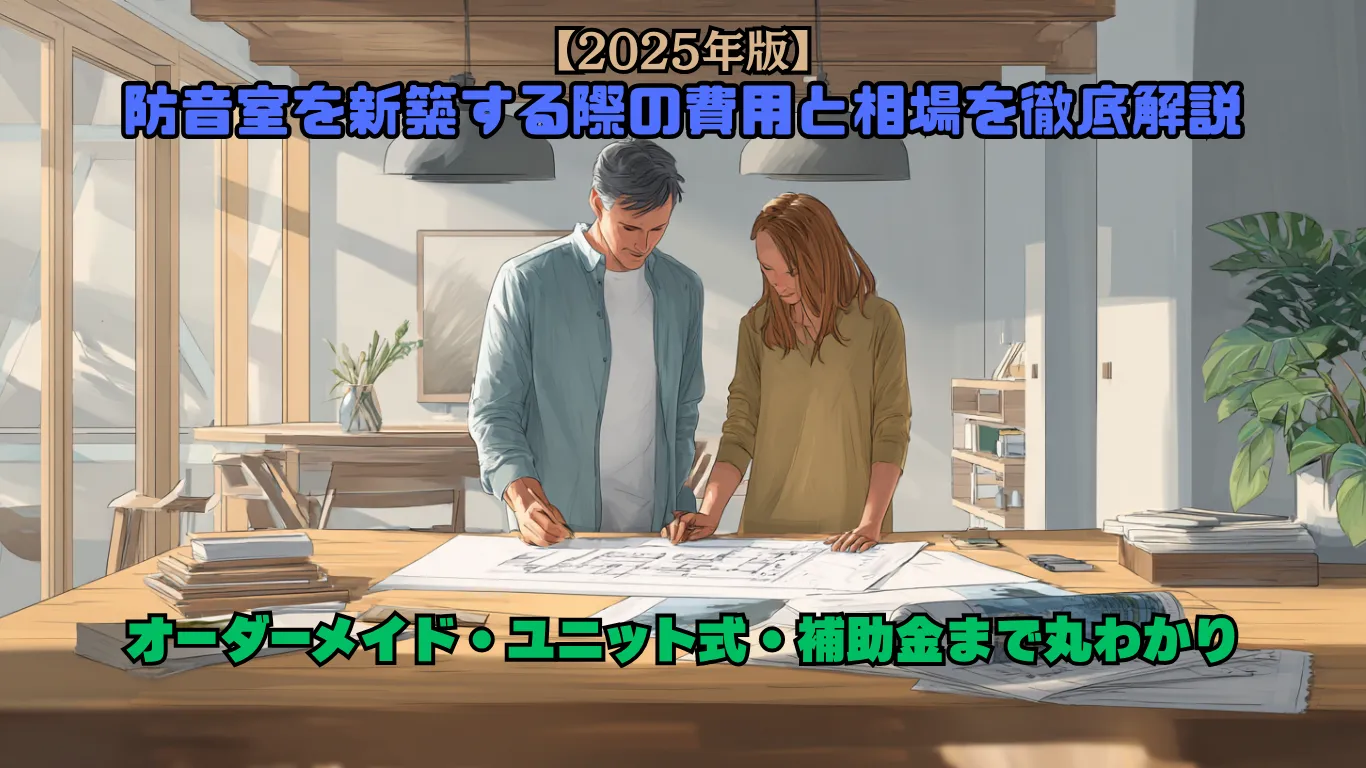




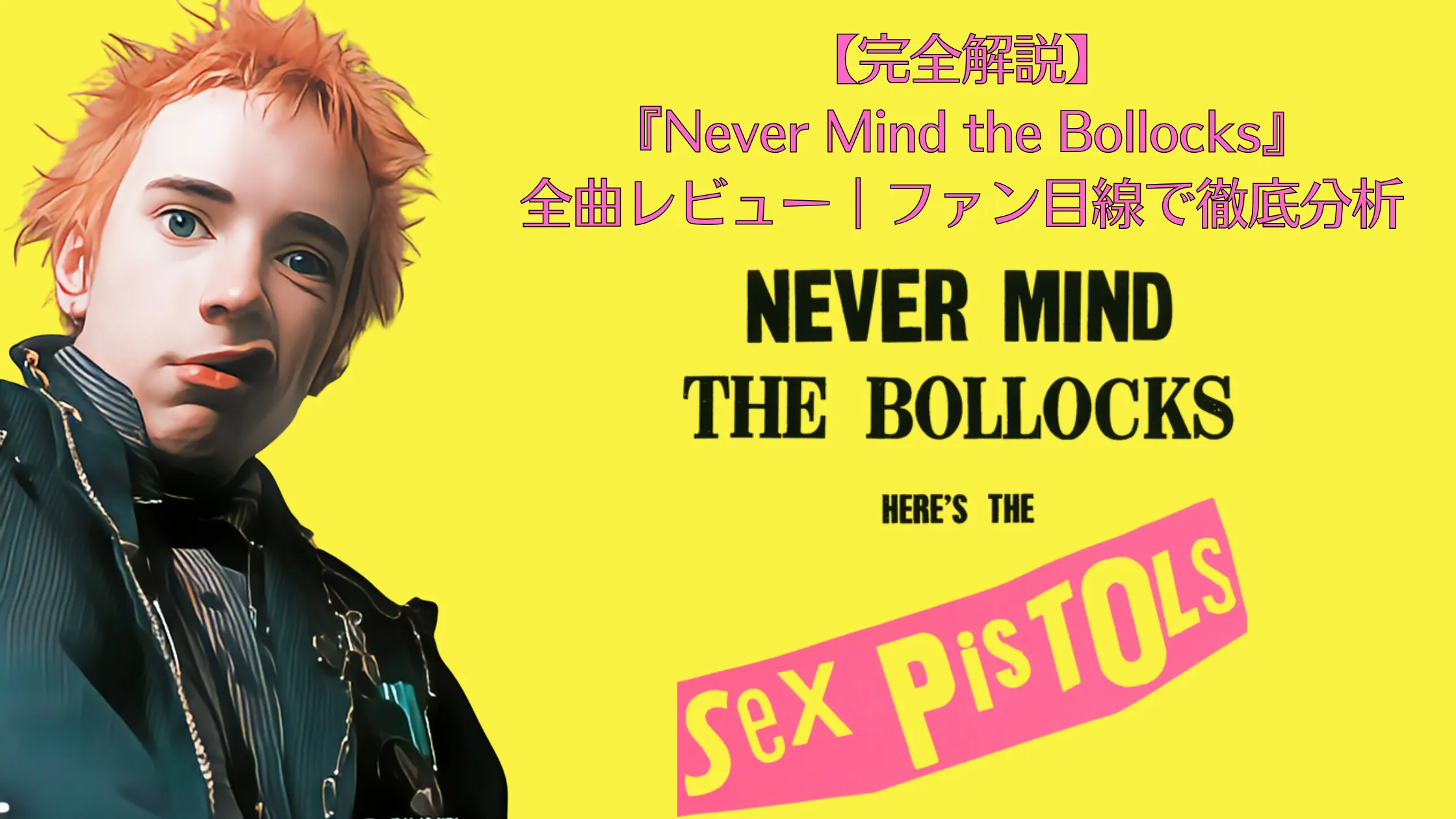

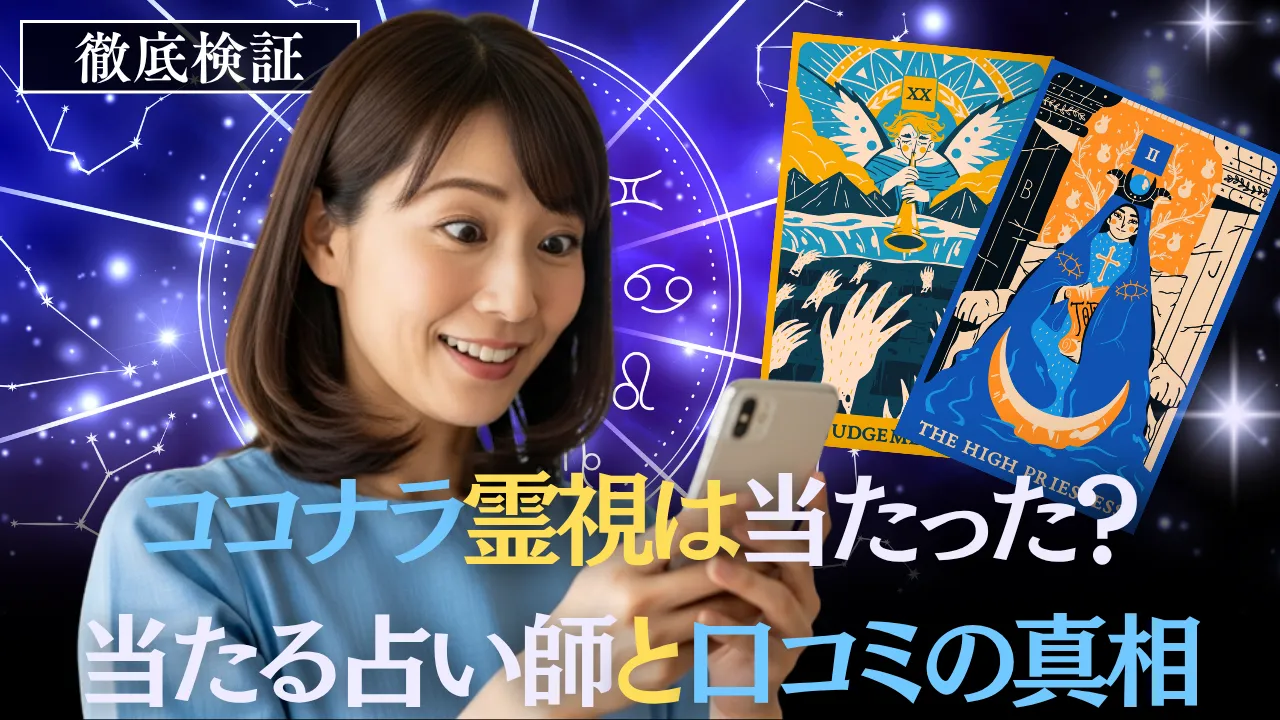
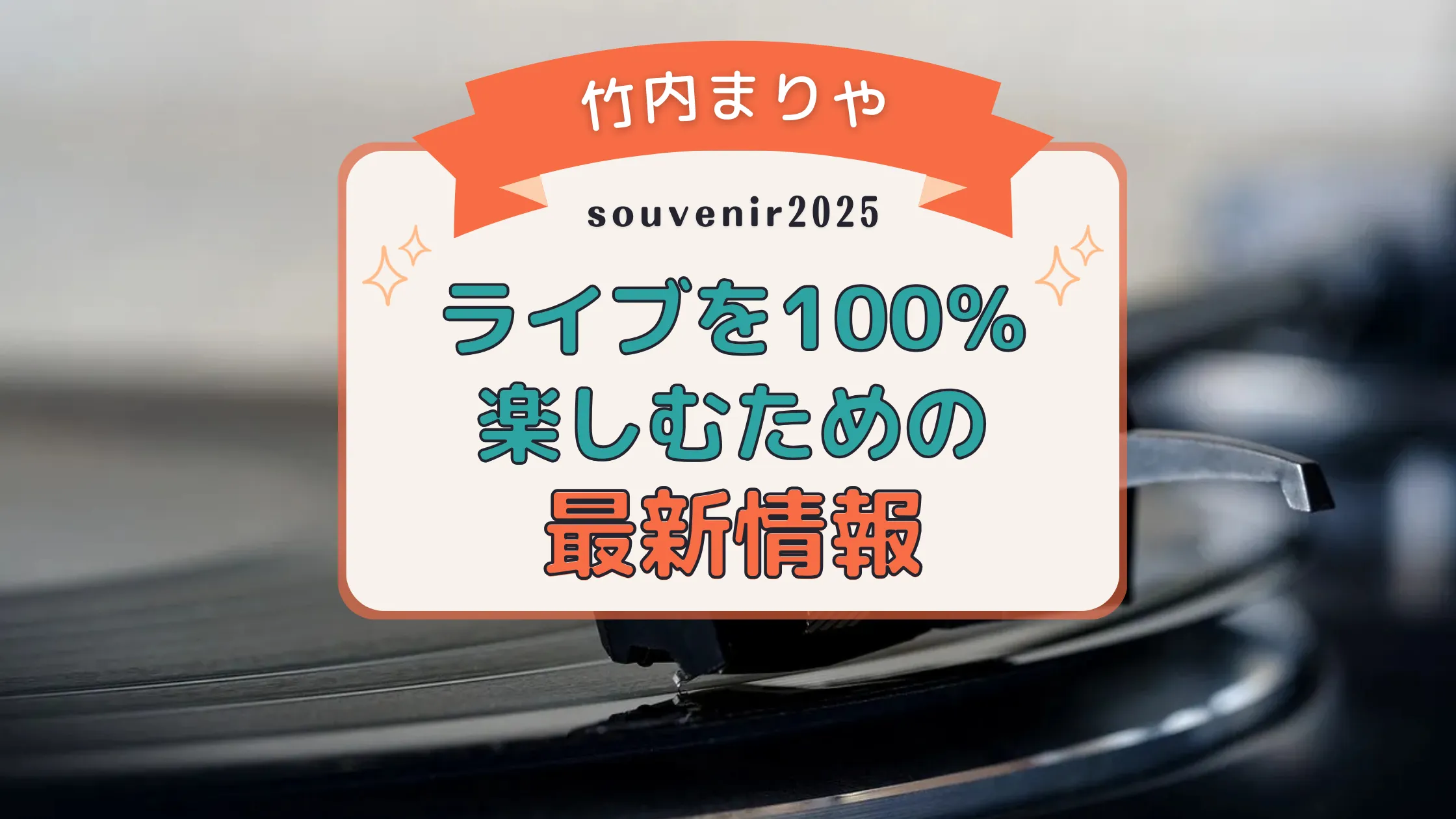


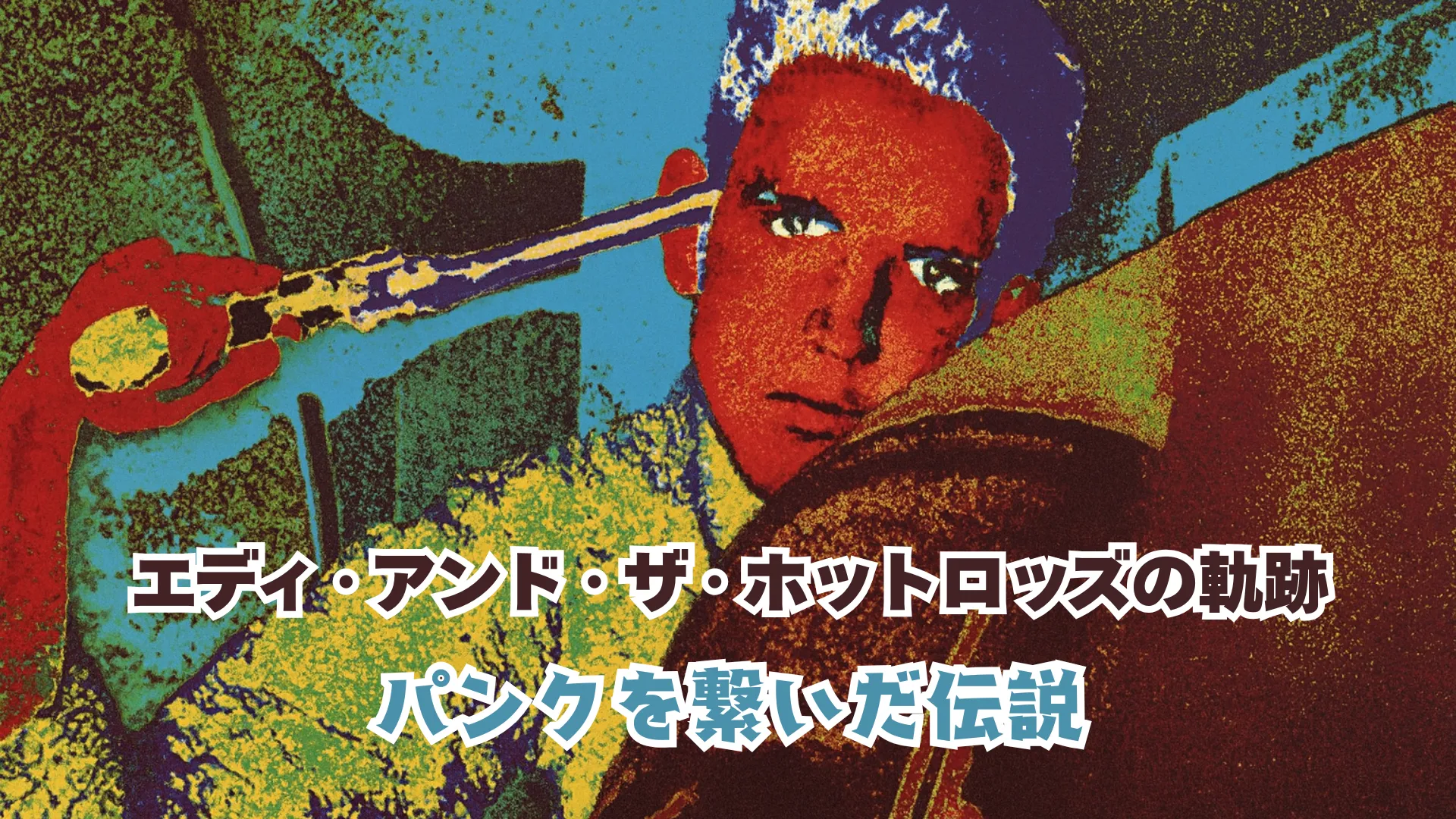






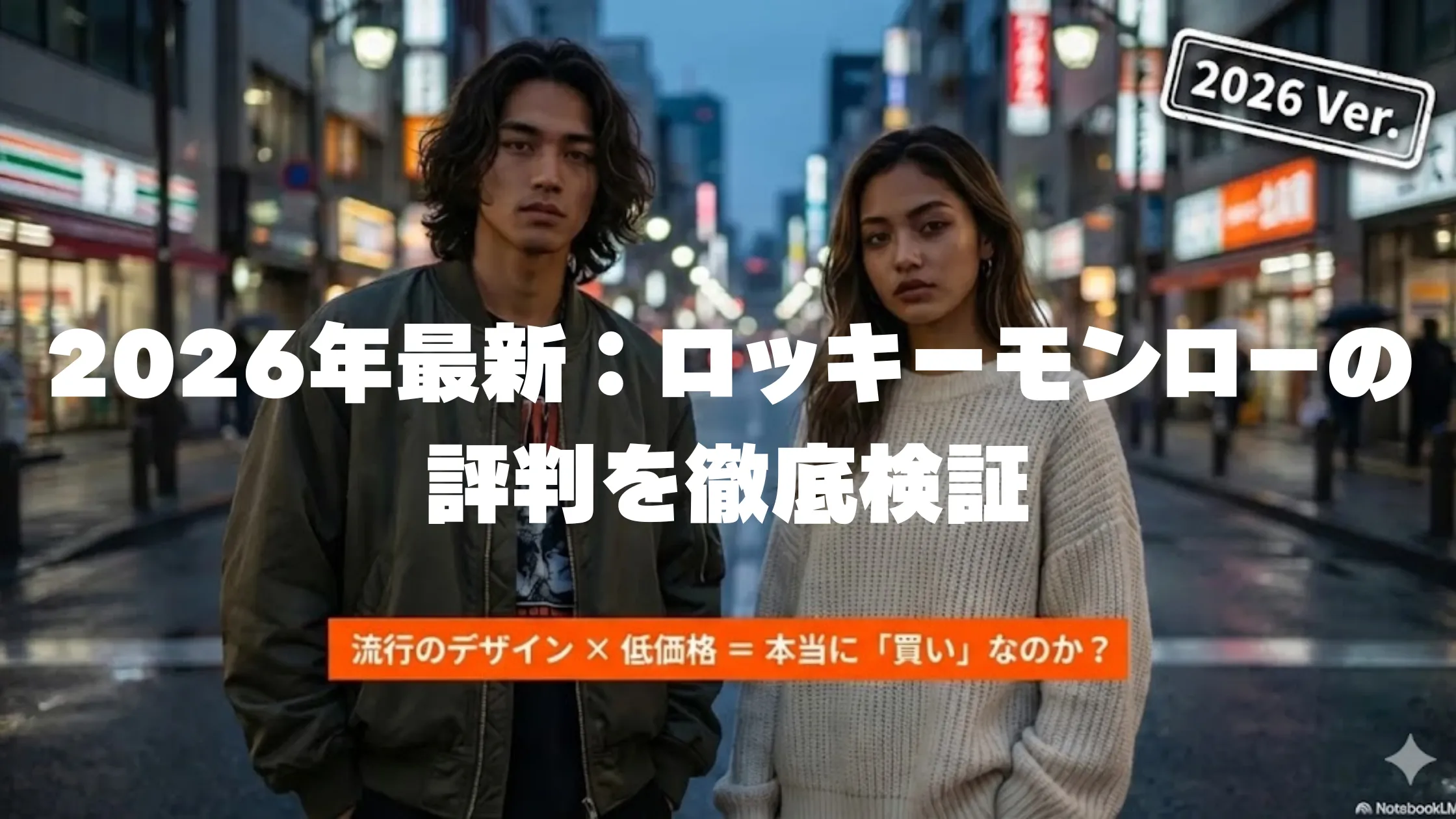
コメント