こんにちは。ジェネレーションB、運営者の「TAKU」です。
1979年、イギリスの若者たちを熱狂させ、今なおモッド・リバイバルの金字塔として語り継がれるザ・ジャムの『ジ・イートン・ライフルズ』。
あの独特なベースラインや鋭いギターのカッティングを聴くと、胸が熱くなる方も多いのではないでしょうか。
私自身のパンクロックの原体験も、実は中学生の頃にAMラジオのヒットチャートで流れてきた、この「イートン・ライフルズ」とザ・クラッシュの「ロンドン・コーリング」でした。
当時はインターネットもなく、歌詞カードと乏しい雑誌情報を頼りに「なんだかすごい怒っている歌だ」ということだけを感じ取っていたのを覚えています。
しかし、大人になり、単なるカッコいいロックナンバーとしてだけでなく、その歌詞に込められた深い意味や和訳、当時のイギリス社会が抱えていた階級対立の背景を知ることで、この曲はまったく違った響きを持って聞こえてきます。
さらに、近年のデヴィッド・キャメロン元首相の発言を巡る論争など、現代にも通じるトピックを含んでいるのも興味深い点です。
今回は、そんな名曲の裏側に隠された真実や、サウンドの秘密について、私の視点で徹底的に掘り下げてみたいと思います。
- 歌詞の和訳から読み解く痛烈な皮肉と階級社会へのメッセージ
- 1979年のイートン校で実際に起きたデモ行進と事件の真相
- 特徴的な転調やベースラインなど楽曲を支える音楽的構造
- デヴィッド・キャメロンの発言とポール・ウェラーの激怒の理由
1. ザ・ジャムの「ジ・イートン・ライフルズ」の歌詞と社会的背景
この楽曲が単なるパンクソングの枠を超えて評価されているのは、ポール・ウェラーが描いた歌詞の文学性と、当時のイギリス社会を鋭く切り取ったリアリズムにあります。
まずは、ザ・ジャムの「ジ・イートン・ライフルズ」が生まれた背景と、歌詞に込められた意味について深掘りしていきましょう。
1-1. 楽曲の歌詞や和訳に込められた意味
『ジ・イートン・ライフルズ(The Eton Rifles)』の歌詞は、単なる反抗の叫びではなく、非常に計算された皮肉と、ある種の「敗北感」が描かれている点が最大の特徴です。
この曲を理解するためには、まず冒頭の歌詞が描く情景をイメージする必要があります。
「ビールを飲み干し、タバコを集めろ(Sup up your beer and collect your fags)」というフレーズ。
これは、パブで管を巻いていた労働者階級の若者たちが、これから隣町のスラウ(Slough)の近くで起きている騒ぎに向かおうとする、日常から非日常への「出撃」の瞬間を切り取っています。
スラウという街は工業地帯であり、ジョン・ベジャマンの詩でも揶揄されたように、労働者階級の生活の象徴として描かれます。
対して、川を挟んですぐそばにあるのが、王室との関わりも深い超名門パブリックスクール、イートン校(Eton College)です。
この物理的な距離の近さと、社会的な距離の絶望的な遠さが、楽曲全体の通奏低音となっています。
歌詞の中で私が特に鳥肌が立つのは、「武器庫(artillery room)」という言葉の使い方です。
「奴らに挑んだときはお前も賢いつもりだったろう。だが奴らの武器庫を覗いたことはなかったな」という一節。
これはイートン校に実在する教練部隊(Cadet Corps)の物理的な武器庫を指すのと同時に、彼らエリート層が生まれながらに持っている「高度な教育」「自信」「弁論術」「家柄」といった知的な武器のメタファーでもあります。
ウェラーは、腕っぷしなら勝てると思っていた労働者階級の若者たちが、エリートたちの持つ「見えない武器」の前に、議論でも精神的にも手も足も出ずに論破され、あしらわれてしまう様を残酷なまでにリアルに描きました。
サビの「Hello-hurrah(ハロー、フレー!)」という掛け声は、一見楽しげなスポーツ観戦のチャントのように聞こえます。
しかし、実際には自分たちを嘲笑う「イートン・ライフルズ(エリート部隊)」に対する皮肉な祝祭であり、「雨で試合が中止になればいいのに」という、正面切って勝てない者の無力な願いが込められています。
この「Hello-hurrah」の部分は、レコーディングスタジオの近くにいた少年たちを招き入れて合唱させたという逸話があり、その無邪気な歌声がかえって不気味なリアリティを生んでいます。
そして曲の最後、「彼ら(イートン・ライフルズ)の一員になるくらいなら、疫病にかかったほうがマシだ(I’d prefer the plague to the Eton rifles)」と吐き捨てるシーン。
ここに、勝利することすら諦め、「彼らとは交わらない」ことだけが唯一の抵抗であり、最後のプライドであるという、ニヒリスティックな現実が突きつけられているのです。
これは、60年代の革命歌のような「世界を変えよう」という希望ではなく、70年代末の閉塞感が生んだ「断絶」の宣言と言えるでしょう。
1-2. 1979年のイートン校とデモ行進

この曲のインスピレーションの源となったのは、1978年6月に実際に行われた「生存権(Right to Work)」を訴えるデモ行進です。
当時、イギリスは「英国病」とも呼ばれる深刻な経済停滞期にあり、失業率が高止まりしていました。
リバプールやグラスゴーといった北部の工業都市から、職を求めてロンドンまで数百キロを歩く行進が行われたのです。
そのルートが、あの上流階級の象徴である「イートン校(Eton College)」の目の前を通過したことは、歴史的な必然だったのかもしれません。
当時の報道やポール・ウェラー自身の回想によると、行進するみすぼらしい身なりのデモ隊に対し、燕尾服を着たイートン校の生徒たちが校門から出てきて、野次を飛ばし、嘲笑したといいます。
この光景こそが、ウェラーに強烈なインスピレーションを与えました。
デモ隊側もただ黙っていたわけではありません。
彼らは、上流階級を揶揄する「銀のスプーンをくわえて生まれてくる(born with a silver spoon in one’s mouth)」という慣用句にちなんで、「巨大な銀のスプーン」の模型を作り、イートン校の生徒代表(Head Boy)に手渡すというパフォーマンスを行いました。
しかし、ウェラーが衝撃を受けたのは、その後の展開です。
エリートの学生たちは動揺するどころか、それをさらりと受け流し、ウィットに富んだ返しで逆にデモ隊をからかって楽しむ余裕さえ見せたのです。
この出来事は、単なる「金持ちと貧乏人の喧嘩」以上の意味を持っていました。
道徳的・倫理的には「働く権利」を訴える労働者たちが正しいはずです。
しかし、圧倒的な「階級の壁」と、支配層が持つ揺るぎない「余裕」の前に、労働者たちが惨めな敗北感を味わわされたという事実。
ウェラーが休暇中のキャラバンで雨に打たれながら書き上げたのは、この「正しさが力に勝てなかった」という悔しさと無力感でした。
イギリスの統計データを見ても、1970年代後半の失業率は上昇の一途をたどっていました。
当時の社会的な閉塞感は、現代の私たちが想像する以上に重苦しいものだったはずです。
英国国家統計局のデータによれば、1979年前後の失業率は5%を超え、その後80年代に入ると急激に悪化していきます。
この曲は、まさにその「不満の冬(Winter of Discontent)」へと突入する直前の、張り詰めた空気を真空パックした歴史的資料とも言えるのです。
1-3. 収録アルバムとリリースの詳細
『ジ・イートン・ライフルズ』は、1979年11月にリリースされたザ・ジャムの4枚目のアルバム『セッティング・サンズ(Setting Sons)』からの唯一のシングルとして、アルバム発売に先駆けて10月に発表されました。
この時期のザ・ジャムは、初期の『イン・ザ・シティ』の頃のような直線的で荒削りなパンクスタイルから脱却し、より複雑で厚みのあるサウンド、そしてより内省的で物語性のある歌詞を模索していた、バンドとしての過渡期にして成熟期でした。
レコーディングはロンドンのシェパーズ・ブッシュにある有名な「タウンハウス・スタジオ(The Townhouse Studios)」で行われました。
このスタジオは、特に「ストーン・ルーム(石造りの部屋)」でのドラム録音で知られ、後にフィル・コリンズがゲート・リバーブ・サウンドを生み出した場所としても有名ですが、ザ・ジャムのこの曲でもその硬質でパワフルな音響特性が存分に活かされています。
プロデューサーのヴィック・カッパー・スミス・ヘヴン(Vic Coppersmith-Heaven)は、バンドが持つライブでの爆発的なエネルギーをそのままスタジオ作品として定着させることに腐心しました。
彼はバンドに対し、スタジオ内でライブと同じように何度も演奏させ、ベストなテイクを模索しました。
しかし、単なる一発録りではありません。
当時はPro Toolsのようなデジタル編集技術など存在しない時代です。
ヴィックは、テープカッターを使ってアナログテープを物理的に切って繋ぐという、気の遠くなるような編集作業を行いました。
伝えられるところによれば、この曲の完成形に至るまでに、なんと65箇所以上ものテープ編集(スプライシング)が行われたと言います。
アルバム『セッティング・サンズ』自体は、もともと幼馴染の3人が成長してバラバラになっていく様子を描くコンセプト・アルバムとして構想されました。
最終的に完全な物語としては未完に終わりましたが、『ジ・イートン・ライフルズ』はそのストーリーラインの中で「無垢な少年時代が終わり、社会の冷酷な現実に直面する瞬間」を象徴する、極めて重要なピースとして機能しています。
1-4. 転調を含むコード進行の独自性
音楽理論的な視点で見ると、この曲が単なる3コードのパンクソングではないことがよく分かります。
ポール・ウェラーのソングライティング能力が飛躍的に向上していたことを証明するのが、曲の展開部(ブリッジ)における大胆かつ計算された転調(Key Modulation)です。
楽曲はF#マイナーを基調とした、不穏で緊張感のあるリフから始まります。
ヴァース(Aメロ)部分では、マイナー調特有の切迫感や鬱屈した怒りが表現されています。
しかし、そこからサビに向かうブリッジ部分で、一時的にF#メジャー(同主調)のような明るい響きへと移行し、視界が開けるような、ある種の「希望」や「高揚感」を与えます。
しかし、私が一番シビれるのは、そこからさらに予期せぬキー(Ebメジャーなど)へと強引にジャンプする瞬間です。
音楽理論にある「五度圏(Circle of Fifths)」のルールから見ても、かなり唐突で距離のある転調です。
ある音楽評論家はこの転調を「脳がショートするような感覚」と表現しましたが、まさにその通りです。
この音楽的な「不安定さ」や「足元がぐらつく感覚」は、歌詞の中で労働者階級の若者が、慣れない上流階級のルールや環境に放り込まれ、翻弄され、バランスを崩していく様子を、言葉ではなく音の構造そのもので表現しているかのようです。
イントロの不協和音とフィードバック・ノイズから始まり、緻密に計算された転調を経て、また不穏なリフに戻っていく。
この「混沌」と「構築美」の同居こそが、当時のポール・ウェラーが到達したソングライティングの境地であり、この曲を名曲たらしめている要因の一つです。
1-5. 特徴的なベースラインと演奏技術
ザ・ジャムのサウンドを語る上で絶対に外せないのが、ブルース・フォクストン(Bruce Foxton)によるアグレッシブかつメロディアスなベースラインです。
彼はこの曲でリッケンバッカー4001ベースを使用し、トレブル(高音域)を強調した、硬質でピアノのような、それでいて強烈なパンチのあるサウンドを響かせています。
特にイントロやAメロの裏で聴ける、「ダッ、ダッ、ダッ」という3連打のリズム(Triplets)に注目してください。
このフレージングは、曲名にある「ライフルズ(連隊)」の行進や、軍事教練(ドリル)の規律正しさを連想させると同時に、通りを行進するデモ隊の足音や、これから始まる暴動の気配をも表現しているように聞こえます。
ベースが単にルート音(根音)を弾いて支えるのではなく、ギターと対等に渡り合い、歌うようにカウンターメロディを奏でるスタイルは、ザ・フーのジョン・エントウィッスルからの影響を色濃く反映しています。
| パート | 特徴 | 役割と象徴 |
|---|---|---|
| ベース (Bruce Foxton) | リッケンバッカー特有の硬質なトーン、3連打のリフ | 軍事的な規律と物理的な衝撃、メロディの牽引 |
| ドラム (Rick Buckler) | マーチングバンド風のスネアロール、タム回し | パブリックスクールの教練部隊(Cadet Corps)のパロディ |
| ギター (Paul Weller) | 鋭いカッティング、空間系のコードワーク | 怒りの感情爆発と、冷静な観察者の視点の切り替え |
ドラムのリック・バックラーも、マーチングバンド風のスネアロールを多用し、楽曲の持つ「軍事的な規律」と「パンクの衝動」という相反する要素を見事に融合させています。
3人の個性がぶつかり合いながらも、奇跡的なバランスで成立しているこのアンサンブルは、その後のバンド解散に向かう過程で失われていく、ザ・ジャムというバンドの「最強の瞬間」を記録したものと言えるでしょう。
2. ザ・ジャム「ジ・イートン・ライフルズ」を巡る論争と評価
リリースから数十年が経ち、この曲は思わぬ形で再び脚光を浴びることになりました。
それが、当時の保守党党首であったデヴィッド・キャメロンの発言です。
ここからは、ザ・ジャムの「ジ・イートン・ライフルズ」が現代社会に投げかけた波紋について見ていきましょう。
2-1. デヴィッド・キャメロンの発言と波紋

2008年、当時イギリス保守党の党首であり、後に首相となるデヴィッド・キャメロンが、BBCラジオ4の長寿番組『Desert Island Discs(無人島に持っていきたいレコード)』やその他のインタビューにおいて、「お気に入りの曲」の一つとして『ジ・イートン・ライフルズ』を挙げたことが、イギリス全土を巻き込む大きなニュースになりました。
何がそんなに問題だったのでしょうか?
それは、キャメロン自身がまさに名門イートン校の出身(Old Etonian)であり、この曲がリリースされた1979年当時、彼は13歳でイートン校の生徒として在籍していたからです。
つまり、彼は歌詞の中でポール・ウェラーによって揶揄され、軽蔑され、批判されている「イートン・ライフルズ」の一員そのものだったのです。
キャメロンはインタビューで悪びれることなくこう語りました。
「私は教練部隊(Corps)にいたんだ。当時の私たちにとって大きな意味のある曲だった」「左翼だけがプロテストソングを聴く権利があるわけじゃない」。
彼は、自分たちが「からかわれている(taking the mick out of)」ことを理解した上で、それでもこの曲が好きだと公言したのです。
この発言は、「自分たちを批判している歌さえも、青春の思い出として消費してしまう」という、エリート層の圧倒的な余裕と、ある種の「文化的な無敵さ」を浮き彫りにしました。
批判すらもエンターテインメントとして消化してしまう彼らのタフさに、多くの音楽ファンや批評家はざわつき、現代社会における「反抗」の難しさを痛感させられたのです。
2-2. ポール・ウェラーによる痛烈な反応
当然のことながら、作者であり、生涯を通じて労働者階級の立場から発言を続けてきたポール・ウェラーは、この発言に対して激怒しました。
彼は『New Statesman』誌や『Mojo』誌などのインタビューで即座に反論し、以下のような痛烈なコメントを残しています。
「彼は曲のどの部分を理解していないんだ?(Which part of it didn’t he get?)」
さらにウェラーは、「あれは士官候補生(Cadet Corps)のための楽しい飲み歌(Jolly drinking song)として書いたわけじゃない」「イートンの生徒であることを祝福する歌だとでも思ったのか?」と怒りを露わにしました。ウェラーにしてみれば、サッチャリズムによって切り捨てられようとしていた労働者階級の怒りや、階級社会への呪詛を込めた歌が、あろうことかその批判対象である人物によって、ノスタルジックなBGMとして愛聴されていたことは、耐え難い屈辱であり、作品への冒涜だと感じたに違いありません。
この一連の騒動は、ロラン・バルトが提唱した「作者の死」――作品の意味は作者の手を離れ、読者(聴き手)によって自由に解釈される――という概念を、最も皮肉な形で、そして政治的な文脈で体現した現代の寓話として語り継がれています。
2-3. 全英チャートでの順位と商業的成功
政治的な論争はさておき、リリース当時のこの曲の成功は凄まじいものでした。
1979年10月にリリースされたシングルは、全英シングルチャート(UK Singles Chart)で最高3位を記録しました。
それまでのシングル(例えば『Down in the Tube Station at Midnight』の15位など)もヒットしていましたが、トップ3へのランクインは、ザ・ジャムにとって初の快挙でした。
これは、彼らが「一部の熱狂的なファンを持つカルト的なパンクバンド」から、名実ともにイギリスを代表する「国民的バンド」へとステージを上げた決定的な瞬間でした。
この曲のヒットによってバンドの勢いは加速し、続くシングル『ゴーイング・アンダーグラウンド(Going Underground)』では、ついに全英初登場1位という歴史的な記録を打ち立てることになります。
当時、BBCの人気音楽番組『Top of the Pops』に出演した際のパフォーマンス映像も伝説的です。
ウェラーの細身のスーツに身を包んだ完璧なモッド・スタイルと、攻撃的なリッケンバッカーの音色は、当時の若者たちのファッションアイコンとなり、第二次モッド・リバイバル・ブームを決定づけました。
パンクの破壊的なエネルギーを持ちながら、ビートルズやザ・フーから受け継いだポップ・センスを兼ね備えたこの曲は、幅広い層に受け入れられ、ラジオから流れ続けるアンセムとなったのです。
2-4. 後世のカバーやアーティストへの影響
『ジ・イートン・ライフルズ』の影響力は、その後のブリティッシュ・ロックシーンにも色濃く残っています。
多くのバンドがこの曲をフェイバリットに挙げ、あるいはその精神性を受け継いでいます。
例えば、政治的なメッセージと文学的な歌詞で知られるウェールズの英雄、マニック・ストリート・プリーチャーズ(Manic Street Preachers)は、ザ・ジャムからの影響を公言しています。
彼らの名盤『The Holy Bible』に収録された『4st 7lb』という曲のギターリフは、『ジ・イートン・ライフルズ』のリフと構造的に非常に似ており、オマージュではないかと指摘されることも多いです。
実際に彼らはライブでこの曲をカバーしたこともあります。
また、2000年代以降のアーティストによるカバーも興味深いものがあります。
ステレオフォニックス(Stereophonics)は2009年に男気溢れるロックなカバーを発表しましたが、特筆すべきはスコットランドのシンガーソングライター、エイミー・マクドナルド(Amy Macdonald)によるアコースティック・カバーです。
彼女のバージョンは、原曲の持つ攻撃的なビートを削ぎ落とし、アコースティックギターと歌声だけで構成されています。
これにより、ポール・ウェラーが書いたメロディの美しさと、歌詞の物語性がより鮮明に浮かび上がり、この曲が「パンク・アンセム」である以前に、極めて完成度の高い「フォーク・ソング」としての骨格を持っていることを証明しました。
これらのカバーは、時代やジャンルを超えて、この楽曲が持つ「持たざる者の物語」としての普遍性が、多くのミュージシャンの心を捉え続けていることを示しています。
2-5. 現代に響くザ・ジャム「ジ・イートン・ライフルズ」
最後に、改めてこの曲が現代に問いかけるものについて考えてみたいと思います。
1979年のリリースから40年以上が経過しましたが、格差社会や「持てる者と持たざる者」の分断は、解消されるどころか、グローバル化と共に形を変えてより深刻化し、今も世界中に存在しています。
デヴィッド・キャメロンのエピソードが残酷なまでに示したように、権力側やエリート層は、自分たちへの批判さえも「多様性」や「寛容さ」の名の下にエンターテインメントとして飲み込んでしまうタフさを持っています。
プロテストソングを歌うことすら、彼らの「コレクション」の一部になってしまうのかもしれません。
しかし、だからこそポール・ウェラーが歌詞の最後に込めた「疫病にかかったほうがマシだ」という、徹底した拒絶の姿勢は、今の時代においても強烈なリアリティを持って響いてきます。
安易な和解や妥協を拒否し、「自分はそちら側には行かない」と線を引くこと。
それが、どれだけ無力に見えようとも、個人の尊厳を守る最後の砦なのかもしれません。
私自身、大人になってから改めてこの曲を聴き直すと、中学生の頃にラジオで聴いたときとは違う、苦味の混じった大人のカッコよさを感じます。
「ザ・ジャムのジ・イートン・ライフルズ」は、単なる懐メロではなく、今もなお私たちの社会認識を試す「踏み絵」のような一曲として、レコードの溝から鋭い視線を投げかけ続けているのです。
正確なリリース情報や歌詞の全文、当時の貴重な写真などについては、バンドの公式ディスコグラフィーや信頼できる音楽データベースサイト等で改めて確認してみることをおすすめします。
歌詞カードを片手に聴くことで、新たな発見があるはずです。
💿 アナログ盤で味わう“生のSetting Sons”

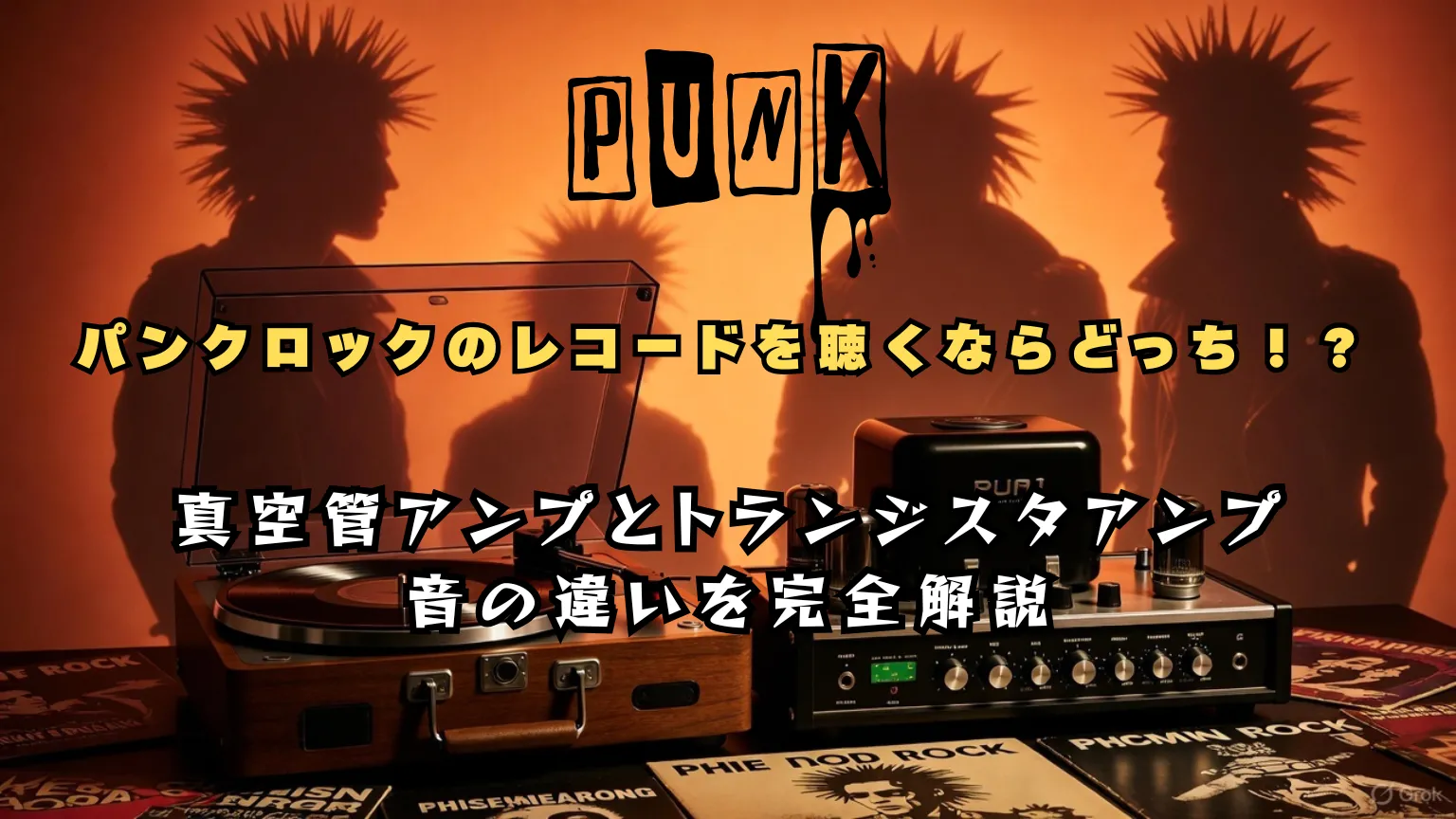

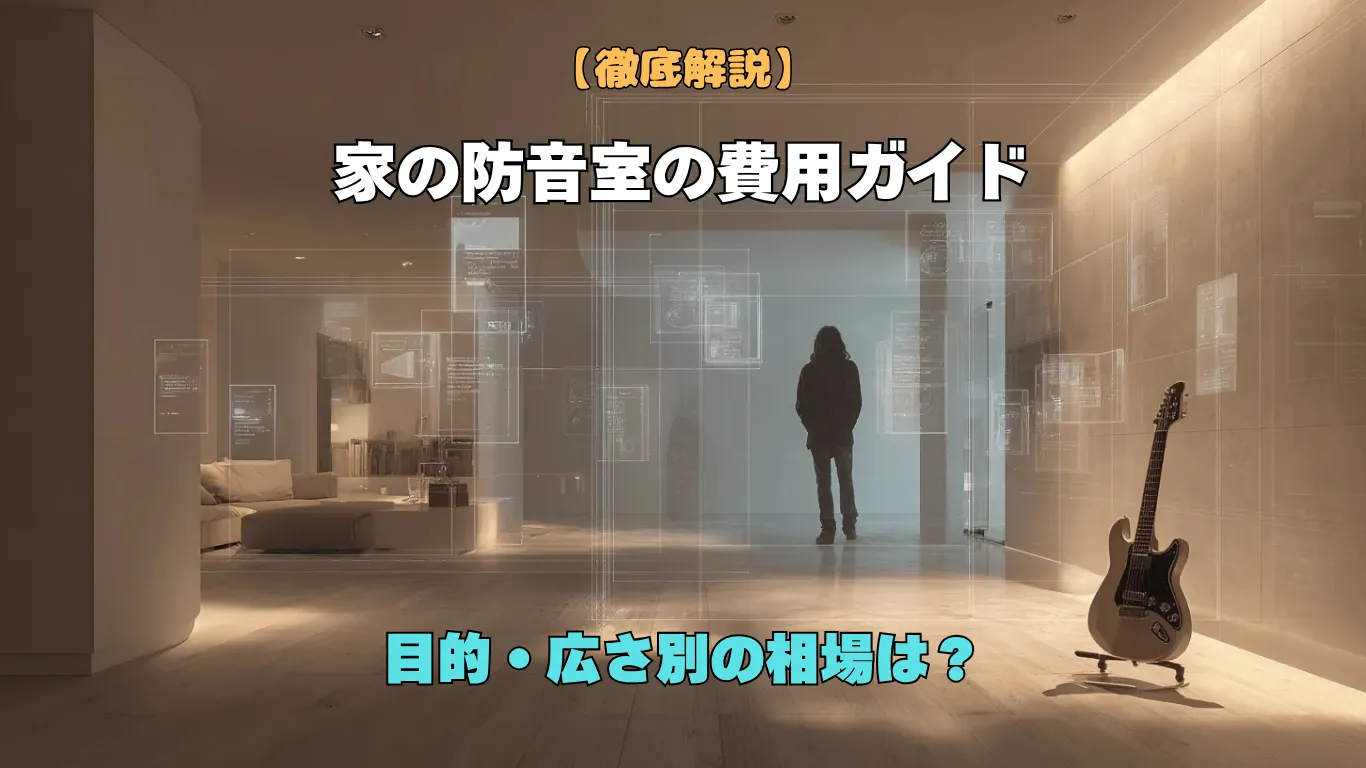
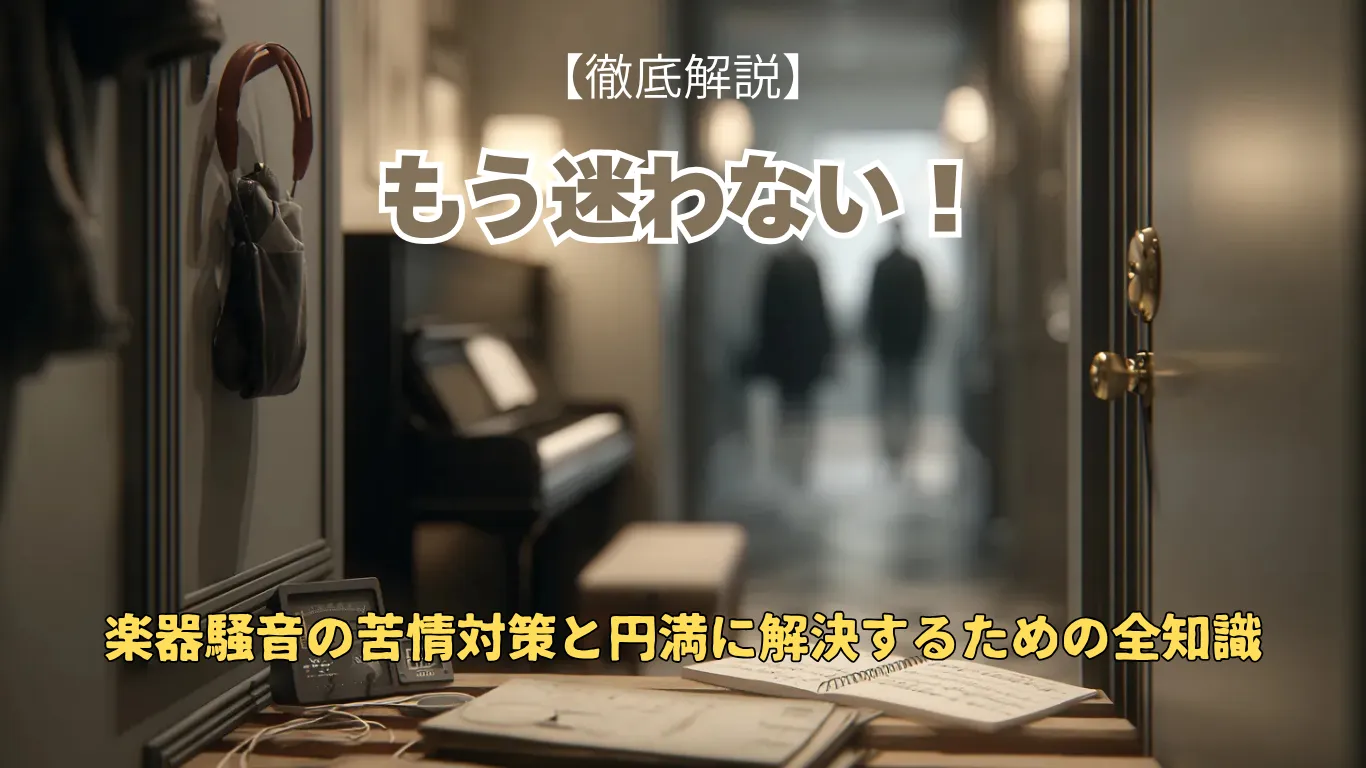
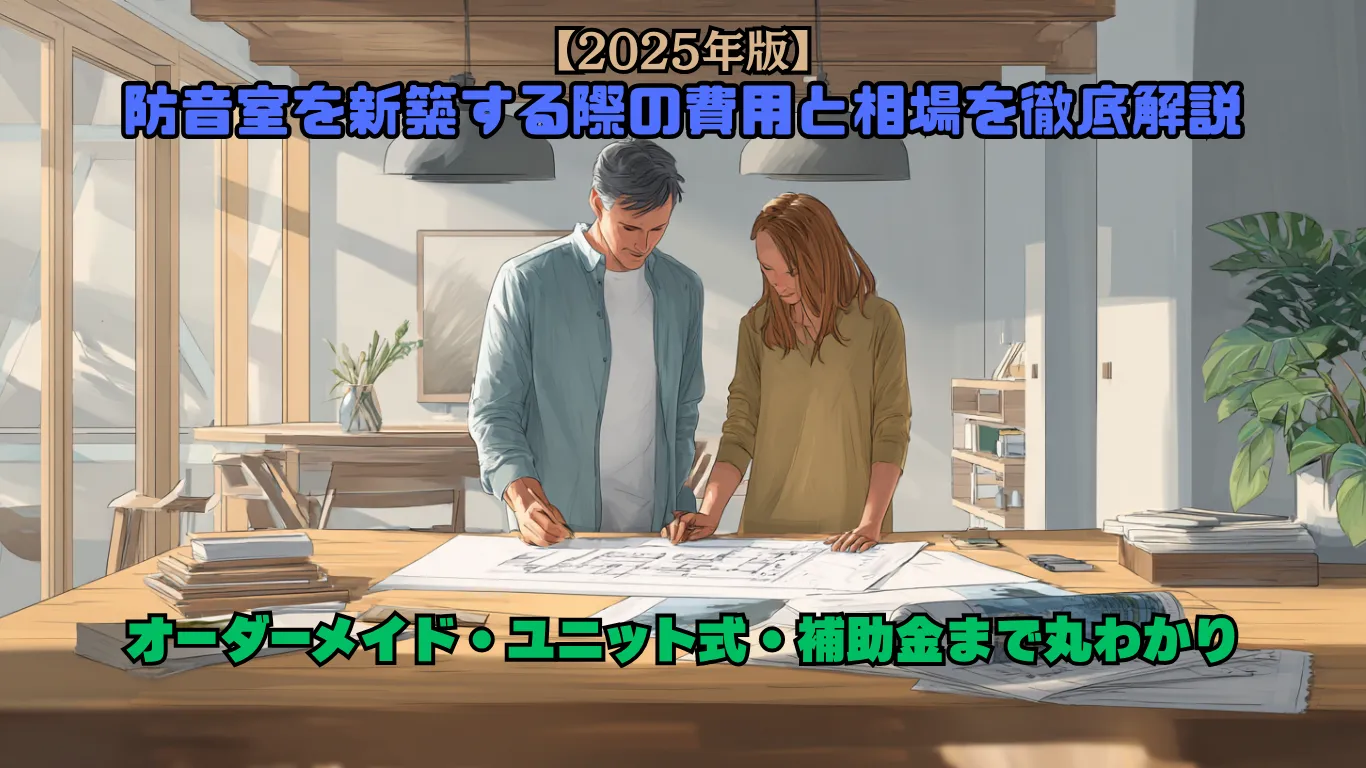

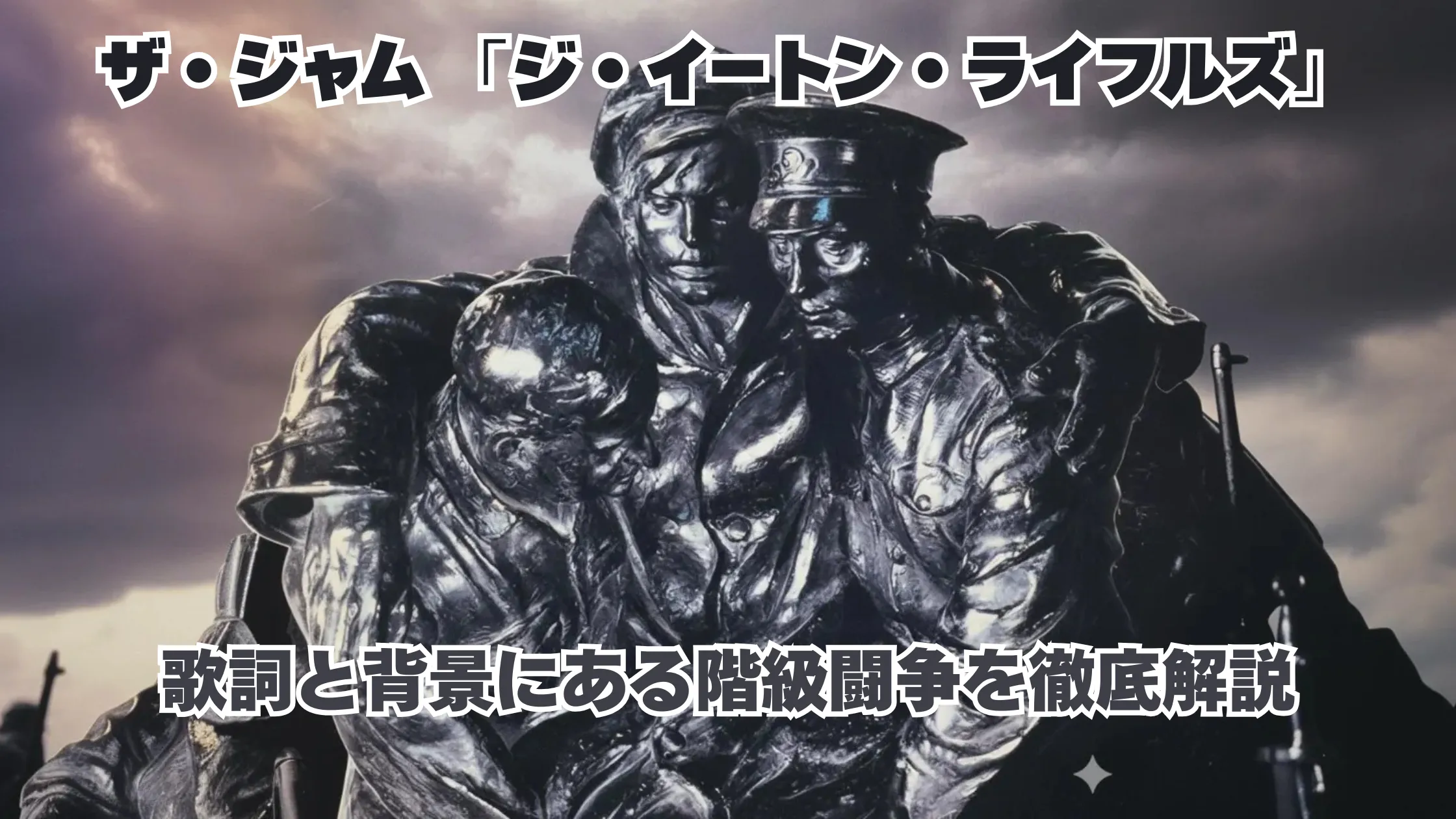


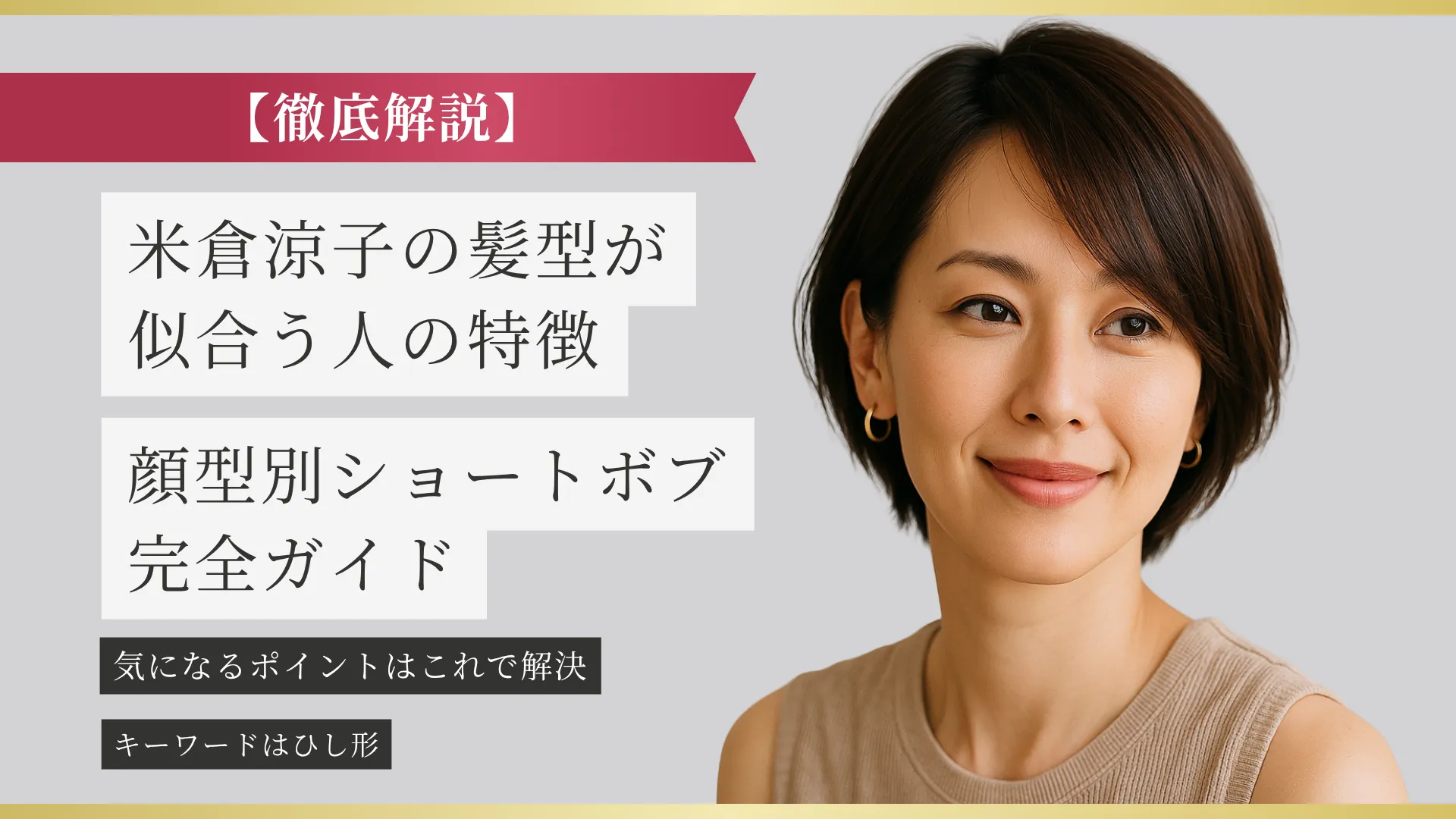

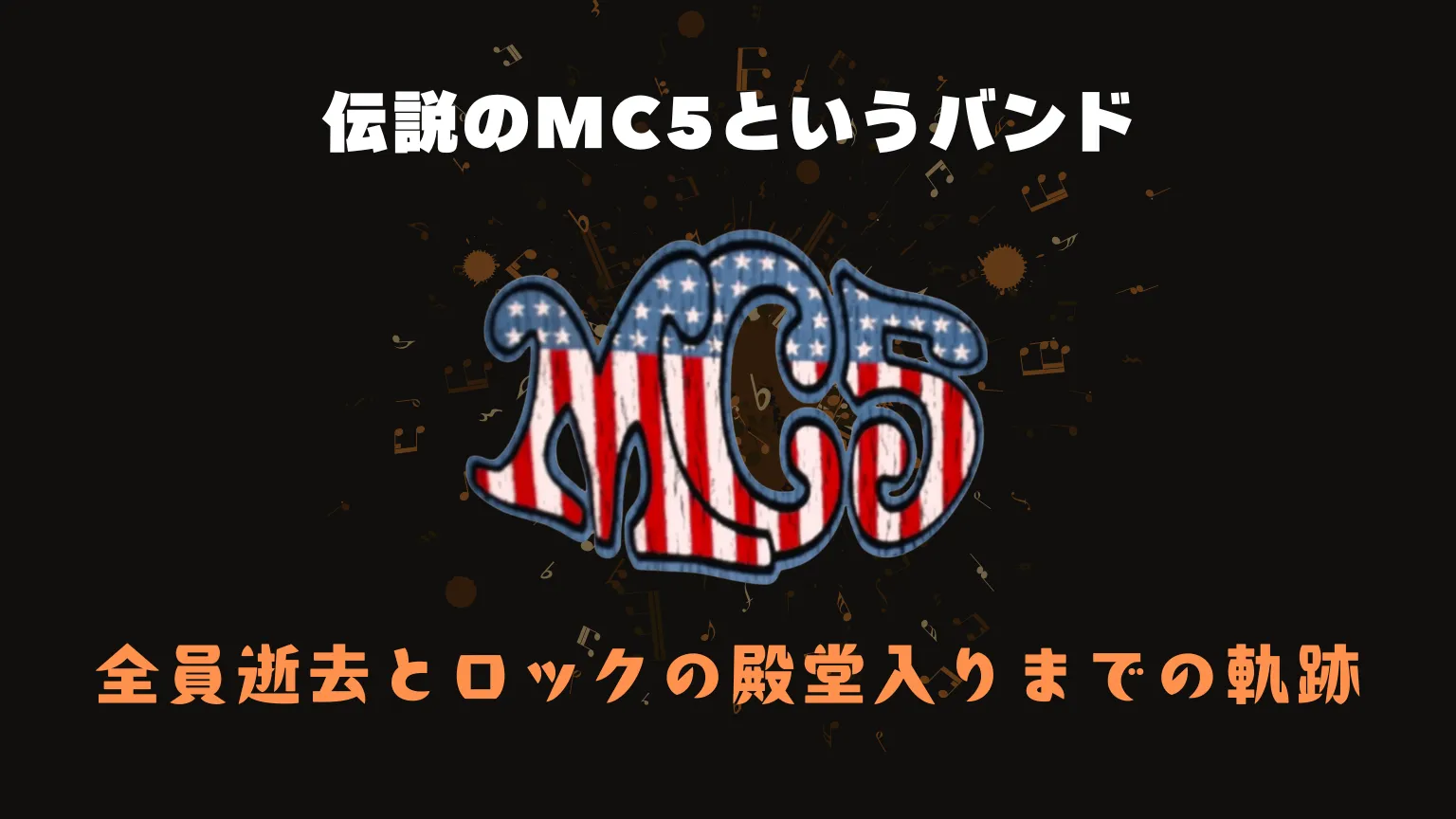
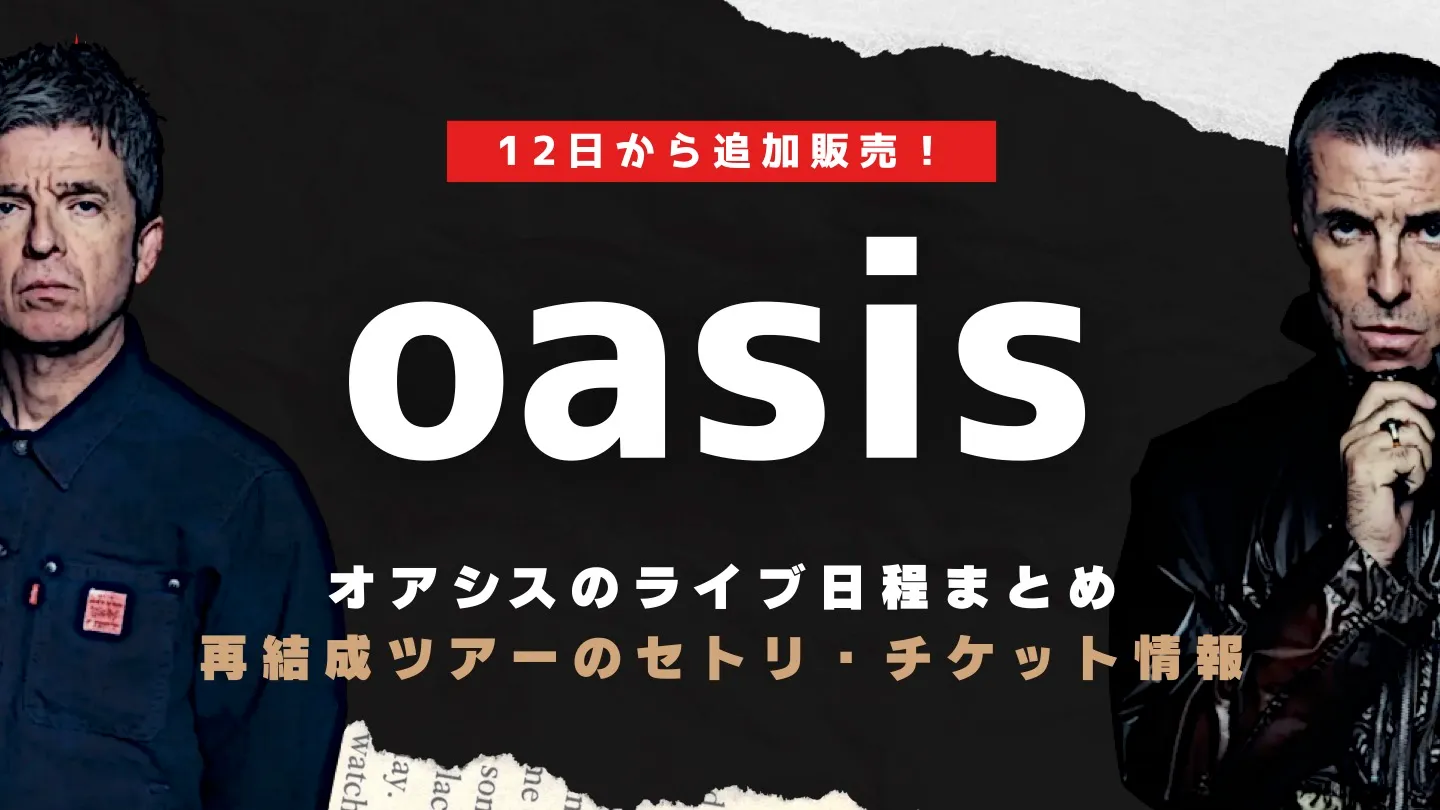
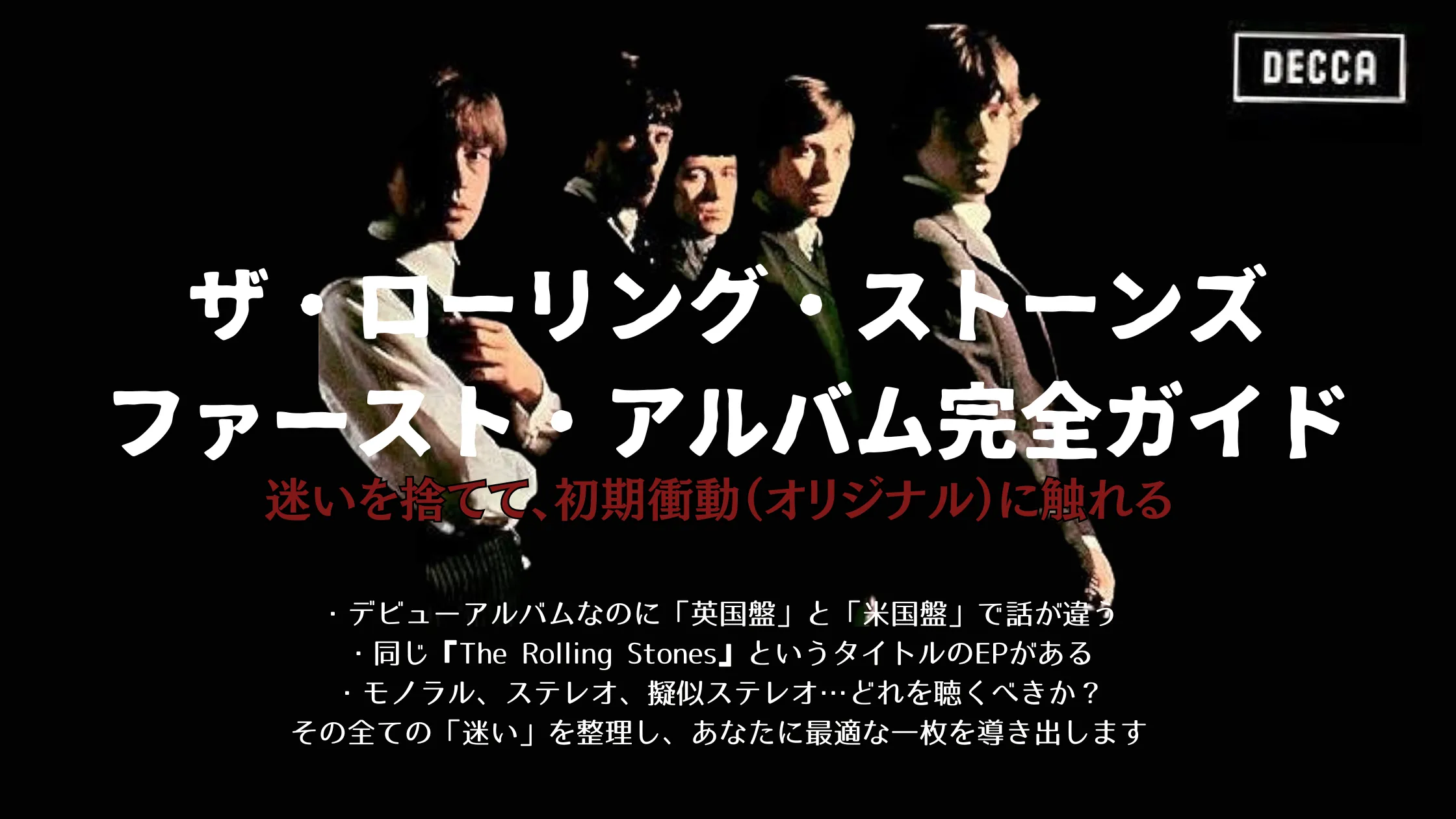







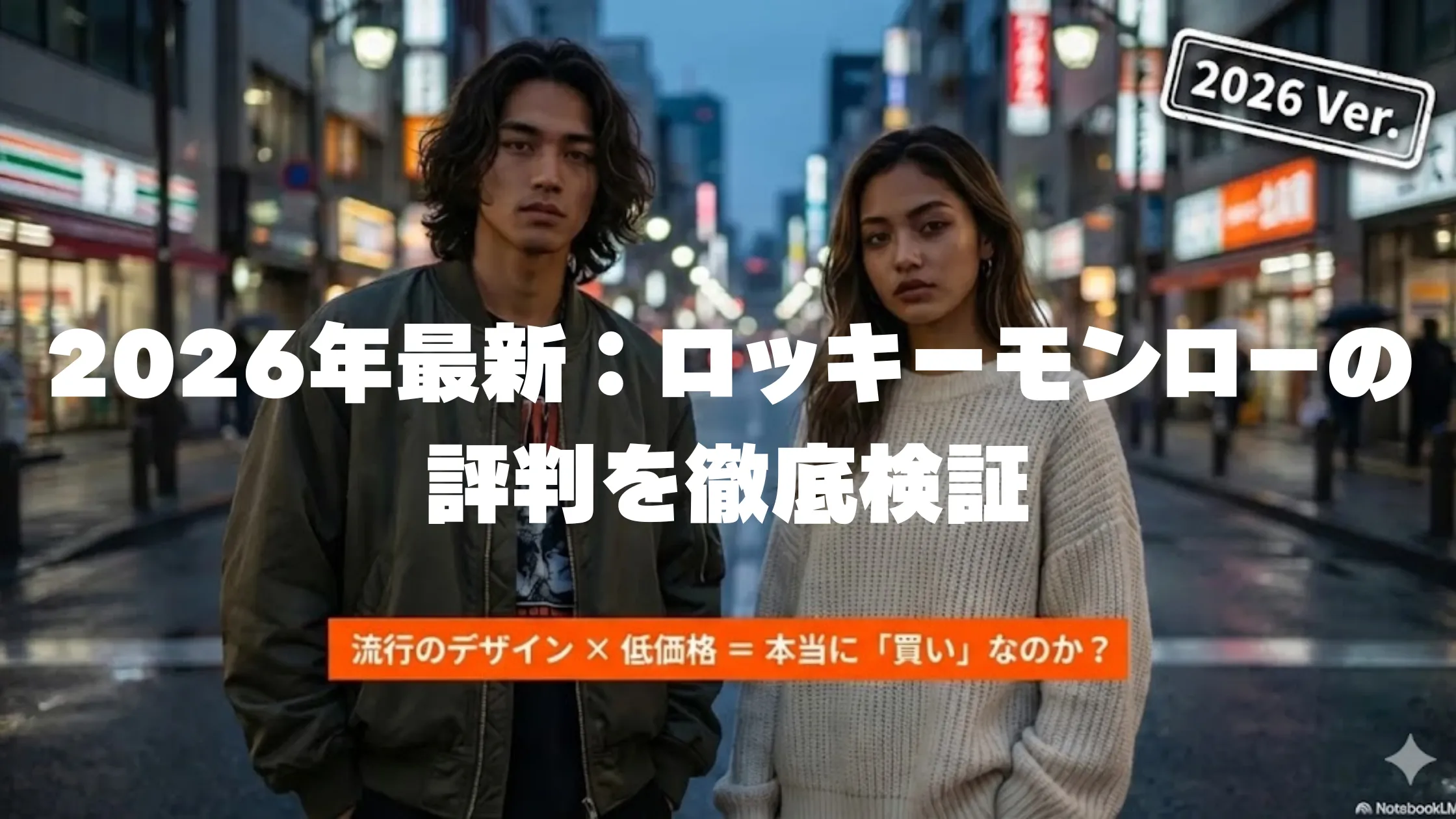
コメント