※この記事はアフィリエイトリンクを含みます。
ストラングラーズの最高傑作を探していますか?そもそもストラングラーズとはどういう意味ですか?と疑問に思う方もいるかもしれません。
個性豊かなストラングラーズのメンバー、そしてストラングラーズのボーカルは誰ですか?という基本的な情報から、彼らの音楽の核心に迫るストラングラーズの代表曲や名盤アルバムまで、この記事では徹底解説します。
伝説となったストラングラーズの来日公演、ストラングラーズが初来日したのはいつですか?といった歴史的背景や、ファンに人気のストラングラーズTシャツのデザインにも触れながら、あなたにとっての最高の一枚を見つけるお手伝いをします。
この記事でわかること
✔︎ ストラングラーズのバンド名の由来とメンバーの経歴
✔︎ 初期の代表作から後期の隠れた名盤までの変遷
✔︎ 最高傑作と評される各アルバムの特徴と魅力
✔︎ 伝説の来日公演やバンドにまつわる逸話

1. ストラングラーズ 最高傑作と名高い初期の作品群
✔︎ ストラングラーズとはどういう意味ですか?
✔︎ 個性豊かなストラングラーズのメンバー
✔︎ ストラングラーズのボーカルは誰ですか?
✔︎ まず聴くべきストラングラーズの代表曲
✔︎ ストラングラーズの名盤と評価されるアルバム
1-1. ストラングラーズとはどういう意味ですか?
ストラングラーズ(The Stranglers)というバンド名が持つ直接的な意味は「絞首刑執行人」です。
この非常に不穏で攻撃的な名前は、1970年代半ばのイギリスで、既存のロックシーンに対するカウンターカルチャーとして発生したパンク・ムーブメントの精神を色濃く反映しています。
当時の音楽シーンは、プログレッシブ・ロックやハードロックが主流で、演奏技術の高さや長大な楽曲構成がもてはやされていました。
ストラングラーズは、そうした権威的で肥大化したロックへのアンチテーゼとして登場し、そのバンド名は既存の価値観や体制に痛烈な裁きを下すという彼らの姿勢を明確に示していました。
歌詞では社会の偽善や矛盾を鋭くえぐり出し、ライブパフォーマンスでは観客を挑発し、時には乱闘騒ぎや警察とのトラブルも辞さないなど、その活動スタイルはまさにバンド名を体現するものでした。
ただ、彼らの音楽は単に暴力的で破壊的なだけではありませんでした。
そこには常に知性に裏打ちされた冷静な批評精神が宿っており、他の多くのパンクバンドが持つ若さゆえの初期衝動とは一線を画す、独特の深みと説得力がありました。
この「知的な暴力性」とも言える二面性こそが、ストラングラーズというバンドの本質であり、その名が持つ意味の奥深さを示していると言えるでしょう。
ポイント
✔︎ バンド名の直訳は「絞首刑執行人」
✔︎ 1970年代のパンク精神と、既存体制への反抗を象徴
✔︎ 単なる暴力性ではなく、知的な批評精神を内包した活動スタイルを示す
1-2. 個性豊かなストラングラーズのメンバー
ストラングラーズが他のパンクバンドと決定的に異なっていた最大の要因は、そのメンバー構成にあります。
多くのパンクバンドが音楽経験の浅い若者たちで結成されていたのに対し、ストラングラーズはそれぞれが豊富な人生経験と高い知性、そして確かな演奏技術を持った「大人」の集団でした。
「インテリヤクザ」とも評された彼らの個性的なプロフィールは、バンドの音楽に他の誰にも真似できない深みと説得力を与えていました。
彼らの異色の経歴は、バンドの音楽的・思想的な基盤を形成する上で重要な役割を果たしています。
| メンバー名 | パート | 特徴・経歴 |
|---|---|---|
| ヒュー・コーンウェル (Hugh Cornwell) | ボーカル、ギター | 名門ブリストル大学で生物化学の学士号を取得し、スウェーデンの大学で研究者として活動していた経歴を持つインテリ。彼の書く歌詞は文学的でシニカルな視点に満ちており、バンドの知的なイメージを牽引しました。 |
| ジャン=ジャック・バーネル (Jean-Jacques Burnel) | ベース、ボーカル | フランス系の両親を持ち、歴史学を専攻。移民としての経験からくる反骨精神を持ち、そのエネルギーを空手と音楽に注ぎ込みました。彼は極真空手の有段者(七段)であり、三島由紀夫の文学に深く傾倒。彼の弾く、ピックを使った硬質で攻撃的なベースラインは「リードベース」と呼ばれ、バンドサウンドの絶対的な核となりました。 |
| デイヴ・グリーンフィールド (Dave Greenfield) | キーボード | メンバーで唯一、音楽大学でクラシック音楽を正式に学んだ人物。プログレ・バンドでの活動経験もあり、その卓越した技術で奏でられるサイケデリックで流麗なキーボードは、ストラングラーズを単なるパンクバンドではない特別な存在へと昇華させました。 |
| ジェット・ブラック (Jet Black) | ドラム | デビュー時すでに38歳という最年長メンバー。音楽活動を本格化させる前は実業家として成功を収めており、複数のアイスクリーム販売車ビジネスや酒類販売店を経営していました。初期のツアーでは、彼が所有するアイスクリーム・バンが移動手段として使われたという逸話も残っています。彼の正確でパワフルなドラムが、バンドのアンサンブルを力強く支えました。 |
このように、生物学者、武道家、クラシック経験者、実業家といった、ロックミュージシャンとしては極めて異色の経歴を持つメンバーが集まったことで、ストラングラーズは他の誰にも似ていない、唯一無二の音楽を生み出すことができたのです。
1-3. ストラングラーズのボーカルは誰ですか?
ストラングラーズの魅力の一つに、楽曲によって異なる表情を見せるボーカルが挙げられます。
これは主に二人のメンバー、ヒュー・コーンウェルとジャン=ジャック・バーネルがボーカルを分担していたことによります。
ヒュー・コーンウェル:知性とニヒリズムの体現者
バンドのメインボーカルであり、フロントマンとして強烈なカリスマ性を放っていたのがヒュー・コーンウェルです。
彼のボーカルスタイルは、パンク的な攻撃性の中にも、常に一歩引いたような冷静さと知性を感じさせるのが特徴でした。
生物学者という経歴を持つ彼ならではの、シニカルで観察眼に優れた文学的な歌詞を、時に吐き捨てるように、時にメロディアスに、そして時には淡々と語るように歌い上げました。
このクールでニヒリスティックな歌声は、ストラングラーズのサウンドに複雑な奥行きと独特の緊張感を与えています。
ジャン=ジャック・バーネル:剥き出しの闘争心と情熱
もう一人のボーカリストが、ベーシストのジャン=ジャック・バーネルです。
彼のボーカルは、ヒューとは実に対照的で、よりストレートで感情的なスタイルが持ち味です。
武道家としての彼の気質が色濃く反映されたかのような、パワフルで情熱的なシャウトは、ライブにおけるエネルギーの源泉でした。
彼がリードボーカルをとる「5 minutes」や「The European Female」といった楽曲は、バンドの持つ武闘派でロマンティックな側面を強く印象付けます。
豆知識:ツインボーカルがもたらす化学反応
ヒューの「静」とジャン=ジャックの「動」。この二つの異なる個性が一つのバンドの中に共存していたことで、ストラングラーズの楽曲は非常に多彩な表情を持つことになりました。曲によってボーカルが入れ替わるだけでなく、一つの曲の中で二人が掛け合いのように歌うこともあり、それがアルバム全体を通して聴き手を飽きさせないドラマティックな展開を生み出しています。このツインボーカル体制は、1990年にヒュー・コーンウェルが脱退するまで続き、バンドの黄金期を支える最も重要な要素の一つでした。
1-4. まず聴くべきストラングラーズの代表曲
50年近いキャリアを誇るストラングラーズの広大なディスコグラフィーの中から、彼らの本質と魅力を知るためにまず聴いておきたい代表曲を厳選してご紹介します。
時代ごとに音楽性は大きく変化しましたが、どの楽曲にも通底する強烈な個性と高い音楽性が感じられます。
No More Heroes (1977)
1977年発表の2ndアルバムのタイトル曲であり、バンドの代名詞とも言える不滅のアンセムです。
「ヒーローはもういらない」とシニカルに歌うこの曲は、パンク・ムーブメントの反骨精神を象徴するだけでなく、続くニュー・ウェイヴ時代の到来を告げるマニフェストとなりました。
ジャン=ジャック・バーネルの地を這うようにうねるベースラインと、デイヴ・グリーンフィールドの洪水のようなキーボードソロは圧巻の一言。
英国のオフィシャル・チャートでもトップ10入りを果たし、彼らの名を世に知らしめました。
Golden Brown (1981)
1981年のアルバム『La Folie』からシングルカットされ、バンド最大のヒットとなった名曲です。
優雅なワルツのリズム(3/4拍子と4/4拍子が交互に現れる複雑な構成)と、デイヴ・グリーンフィールドが奏でるチェンバロの美しい音色が特徴。
初期のパンクサウンドとは180度異なる耽美的で洗練された世界観は、パンクファン以外にも広く受け入れられ、彼らの音楽性の幅広さを見せつけました。
歌詞の解釈を巡っては様々な議論を呼びましたが、そのミステリアスな魅力もまた、この曲を特別なものにしています。
Peaches (1977)
デビューアルバム『Rattus Norvegicus』に収録された、初期の人気曲です。
気だるいレゲエ調のリズムと、J.J.バーネルの唸るようなベースラインが印象的。
ヒュー・コーンウェルの投げやりなボーカルが、夏のけだるい雰囲気を完璧に表現しています。
しかし、その挑発的で性的な歌詞が問題視され、BBCでは放送禁止措置を受けました。
こうした体制との衝突も、当時の彼らのスタイルを象徴する出来事でした。
Something Better Change (1977)
「何かが変わらなきゃいけない」というストレートなメッセージを、性急なビートに乗せて叩きつける初期のパンクナンバー。
シンプルながらも疾走感と焦燥感に満ちたサウンドは、ライブでも絶大な人気を誇ります。
特に1979年の初来日公演の最終日、この曲を5回連続で演奏してステージを降りたという逸話は、彼らの伝説を語る上で欠かせないエピソードです。
注意点:代表曲は氷山の一角
ここで紹介したのは、ストラングラーズの魅力を知るための入り口に過ぎません。「(Get A) Grip (On Yourself)」「Nice ‘n’ Sleazy」「Always the Sun」など、彼らのキャリアを彩る名曲は数多く存在します。ぜひアルバムを通して聴き、あなただけのお気に入りの一曲を見つけてみてください。
1-5. ストラングラーズの名盤と評価されるアルバム
「ストラングラーズの最高傑作は?」という問いに対して、多くのファンや批評家がまず挙げるのが、1977年から1978年にかけて、わずか1年余りの間にリリースされた初期の3枚のアルバムです。
これらの作品には、パンクの衝動と彼ら独自の知性、そして卓越した演奏技術が、最も純粋で爆発的な形で凝縮されています。
1st: Rattus Norvegicus (夜獣の館) – 1977年
『Rattus Norvegicus』を聴く
記念すべきデビューアルバムでありながら、すでに新人離れした完成度を誇る名盤です。
ジャケットに大きく記された「Ⅳ」の文字は、バンドが結成から4年のキャリアを持っていることを示唆しており、一朝一夕ではないその実力を物語っています。
ドアーズを彷彿とさせながらも、より攻撃的でねじれたデイヴ・グリーンフィールドのキーボード、そして楽曲の主役と言っても過言ではないJ.J.バーネルの「リードベース」が絡み合い、他のどのパンクバンドとも違う、唯一無二のサウンドを確立しました。
「Sometimes」の暴力的な緊張感から「(Get A) Grip (On Yourself)」の疾走感、そして「Peaches」の気だるさまで、アルバム一枚で多彩な表情を見せつけます。
2nd: No More Heroes - 1977年
『Mo More Heroes』を聴く
デビューからわずか半年後という驚異的なペースでリリースされた2ndアルバム。
前作で確立したスタイルを継承しつつ、よりスピード感とポップなフックを増強した、まさに捨て曲なしの傑作です。
タイトル曲「No More Heroes」はバンドの代表曲となり、反英雄主義を掲げたニューウェーブの道標として、時代を象徴する一曲となりました。
「Something Better Change」や「Bitching」など、ストレートなパンクナンバーの切れ味は鋭く、アルバム全体が初期衝動の塊のようなエネルギーに満ちています。
3rd: Black and White - 1978年
『Black and White』を聴く
多くの識者から「パンクの最高傑作の一枚」、そしてストラングラーズのキャリアの頂点と称される3rdアルバムです。
前2作の勢いに加え、サウンドにさらなる重厚さと実験性が加わりました。
アナログ盤ではA面を「White Side」、B面を「Black Side」とコンセプトを分け、より深く、暗い世界観を構築。
リズムパターンは格段に多様化し、サウンドは立体的で複雑なものへと進化しています。
J.J.バーネルが敬愛する三島由紀夫に捧げられた「Death and Night and Blood (Yukio)」も収録。
このアルバムの発表後に行われた初来日公演は、その過激さから日本のロック史に残る伝説となりました。
この初期3部作は、まさに「神がかり的」と評されるほどの創造力に満ちています。
ストラングラーズというバンドの核を理解するためには、絶対に避けては通れない必聴の作品群と言えるでしょう。
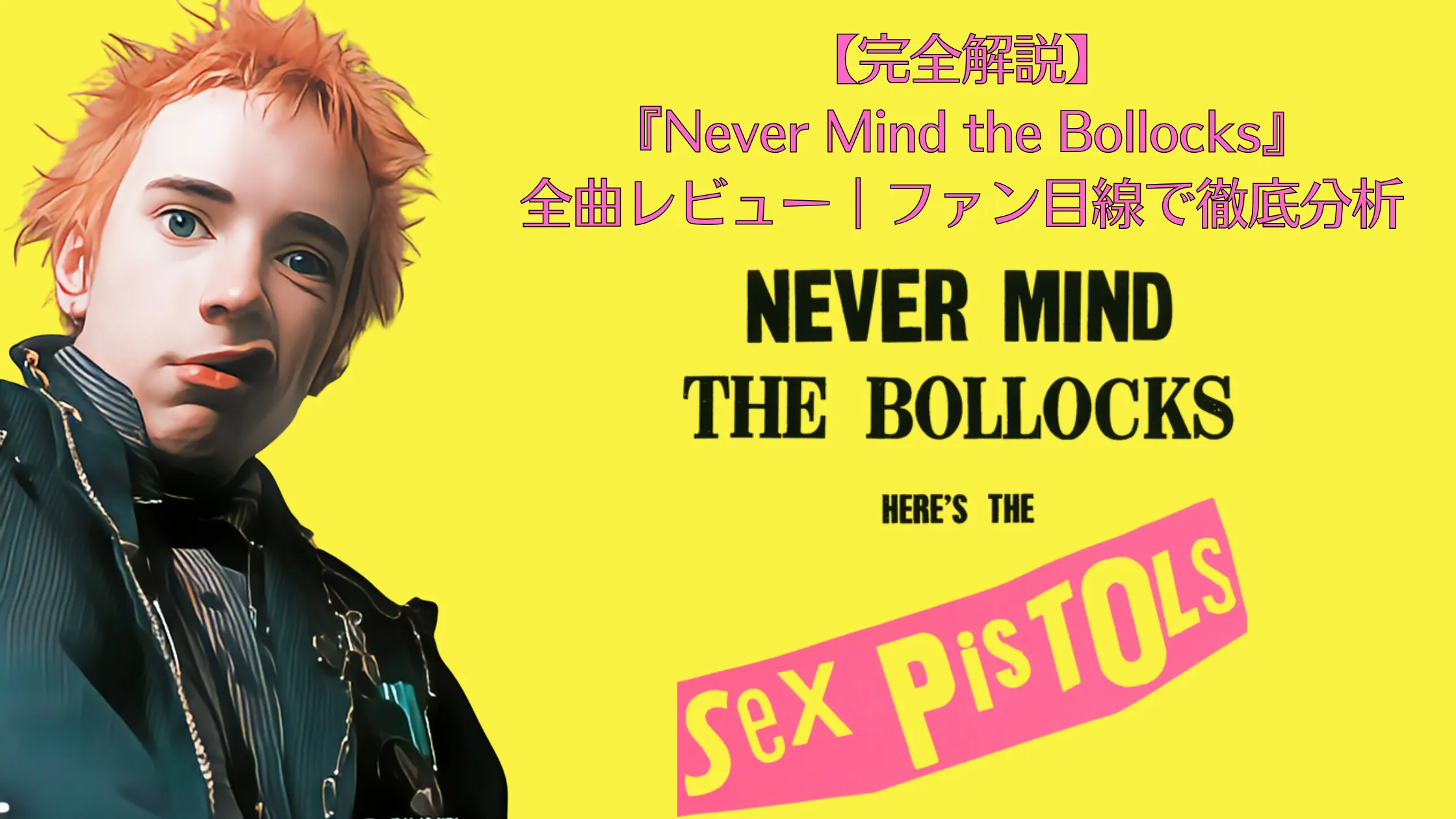
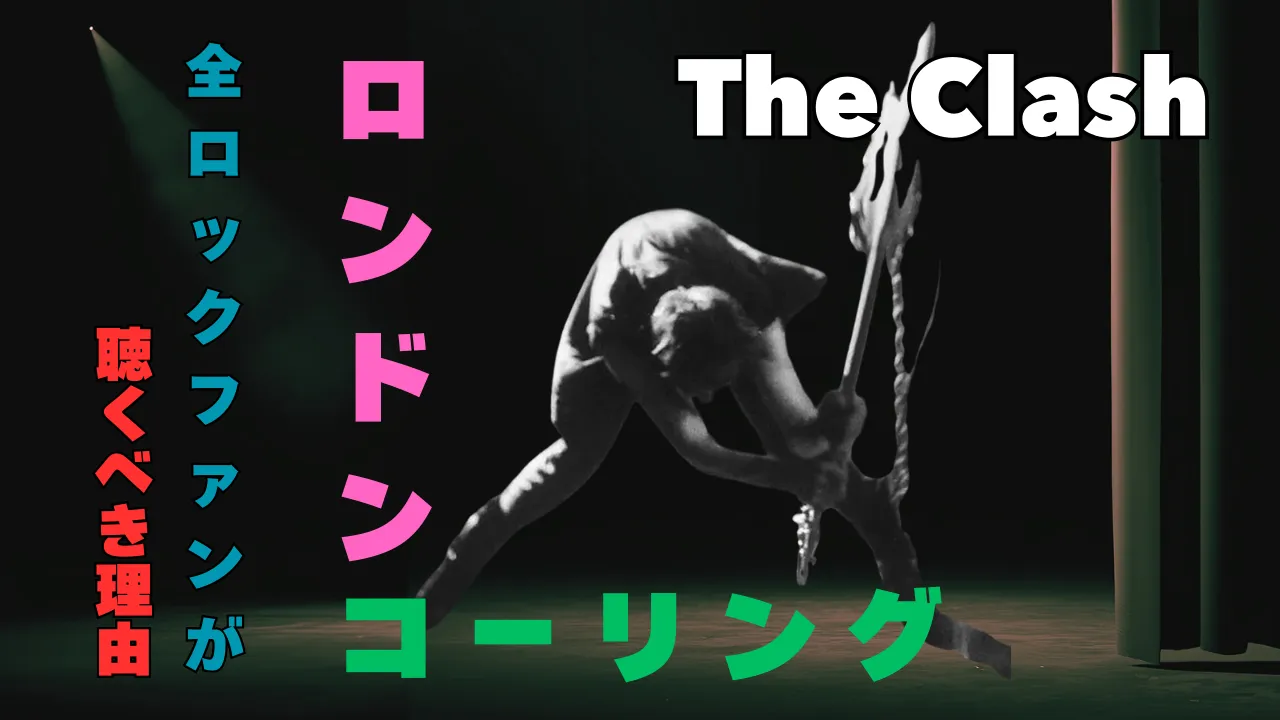
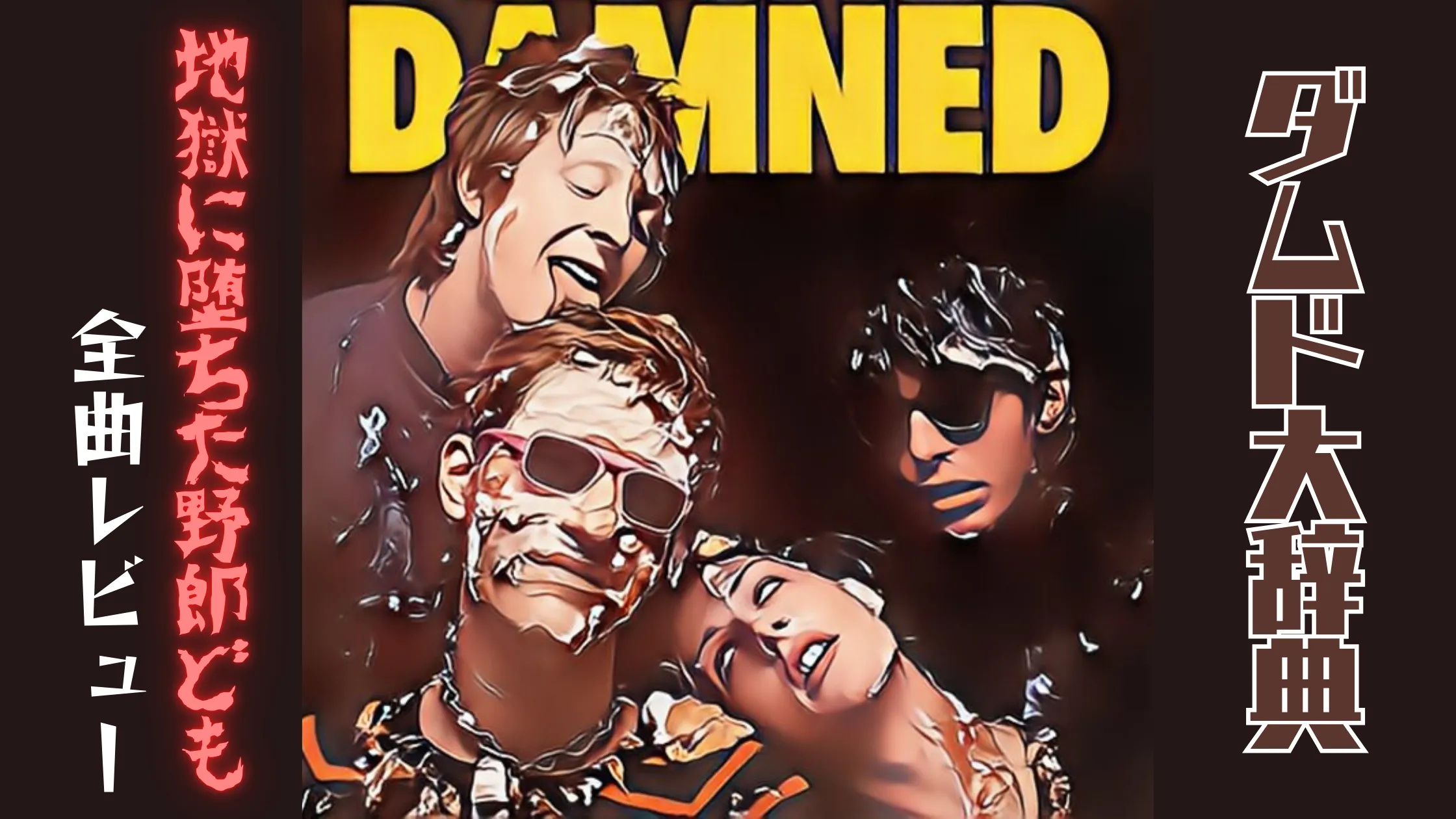
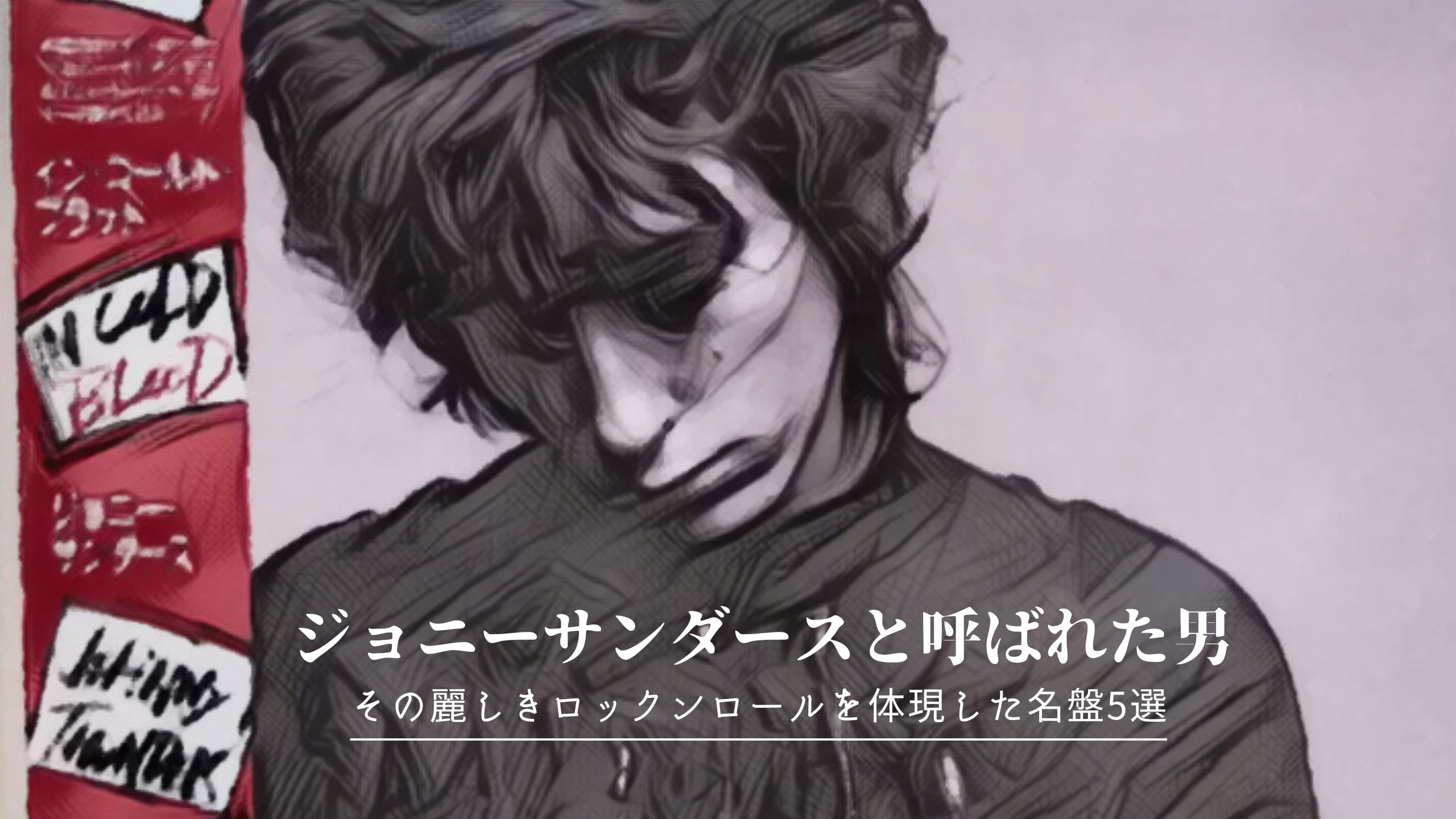
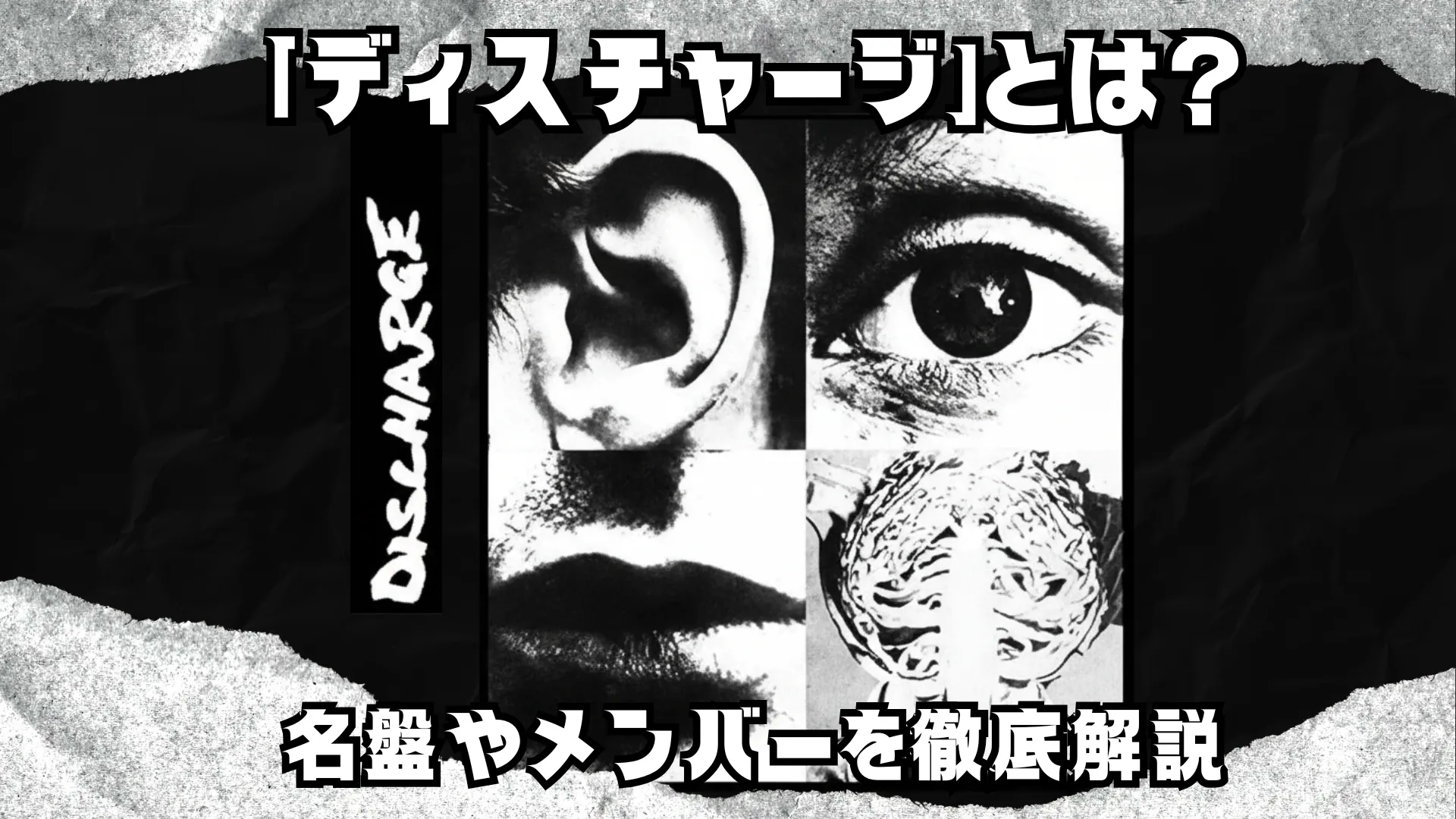

2. 音楽性の変遷とストラングラーズ 最高傑作の多様性
✔︎ 進化を続けたストラングラーズのアルバム
✔︎ ストラングラーズが初来日したのはいつですか?
✔︎ 伝説となったストラングラーズの来日公演
✔︎ 人気のストラングラーズTシャツのデザイン
✔︎ あなたが選ぶストラングラーズ 最高傑作は?
2-1. 進化を続けたストラングラーズのアルバム
初期のパンクサウンドで確固たる地位を築き上げたストラングラーズですが、彼らが真に非凡なバンドである所以は、そこに安住することなく、常に自らの音楽性を破壊し、再構築し続けた点にあります。
1980年代に入ると、彼らのサウンドは劇的な変貌を遂げ、初期のファンを戸惑わせながらも新たなリスナーを獲得していきました。
The Raven (1979年) - 変革の序章
『The Raven』を聴く
4作目となるこのアルバムは、パンク時代との決別と、新たな領域への旅立ちを告げる過渡期の作品です。
初期3部作の暴力的な怒りは影を潜め、シンセサイザーが本格的に導入されたことで、サウンドはよりモダンで内省的なものへと変化しました。
ヴァイキングの神話をモチーフにした壮大なタイトル曲など、よりコンセプト性を重視したアプローチが特徴で、物語性の強いアルバムに仕上がっています。
当初のLP盤は、世界で初めて3Dホログラムをジャケットに採用したことでも話題となりました。
The Gospel According to the Meninblack (1981年) - 最大の問題作
『The Gospel According to the Meninblack』を聴く
彼らのキャリアにおける最大の問題作であり、最も実験精神に満ちたアルバムです。
UFOや聖書をテーマにした壮大で難解なコンセプトを掲げ、従来のロックンロールのフォーマットは完全に放棄。
電子音や不気味なノイズ、機械的なリズムが全編を覆う、非常にアヴァンギャルドな内容となっています。
この急進的な変化により多くのファンが離れてしまいましたが、その誰にも媚びない挑戦的な姿勢は、バンドの本質を象徴するものとして、一部でカルト的な評価を得ています。
La Folie (1981年) & Feline (1983年) - 耽美派への転生
『La Folie』を聴く
『Feline』を聴く
『Meninblack』での徹底的な自己破壊の後、バンドは驚くべきことに、ポップでメロディアスな側面を前面に押し出します。
フランス語で「狂気」を意味する『La Folie』に収録された「Golden Brown」は、その美しいメロディでバンド史上最大のヒットを記録。
続く『Feline』(黒豹)では、アコースティックギターや電子ドラムを多用し、ヨーロッパ的な湿潤さと退廃的な美意識に満ちた、洗練された独自のユーロロックを完成させました。
この時期の彼らは、もはやパンクバンドではなく、孤高の芸術家集団といった趣を呈しています。
ポイント:変化を恐れない姿勢
ストラングラーズは、パンクからニューウェーブ、アヴァンギャルドな電子音楽、そして耽美的なユーロロックへと、一枚ごとにその音楽性を大胆に変化させていきました。この絶え間ない変化と進化を恐れない姿勢こそが、彼らが50年近くにもわたって活動を続けられた原動力であり、彼らの「最高傑作」が一枚に絞れない最大の理由でもあるのです。
2-2. ストラングラーズが初来日したのはいつですか?
ストラングラーズが記念すべき初の日本公演を行ったのは、1979年2月のことです。
これは、セックス・ピストルズやザ・クラッシュといった他の主要なパンク・バンドに先駆けての来日であり、日本のロックファンにとってはまさに歴史的な出来事でした。
当時の日本において、パンクロックはまだ音楽メディアでスキャンダラスに取り上げられることが中心で、その本質的な音楽性やカルチャーとしての重要性は十分に理解されていませんでした。
そんな状況下で、シーンの最前線で活動し、すでに本国イギリスで数々のヒットアルバムをリリースしていたストラングラーズの来日は、「本物」のパンクを体験できる貴重な機会として、大きな注目を集めたのです。
ツアーは1979年2月13日の福岡・少年文化会館を皮切りに、大阪、京都、名古屋を巡り、東京・後楽園ホールで3日間の公演を行うという、新人バンドとしては異例の規模で行われました。
彼らの生々しく、凶暴なエネルギーに満ちたパフォーマンスは、レコードで聴くのとは比較にならないほどの衝撃を日本の若者たちに与え、この初来日公演は、日本のパンク/ニューウェーブシーンが本格的に幕を開ける、重要なきっかけの一つとして記憶されています。
補足:異例の速さでの再来日
初来日の成功と日本での熱狂的な歓迎を受け、ストラングラーズは同年の12月には早くも2度目の来日公演を実現しています。わずか10ヶ月という短いインターバルでの再来日は極めて異例であり、当時の彼らが日本でいかに強いインパクトを残したかを物語っています。
2-3. 伝説となったストラングラーズの来日公演
前述の通り、ストラングラーズの初来日は1979年2月ですが、この時の公演、特に東京でのコンサートは数々の衝撃的な逸話を残し、今なお日本のロック史における「伝説のライブ」として語り継がれています。
その伝説の背景には、当時の日本とイギリスのコンサート文化の大きなギャップがありました。
当時の日本のコンサート会場では、観客は指定された座席に座って静かにステージを鑑賞するのが一般的でした。
一方、本国イギリスでオーディエンスと一体となって暴動寸前の熱狂的なライブを繰り広げてきた彼らにとって、そのお行儀の良い光景は信じがたいものであり、大きなフラストレーションの原因となったのです。
特に血気盛んなベーシスト、ジャン=ジャック・バーネルの怒りは凄まじく、おとなしい日本の観客に対し「Don't smile so much, It makes you blind.(そんなに笑うな、盲目になるぞ)」という有名な挑発の言葉を投げかけたとされています。
彼はライブ中に客席に飛び込んで乱闘騒ぎを起こしたり、警備員と衝突したりと、その武闘派ぶりを遺憾なく発揮しました。
前代未聞の「Something Better Change」5回連続演奏事件
そして、この来日公演を象徴する最も有名なエピソードが、ツアー最終日の東京公演での出来事です。日本のコンサートの閉鎖的な雰囲気に最後まで苛立ちを募らせたバンドは、アンコールに応えてステージに登場すると、代表曲「Something Better Change」を5回も連続で演奏し、観客を呆然とさせたままステージを去ってしまったのです。これは、彼らの怒りと、商業的なショービジネスに対する徹底した抵抗の意思表示でした。
この一連の出来事は、ストラングラーズの「危険で予測不可能」というイメージを日本のファンに強烈に植え付けるとともに、日本のロックコンサートのあり方そのものに一石を投じるものとなりました。
彼らのライブは単なる音楽の演奏ではなく、文化や価値観が激しくぶつかり合う、観客との真剣勝負の場であったのです。
2-4. 人気のストラングラーズTシャツのデザイン
ストラングラーズは、その先進的な音楽性だけでなく、アルバムのアートワークやビジュアルイメージにおいても、非常に高い美意識と独自の世界観を持っていました。
そのため、彼らのバンドTシャツは、単なるファングッズという枠を超え、今日でもファッションアイテムとして高い人気を誇っています。
特にアイコニックで人気が高いのは、以下のようなデザインです。
時代を象徴するバンドロゴ
最もシンプルでありながら、強力なアイデンティティを放つのがバンドロゴをあしらったTシャツです。
独特の角張ったフォントでデザインされた「The Stranglers」のロゴは、一目で彼らのものと分かる象徴的なデザインです。
特に初期のパンク時代を彷彿とさせる、黒地に白文字(またはその逆)というミニマルなデザインは、時代を超えて愛される定番アイテムとなっています。
芸術性の高いアルバムアートワーク
ストラングラーズは、レコードジャケットのデザインが秀逸なことでも知られています。
それぞれの時代の音楽性を象徴するアートワークをプリントしたTシャツは、ファンにとって特別な意味を持つアイテムです。
これらのTシャツは、着るだけでそのアルバムへの愛着や、バンドの特定の時代への思い入れを表現できるため、ファンにとっては単なる衣服以上の価値を持っています。
Tシャツ選びのポイント
ストラングラーズのTシャツは、ヴィンテージ市場でも非常に人気が高く、70年代、80年代の当時のオリジナルTシャツは高値で取引されています。近年ではバンドの公式サイトやライセンスを持つメーカーから様々なデザインの復刻版もリリースされているので、ぜひお気に入りの一枚を探してみてください。音楽だけでなく、彼らが創造したビジュアルの世界観からその魅力に触れるのも、素晴らしい体験です。
2-5. あなたが選ぶストラングラーズの最高傑作は?
ここまでストラングラーズの歴史と音楽性の変遷を辿ってきましたが、結局のところ「最高傑作はどれか」という問いに対する唯一の答えは存在しません。
それは、彼らが常に変化し続け、それぞれの時代で異なる頂点を極めてきたからです。
この記事の最後に、あなたが自身にとっての最高傑作を見つけるためのポイントをまとめます。
✔︎ ストラングラーズのバンド名は「絞首刑執行人」を意味しその攻撃的な姿勢を象徴する
✔︎ メンバーは元生物学者や武道家など異色の経歴を持つインテリ集団であった
✔︎ ボーカルは知的なヒュー・コーンウェルと情熱的なJ.J.バーネルが分担した
✔︎ 初期3部作はパンクの衝動と知性が融合した攻撃的なサウンドが特徴
✔︎ 『No More Heroes』は反英雄主義を掲げた時代を象徴する歴史的な名盤である
✔︎ 『Black and White』は多くの批評家からパンクの金字塔と評されている
✔︎ 中期以降は音楽性を大きく変化させシンセを多用した耽美的なユーロロックへと移行した
✔︎ 実験的なコンセプトアルバム『The Meninblack』は彼らのキャリアで最大の問題作とされる
✔︎ 『Golden Brown』はチェンバロとワルツのリズムを取り入れたバンド最大のヒット曲となった
✔︎ バンドは常に同じスタイルに留まることを良しとせず進化と変化を恐れなかった
✔︎ 1979年の初来日公演はその過激なパフォーマンスから数々の伝説を残した
✔︎ 彼らにとってライブは観客との対峙を重視する真剣勝負の場であった
✔︎ 最高傑作は初期のパンク期か後期の耽美派期かでファンの評価は大きく分かれる
✔︎ 各アルバムが異なる魅力を持っているため時代を追って聴き比べる楽しみがある
✔︎ 最終的にどのアルバムを最高傑作と感じるかはあなた自身の感性次第である
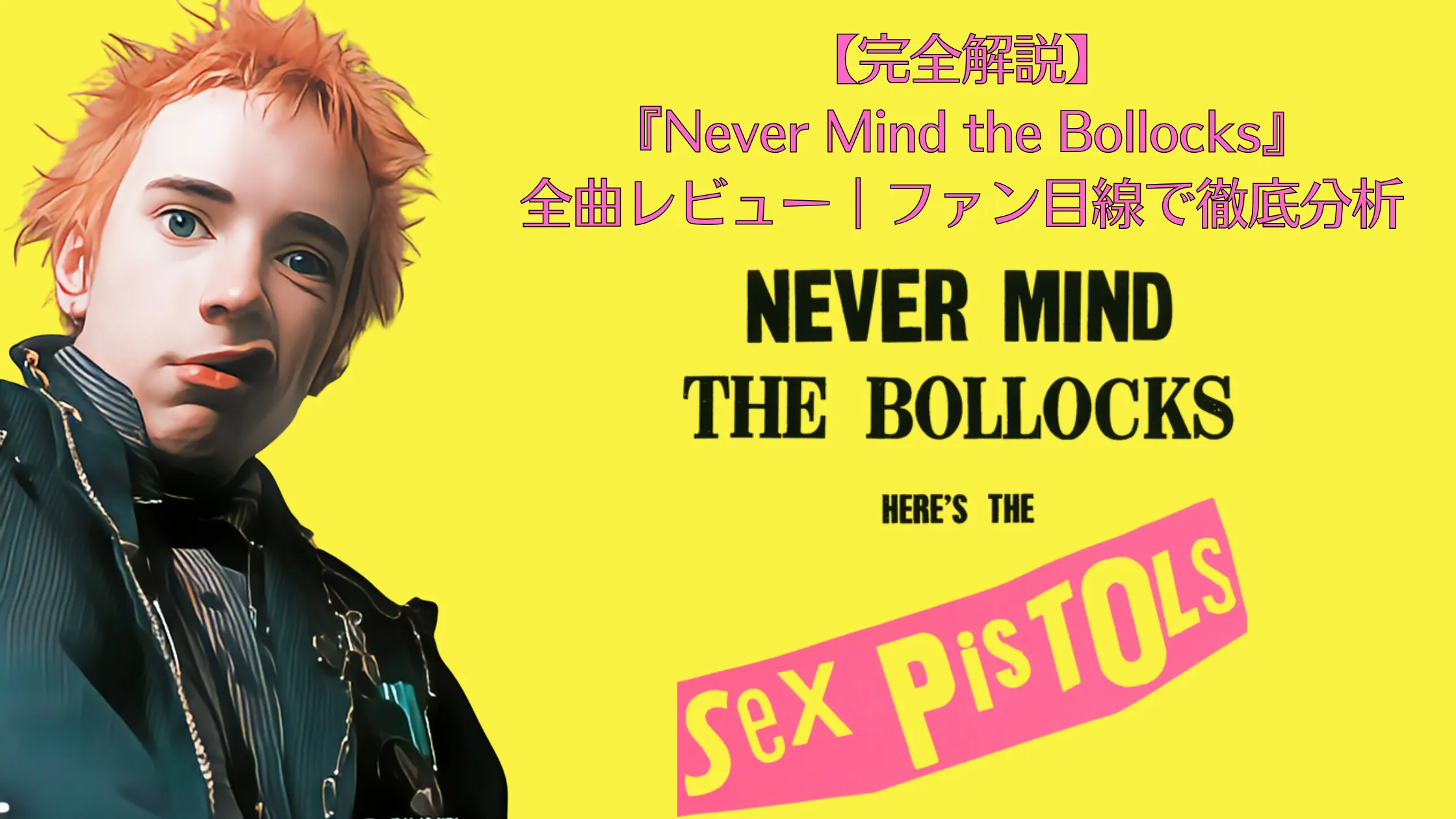
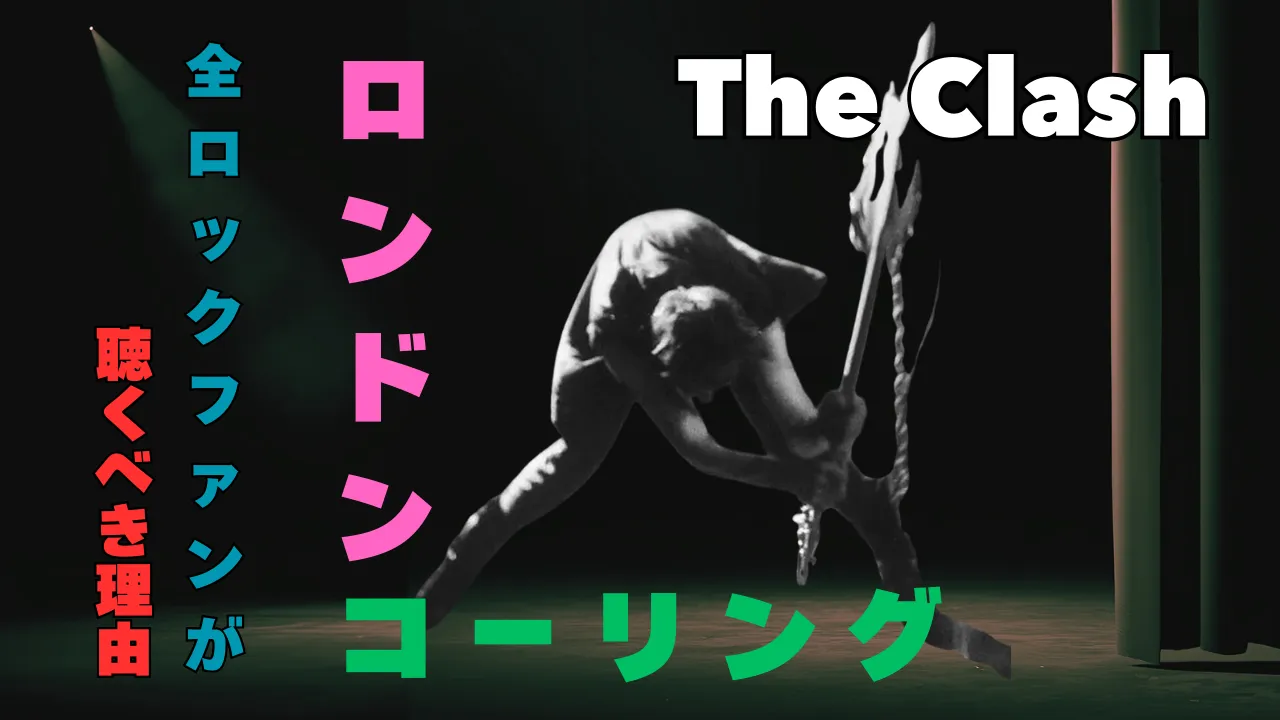
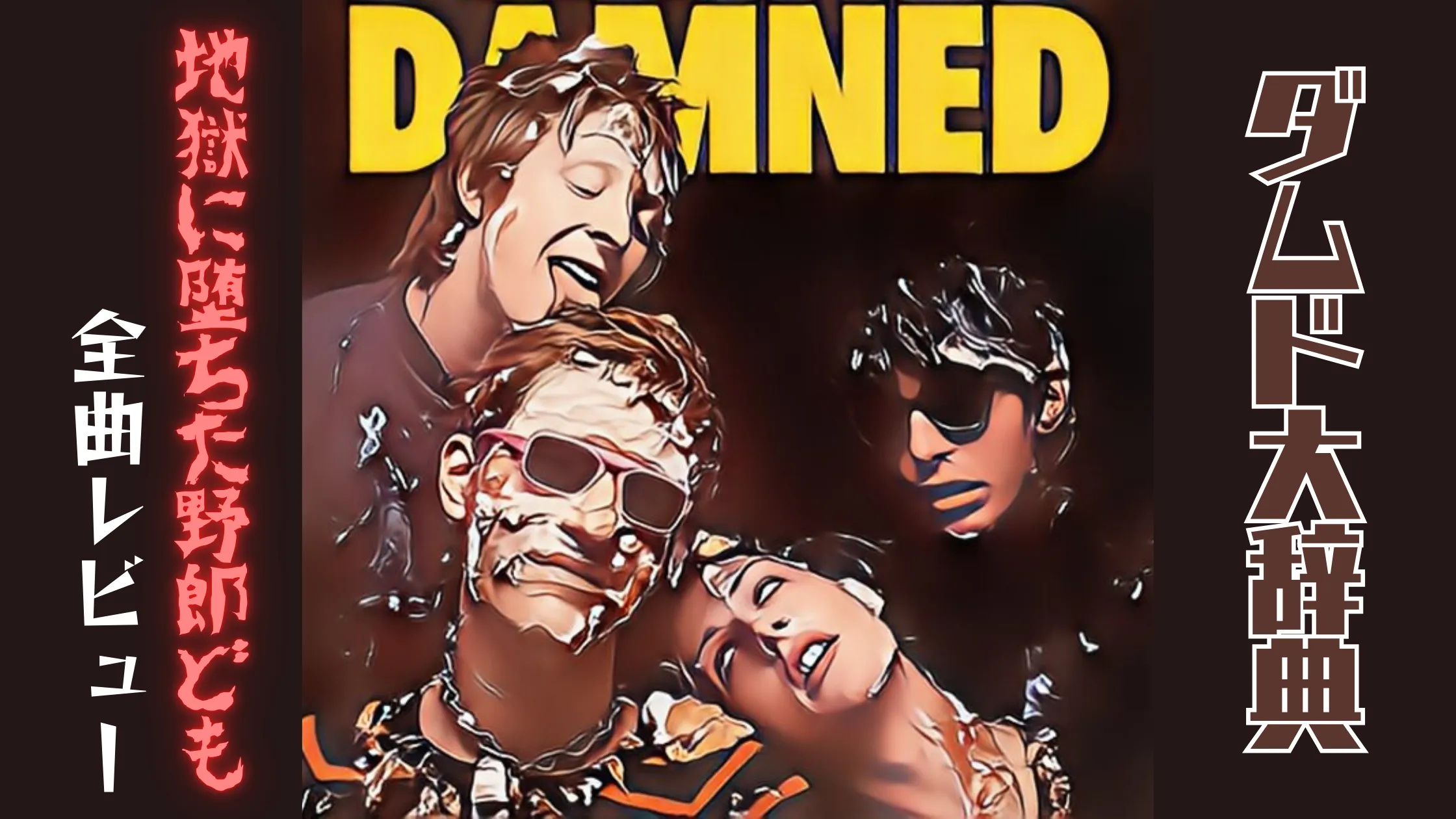
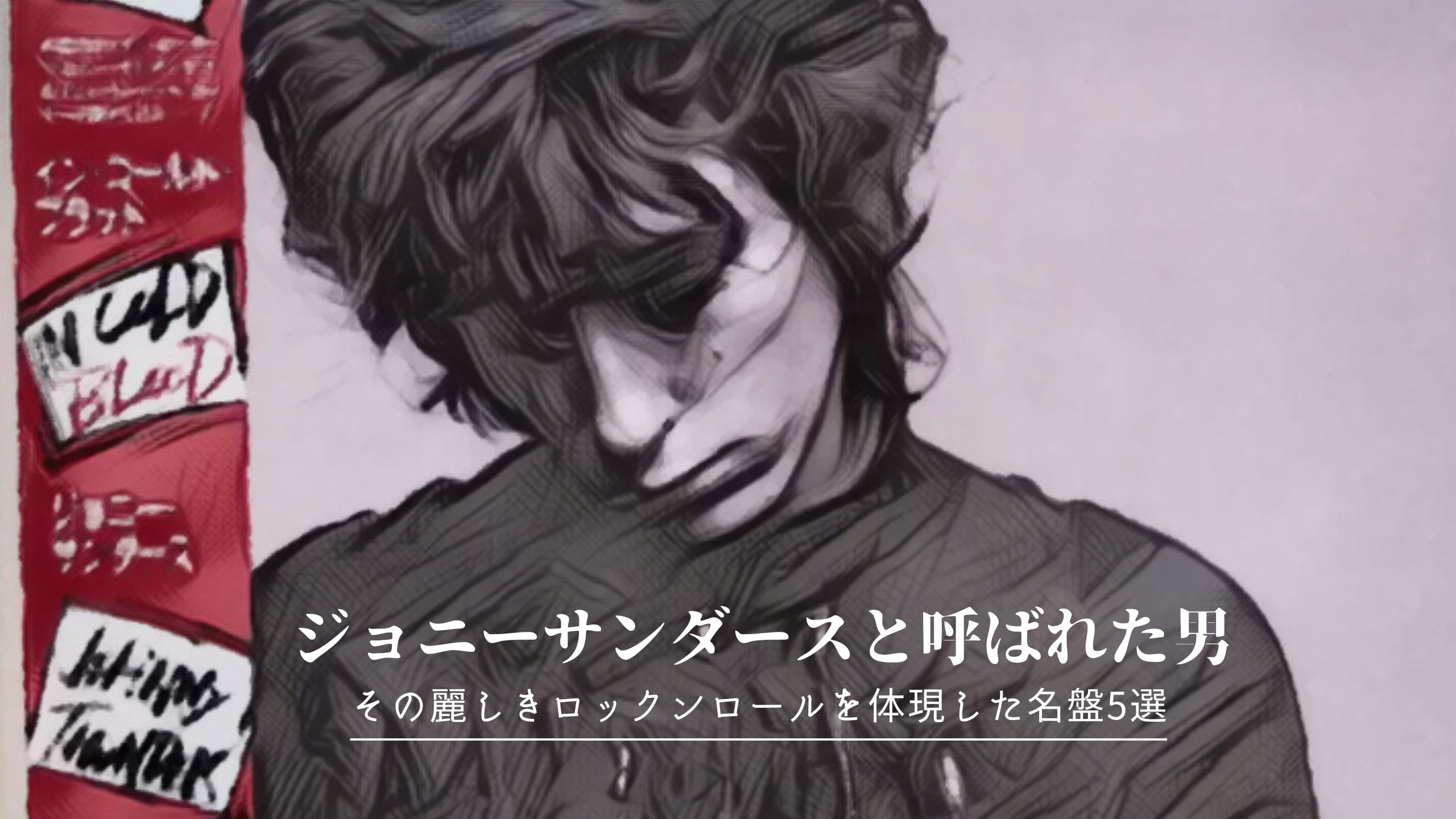
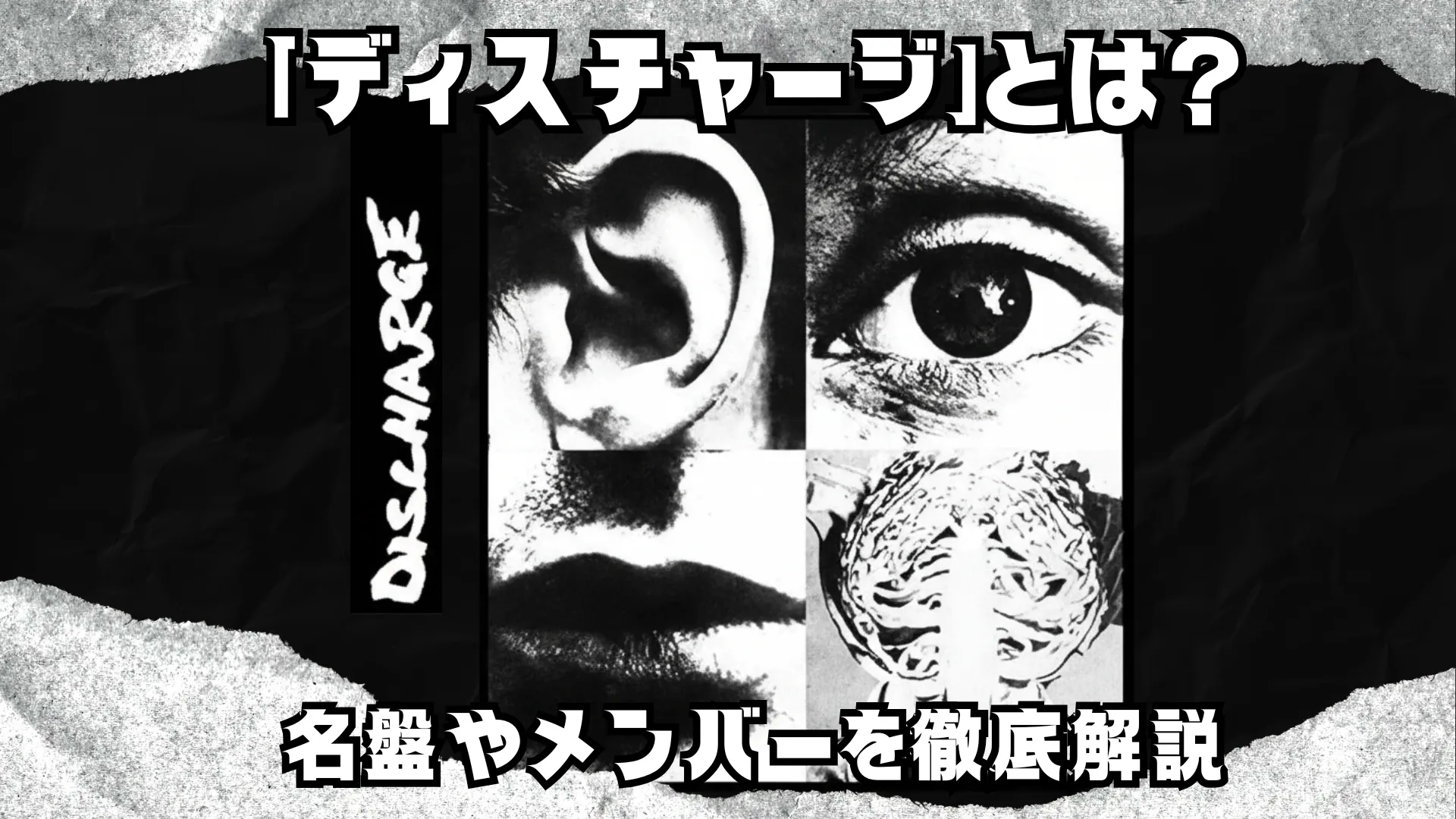

【人生の初期衝動】
「彼らは体制を拒否した。しかし、現実の生活は続く。『反体制』を貫くための現実的な財産形成はこちらで確認できます。」
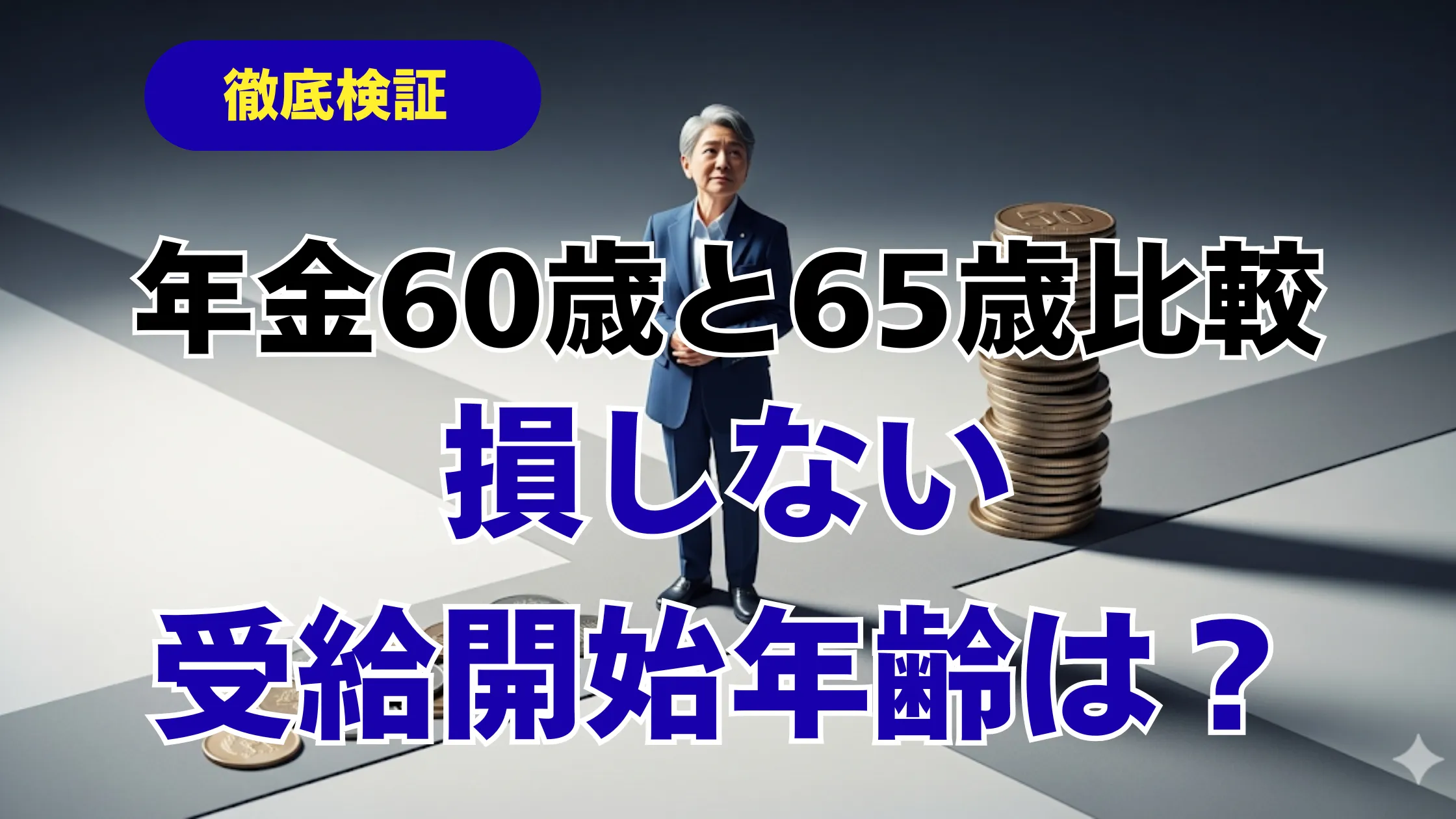

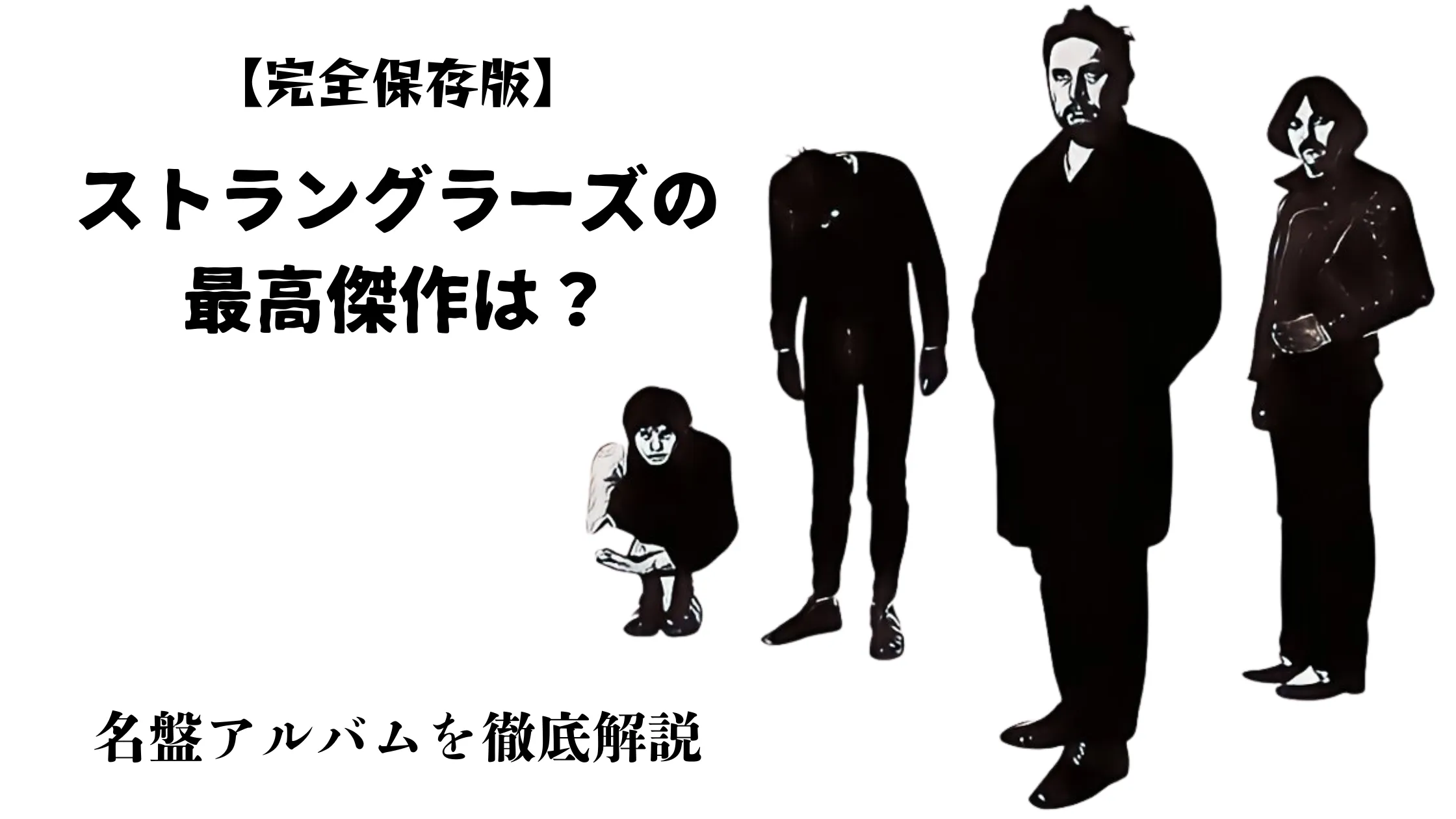





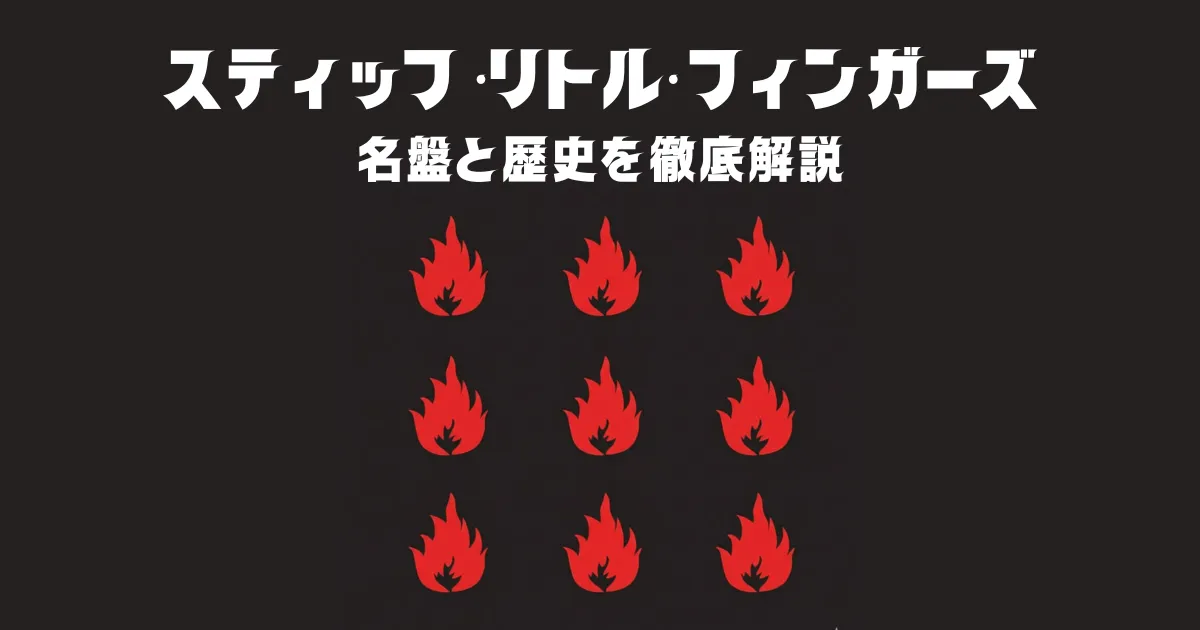
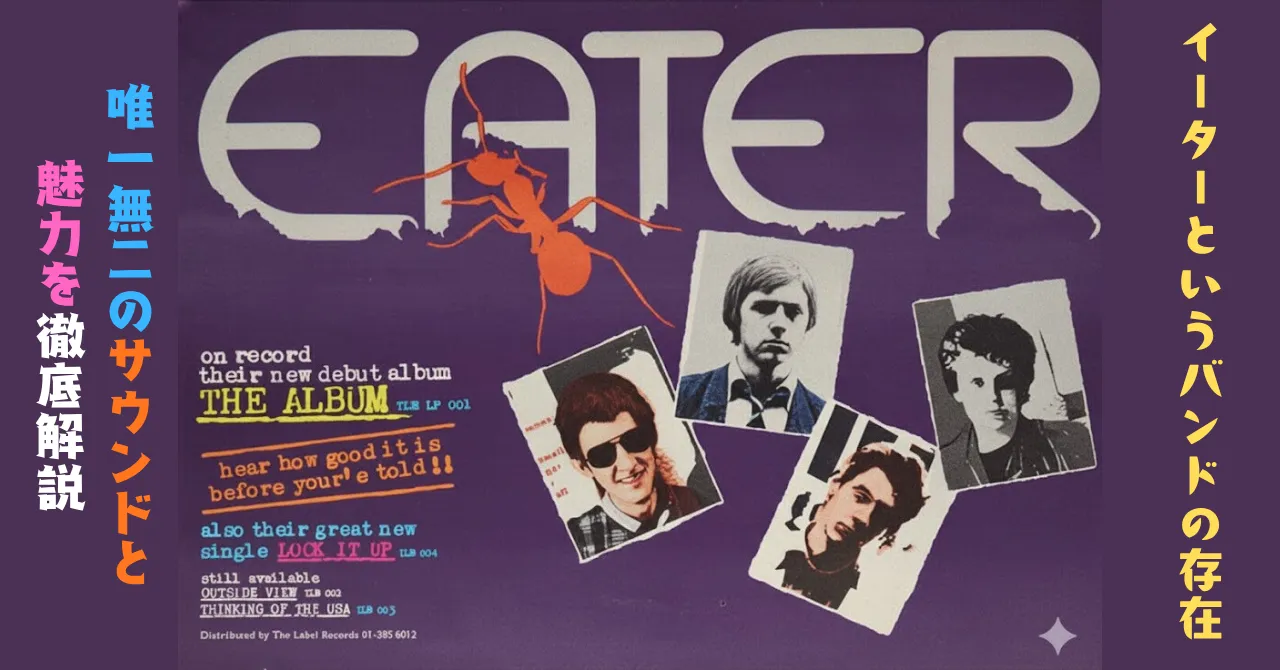
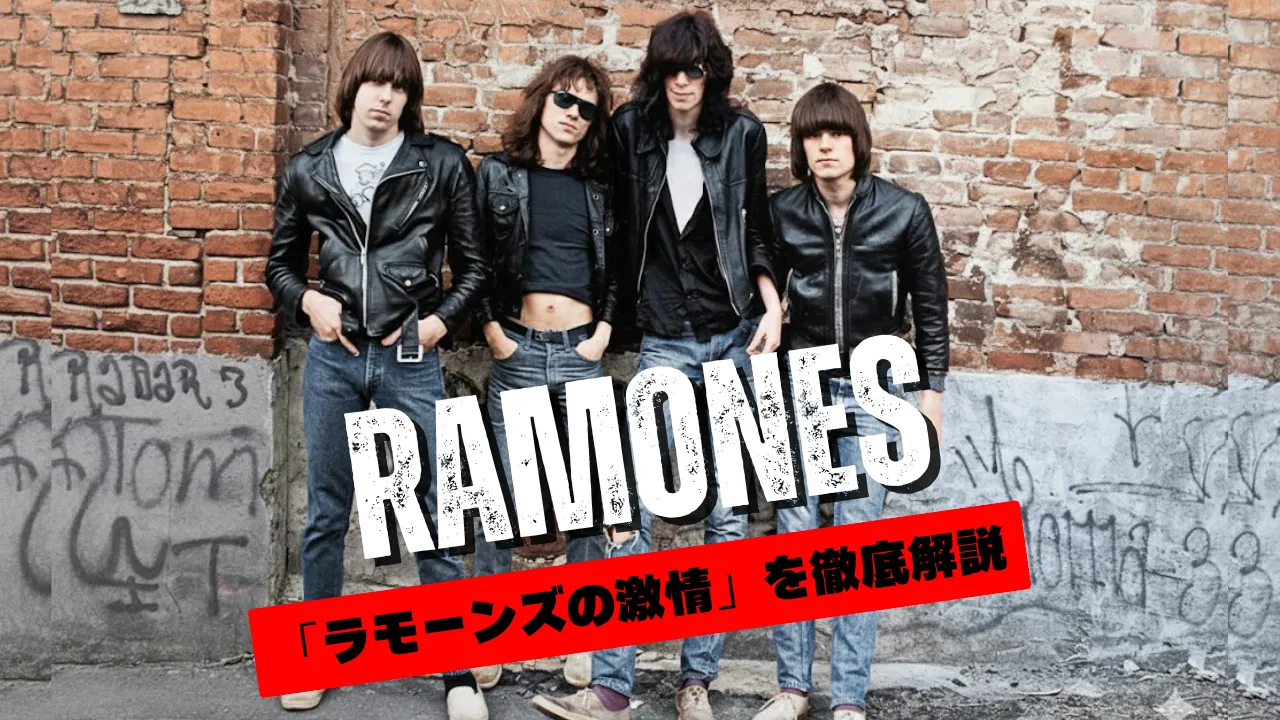
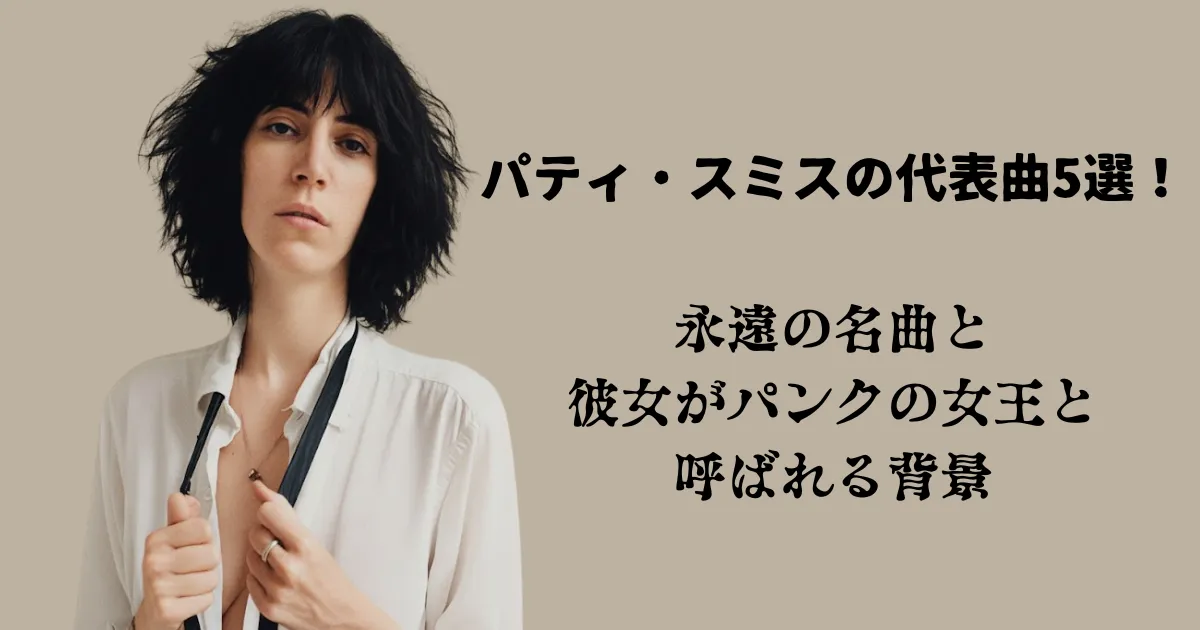

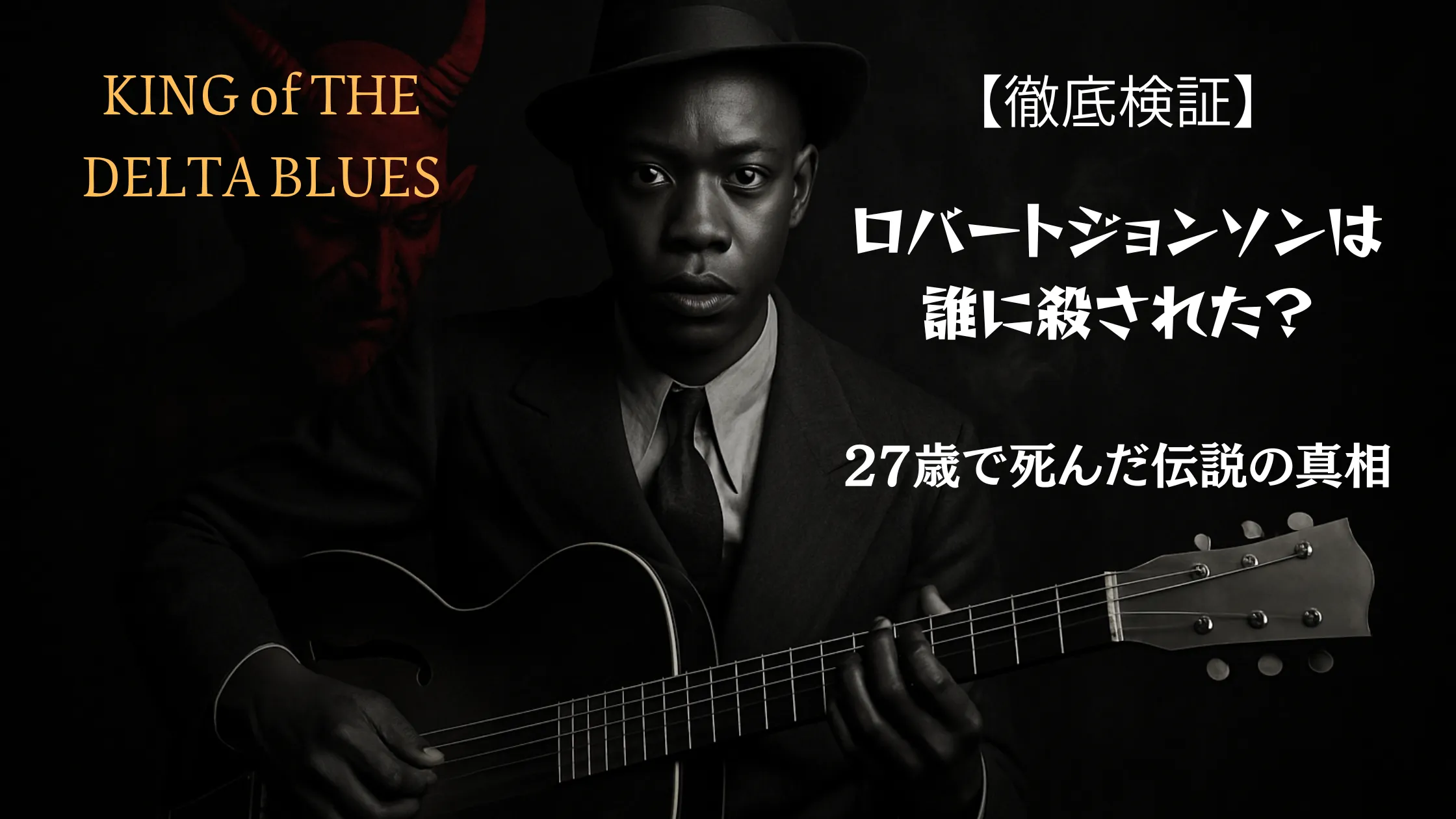

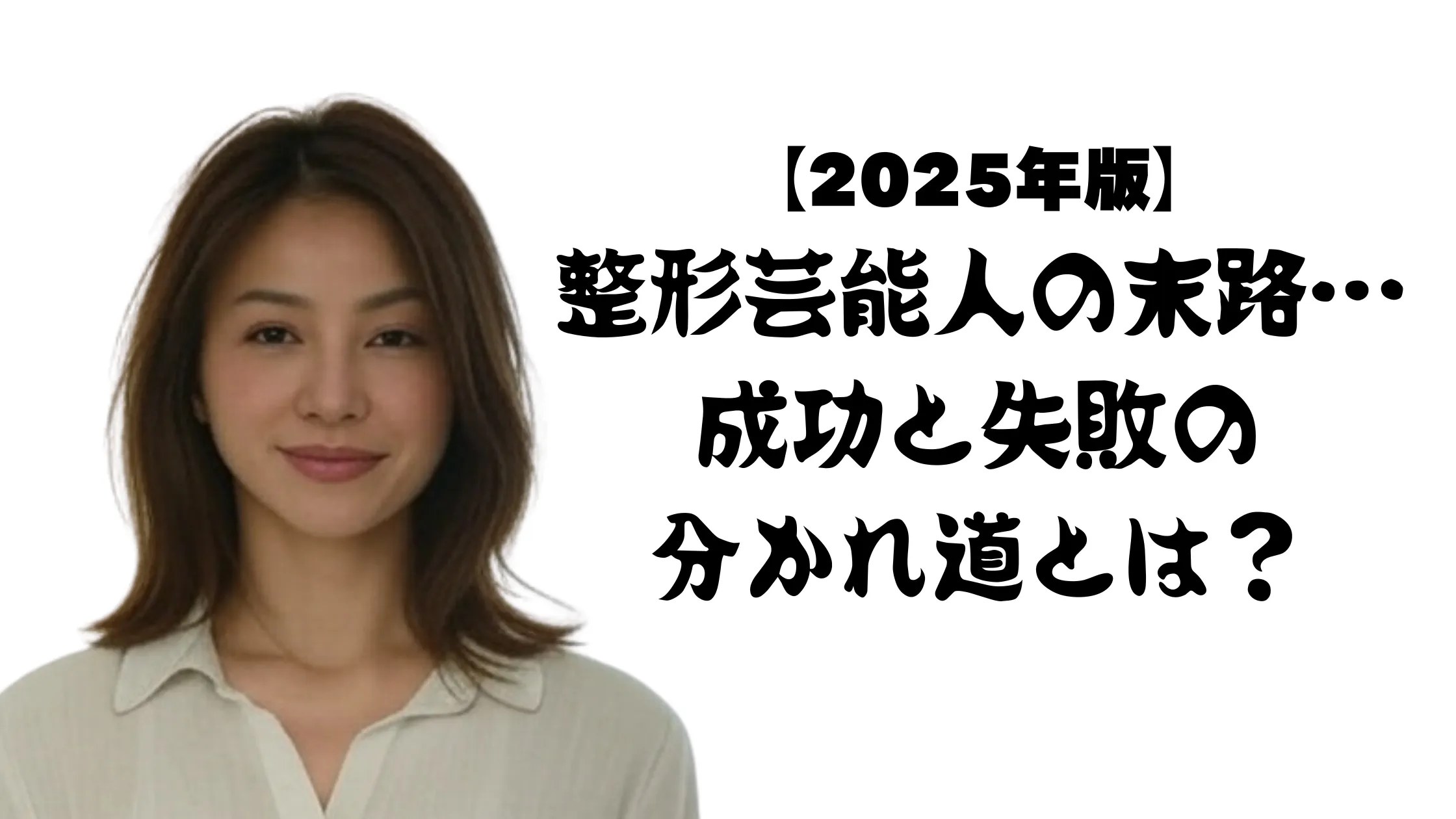





コメント