こんにちは。ジェネレーションB、運営者の「TAKU」です。
家で楽器を弾いていたら、突然ピンポンが鳴って「音がうるさい」と苦情が…。
考えただけでも冷汗が出ますよね。
マンションや賃貸アパートでピアノや他の楽器を演奏するとき、この「楽器 騒音 苦情」の問題は避けて通れません。
「どれくらいの音ならセーフ?」「もし苦情が来たら、謝罪はどうすれば?」「管理会社に相談してもダメなら警察を呼ぶべき?」など、悩みは尽ないと思います。
最悪、裁判や慰謝料なんて話になったら…と不安になりますよね。
この記事では、そんな楽器の騒音問題について、法的な基準はどこにあるのか、そして具体的な防音対策、万が一苦情を受けた時の対応まで、私なりにしっかり調べてまとめてみました。
演奏する側も、悩まされる側も、円満に解決するためのヒントを探っていきましょう。
この記事でわかること
- 騒音とされる法的なデシベル基準と裁判例
- 「楽器可」物件の落とし穴とチェック点
- 苦情を受けた時の正しい謝罪と対応ステップ
- すぐにできる防音マットから防音室導入の選択肢
1. 楽器の騒音苦情、その音は違法?
まず気になるのが、「どこからが法的にアウトなのか?」ってことですよね。
練習したい気持ちと、近所迷惑かもという不安の間で揺れ動くのは辛いものです。
感情論じゃなく、法律や過去の裁判がどう判断しているのか。その「境界線」をしっかり探ってみます。
1-1. 騒音の基準、デシベルで知る

「うるさい」って、結局は個人の感覚じゃん?と思いがちですが、一応、国が定めた「環境基準」という公的な目安があります。
これは環境基本法という法律に基づくもので(出典:環境省「騒音に係る環境基準について」 )、行政が公害対策を進める上での「目標値」です。
これ自体に個人の行動を直接縛る法的拘束力はありませんが、後の裁判などで「我慢の限度」を判断する上で、めちゃくちゃ重要な参考値になります。
一般的な住宅地だと、こんな感じの基準になっています 。
- 昼間(午前6時~午後10時):55デシベル(dB)以下
- 夜間(午後10時~翌午前6時):45デシベル(dB)以下
驚きなのが、人が「うるさい」と感じ始めるのがだいたい50dBくらいからと言われていること。
つまり、昼間の基準値55dBって、私たちが「ちょっと、うるさいかも」と感じるラインとほぼ同じなんですよね…。
法律の基準って、私たちが思うよりずっと静かなレベルなんです。
じゃあ、私たちが練習する楽器の音って、一体どれくらい出てるんでしょうか?
| 楽器の種類 | 最大音量(目安) | 身近な音との比較 |
|---|---|---|
| チェロ | 最大 87dB | 騒々しい工場の中 |
| ピアノ | 80~90dB | 人の大声(90dB) |
| ヴァイオリン、ギター | 最大 90dB | 犬の鳴き声(90-100dB) |
| フルート | 最大 92dB | 騒々しい工場レベル |
| トランペット | 最大 100dB程度 | 電車が通る時のガード下 |
…いや、もう、基準値(55dB)を余裕でブッちぎってます 。
ヴァイオリンなんて、演奏者が難聴になりやすいって言われるくらい、耳元で工場レベルの騒音を聴き続けてるわけです。
しかもデシベルって対数なので、3dB違うと音量は1.4倍 になります。
55dBと90dBの差は、エネルギーで言えば3,000倍以上。
防音対策なしで弾いたら、そりゃ苦情が来るよな、と納得せざるを得ない数字ですね。
音の「種類」にも注意!
この基準値はあくまで行政上の「目標」で、これを超えたら即アウト(違法)ってわけじゃないです。
でも、次の「受忍限度」を判断する上で、めちゃくちゃ重要な参考値になります。特に注意したいのが音の伝わり方。メロディのような「空気音」だけでなく、ペダルを踏む「ドン!」という振動=「固体振動音」 は、床や壁を伝って響くため、よりトラブルになりやすいんです。
1-2. 裁判で問われる「受忍限度」とは

じゃあ、実際に裁判になったら何が基準になるのか。
それが「受忍限度(じゅにんげんど)」 という考え方です。
簡単に言うと、「社会生活を送る上で、お互い様として我慢すべき限度」ってこと。
この限度を超えた騒音は、「違法な権利侵害」と判断されて、損害賠償や演奏の差止命令が出ちゃう可能性があるんです 。
裁判所が「受忍限度を超えてるか」を判断するときは、デシベルの数字だけじゃなくて、色々なことを総合的に見るみたいです 。
1. 音の大きさや性質
もちろん、音の大きさ(dB)が環境基準(55dB)を超過しているかは、重要な判断要素です 。でもそれだけじゃなく、音の「性質」も見られます。同じデシベルでも、ペダルを踏む「ドン!」みたいな衝撃音や、甲高い金属音、高周波音は、人が不快に感じやすいため、受忍限度を超えやすいと判断される傾向があります 。
2. 発生の時間帯
これは当然ですが、深夜(午後10時以降 )や早朝の演奏は圧倒的に不利です 。みんなが寝ている時間に、「平穏に生活する権利」を侵害する度合いがケタ違いに高くなるからです。
3. 発生の頻度・継続性
年一回のお祭りの音なら我慢できても、毎日毎日、何時間も続く楽器の練習音は、被害者の精神的苦痛が大きくなると評価されます 。一回きりの音よりも、断続的・継続的に発生する音の方が、受忍限度を超えやすいと判断されます。
4. 地域性・場所的状況
騒音が発生している場所が、もともと静かな生活が期待される「閑静な住宅街」なのか、それとも元々騒がしい「商業地域」や「工業地域」なのかも考慮されます 。閑静な住宅街では、当然、我慢の限度は低く(=騒音に対して厳しく)判断されます。
5. 被害の程度(健康被害の有無)
これが決定打になることも。騒音が原因で、被害者が「眠れない」「頭痛がする」となり、不眠症、適応障害 、神経症 などを発症して医師の診断書がある場合、それは騒音が客観的に「受忍限度」を超えていることを示す強力な証拠となります。
ポイントは、たとえ基準値の55dB以下でも、他の要素と合わせて「受忍限度を超えている」と判断されれば違法になる可能性があるってことです 。
逆に、工場や建設工事のように「公共性・社会的価値」が高い活動 は、多少基準値を超えても我慢すべきと判断されやすいですが…残念ながら、個人の趣味としての楽器演奏は、この「公共性」がほぼ認められません。
だからこそ、かなり厳しく見られると思った方がよさそうです。
1-3. ピアノ騒音の判例と慰謝料

「受忍限度」って言われてもピンと来ないかもですが、実際にお金が動いた判例があります。
これを知っておくと、リスクの大きさがリアルに感じられると思います。
例えば、アパートで深夜に歌ったり大声を出したりしたケースでは、上の階の人が不眠症や適応障害になって、加害者に60万円の支払いが命じられています 。
私が一番衝撃だったのは、楽器じゃなくて「子供の足音」のケース。
分譲マンションで、上の階の子供が深夜まで室内を走り回る音(足音)により、下の階の住人に受忍限度を超える被害が生じたとして、なんと約94万円(うち精神的苦痛に対する慰謝料30万円)の賠償が認められたことがあるんです 。
なぜ「子供の足音」がピアノと関係ある?
これ、ピアノ弾く人にとっては他人事じゃないですよね。なぜなら、ピアノのペダルを踏む「ドン!」っていう音や、鍵盤を叩く「カタカタ」っていう音は、まさに子供の足音と同じ「固体振動音」 だからです。
電子ピアノにしてヘッドホンで練習して、メロディ(空気音)は消せても、この「振動」だけは床や壁を伝って階下や隣室に響きやすいんです 。
「子供の足音」という、ある意味「仕方のない」音に対しても約94万円の賠償が命じられたという事実は、「ピアノの振動」なら…と考えると、かなりリアルな金額感かなと思います。
「高価な楽器が買えるくらいの賠償を命じられる」 という警告は、決して大げさじゃないんです。
もちろん、すべての騒音トラブルで賠償が認められるわけではありません。
例えば、保育園の園児の声を「騒音」だとして慰謝料や差止を求めた裁判 では、近隣住民の請求が棄却されたケースもあります。
ただ、これらはあくまで一例です。
具体的な金額や法的な判断はケースバイケースなので、もし本当にトラブルになったら、必ず弁護士などの専門家に相談してくださいね。
1-4. マンションや賃貸の規約を確認
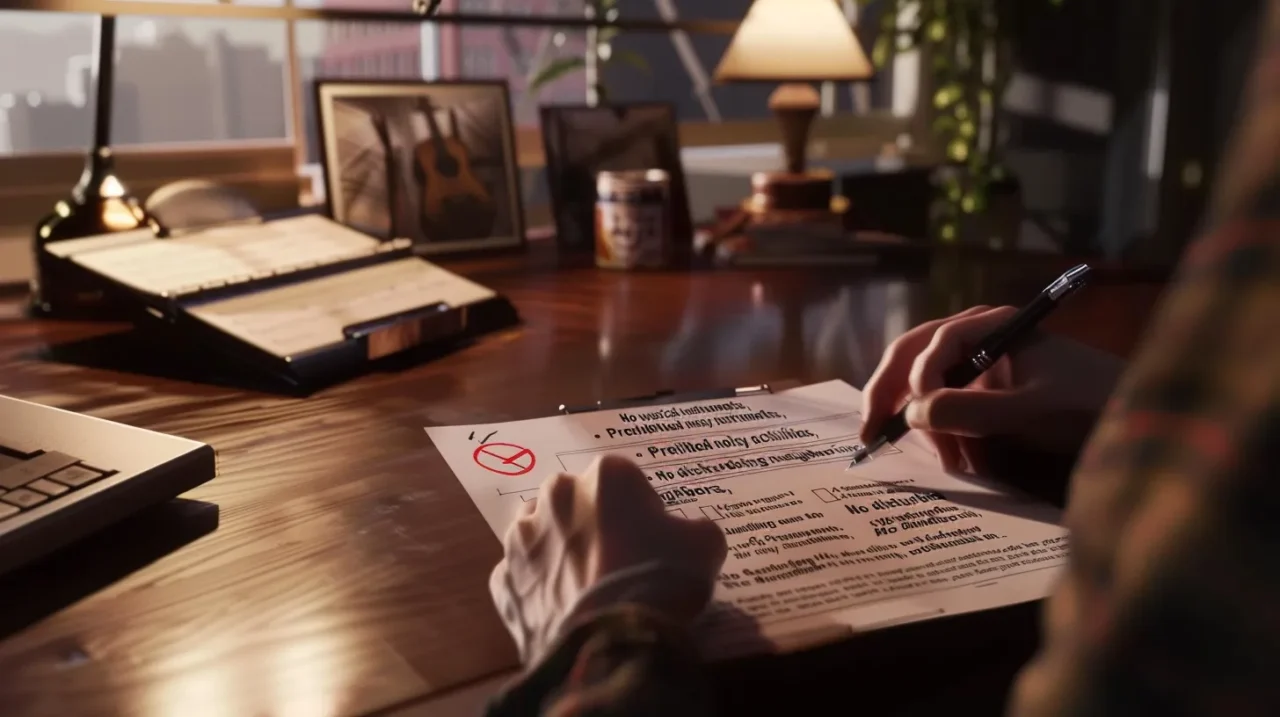
法律や判例も大事ですが、それ以前に、今住んでいるマンションや賃貸アパートの「契約書」や「管理規約」がすべての基本です。
これが一番直接的なルールになります。
契約書に「楽器演奏の禁止」ってはっきり書いてあったら、もうそれは議論の余地なくアウト。
たとえ防音室を入れても、規約違反は規約違反です。
演奏はできません 。
やっかいなのが、「騒音を発生させる可能性のある行為の禁止」とか「他人に迷惑を及ぼす物品の持ち込み禁止」 みたいな、ちょっと曖昧な書き方。
この場合、入居時はOKだったとしても、一度でも苦情が出た時点で「迷惑を及ぼす物品=楽器」「騒音を発生させる行為=演奏」と管理会社や大家さんに認定されて、演奏NGになる可能性が高いと思ったほうがいいです。
この条項は、実質的に「苦情が出たら禁止できる」というカードを大家さん側が持っているようなものなんですよね。
1-5. 楽器可物件と「楽器相談可」の違い

これから引っ越すなら、「楽器可物件」を探すのが大前提ですよね。
でも、ここで「楽器可」と「楽器相談可」の決定的な違い を知っておかないと、マジで詰みます。この二つ、天と地ほど違います。
| 表記 | 意味 | 安心度 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 楽器可 | 明確な条件付きで演奏が許可されている | ◎(安心して演奏できる) | 管理会社も理解があり、他の入居者も演奏者が多い 。選ぶなら絶対これ。 |
| 楽器相談可 | 要相談。基本NGだが交渉の余地あり | △(リスク高い) | 音に不慣れな不動産会社が使っていることも 。入居後に「やっぱりダメ」や即苦情のリスクあり。 |
「楽器可」物件のワナ(=防音物件ではない)
よし、「楽器可」物件を見つけた!これで安心だ!と思うのは、残念ながらまだ早いんです。
一番のワナは、「楽器可」=「防音物件」とは限らない という点。
単に「規約で演奏を許可してますよ」というだけで、建物の構造は普通のマンションと変わらない、なんてケースもザラにあります。
「楽器可なのに苦情が来た…」という最悪の事態を避けるため、契約する前に、必ず管理規約や契約書の細則で、以下の2点を自分の目で確認しましょう。
- 演奏可能時間帯:「平日・休日の何時から何時まで」と具体的に定められているか 。例えば「夜8時以降の演奏は禁止」 など、このルールが自分のライフスタイルと合うかどうかが超重要です。
- 遮音等級(防音性能):建物の防音性能が「D-60以上」 など、具体的な数値(遮音等級)で示されているか。これが明記されている物件は、防音性能に自信がある可能性が高いです。逆に何も書かれていない場合は、防音性能は期待できないかもしれません。
2. 楽器の騒音苦情を解決する対策
じゃあ、具体的にどうすればトラブルを防げるのか。
もし苦情が来ちゃったらどうするのか。
ここからは、演奏する側と、悩まされる側、両方の視点で現実的な解決策を探っていきます。
2-1. まず管理会社や大家へ相談

ここからは、もし自分が「騒音に悩まされている側」になった時の話です。
毎日続く騒音は本当に辛いですが、行動の順番を間違えると、かえって事態が悪化しかねません。
うるさいからといって、いきなり相手の部屋のインターホンを押して「うるさい!」と怒鳴り込むのは絶対にNGです。
相手も感情的になって、「こっちだって気をつけてる!」「楽器可の物件だ!」と反論され、ただの感情的な対立になって解決が遠のきます。
第一歩は、必ず物件の管理者(管理会社や大家さん)に連絡すること 。
彼らには、入居者が快適に生活できる環境を維持する責任(あるいは契約上の義務)があります。
この時、「いつも、うるさくて迷惑してる!」と感情的に伝えるだけじゃダメです。
次の「証拠の記録」で説明する「騒音日記」 を手元に用意して、冷静に、「事実」と「規約違反の可能性」をセットで伝えるのが効果的です。
(伝え方の例)
「〇〇号室の者ですが、上の階(あるいは隣の〇〇号室)の楽器の音で悩んでいます。
こちらに記録があるのですが、管理規約で演奏禁止とされている夜8時 を過ぎた、夜9時~10時頃にピアノのペダルを踏むような重低音が響いてきます。
規約違反の可能性があるので、全戸への注意喚起の貼り紙、または該当の部屋への事実確認と指導をお願いできませんか?」
管理会社が動いてくれない場合
残念ながら、「言ったけど対応してくれない」 というケースは頻繁に発生します。その場合は、次の手を検討します。
- 大家(オーナー)への直接連絡:管理会社がダメなら、建物の所有者である大家さん に直接、管理会社への指導か、大家さんからの直接対応を要請します。
- 自治体(市区町村)の相談窓口:環境課や公害苦情相談窓口などで、アドバイスを受けられる場合があります 。行政から指導が入ることも。
- 内容証明郵便の送付:管理会社や大家に対し、「騒音の事実」「対応の要請」「対応しない場合は法的措置も辞さない」という旨を「書面」で送ることで、相手にプレッシャーをかけ、対応を促します。
2-2. 警察を呼ぶ目安と証拠の記録
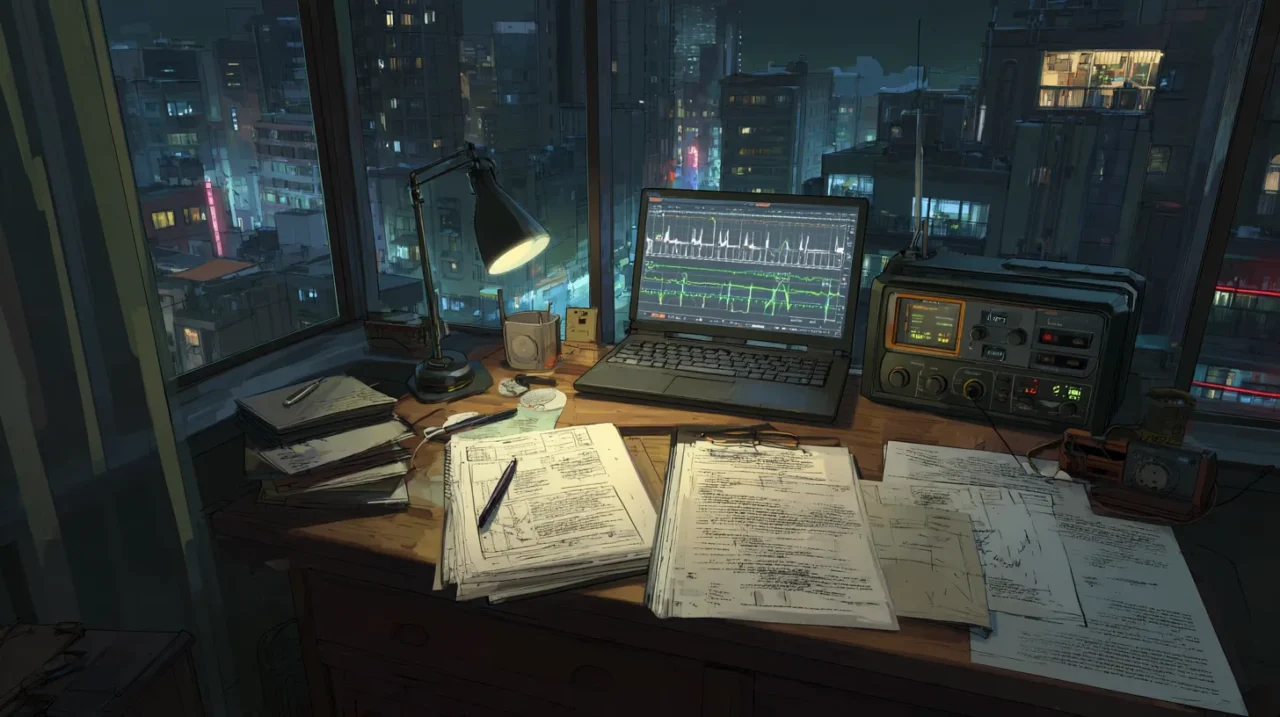
証拠を記録する(最重要)
管理会社への相談や、その先の法的な手続きを考える上で、一番大事なのが「客観的な証拠」です。
「いつも、うるさい」という曖昧な主張は、残念ながら証拠としては扱われません。
最低でも数週間、できれば1ヶ月くらい、以下の内容を「騒音日記」として詳細に記録(ログ)してください 。
- 発生日時:何月何日、何時何分から何時何分まで
- 継続時間:1回あたり何分間か、1日に何回か
- 騒音の内容:「ピアノのメロディ(曲名は不明)」「重低音(ドンドンというペダル音)」「トランペットの高音」「打鍵音(カタカタ)」など、具体的に
- 被害の状況:「テレビの音が聞こえづらかった」「子供が起きてしまった」「読書に集中できなかった」など
これが、後で「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、管理会社や弁護士に相談する際の最強の武器になります。
証拠のレベルアップ:騒音測定業者の活用
騒音日記だけでは相手が「そんなにうるさくないはずだ」としらばっくれる場合、次の手は「客観的な数値」を叩きつけることです。
騒音計のレンタルや測定・分析サービスを提供する専門業者が存在します 。
これらの業者は、高機能な騒音計を貸し出し、測定されたデータを解析し、「何時何分に、何デシベルの騒音が、どのような周波数特性で発生したか」をまとめた法的に有効な報告書を作成してくれます 。
費用は業者によって様々ですが、振動レベル計の貸出と解析報告書作成を含むパックで約10万円(例:税込109,780円) 、一般の環境調査会社では10万円以上 が相場のようです。
「10万円は高い…」と思うかもしれませんが、これは「戦略的投資」です。
裁判での賠償額が60万~90万円 にもなることを考えれば、この10万円の投資で得られる「客観的な報告書」は、動かない管理会社を動かし、最終的に裁判で勝訴し、損害賠償を得るための決定的な「布石」となります。
警察を呼ぶ目安は?
警察への通報(110番)は、かなり慎重になるべき「最終手段」と考えた方がいいです 。
なぜなら、警察には「民事不介入」という原則があり、個人間の騒音トラブルには基本的に介入できないからです。
日中の規約時間内の楽器演奏で警察を呼んでも、「当事者同士で話し合ってください」「管理会社に言ってください」と言われて、即座の解決には至らないことがほとんど。
むしろご近所関係が修復不可能になるリスクがあります。
警察が動いてくれる可能性があるのは、軽犯罪法 が適用されるような悪質なケース。
例えば、深夜(騒音規制法が営業を禁じる午前0時 などが目安かも)に大音量で演奏が続いて、再三の注意を無視し続けるような、社会通念を著しく逸脱したケースに限られるでしょう。
基本はまず管理会社です。
2-3. 苦情を受けたら謝罪とお詫びを
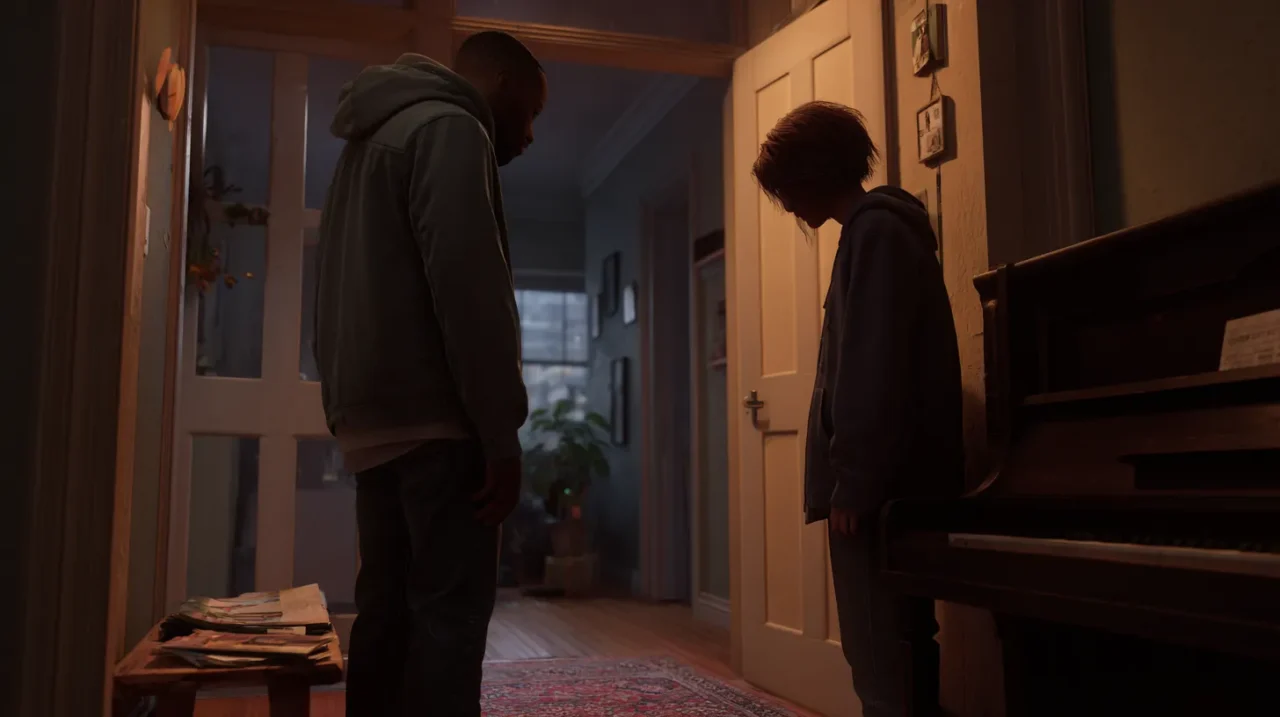
今度は逆に、自分が「演奏者側」で、近隣から苦情を受けてしまった時の対応です。
ピンポンが鳴って(あるいは管理会社から電話が来て)「うるさい」と言われたら、もう心臓バクバクで、頭が真っ白になりますよね。
でも、ここで一番やっちゃいけないのが、「は?こっちは規約の時間守ってるし」「楽器可物件なんですけど?」と反論することです。
たとえ規約を守っていても、相手が「我慢の限度(受忍限度)に達した」というSOSサイン を送ってきたという事実は変わりません。
これを「攻撃」と捉えて反論した瞬間、関係は修復不可能になり、相手は「話し合いは無駄だ」と判断し、法的なステップ(騒音測定や弁護士への相談)に進んでしまう可能性が非常に高くなります。
まずは、工事騒音のお詫び状 にも見られるように、真摯な謝罪が不可欠です。
「この度は、私のピアノ(楽器名)の音でご迷惑をおかけし、本当に申し訳ございません」
と、まずは非を認め、迷惑をかけたという「事実」に対して謝ること。
その上で、「具体的な改善策」をセットで提示するんです 。
口先だけの謝罪は、相手の怒りを増幅させるだけです。
「謝罪」と「具体策」はセットで提示する
(対応例)
「誠に申し訳ありません。
ご指摘を受け、今後は夜8時以降の演奏は一切やめます。
日中も、音が響きにくいように、すぐにピアノ(電子ドラム)用の防振マットを注文しました。
到着するまでは、日中の演奏も控えるようにいたします。本当に申し訳ありませんでした」
このように、「謝罪」と「具体的な行動(時間厳守、物理的対策 )」をセットで伝えることで、相手の感情的な対立を避けて、話し合いのテーブルにつくことができます。
初期対応がすべてを決めると言っても過言じゃないですね。
2-4. ピアノやドラムの防振マット対策

苦情対策として、すぐにできるハード面の対策がマットです。
これは苦情を受ける前、入居と同時にやるべき最低限の対策とも言えますね。
ここで重要なのが、「防音マット」と「防振マット」は似ているようで、役割が全く違うということです 。
「防音」と「防振」の違い
- 防音(遮音・吸音):音色(空気音)が外に漏れるのを減らす対策。トランペットのメロディや歌声など、空気を伝わる音に効果があります。
- 防振:振動(固体振動音)が床や壁に伝わるのを抑える対策。ピアノのペダル音、電子ドラムのキックペダルを踏む「ドン!」という振動 、子供の足音 など、固体を伝わる音に効果があります。
マンションやアパートで最も問題になりやすいのは、メロディそのものよりも、階下や隣室に響く、不規則で不快な「固体振動音」 です。
だから、特にピアノ、電子ピアノ、電子ドラム を設置する場合、必要なのは単なる防音マットじゃなくて、「防振マット」なんです 。
安価なコルクマットや、普通のジョイントマットだと、クッション性はあっても振動を抑える効果(防振性能)はほとんど期待できない可能性があります 。
製品を選ぶときは、「遮音等級」がちゃんと書かれているか 、楽器用(特にピアノやドラム用)として販売されているか、ゴムとフェルトが層になっているような重量のある製品かをしっかり確認するのが大事ですね。
2-5. ヤマハやカワイの防音室という選択

時間帯に気をつけたり 、高性能な防振マットを敷いたりしても、やっぱり楽器の生音(80dB以上 )と、法的な基準値(55dB )の間には、簡易対策だけでは埋めがたい、根本的な音量差が存在します。
ビクビクしながら練習するくらいなら、いっそ「防音室」を導入するのが、演奏者にとっても近隣住民にとっても一番平和で、根本的な解決策かなと思います。
これは「出費」ではなく、安心して演奏する自由と、法的リスクを回避するための「投資」ですね。
主要メーカーと価格帯
日本で手軽に設置できるユニット型防音室といえば、主に2大メーカーです。
- ヤマハ「アビテックス (Avitecs)」:セフィーネNS やアビテックスミニ などのラインナップがあります。
- カワイ「ナサール (Nassale)」:スタンダードタイプ やカスタムタイプ などがあります。
ただ、ネックはやっぱり価格。
新品だと、1.5畳~2.0畳の、まあまあ現実的なサイズでも平気で120万円~140万円以上 します。
なかなかポンと出せる金額じゃないですよね。
でも、諦めるのはまだ早いかも。
中古防音室という最強の投資
私が調べた中で「これだ!」と思ったのが、中古品や展示特価品です。
専門に扱っている業者さんや楽器店を探してみると、例えばこんな価格で出ています。
- ヤマハ アビテックスミニ(1.2畳 / Dr-35)の中古品が約26万円
- ヤマハ セフィーネ(0.8畳 / Dr-40)の中古品が約42万円
- カワイ ナサール(2.0畳 / Dr-35)の店頭展示特価品が約81万円
どうでしょう? 新品に比べれば、かなり現実的な価格感じゃないですか?
ここで、さっきの判例を思い出してください。
騒音トラブルの賠償額は60万円~94万円 でしたよね。
つまり、中古の防音室を買う費用(例:26万円 )は、裁判で一回負けた時の賠償額(例:60万円 )より安いんです。
こう考えると、法的リスクを回避し、何より近隣に配慮しながらも自分の演奏の自由を確保するための「投資」として、中古防音室は極めて合理的で賢明な選択肢かなと思います。
価格はあくまで私が見た時点での一例です。中古品や特価品は一点モノなので、タイミングによって在庫や価格は変動します。
また、実際の費用には本体価格だけでなく、別途、運送料や組立設置費 が数万円~十数万円かかるのが普通です。
購入の際は、必ず専門の業者さんに見積もりを取って、総額を確認してくださいね。
2-6. 楽器の騒音苦情、円満解決の道

「楽器 騒音 苦情」の問題って、結局は「演奏する自由」や「音楽を楽しむ権利」と、「静かに、平穏に生活する権利」という、どちらも大事な権利がぶつかり合う、根深い問題なんですよね。
どちらか一方が100%我慢するのではなく、お互いが納得できる着地点を見つける努力が不可欠です。
演奏者側が持つべき「義務」
演奏する側は、まず「自分は悪くない」という考えを捨てることかなと思います。
自分の楽器が、法的基準をはるかに超えるデカい音 を出しているという客観的な事実と、特にメロディではなく「振動音」 が近隣トラブルの最大の火種であるということを、深く自覚するのがスタートラインです。
その上で、時間帯への配慮 はもちろん、防振マットや、最終的には防音室といった「音を漏らさない」ための積極的な対策を講じる「義務」がある、と認識を改める必要があるかなと思います。
被害者側が取るべき「冷静な行動」
一方で、苦情を言う側(被害者側)も、感情的になって怒鳴り込むという行動は、解決を遠ざけるだけです。
まずは冷静に「記録」 を取ること。
そして、管理会社 を通じて「規約」と「事実」に基づいて改善を求めるという、冷静なステップを踏むことが大事ですね。
それでもダメなら、騒音測定 という客観的な証拠を揃えて、法的な「受忍限度」 を超えていることを立証する準備を淡々と進める。
これが、感情論ではない、現実的な解決への道です。
お互いが、感情論ではなく、法律の基準 や裁判のリスク といった「客観的な事実」を共通の物差しとして理解し、誠実に対応すること。
それが、泥沼の対立を避け、お互いが納得できる道を見つける唯一の方法かなと思います。
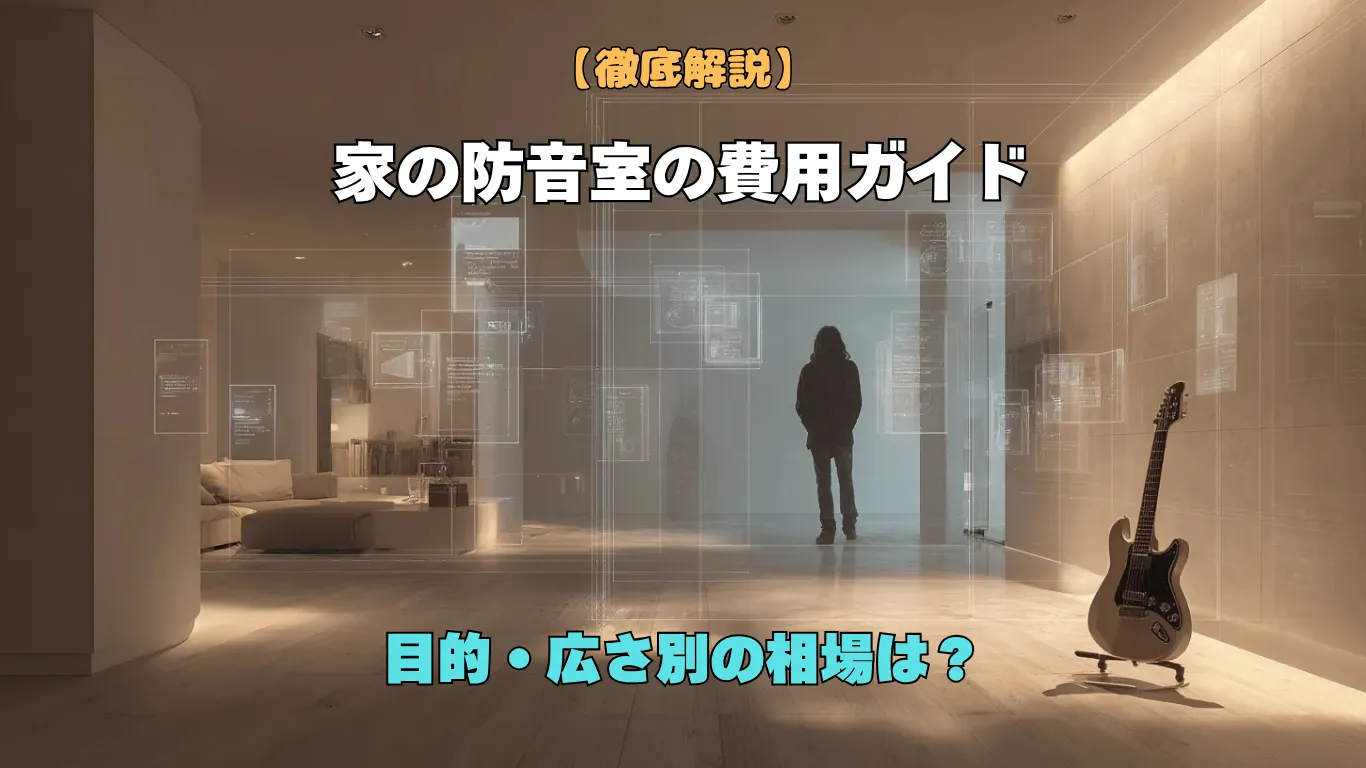
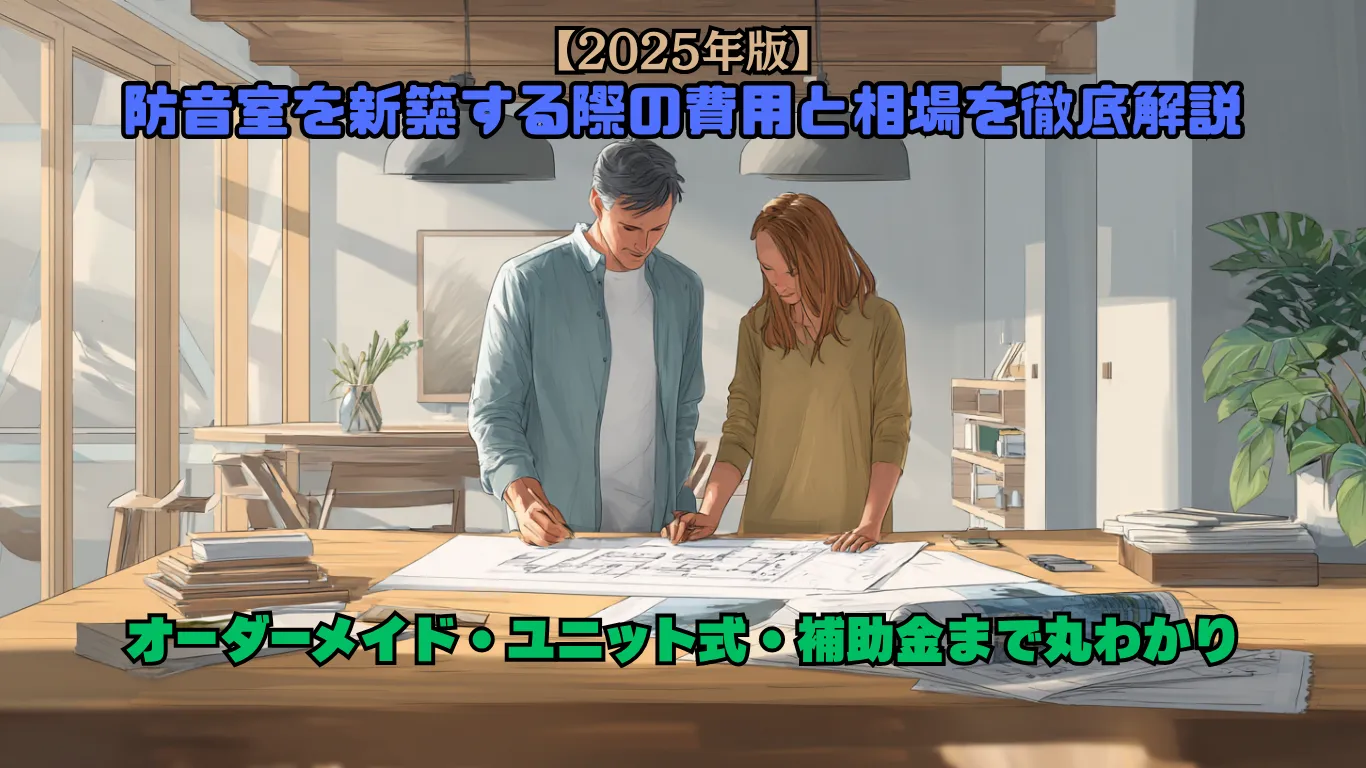

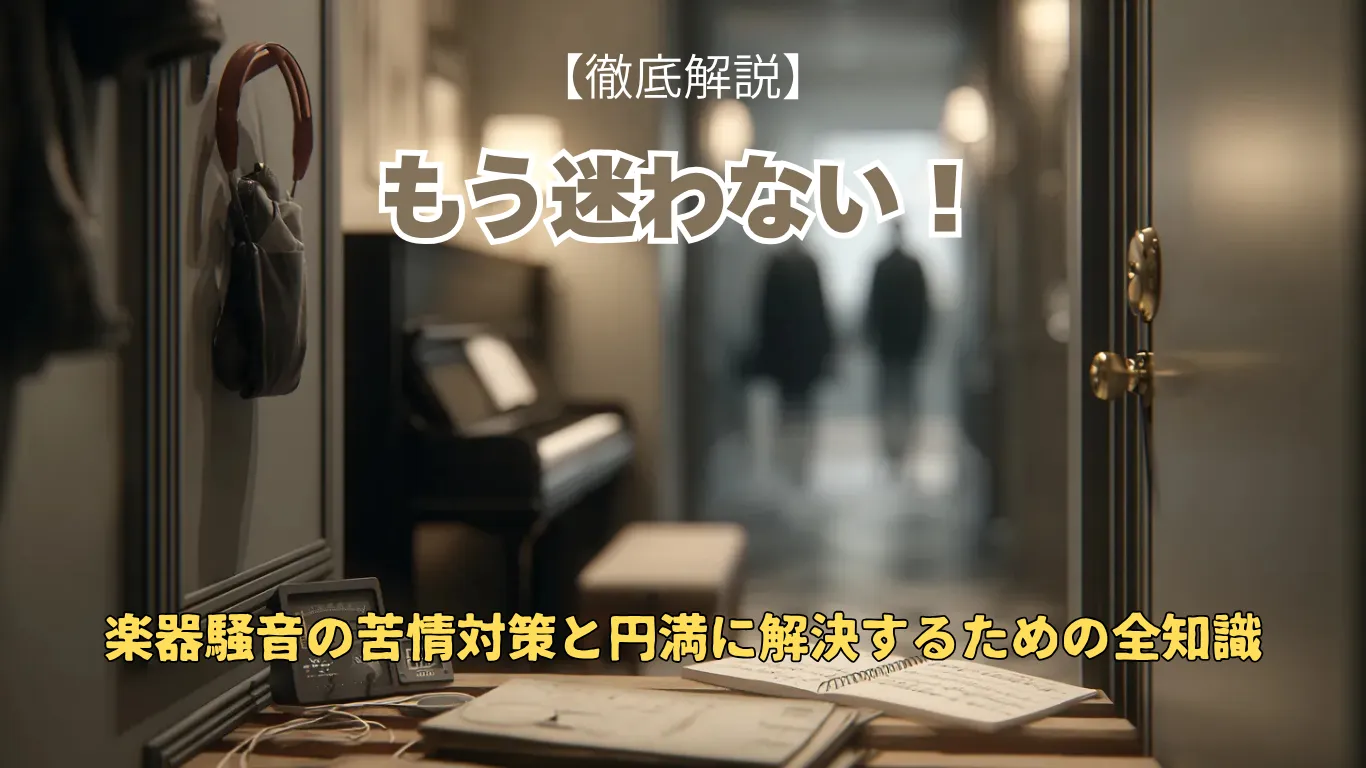
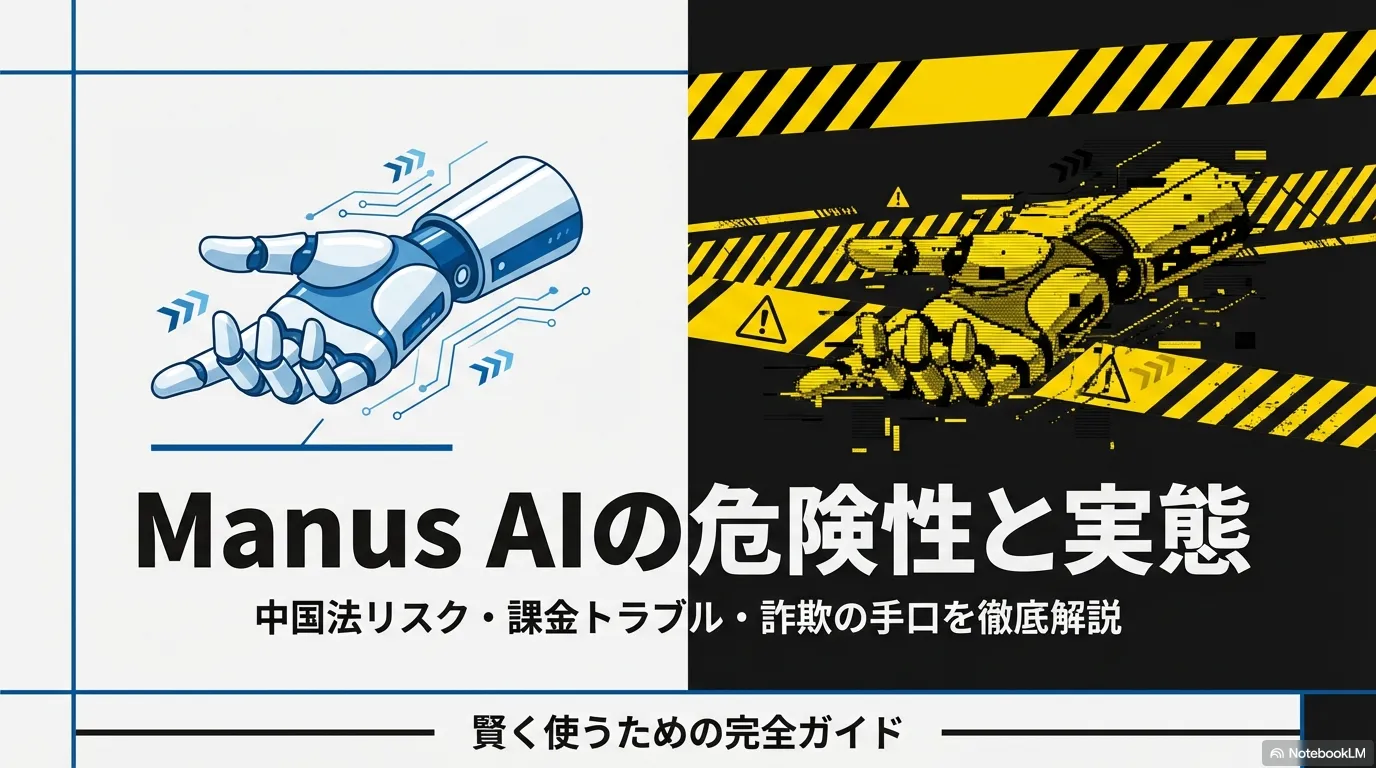
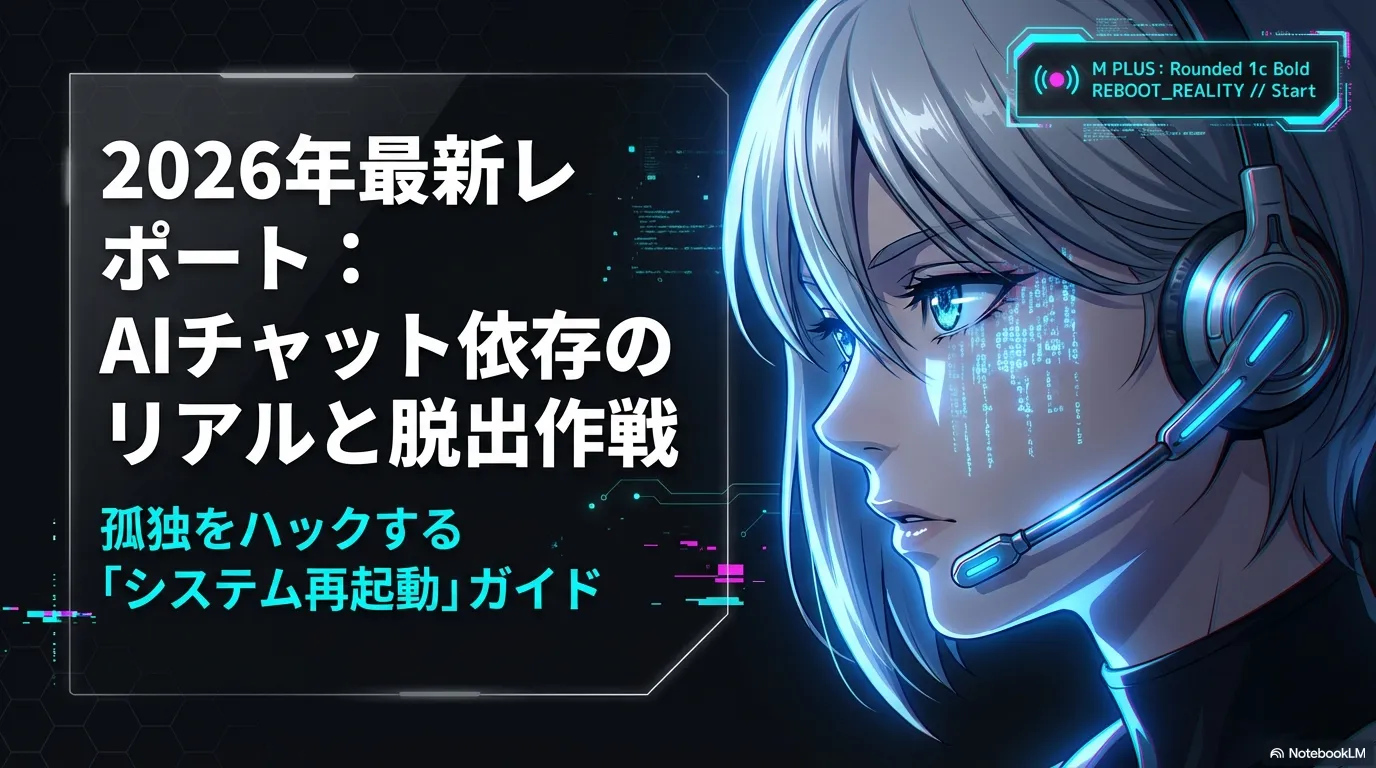
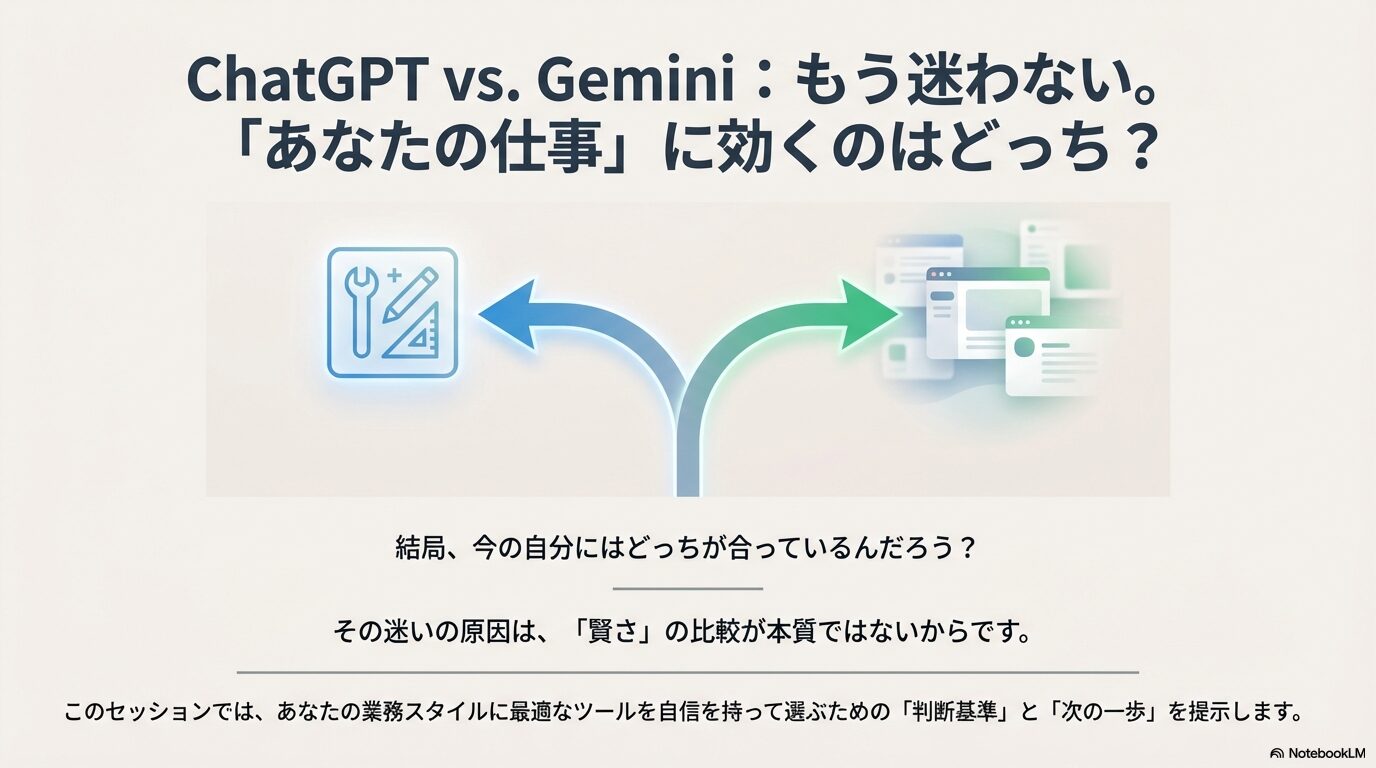

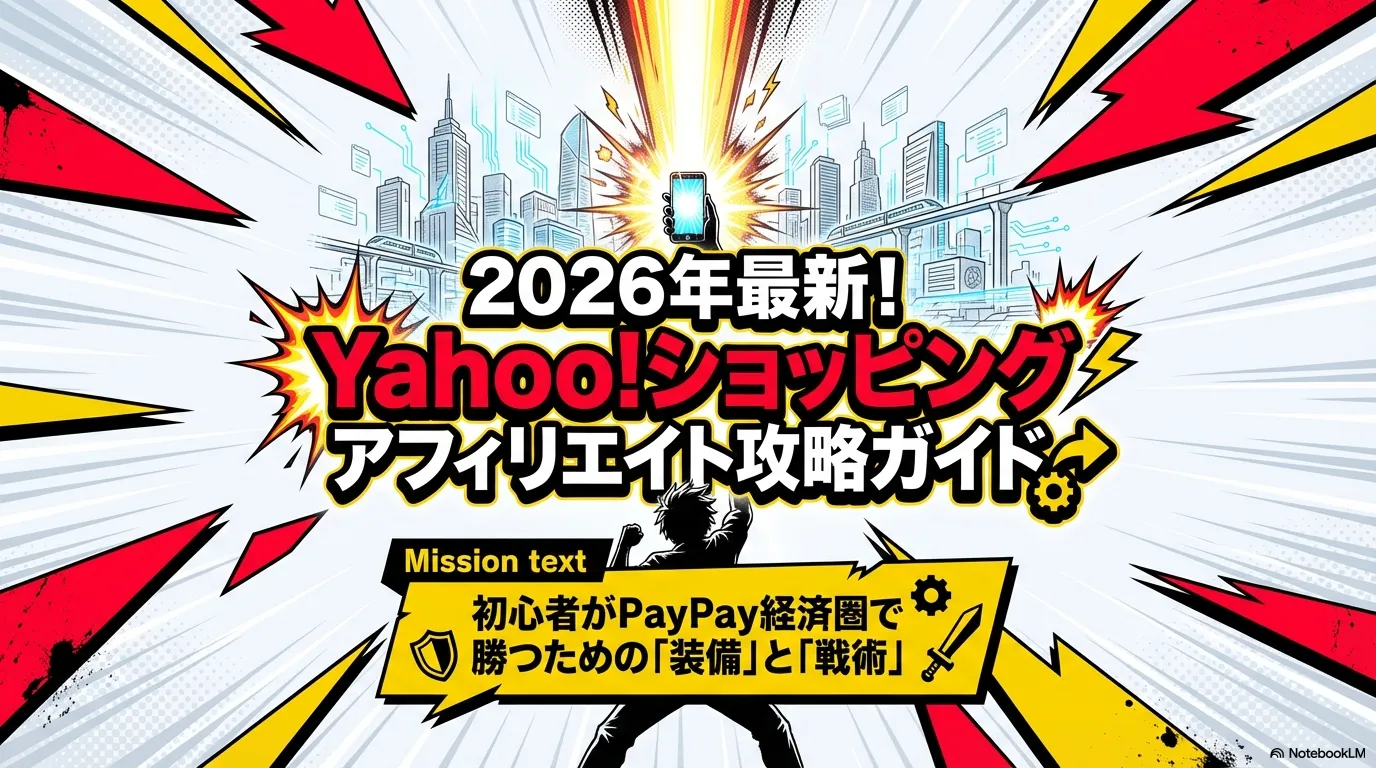

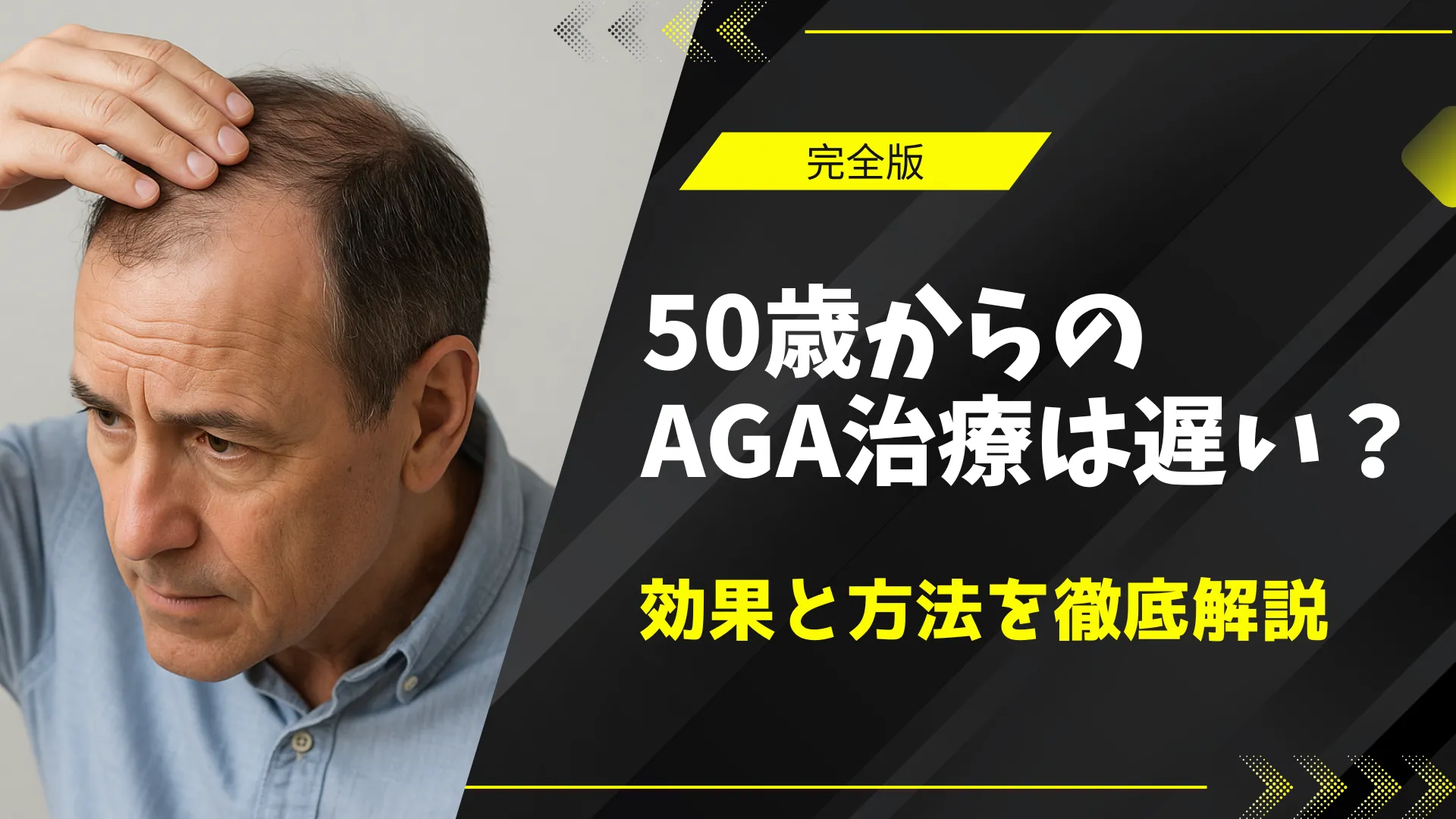





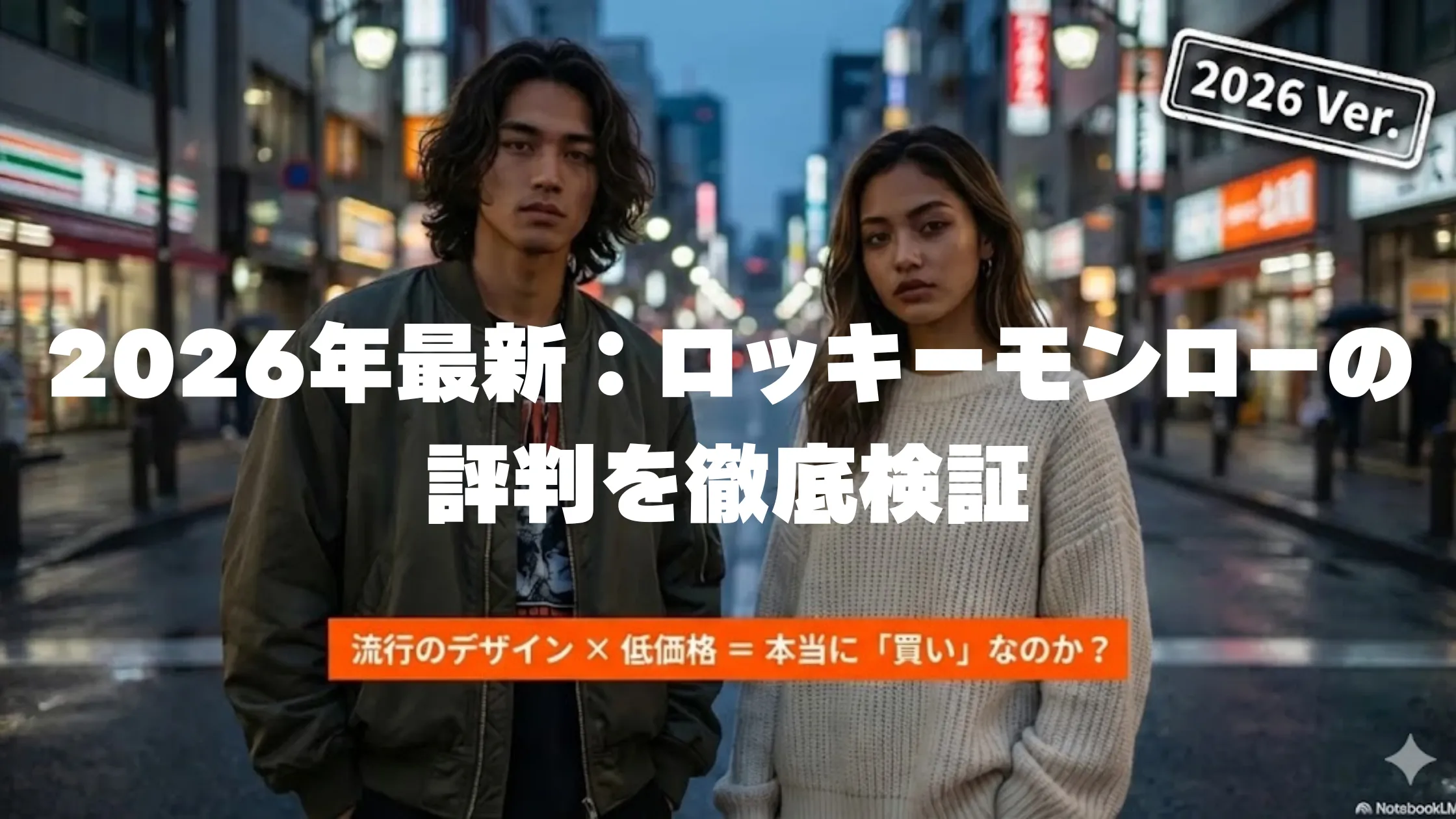
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] […]
[…] […]