こんにちは。ジェネレーションB、運営者のTAKUです。
Turnstileメンバーについて検索しているあなたは、おそらく今のメンバー構成や誰が脱退したのか、Turnstileメンバー年齢や出身、さらには女性ギタリストとして話題のTurnstileメグメンバーのことまで、一気に整理して知りたいところかなと思います。
SNSや断片的なニュースを追っているだけだと、Turnstileメンバー現在の編成がよく分からなかったり、Turnstileメンバー脱退の背景が噂レベルの情報とごちゃまぜになってしまって、モヤモヤしますよね。
しかも『Glow On』の頃からハマった人と、『Never Enough』から入った人とでは、「どの時期のTurnstileをスタンダードと感じているか」が違うので、メンバーの入れ替わりや時期ごとの雰囲気が頭の中でごちゃっとしがちです。
アルバムを聴くたびに「このリフ誰が弾いてるんだっけ?」と気になってしまうことも多いはずです。
この記事では、ハードコア好きの中年世代として長年Turnstileを追いかけてきた私が、最新作『Never Enough』期のラインナップを軸に、メンバーのプロフィール、年齢と出身、過去の脱退劇、そしてメグが加わった現在の姿まで、できるだけ分かりやすく整理していきます。
ライブで飛び跳ねる若いキッズはもちろん、家でレコードをじっくり聴きながらTurnstileのメンバーの背景まで深掘りしたい大人世代のあなたにも、しっかり届く内容にしていきますね。
読み終わるころには、「この曲はこの人のこういうバックグラウンドが出てるんだ」と、音と人がきれいにつながって見えてくると思います。
この記事でわかること
- Turnstileメンバーの現在とこれまでの変遷を整理して理解できる
- 主要メンバーの年齢や出身、キャリア背景を把握できる
- 脱退したメンバーとその理由、噂との違いが分かる
- Never Enough期のサウンドとメンバーの役割がつながって見える
1-1. Turnstileのメンバー徹底解説
ここでは、Turnstileメンバーの基本的なプロフィールから、年齢と出身、これまでのメンバー変遷、そして脱退したギタリストやメグ加入の流れまでを一気に整理していきます。
まずは全体像をざっくり掴んでから、気になるポイントを深掘りしていきましょう。
特に『Never Enough』期に絞ってみると、バンドとしてのモードチェンジとメンバー構成の変化がぴったりリンクしていて、「ああ、だから今こういう音なんだな」と感じられるはずです。
1-1. Turnstileのメンバープロフィール
まずは、『Never Enough』期のTurnstileのメンバーをざっくり俯瞰しておきましょう。
2025年時点での「コア5人」は以下の通りです。
ここを押さえておくだけで、インタビューやライブレポ、SNSのポストを読んだときの理解度が一気に上がりますよ。
| 名前 | 担当 | おおよその年齢(2025年時点) | 出身・バックグラウンド |
|---|---|---|---|
| Brendan Yates | ボーカル、パーカッション、キーボード | 約35歳 | メリーランド州ボルチモア。Trapped Under Iceのドラマーとしても活動 |
| Franz Lyons | ベース、ボーカル | 約37歳 | ボルチモア周辺。ファンクやR&B色の強いグルーヴが持ち味 |
| Daniel Fang | ドラム、プログラミング | 約35歳 | オハイオ州立大で学びつつ、ボルチモアHCシーンで活動 |
| Pat McCrory | リードギター、バッキングボーカル | 約36歳 | Angel Du$tとの掛け持ちでも知られるギタリスト |
| Meg Mills | リズムギター、バッキングボーカル | 約28歳 | イギリス出身。Big CheeseやChubby and the GangなどUKHCで活躍 |
※年齢はインタビューや公表情報から逆算した一般的な目安です。
ブレンダン:ビジョンを描くフロントマン
Brendan Yatesは、単なるボーカリストではなく、Turnstileというプロジェクト全体の「監督」的な存在です。
歌やシャウトに加えて、パーカッションやキーボードも操り、楽曲の構成やサウンドの方向性を決める立場にいます。
元々は「Trapped Under Ice」でドラムを叩いていたので、リズム感が異常に良く、ボーカルラインもビートの隙間にきれいにハマるのが特徴です。
映像監督としての顔も持っていて、「Glow On」以降のミュージックビデオや、『Never Enough』と連動したビジュアルアルバムでは、そのセンスが爆発しています。
ステージではクールに見える瞬間も多いですが、実際はかなりエモーショナルで、ハードコアに「脆さ」や「優しさ」を持ち込んだ張本人だと私は感じています。
フランツ:グルーヴとファッションの要
Franz Lyonsは、ベースのグルーヴと歌心、そしてファッション面での存在感を兼ね備えたメンバーです。
ベースラインはファンク寄りのうねりが強く、ただ低音を支えるだけでなく、メロディ的な動きで曲を引っ張っていきます。
「Moon」や「No Surprise」でのボーカルを見ると分かる通り、声の質感も非常にソウルフルです。
さらにGuess Jeansのモデルに起用されたり、ファッション誌で特集されたりと、音楽外での露出も増えていて、Turnstileの「見た目のかっこよさ」を牽引している存在でもあります。
ストリートウェアとハイブランドをミックスしたスタイリングは、ハードコアのステレオタイプを軽々と飛び越えていて、若いファンはもちろん、服好きの大人から見ても刺激的ですよ。
ダニエル:知性派ドラマー/デザイナー
Daniel Fangは、テクニカルで頭脳派なドラマーです。
D-beatや2ビートを基本にしつつ、ラテンリズム、サンバ、ゴーゴー、さらにはアンビエント寄りのパターンまで幅広く取り込み、Turnstileの「踊れるハードコア」を形作っています。
しかも彼はランナーとしての顔も持っていて、マラソンに挑戦するほどの体力の持ち主。
あの激しいドラミングを最後までキープできるのも納得です。
アートやデザインの方面にも精通していて、グッズやアートワークのアイデア出しにも深く関わっています。
ジャケットやツアーポスターの細部を見ると、「あ、これはダニエルっぽいな」と感じるモチーフが散りばめられていて、好きな人はそういう部分を追いかけるのも楽しいと思います。
パット&メグ:ギター陣の二枚看板
Pat McCroryは、Angel Du$tでの活動を通じてポップパンク〜オルタナ寄りの感覚を持ち込むギタリストです。
前任ギタリストBradyの「メトロノームのような精度のリフ」と比べると、少しルーズで、弾きながら揺れているようなニュアンスを大事にするタイプ。
『Never Enough』期では、ディレイやコーラスを使った空間系のサウンドを駆使し、バンド全体を包み込むようなギターテクスチャを担当しています。
Meg Millsは、UKHCで鍛えた骨太なリフとストリート感あふれる佇まいを持つリズムギタリストです。
ガツンとくるコードワークで土台を支えつつ、コーラスやステージングで華やかさをプラス。
ふたりを合わせて見ると、「有機的なリード」と「タフなリズム」という、かなり理想的なギターチームが出来上がっていると感じます。
メンバーを「担当楽器」だけで覚えると、Turnstileの面白さの半分を見落とします。
映像やアートワーク、ファッションまで含めてセットで見ていくと、「あ、こういう世界観だからあのサウンドなんだ」と腑に落ちやすくなりますよ。
1-2. Turnstileメンバー年齢と出身
Turnstileメンバー年齢をざっくり見ると、全員30代前半〜後半に差し掛かった、いわゆる「大人のハードコア世代」です。
10代〜20代前半のキッズが多いシーンの中で、彼らが少し上の世代にいるのは、音楽の「落ち着き」や「メロウさ」にも表れています。
「若さの勢い」だけで押し切るのではなく、自分たちの生活や体験からにじみ出る感情をちゃんと曲に落とし込んでいる感じがするんですよね。
ボルチモア出身3人衆の共通点
Brendan、Franz、Danielの3人は、メリーランド州ボルチモアを軸にしたシーンで育った仲間同士です。
ボルチモアは、決して巨大な大都市ではないけれど、ハードコアやヒップホップ、クラブミュージックなどが混ざり合う独特なカルチャーを持った街。
そういう環境で、Trapped Under IceやPraise、Diamond Youthといった複数のバンドを掛け持ちしながら活動してきたので、ひとつのジャンルに閉じこもらない感覚が自然と身についています。
例えば、ハードコアなのに妙にファンクっぽかったり、ラテンのリズムが紛れ込んでいたり、アンビエントみたいな静かなパートが急に出てきたり。
これって、「ジャンルをミックスしてやろう」と構えてやっているというより、ボルチモアでの日常的な音楽体験がそのまま反映されている感じが強いんですよね。
だからTurnstileのサウンドは、実験的でありながらも自然体で、聴いていて無理がないのかなと思います。
また、3人とも10代〜20代の頃からツアー生活を経験していて、アメリカ各地のシーンやヨーロッパ、日本などの海外シーンとも若いうちから触れ合ってきました。
こういう「移動の多い人生」を送ってきた人たちならではの感覚も、歌詞のテーマやメロディの郷愁感ににじみ出ています。
メグとパットがもたらす「外の空気」
一方、PatとMegは、ボルチモアとは違う文脈からTurnstileに合流した「外の空気」を持ち込む存在です。
PatはAngel Du$tでの活動を通じて、オルタナ、グランジ、パワーポップなど、「ハードコア以外のギターロック」に深く浸かってきたタイプ。
彼のフレーズやコードボイシングには、90年代オルタナやインディロックの影響がはっきりと感じられます。
MegはUKHC出身ということで、ロンドン〜リーズあたりの荒々しいストリート感や、パブとクラブ文化が混ざった独特のノリをTurnstileに持ち込んでいます。
イギリスのハードコアは、アメリカよりもオイパンクやストリートパンクの要素が濃く混ざっていることが多く、そこから来る「泥臭さ」や「シャウトの響き方」が、彼女のプレイにも表れていると感じます。
結果として、Turnstileメンバー年齢と出身を整理してみると、
- ボルチモア勢:グルーヴとビジョン、DIYマインドの核
- Pat:アメリカン・オルタナ〜インディの色味
- Meg:UKHCとロックンロールの荒々しさ、ストリート感
という役割分担が見えてきます。
これがそのまま、『Never Enough』のサウンドにも反映されていると考えると、かなり分かりやすいですよね。
ざっくりまとめると、ボルチモア勢が「核」や「軸」を作り、パットとメグが「色」と「風通しの良さ」を足している。
このバランスが、Never Enough期のTurnstileの魅力を支えています。
「メンバーの歳が自分と近いと、ちょっと親近感が湧く」という人も多いと思います。
私自身も50代になってから、同世代〜少し下のバンドが世界の最前線にいるのを見ると、「まだまだこっち側からも追いかけられるな」と励まされますね。
Turnstileは、年齢を重ねても新しい音楽をアップデートし続けることの楽しさを体現しているバンドだと思います。
1-3. Turnstileメンバー現在の編成
Turnstileメンバー現在の編成は、先ほど触れたように5人。
ですが、ここまで来るまでには、ギタリストの入れ替わりやツアーメンバーのサポートなど、いくつかのステップがありました。
「Glow On」で人気が爆発したタイミングと、創設メンバーの脱退、そして新メンバーの台頭がほぼ同じ時期に起きているので、「いつ誰がいたのか」を整理しておくと、作品ごとの雰囲気の違いが理解しやすくなります。
初期ラインナップから現在までの流れ
- 2010年〜:Brendan / Franz / Daniel / Brady Ebert(G)/ Sean “Coo” Cullen(G)
- 2015年頃〜:Seanが離脱し、Pat McCroryがギタリストとして合流
- 2022年:創設メンバーのBradyが正式に脱退
- 2022〜2023年:Greg Cerwonka(Take Offense)がツアーギタリストとして参加
- 2023〜2025年:Meg Millsがツアーメンバーとして帯同
- 2025年:Megが正式メンバーとしてクレジットされ、現在の5人体制に
この流れを見ると分かる通り、Turnstileの「変わらない部分」はリズム隊とブレンダンのビジョンです。
ギターのポジションは、その時々のサウンドの変化とともに、少しずつ入れ替わってきました。ハードコアのバンドだと、リズム隊が変わってサウンドがガラッと変貌するパターンも多いですが、Turnstileの場合はそこがずっと同じなので、「別バンドになった」感があまりないのも特徴です。
ツアーメンバーの重要性
2022年以降の移行期間において、Greg CerwonkaやMeg Millsのようなツアーメンバーの存在はかなり大きかったと思います。
Bradyが抜けた直後は、世界規模のツアーがすでに決まっている状況で、急遽ギタリストを確保しなければならなかったわけですが、その期間をしっかり支えてくれたのがGregたちでした。
ツアーメンバーという立場は、どうしても「正式メンバーの影」と見られがちですが、Turnstileはそこをかなりフェアに扱っている印象があります。
ライブビデオやオフィシャルフォトでもしっかり映るようにしていたり、SNSでも頻繁に名前が出てきたりと、「仲間」としての扱いがとても自然なんですよね。
この空気感があったからこそ、Megも安心してバンドの中に入り込んでいけたんじゃないかなと感じています。
2025年以降の5人体制の意味
2025年にMegが正式メンバーとしてクレジットされ、Turnstileメンバー現在の編成が固まったことで、ようやく「Never Enough期のTurnstile」という一枚岩のイメージができあがりました。
リードギターのPat、リズムギターのMegという構成は、ライブでもレコーディングでも非常にバランスが良く、ハードコアのラフさを維持しつつ、アンビエント〜ポップ寄りのアレンジにも柔軟に対応できる布陣です。
個人的には、この5人体制は「Turnstile第二章の完成形」のように感じています。
『Glow On』までのTurnstileがハードコアの枠内から外側へ飛び出していく過程だったとしたら、『Never Enough』期は、その広がったフィールドの中で、自分たちの居場所をちゃんと見つけ直したフェーズと言えるかもしれません。
元ギタリストBradyの「機械的で精密なリフ」と、Patの「少しルーズで生々しいリフ」。
このコントラストは、バンドのサウンド変化を語るうえでの重要ポイントです。
詳しくは後半のNever Enoughの章でも触れていきます。
1-4. Turnstileメンバー脱退と理由
Turnstileメンバー脱退の話題で最も大きかったのが、リードギタリストBrady Ebertの離脱です。
これは単純な「音楽性の違い」ではなく、実際に法的手続きまで絡んだシリアスな出来事でした。
ファンの間でも議論が飛び交い、「一体何が起きていたのか?」という疑問を抱いた人も多かったと思います。
Brady Ebert脱退までの経緯
2022年、ドラマーのDaniel Fangが、メリーランド州の制度を通じてBradyに対するピースオーダー(接近禁止命令に近いもの)を申請したことが報じられました。
最終的には「法的救済の根拠に乏しい」として棄却されていますが、バンド内の人間関係が深刻なレベルでこじれていたことだけは読み取れます。
この件に関して、バンド側もBrady側も詳細を語っていないため、外部から見えるのはごく一部の情報だけです。
その隙間を埋めるように、薬物使用の噂やロイヤリティのトラブル、SNSでの発言を元にした憶測などがネット上に広がりましたが、どれも決定的な証拠があるわけではありません。
ハードコアシーンはDIYであるがゆえに、内輪の事情がそのまま外部に出てこないことも多く、この件もその典型かなと思います。
噂話は一人歩きしやすいですが、当事者の生活やメンタルにも直結するセンシティブな問題です。
ファンとしては「真実を知りたい」と思ってしまいますが、ここでは公式に確認できる範囲の事実だけにとどめておきます。
サウンド面への影響と受け止め方
Bradyは、初期Turnstileの「機械的で精密なリフ」を作り上げた重要人物です。
Time & Spaceや初期のEPを聴くと、ギターがかなりタイトに刻まれていて、リフそのものが曲の主役になっている瞬間も多いですよね。
彼の離脱は、バンドからこの「精密さ」が一部削がれた、という見方もできます。
一方で、Patがリードギターにシフトしたことで、リフは少しルーズになり、その代わりに「揺れ」や「余白」が生まれました。
『Never Enough』期のTurnstileのサウンドは、この変化がなかったら到達できなかったものだと私は思っています。
初期のキレッキレのハードコアが好きだった人にとっては賛否が分かれるポイントかもしれませんが、「別バンドになった」というよりは、「同じメンバーが別フェーズに入った」と考えるとしっくりくるかなと。
Bradyの現在とファンとしての距離感
Bradyは脱退後、新バンドThe S.E.Tを立ち上げて活動を続けています。
初期Turnstileが好きだった人には、「あ、あの精密なリフが戻ってきた」と感じるようなサウンドも多く、これはこれでひとつの「答え」だなと私は受け止めています。
Turnstileとは別の道を歩みながらも、それぞれのバンドで自分のスタイルを追求していると考えると、少し安心しますよね。
大事なのは、「どちらか一方を選ばなければならない」と思い込まないことかなと思います。
Bradyのいた頃のTurnstileも、PatとMegがいる今のTurnstileも、それぞれ別の良さがあるので、気分によって聴き分ければいいだけです。
人間関係の詳細は当事者にしか分かりませんが、リスナーとしては、音源とライブから伝わってくるものに素直に向き合うのがいちばん健全かなと感じます。
一方で、Brady不在になったTurnstile側は、パットのルーズで有機的なギターワークに比重が移り、ライブ感と感情の揺れをそのままパッケージしたようなサウンドへと進化していきます。
この「機械的な精密さから、人間味のあるグルーヴへ」という流れこそ、『Never Enough』期を理解するうえで重要なポイントですね。
Turnstile女性メンバーのメグ
検索キーワードでも目立つのが「Turnstile メンバー メグ」。
それだけ、Meg Millsがシーンにもたらしたインパクトが大きかったということだと思います。
ハードコアバンドの正式メンバーとして女性ギタリストが入ること自体は今では珍しくなくなってきましたが、Turnstileの規模感(世界ツアー・大型フェスの常連)と、彼女が持ち込んだUKHCのバックグラウンド、そしてファッション性が組み合わさることで、かなり象徴的な存在になっています。
UKHCから世界的バンドへのジャンプアップ
メグはイギリスのハードコア・シーンで育ったギタリストで、Big CheeseやChubby and the Gangといったバンドに在籍していました。
どちらもアンダーグラウンドの熱さと古き良きロックンロールの匂いを併せ持つバンドで、DIYスペースや小さなクラブでガンガンに鳴らされるタイプの音です。
そういう場所で鍛えられてきたプレイヤーなので、ステージ上の立ち居振る舞いがとにかく自然なんですよね。
ギターを始めたきっかけとして、映画「Freaky Friday(邦題:フォーチュン・クッキー)」でリンジー・ローハンがギターをかき鳴らすシーンに衝撃を受けた、というエピソードも有名です。
「あの地下室のバンド練習シーンで、自分の脳内の配線が変わった」と語っていて、ここにTurnstileのポップカルチャーとの親和性を感じます。
ハードコアにどっぷり浸かる前に、映画やポップミュージックからインスピレーションを受けているのも、現代的なミュージシャンっぽいですよね。
ステージでのメグの役割
ツアーメンバーとしてTurnstileに帯同し始めたのは2023年。
いきなり2万人規模のアリーナ(ミネソタ州Xcel Energy Center)デビューという「火の洗礼」を受けながら、徐々にバンドの一員として存在感を増していきます。
最初期のライブ映像と最近の映像を見比べると、立ち位置や動き方、メンバーとのアイコンタクトの量がどんどん変化していて、「あ、今は完全にバンドの中に溶け込んでいるな」と感じられます。
ギタープレイとしては、歪み具合やコードボイシングがUKHC寄りで、リズムとしてのガツンとした押し出しが強いです。
リフの細かい装飾よりも、ダウンピッキングでズシズシと押していくタイプなので、Patの空間系エフェクトを駆使したリードと非常に相性が良いんですよね。
ふたりのギターが重なったとき、「骨太なリズムとポップなメロの橋渡し役」として機能しているのがよく分かります。
メグのギターは、歪み具合やコードボイシングがUKHC寄りで、「骨太なリズムとポップなメロの橋渡し役」になっているのが面白いところです。
リズムギターとして土台を固めつつ、コーラスワークやステージングで華やかさも足してくれています。
ファッションとロールモデルとしての側面
ファッション面でも、Vivienne Westwoodや古着のミックスなど、ロンドンのストリートとハイファッションをつなぐようなスタイルで、バンド全体のビジュアルをアップデートしています。
Guess Jeansのキャンペーンに起用されたFranzと並んで、Turnstileの「今っぽさ」を体現するメンバーだと感じますね。
また、メグの存在は「女性がハードコアバンドでギターを弾く」という当たり前を広げる意味でもすごく大きいです。
若い女の子がTurnstileのライブ映像を見て、「自分もあっち側に行けるかも」と思えるロールモデルになっているのは間違いありません。
ジェンダー的な話を必要以上に前面に押し出す必要はないと思いつつも、こういう存在が増えていくことは確実にシーンを豊かにしてくれると感じます。
2. Turnstileのメンバー最新像
ここからは、『Never Enough』期のTurnstileメンバーにフォーカスして、サイドプロジェクトとの関係、最新アルバムでの役割分担、使用機材、そして日本とのつながりまでを立体的に見ていきます。
単なるメンバー紹介から一歩進んで、「今のTurnstileがどこへ向かっているのか」を一緒に掴んでいきましょう。
『Glow On』で評価を固めたあと、なぜあえてさらに実験的な方向に舵を切れたのか、その背景にはメンバーそれぞれの活動と成長が深く関わっています。
2-1. Turnstileメンバーとサイド活動
Turnstileメンバーを語るうえで外せないのが、各自のサイドプロジェクトです。
彼らはとにかく多作で、それぞれのバンドで磨いたエッセンスをTurnstileに持ち込んでいます。
ある意味、Turnstileは「メインバンド」であると同時に、さまざまなプロジェクトの交差点のような場所でもあるんですよね。
Angel Du$tと「ポップなハードコア」
Brendan、Franz、Pat、Danielの4人が関わるAngel Du$tは、アコースティック寄り、オルタナ寄りの楽曲も多い、軽やかなバンドです。
ハードコアのテンションは保ちながらも、ビーチミュージックやパワーポップ的な明るさを前面に出していて、Turnstileよりもさらに「軽快でポップ」な印象があります。
ここで培われた「ポップだけどラフ」「メロディアスだけど過度に整えない」感覚が、『Glow On』以降のTurnstileにしっかり流れ込んでいます。
特にコーラスの付け方やクリーントーンの使い方は、Angel Du$t経由でアップデートされた部分だと感じますね。
Trapped Under Iceとリズムへのこだわり
BrendanとFranzが関わってきたTrapped Under Iceは、ボルチモアHCの象徴と言っていいほどの存在。
ゴリゴリのハードコアでありながら、妙にグルーヴィで、ビートダウンやブレイクの入れ方がとにかく上手いバンドです。
ここでの経験が、Turnstileの「踊れるけど重い」グルーヴの原点になっているのは明らかです。
Brendanがドラムを叩いていた経験は、ボーカルでありながらリズムの細かいニュアンスにめちゃくちゃ敏感なフロントマンを生み出しました。
歌メロの裏で鳴っているパーカッションやシンコペーションの入れ方に、そのこだわりがよく表れています。
その他のプロジェクトとメンタル面への影響
Danielが関わるPraiseは、80年代DCハードコア(Dag Nastyなど)からの影響が強いメロディック・ハードコアで、Turnstileの中でも特にメロウな側面に通じていると思います。
BrendanやFranz、Danielが関わっていたDiamond Youthは、90年代オルタナへの愛情が詰まったプロジェクトで、ここで培ったギターポップ的なセンスが、Turnstileの「ドリーミーな部分」に繋がっています。
こうしたサイド活動は、単なる「余暇のバンド」ではなく、メンバーのメンタルバランスを保つ役割も果たしているように思います。
Turnstileのような大きなバンドだけに全てを賭けてしまうと、どうしてもプレッシャーが大きくなりすぎますが、別のプロジェクトで違う自分を出すことで、良い意味で力が抜けているのかなと感じます。
ルーツをもっと掘りたいあなたへ
もしTurnstileからハードコア/パンクのルーツに遡ってみたくなったら、同じジェネレーションB内でまとめている
あたりも合わせて読んでもらえると、プロトパンク〜70年代UKパンクまでの歴史がつながって見えてくると思います。
Turnstileメンバーが愛してきた音楽の源流に触れることで、彼らのサウンドの「なじみやすさ」の理由も見えてきますよ。


2-2. Turnstileのメンバーと『NeverEnough』
2025年6月にリリースされた4thアルバム『Never Enough』は、Brady脱退後の新体制で作られた、Turnstileにとって重要なターニングポイント作品です。
『Glow On』で一気にメインストリームの注目を浴びたあと、「その次に何をやるのか?」というプレッシャーの中で生まれた作品でもあり、メンバーそれぞれの役割やクリエイティブ面の比重が大きく変化しています。
Never Enoughでの各メンバーの役割
- Brendan:メインプロデューサー的な立ち位置で、ボーカルだけでなくキーボードやサウンドデザインにも深く関与。さらに、同作と連動するビジュアルアルバムの監督も務めています。
- Franz:ベースでグルーヴの核を作りつつ、「Seein’ Stars」「Birds」などで歌メロを支える存在に。ファッション文脈でもアルバムのイメージを牽引。
- Daniel:ドラムとプログラミングで、ラテンやサンバ、アンビエント寄りのビートまで自在に展開。長尺曲「Look Out for Me」のダイナミクスは彼ならでは。
- Pat:リードギターとして、以前よりも余白を活かしたフレージングと空間系エフェクトで、アンビエント寄りの質感を作り出します。
- Meg:公式アルバムとしては初参加。リズムギターとコーラスで、ラフなUKHC感とポップなノリを同居させています。
特にBrendanの役割は大きくて、プロデューサー/ディレクターとしての顔が一気に前面に出てきました。
『Glow On』でもすでにその片鱗はありましたが、『Never Enough』では「楽曲単体」よりも「アルバム全体の体験」や「映像との連動」が重視されていて、もはやハードコアバンドの枠だけで語るのはもったいないプロジェクトになっています。
『Never Enough』の収録曲は、ハードコア〜アンビエントまでを揺れ動くような構成になっています(曲順や曲名は地域盤・エディションによって一部異なる場合があります)。
| トラック | タイトル | ざっくり一言メモ |
|---|---|---|
| 1 | Never Enough | 壮大なオープナー。Mystery以降の延長線上にある新機軸 |
| 2 | Sole | ミドルテンポでじわじわと高揚する1曲 |
| 3 | I Care | ポップ寄りで、Turnstile流のラブソング的側面も |
| 4 | Dreaming | 管楽器を導入した、ラテンビート進化形 |
| 7 | Sunshower | パンクからアンビエントへ溶けていく構成が秀逸 |
| 8 | Look Out for Me | 長尺インストパートを含む、アルバムのハイライト |
| 10 | Seein’ Stars | モッシュ必至のキラーチューン。ビデオも必見 |
| 11 | Birds | Franzの存在感が光る、映像映えする1曲 |
※曲順・収録内容はエディションにより異なる場合があります。正確な情報はレーベルや公式サイトをご確認ください。
ビジュアルアルバムとしての側面
『Never Enough』は、音源だけでなく、映像作品「TURNSTILE: NEVER ENOUGH」とセットで語られることが多い作品です。
映画館で上映されるビジュアルアルバムという形で公開され、楽曲ごとの世界観が映像としても体験できるようになっています。
これは、BrendanとPatが映像表現に本格的に踏み込んだ結果であり、Turnstileが「ライブバンド」から「トータルアートプロジェクト」へと進化した証でもあります。
作品自体のリリース情報やクレジットは、Roadrunner Recordsおよびアーティスト側の公式ページで公開されています。
詳しい仕様やリリースフォーマットを確認したい場合は、Roadrunner Recordsの公式商品ページ(出典:Roadrunner Records公式ストア「Spotify Fans First – NEVER ENOUGH」)をチェックしてみてください。
Charli XCXが「2025年の夏はTurnstileの夏になる」とコメントしたのも象徴的で、ポップシーン側からもTurnstileメンバーとそのサウンドが強く意識されていることが伝わってきます。
ハードコアの枠内にとどまらず、ポップカルチャー全体の中で語られるバンドになった、という意味で、『Never Enough』期のTurnstileはかなり特別なフェーズに入っていると言えるでしょう。
2-3. Turnstileメンバー使用機材解説

Turnstileメンバーの中でも、特にギタリストPat McCroryの機材は、多くのギターファンが気にしているポイントだと思います。
もちろんFranzのベースやDanielのドラムセットも魅力的なのですが、このセクションでは、バンドのサウンドキャラクターを大きく左右している「ギター周り」を中心に見ていきます。
あくまで「一般的な目安」として捉えてもらえればOKです。
Pat McCroryのアンプとエフェクター
Patは基本的に「シンプルなセットアップで、手元のニュアンスを出す」タイプのギタリストです。メインのアンプとしては、
- Orange Rockerverb 50 MkIII
- EVH 5150III
あたりを使うことが多く、そこにアナログ寄りのペダルを少数組み合わせるスタイルが定番になっています。
スタジオではKemperなどのプロファイリングアンプを併用することもあるようですが、ライブでは真空管アンプの「押し出し」を重視している印象です。
あくまでも一例ですが、Patのサウンドイメージに近づきたい人向けに、ざっくりした設定値のイメージを載せておきます。
| パラメータ | クリーン寄り | リード寄り |
|---|---|---|
| Gain | 4〜5 | 7〜8 |
| Bass | 7前後 | 7前後 |
| Middle | 4〜5 | 4〜6 |
| Treble | 8前後 | 8前後 |
| Presence | 6〜7 | 6〜7 |
※実際のライブ・レコーディングでは会場や機材に合わせて細かく変更されています。
エフェクターで特に重要なのが、
- MXR Carbon Copy:アナログディレイ。ソロやアルペジオで空間を足す要
- Fulltone OCD:オーバードライブを2台使い分け、基本歪み+ソロブーストとして活用
- BOSS Super Chorus:クリーンパートの揺らぎ用
ポイントは「ペダルの数よりも、どれだけ手元のニュアンスを出せるか」です。
Turnstileのギターは、音の切り方・ミュートの仕方・コードの鳴らし方でかなり表情が変わるので、真似をするならまず右手と左手の使い方から観察してみると良いですよ。
FranzのベースとDanielのドラム
Franzのベースは、フェンダー系のベースとAmpeg系のベースアンプを組み合わせた、クラシックなハードコアセットアップが基本です。
ただし、ピック弾きでゴリゴリに攻めるだけではなく、指弾きでグルーヴを出す場面もあり、曲によってかなり使い分けています。
エフェクターは比較的シンプルですが、オーバードライブやコンプでアタックを前に出しつつ、ローをしっかり残すセッティングが多い印象です。
Danielのドラムセットは、スタンダードなロックセットをベースにしつつ、パーカッションや電子ドラムパッドを足した構成。
ラテンやサンバ系のフレーズを叩くときは、カウベルやウッドブロック、シェイカーなどを巧みに使っていて、ライブでよく見るとかなり楽しいポイントです。
チューニングも比較的高めで、抜けの良いアタック重視のサウンドになっています。
機材にこだわりたい人への補足
もし「ギターだけじゃなく、再生環境もちゃんと整えたい」と感じたなら、同じジェネレーションBで書いているパンクロックのレコードを真空管アンプとトランジスタで聴き比べる記事も役立つと思います。
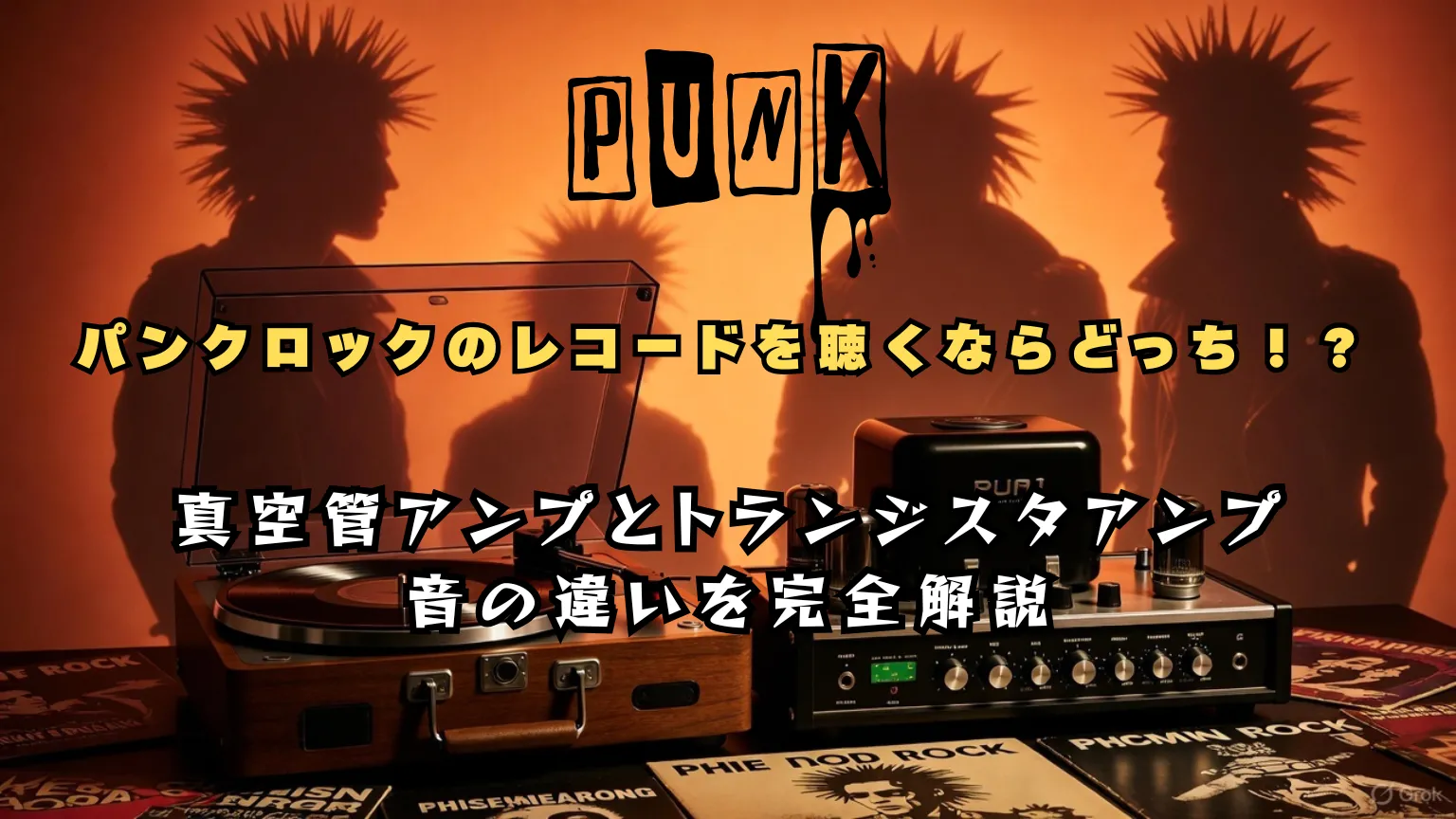
Turnstileのレコードをどんなアンプで鳴らすかで、印象がガラっと変わりますからね。
なお、ここで紹介した設定値や機材構成は、あくまで一般的な目安です。
正確な仕様や価格、最新のモデルチェンジなどは、各メーカーや販売店の公式情報を必ず確認してください。
高価な機材を検討する場合は、最終的な判断は信頼できるオーディオショップや技術者などの専門家にご相談いただくのがおすすめです。
2-4. Turnstileメンバー来日公演歴
Turnstileメンバーと日本の関係も、ファンとしては押さえておきたいところ。
彼らはキャリアの重要なタイミングで、何度も日本を訪れています。
ライブでの姿を実際に見たことがあるかどうかで、バンドへの解像度は一気に変わりますし、日本での経験がバンド側に与えた影響も少なくありません。
代表的な来日タイミング
- 2015年:『Nonstop Feeling』期に初来日。小〜中規模のライブハウスツアーで、日本のハードコアシーンと濃密に交流。
- 2018年:東京のBloodaxe Festivalに出演。Danielが「日本の友人たちが一気に集結した魔法の夜」と振り返るほどの熱量。
- 2024年:フジロックフェスティバルのホワイトステージに出演。雨の中でのモッシュとシンガロングは、完全に「伝説級」のパフォーマンスでした。
2015年の初来日は、まだ今ほど大きなバンドではなかったタイミングで、純粋に「海外のハードコアバンドが日本のDIYシーンとぶつかる」感覚が強かった時期です。
小さめのライブハウスで、ステージと客席の境界がほとんどない状態でのライブは、彼らにとってもかなり刺激的だったはずです。
2018年のBloodaxe Festivalは、日本のハードコア・パンク・メタルコアが一堂に会する場で、Turnstileもその一角として参加しました。
ここで築かれた日本とのコネクションが、その後の単独ツアーやフェス出演につながっていったと考えられます。
そしてフジロック2024では、ホワイトステージのトリというポジションで、完全に「新世代のヘッドライナークラス」に昇格した姿を見せてくれました。
雨の中でも客席がまったく引かず、サークルモッシュとシンガロングが続く光景は、YouTubeのライブ映像を見ても鳥肌ものです。
ステージ上のTurnstileメンバーも、日本の観客のノリを完全に信頼しているような表情で、とても印象的でした。
ステージ上のTurnstileメンバーを見ると、日本のファンに対してもかなりオープンで、ステージと客席の境界を取り払うようなムーブが多いのが印象的です。
「大規模フェスなのにDIYハードコアの距離感を保とうとしている」のが、彼らの美学なんだろうなと感じます。
今後の来日予想と注意点
今後の来日予定については、ツアーサイクルやフェスのブッキングの状況にも左右されます。
過去のペースやアジアツアーの組み方を考えると、数年以内にまた日本で観られる可能性は十分あると思いますが、これはあくまで個人的な見立てです。
海外バンドのツアーは、政治情勢や為替、航空事情など、さまざまな要素で簡単に変わってしまうので、あくまで「来てくれたらラッキー」くらいの温度感で待つのが良いかなと思います。
ライブ日程やチケット情報は変動が激しく、ここで書いた内容はあくまで一般的な傾向・目安に過ぎません。
必ずバンドの公式サイト、各種SNS、フェスや会場の公式ページで最新情報を確認してください。
2-5. Turnstileメンバーまとめと魅力
最後に、ここまで見てきたTurnstileメンバーの魅力を、改めて整理しておきます。
メンバーそれぞれのバックグラウンドや役割を押さえておくと、アルバムやライブの見え方が本当にガラッと変わりますよ。
- Brendan / Franz / Danielというボルチモア出身の中核メンバーが、バンドの「背骨」と「グルーヴ」を作っている
- Patの有機的なギターワークと、MegのUKHC由来のラフさ&ファッションセンスが、最新のTurnstileサウンドをアップデートしている
- 脱退したBradyを含め、それぞれのギタリストの個性がバンドのフェーズごとの変化を象徴している
- サイドプロジェクトや映像、デザイン、ファッションまで含めると、Turnstileメンバーは「バンド」というよりクリエイティブ集団に近い存在になっている
私自身、10代の頃に聴いていたパンクやハードコアと比べても、Turnstileは「音の強度」と「ポップさ」と「開かれたマインド」のバランスが抜きん出ているバンドだと感じています。
だからこそ、若い世代だけでなく、ジェネレーションB世代のあなたにも強くおすすめしたいんですよね。
生活や仕事に追われていると、新しいバンドを追いかける余裕がなくなりがちですが、Turnstileは「今の自分」にもストレートに刺さる要素がちゃんとあります。
Turnstileメンバーをしっかり知ると、1曲1曲の聴こえ方が変わります。
誰がどのパートを支え、どんなバックグラウンドを持ってステージに立っているのかを意識しながら聴くと、同じアルバムでもまったく違う作品のように感じられるはずです。
この記事で紹介した年齢・機材・ツアー情報などは、いずれも2025年時点の一般的な目安であり、今後変わる可能性があります。
正確な最新情報は、必ずバンドの公式サイトやレーベル、機材メーカーや販売店などの公式情報をチェックしてください。
また、高価な機材の購入や遠征を伴うライブ参加など、人生やお財布に影響する判断については、最終的な判断は専門家や信頼できる販売店・関係者にご相談いただくことをおすすめします。
💿 アナログ盤で味わう“生のTurnstile”

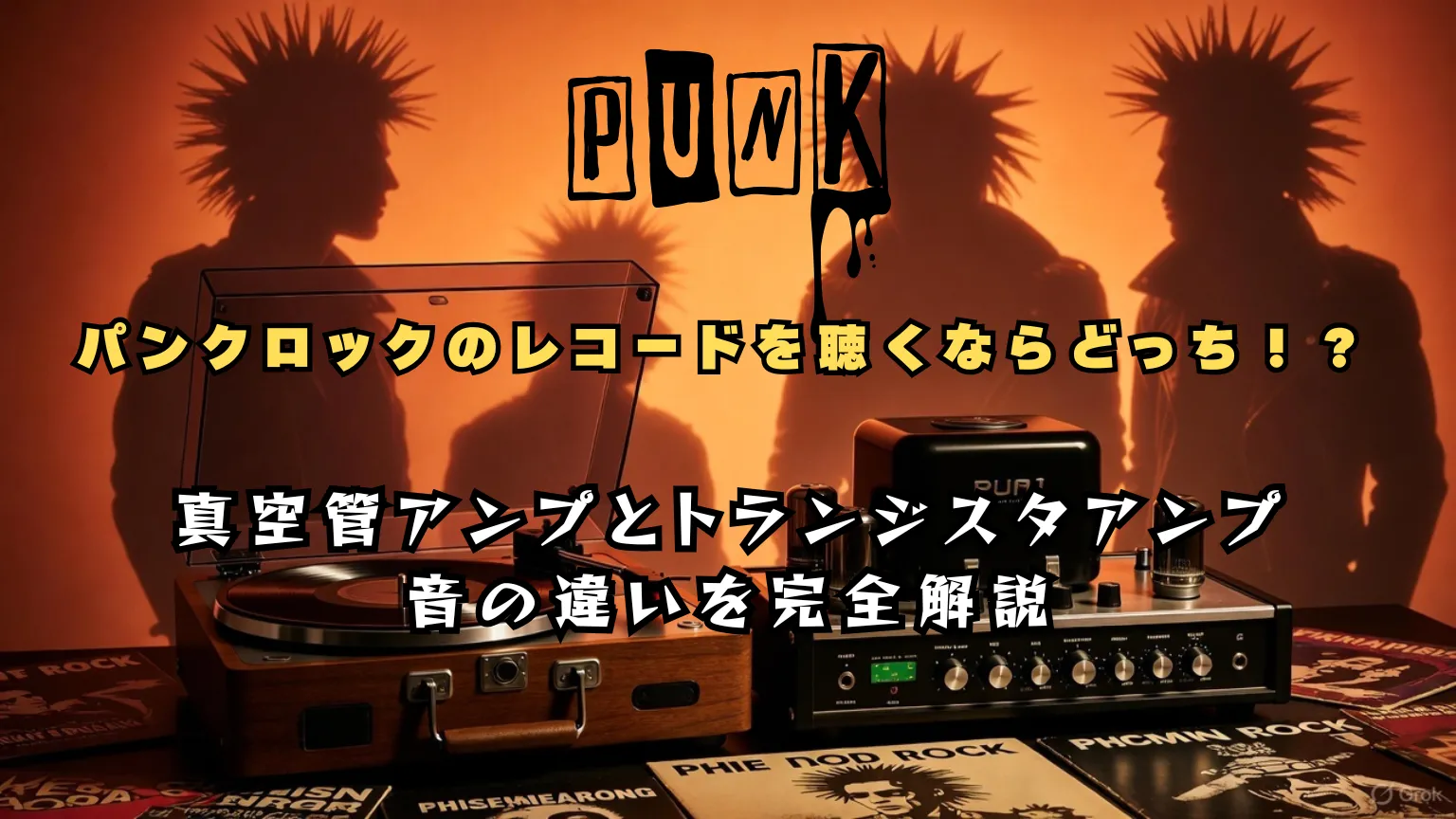

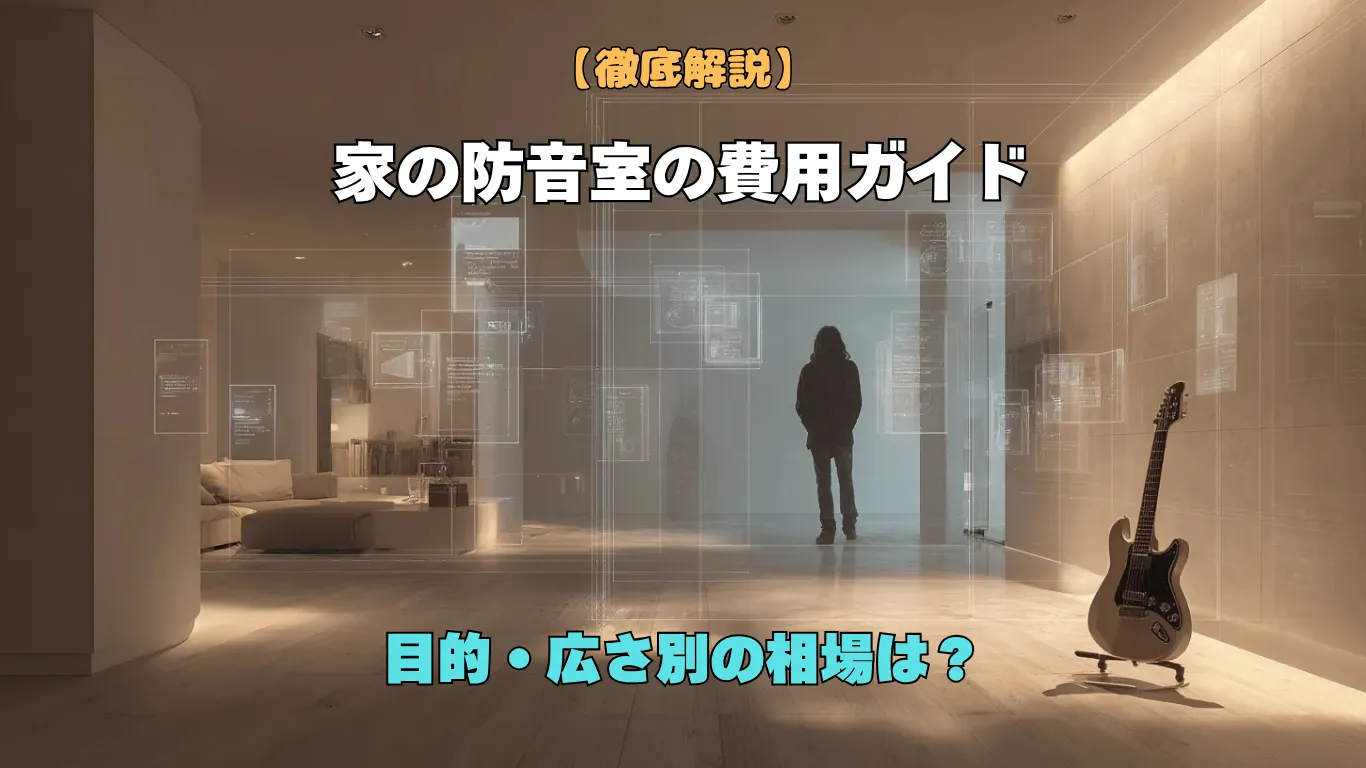
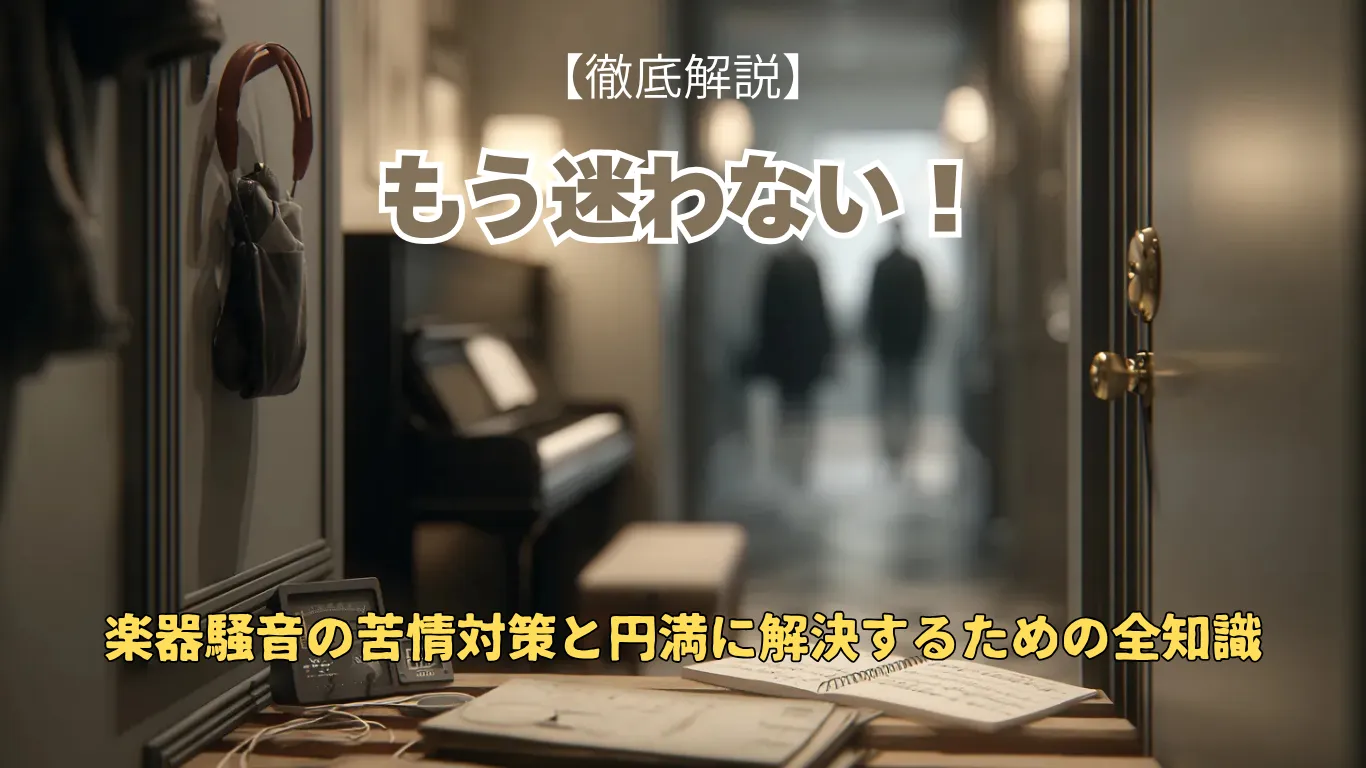
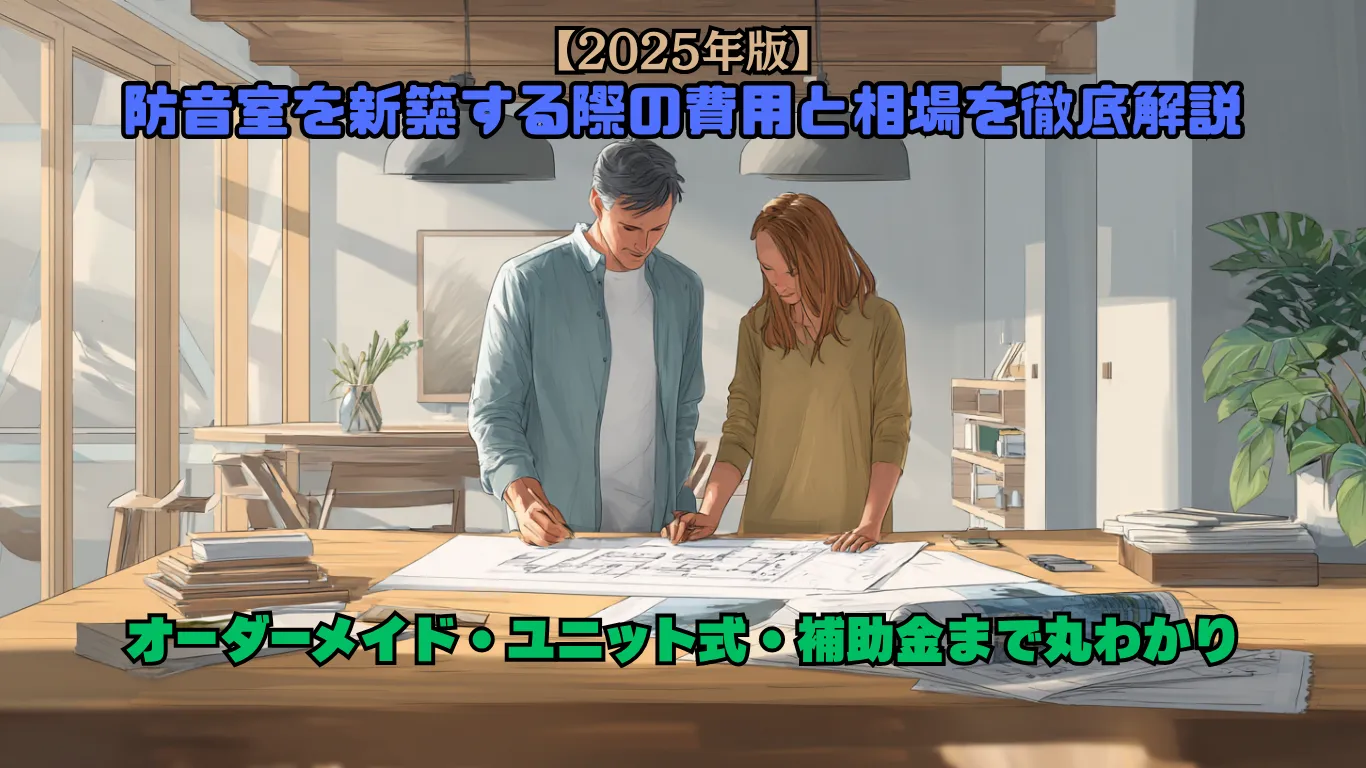





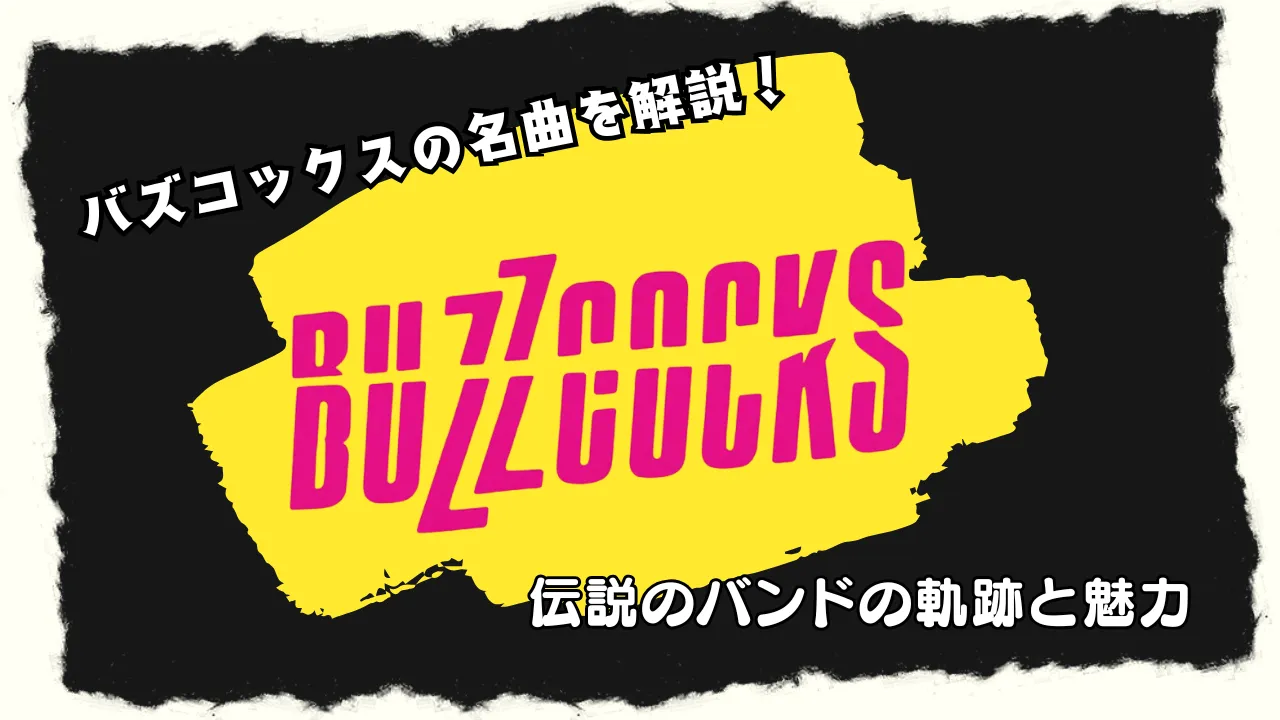
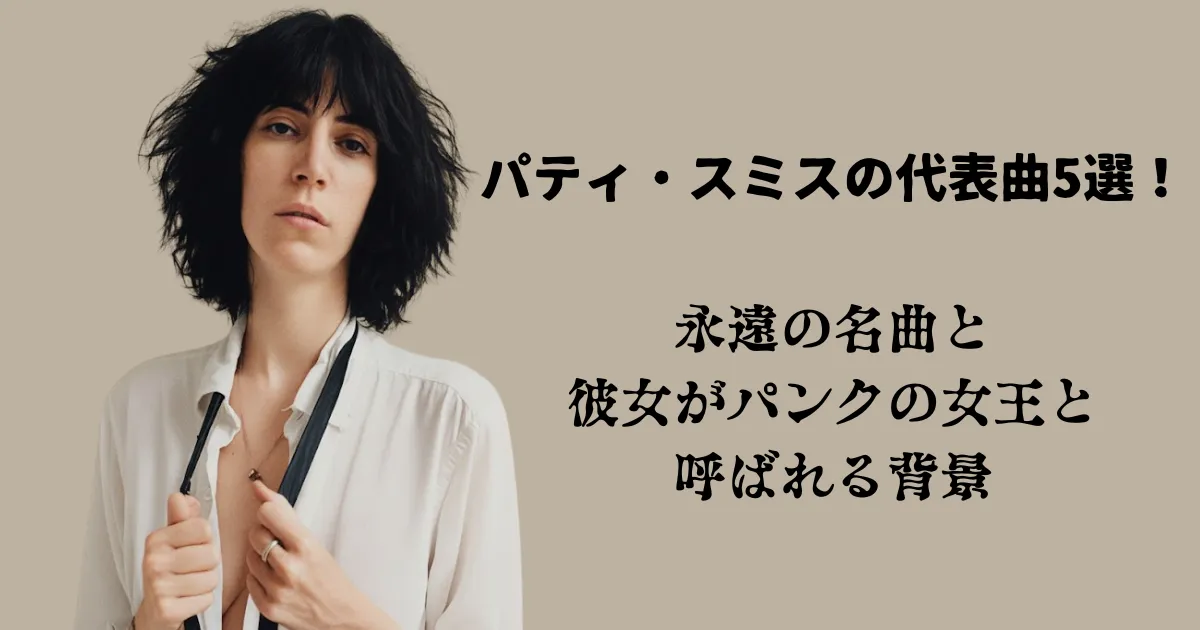
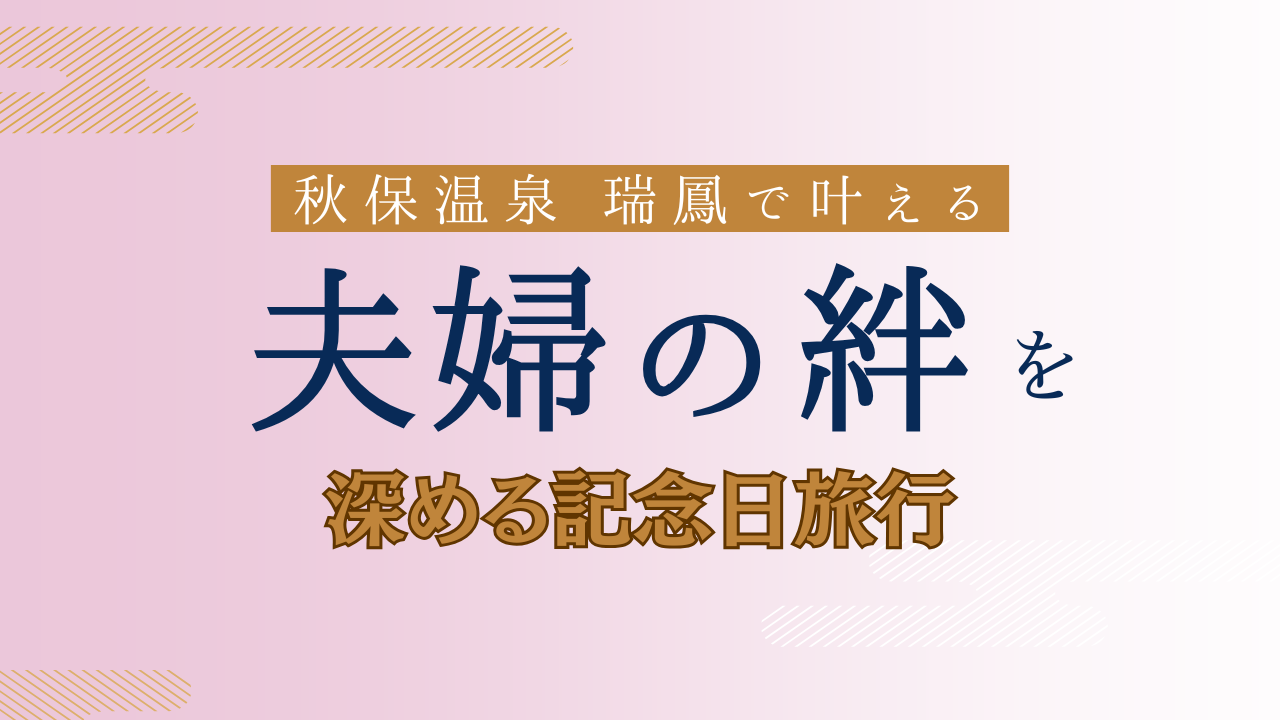









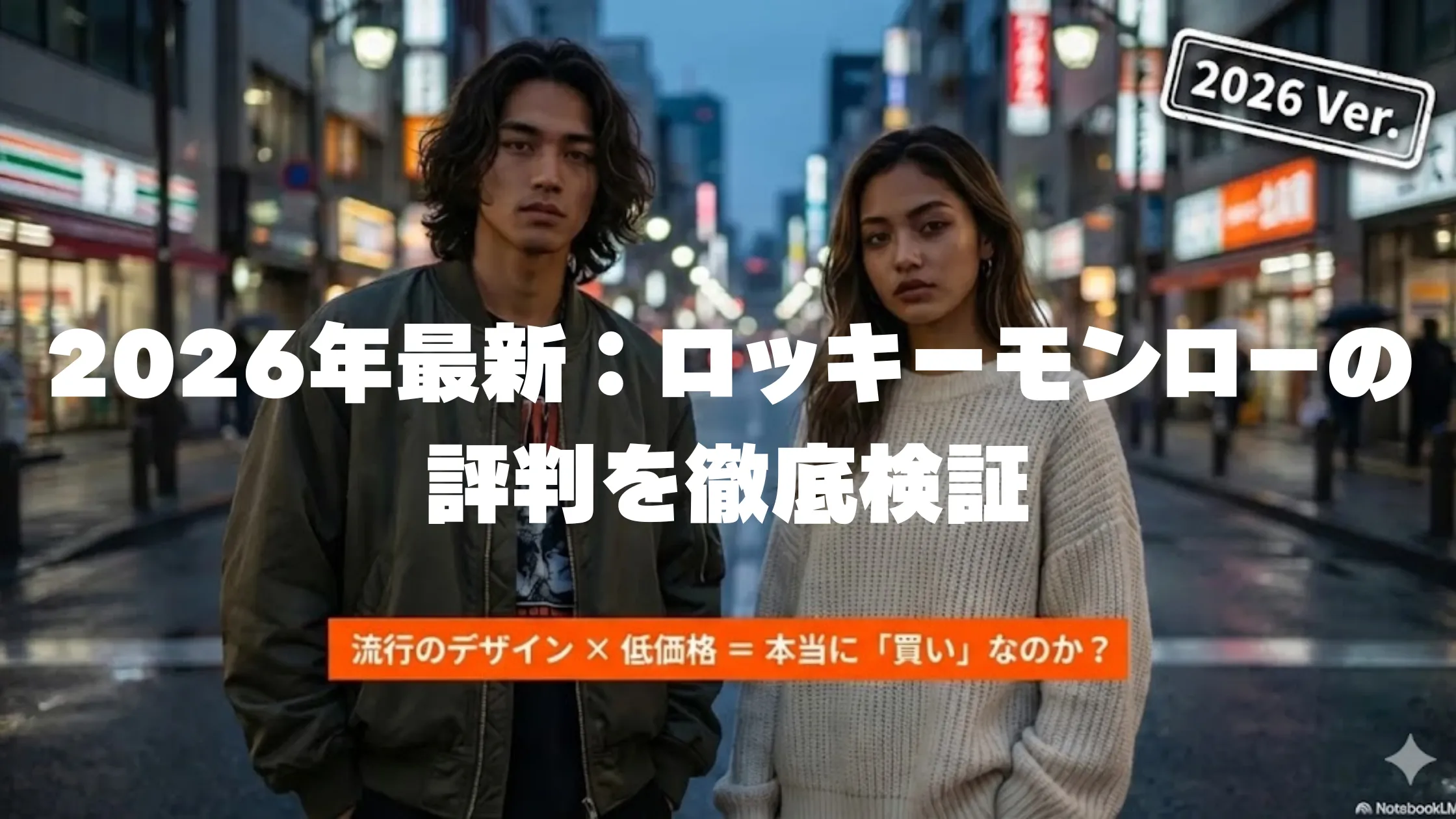
コメント