煤けたバーの片隅で、バーボン片手にピアノを爪弾く吟遊詩人。
壊れたラジオから流れてくるような、しゃがれた歌声。
トム・ウェイツというアーティストを形容する言葉は数多くあれど、そのどれもが彼の本質の一面にしか過ぎません。
彼はソングライターであり、コンポーザーであり、俳優であり、そして何よりも唯一無二の物語作家です。
そのキャリアは50年以上に及び、発表されたアルバムは時代ごとにその音楽性を大きく変貌させ、出演した映画では忘れがたい強烈な印象を残してきました。
本記事では、この孤高のアーティスト、トム・ウェイツの長く深いキャリアを「ソングライター」と「俳優」の両面から徹底的に解剖します。
初期のフォーキーなバラードから、中期の実験的なインダストリアル・サウンド、そして円熟期に至るまでの音楽の変遷を全アルバムレビューと共に詳説。
さらに、スクリーンで見せたもう一つの顔を全出演作品レビューで振り返ります。
初心者にはその全体像を、コアなファンには新たな発見を。30,000字を超えるボリュームで、トム・ウェイツという迷宮の地図を、ここに描き出します。
この記事でわかること
✔︎ トム・ウェイツのキャリアと音楽性の変遷がわかる
✔︎ 初心者におすすめの代表曲と名盤がわかる
✔︎ キャリアを彩る全オリジナルアルバムの概要と特徴を掴める
✔︎ 俳優としての全出演作もまとめて理解できる
1. 酔いどれ詩人トム・ウェイツの代表曲 その世界
1-1. 「酔いどれ詩人」の異名で知られる歌手
トム・ウェイツは、「酔いどれ詩人」という異名で世界的に知られるアメリカのシンガーソングライターであり、俳優です。
その最大の特徴は、一度聴いたら忘れられないしゃがれた歌声にあります。
まるでウイスキーで喉を焼き、タバコの煙で燻したようなダミ声は、彼の音楽のトレードマークとなっており、キャリアを重ねるごとにその深みを増していきました。
しかし、彼は単に声が特徴的なだけの歌手ではありません。
トム・ウェイツの本質は、優れた物語作家(ストーリーテラー)である点にあります。
彼の楽曲は、社会の片隅で生きる人々、孤独な魂、負け犬たちの悲哀や喜びを、まるで一本の短編映画のように描き出します。
ジャズ、ブルース、フォーク、ロックンロールといったアメリカ音楽のルーツに根差しながらも、その表現方法は極めて独創的で、聴く者を一瞬で楽曲の世界へ引き込みます。
ロックの殿堂入りも果たしたレジェンド
その功績は広く認められており、2011年にはロックの殿堂入りを果たしています。
ニール・ヤングがプレゼンターを務めた式典では、ウェイツ自身が「曲はとても不思議なもの。まるで夢から拾い上げて、きれいにして皿に乗せるみたいだ」と語りました。
ミュージシャンからの支持も非常に厚く、ブルース・スプリングスティーンやロッド・スチュワート、スカーレット・ヨハンソンなど、数多くのアーティストが彼の楽曲をカバーしていることからも、その影響力の大きさがうかがえます。(参照:Rock & Roll Hall of Fame 公式サイト)
また、歌手活動と並行して俳優としても目覚ましい活躍を見せており、ジム・ジャームッシュやフランシス・フォード・コッポラといった名だたる監督の作品で、その唯一無二の存在感を放っています。
このように、トム・ウェイツは音楽と演技の両面で、誰にも真似できない独特の世界観を築き上げた、現代における真のアーティストなのです。
1-2. 音楽性の変遷:三つの時代
トム・ウェイツの長大な音楽史は、大きく3つの時代に分けて理解することができます。
それぞれの時代で彼の音楽は全く異なる様相を呈しており、その変遷を辿ることは、一人のアーティストの芸術的進化のドラマを目の当たりにするような興奮に満ちています。
第1期:アサイラム時代の叙情と酩酊 (1973-1982)
キャリアの初期、アサイラム・レコードに在籍していた時代のトム・ウェイツは、ロサンゼルスの裏町に生きる人々、孤独、失恋、そして深夜のセンチメンタリズムを歌う「ピアノ・マン」でした。
ジャック・ケルアックやチャールズ・ブコウスキーといったビート文学の作家たちに影響を受けた歌詞の世界は、ジャズ、ブルース、フォークが溶け合ったメロディに乗せて、気だるくもロマンティックに描かれます。
深夜のダイナー、安ホテル、場末のバーが彼の物語の舞台であり、しゃがれてはいるものの、まだ若々しさが残る声で、都会の夜の心象風景をスケッチしていきました。
この時代の彼は、多かれ少なかれ伝統的なシンガーソングライターの枠組みの中にいましたが、その唯一無二のキャラクターと詩情はすでに確立されていました。
第2期:アイランド時代の革新と実験 (1983-1993)
1980年、脚本家のキャスリーン・ブレナンとの結婚は、トム・ウェイツの人生と音楽に革命的な変化をもたらしました。
彼女はウェイツにキャプテン・ビーフハートのような前衛的な音楽を紹介し、彼の内なる実験精神を解放する触媒となります。
アサイラムを離れ、アイランド・レコードへ移籍した彼は、それまでのピアノマンとしてのイメージを自ら叩き壊します。
1983年の『Swordfishtrombones』を皮切りに、彼の音楽は予測不可能な方向へと舵を切りました。
マリンバ、バグパイプ、ガラスハーモニカ、ガラクタから作られたパーカッションといった異質な楽器が混ざり合い、歌詞の登場人物はより奇妙でグロテスク、しかし愛すべきキャラクターへと変化。
サウンドは「ガラクタ置き場のオーケストラ」とでも言うべき、原始的でインダストリアルな質感を持つようになります。
この時代、彼は伝統的なソングライティングの構造を破壊し、音のコラージュによって物語を構築するという、全く新しい表現方法を確立しました。
第3期:ANTI-時代の円熟と深化 (1999-現在)
長い沈黙を破り、インディーズ・レーベルANTI-から『Mule Variations』を発表した1999年以降、トム・ウェイツは円熟期に入ります。
この時代の彼の音楽は、アサイラム時代の叙情性とアイランド時代の実験性が見事に融合し、より深く、より広範な世界観を獲得しています。
ブルース、ゴスペル、ロックンロールといったアメリカン・ミュージックのルーツに根差しながらも、そのサウンドは常に前衛的。
家族や故郷といったパーソナルなテーマが増え、声はさらに凄みを増し、もはや楽器の一部として機能しています。
ヒューマン・ビートボックスを取り入れるなど、新たな試みも怠りません。
この時期の彼は、もはや特定のジャンルに属さない、「トム・ウェイツ」という一つのジャンルそのものとして、孤高の存在感を放っています。
2. 全スタジオ・アルバム徹底レビュー 〜アサイラム・イヤーズ〜
彼の音楽的冒険の全てが刻まれたスタジオ・アルバムを、リリース順に1枚ずつ、可能な限り全曲にコメントを添えて解説します。
1st: Closing Time (1973)
記念すべきデビュー・アルバム。
ロサンゼルスのうらぶれたバーで弾き語りをしている青年が目に浮かぶような、瑞々しくも物悲しい名盤。
ジャズ、フォーク、ブルースがナチュラルに融合し、後のウェイツの原石がここにあります。
しゃがれてはいるものの、キャリアの中で最もクリアで若い声が聴けるのも特徴です。
多くのファンが彼の最高傑作であり、彼の音楽への入り口としてこれ以上のものは無いと評価しています。
- Ol’ ’55: キャリアの幕開けを飾る名曲。「オール55」とは、1955年型の古い車という意味で、実際にトム・ウェイツが乗っていた55年型ビュイック・ロードマスターのことだと言われています。夜明けのハイウェイを走る情景が目に浮かぶ、切なくも美しいピアノ・バラード。後にイーグルスがカバーしたことで、彼の名は広く知られることとなりました。
- I Hope That I Don’t Fall in Love with You: バーで一人飲む男の独白。美しい女性に惹かれながらも、傷つくことを恐れる臆病な心を歌うアコースティック・ナンバー。多くの人が共感できるであろう普遍的なテーマを、シンプルで心に響く言葉で綴っています。
- Virginia Avenue: 軽快なジャズ・チューン。アップライトベースの心地よいウォーキング・ラインの上で、少しだけ陽気なウェイツが顔を覗かせます。それでも歌詞には都会の夜の一抹の寂しさが漂います。
- Old Shoes (& Picture Postcards): 古い靴と絵葉書が喚起する、過去の恋人との思い出。カントリー・フレイバー溢れる、温かくもほろ苦い一曲。彼の旅人としての一面が早くも現れています。
- Midnight Lullaby: 「真夜中の子守唄」というタイトル通り、優しく穏やかなメロディ。歌詞を見ずともその情景が伝わってくる表現力の豊かさは、デビュー作とは思えません。夜の静寂の中に溶けていくような歌声が印象的です。
- Martha: 本作のハイライトの一つ。初老らしき男が昔の恋人マーサに40年ぶりに長距離電話をかけるという、短編小説のような楽曲。ピアノの旋律が物語の情感を深く描き出し、聴く者の涙を誘います。「一緒になれる運命ではなかったけど、それでもおれは君を愛してる」という想いの重さに震える名曲です。
- Rosie: アップテンポでご機嫌なピアノ・ロックンロール。若き日の過ちと、それ故に失った恋人ロージーへの想いを、少しやんちゃな雰囲気で歌います。
- Lonely: タイトル通り、孤独をストレートに歌ったブルージーなバラード。シンプルな構成だからこそ、彼の声の表現力が際立ちます。
- Ice Cream Man: 楽しげな曲調とは裏腹に、どこか怪しげな雰囲気が漂うジャズ・ナンバー。「アイスクリーム屋」が何を意味するのか、想像を掻き立てられる歌詞がユニークです。彼のユーモアのセンスが光ります。
- Little Trip to Heaven (On the Wings of Your Love): 天国への小さな旅。愛する人と共にいる幸福感を、甘く穏やかに歌い上げるストレートなラブソング。
- Grapefruit Moon: グレープフルーツのような色をした月を見上げながら、遠い恋人を想う。本作中最もロマンティックで詩的な一曲。「時の流れは戻せやしない」という歌詞が、美しさの中に切なさを加えます。
- Closing Time: アルバムの最後を飾るインストゥルメンタル。閉店時間、客が去った後のバーの静けさと余韻を感じさせる名演。美しいトランペットの音色が、長い夜の終わりを静かに告げます。
2nd: The Heart of Saturday Night (1974)
前作の路線を継承しつつ、よりジャジーで都会的なサウンドへと進化したセカンド・アルバム。
「土曜の夜」をコンセプトに、街へ繰り出す高揚感からその後に訪れる孤独までを鮮やかに切り取っています。
ストリングスのアレンジも効果的で、映画のサウンドトラックのような趣があります。
- New Coat of Paint: 新しいペンキを塗って気分を一新するように、新しい恋への期待を歌うスウィンギーなオープニング。軽快なベースとサックスが土曜の夜の始まりを告げます。
- San Diego Serenade: 故郷サンディエゴへの想いを綴った美しいバラード。ストリングスが郷愁を誘う。「君に出会うまで、僕は本当の恋を知らなかった」という一節が心に残ります。
- Semi Suite: トラックドライバーの視点から描かれるロード・ソング。カントリー調のメロディに乗せて、長距離運転の孤独とダイナーでの束の間の出会いを歌います。
- Shiver Me Timbers: 「船乗りみたいに骨まで凍えさせてくれ」と歌う、海への憧憬に満ちた壮大なバラード。ピアノとストリングスがドラマティックに盛り上がります。
- Diamonds on My Windshield: フロントガラスについた雨粒をダイヤモンドに喩える詩的な表現が光る、ポエトリー・リーディング。アップライトベースをバックに、夜のドライブの情景を語るように歌います。
- (Looking for) The Heart of Saturday Night: アルバムのタイトル曲にして、彼の代表曲の一つ。土曜の夜の喧騒を求めて夜の街に車を走らせる、孤独な男の姿を描きます。シンプルで心に染み入るメロディと歌詞が完璧にマッチしています。
- Fumblin’ with the Blues: ブルースとの不器用な格闘。よりブルース色が濃く、しゃがれ声も板についてきた一曲。ユーモラスな歌詞がウェイツらしいです。
- Please Call Me, Baby: 電話を待つ男の切ない心情を歌ったピアノ・バラード。孤独な夜の静けさと焦燥感がひしひしと伝わってきます。
- Depot, Depot: バス停での光景をスケッチした楽曲。旅立つ人々、見送る人々、それぞれのドラマを軽快なジャズに乗せて歌います。
- Drunk on the Moon: 月に酔ってしまった男の歌。幻想的でロマンティックな歌詞と、浮遊感のあるメロディが一体となった名曲です。
- The Ghosts of Saturday Night (After Hours at Napoleone’s Pizza House): 土曜の夜が明けた後のピザハウスの情景を描いた、長尺のポエトリー・リーディング。ジャズの演奏をバックに、深夜の住人たちの姿が目に浮かぶようです。
3rd: Nighthawks at the Diner (1975)
ライブ・アルバムと銘打たれているものの、実際にはスタジオに少人数の観客を招いて行われたセッションを収録した、いわば「疑似ライブ盤」。
曲の合間の長尺のMC(語り)が素晴らしく、彼のスタンダップ・コメディアンやストーリーテラーとしての一面が存分に発揮されています。
演奏は最高のジャズバンドをバックに、リラックスした雰囲気で進行します。
(注:本作は語りが多いため、楽曲を中心に抜粋してコメントします)
- Emotional Weather Report: 「感情の天気予報」というユニークなタイトルの曲。クールなジャズに乗せて、恋模様を天気予報に見立てて語る、彼のセンスが光る一曲。
- Eggs and Sausage (In a Cadillac with Susan Michelson): キャデラックに乗ってダイナーに乗り付ける男女の物語。ファンキーな演奏が楽しめる、グルーヴィーなナンバー。
- Better Off Without a Wife: 結婚生活の面倒くささを歌いながらも、最後には「君が必要だ」と締めくくる、愛情の裏返しのようなバラード。彼のユーモアと優しさが詰まっています。
- Nighthawk Postcards (From Easy Street): 深夜の街の風景を次々と描写していく、本作のハイライトとも言える長尺のポエトリー・リーディング。情報量の洪水とクールな演奏が圧巻です。
- Warm Beer and Cold Women: 「ぬるいビールと冷たい女」という、これ以上ないほどウェイツ的なテーマ。どうしようもない状況を嘆くブルースで、彼の歌声が最も似合うシチュエーションの一つです。
- Big Joe and Phantom 309: 有名なカントリーソングのカバー。トラック野郎の幽霊の物語を、ウェイツの語り口が臨場感たっぷりに伝えます。
4th: Small Change (1976)
商業的にも批評的にも成功を収めた、アサイラム時代の最高傑作との呼び声も高いアルバム。
アルコール依存が悪化していた時期に制作され、全体的にダークで荒涼とした雰囲気が漂います。
しかし、その詩情はより深く、しゃがれ声は凄みを増し、「負け犬の美学」が極致に達しています。
ストリングスのアレンジも秀逸です。
- Tom Traubert’s Blues (Four Sheets to the Wind in Copenhagen): オーストラリアの国民的楽曲「Waltzing Matilda」のフレーズを引用した、彼の代表曲。異国の地で酔い潰れ、孤独と絶望を歌う壮大なバラード。日本では2009年のドラマ『不毛地帯』のエンディング曲に使われました。20代半ばでこの深みに到達したことに驚愕するしかありません。
- Step Right Up: まるで怪しげなセールスマンの口上のような、早口のトーキング・ブルース。消費社会を痛烈に皮肉った歌詞が圧巻です。
- Jitterbug Boy (Sharing a Curbstone with Chuck E. Weiss, Robert Marchese, Paul Body and The Mug and Artie): 友人たちとの路上での会話を元にした楽曲。人生の悲哀とユーモアが入り混じる、ウェイツらしい人間賛歌。
- I Wish I Was in New Orleans (In the Land of Mardi Gras): ニューオーリンズへの憧れを歌った、郷愁に満ちたバラード。ブラスバンドの響きが物悲しいです。
- The Piano Has Been Drinking (Not Me) (An Evening with Pete King): 「ピアノが酔っ払ってるんだ、俺じゃない」という言い訳が秀逸なコミックソング。酔っ払いの酩酊状態を巧みに表現した演奏と歌唱が見事です。
- Invitation to the Blues: ブルースへの招待状。ハードボイルド小説のような世界観を持つ、クールでメランコリックな名曲。
- Pasties and a G-String (At the Two O’Clock Club): ストリップ劇場とそのダンサーを描いた楽曲。猥雑さと哀愁が同居しています。
- Bad Liver and a Broken Heart (In Lowell): ボクサー崩れの男の独白。壊れた肝臓と失恋を抱え、それでも生きていく男の姿が胸を打ちます。
- The One That Got Away: 逃した魚は大きい、という使い古された言葉に、新たな詩情を吹き込んだ曲。ジャジーな演奏が夜の闇に溶けます。
- Small Change (Got Rained on with His Own .38): 小悪党の無様な死を描いた、冷徹でノワールな一曲。乾いたサックスの音が印象的です。
- I Can’t Wait to Get Off Work (And See My Baby on Montgomery Avenue): 仕事が終わって恋人に会うのが待ちきれない、という純粋な気持ちを歌った、アルバムの中で唯一とも言える希望に満ちた曲。一日の終わりに安らぎを与えてくれます。
5th: Foreign Affairs (1977)
よりフィルム・ノワール的な世界観を追求した野心作。
全体的にダークで、ジャズへの傾倒がさらに深まっています。
ベット・ミドラーとのデュエットも収録され、ストーリーテラーとしての側面が強調されたアルバム。
前作『Small Change』の成功を受け、やや実験的なアプローチも見られます。
- Cinny’s Waltz: 映画のオープニングのように幕を開ける美しいインストゥルメンタル。もの悲しいワルツがアルバムの世界観へと誘います。
- Muriel: 酒場で出会った女性ムーリエルへの想いを歌う、しっとりとしたピアノ・バラード。孤独な男の心情が痛いほど伝わってきます。
- I Never Talk to Strangers: ベット・ミドラーとのデュエット曲。バーで出会った男女の駆け引きをミュージカルのように描く。二人の対照的な歌声のコンビネーションが絶妙で、物語に深みを与えています。
- Medley: Jack & Neal / California, Here I Come: ビート文学の英雄ジャック・ケルアックとニール・キャサディに捧げられた曲。アップテンポなジャズに乗せて、放浪への憧れを歌います。
- A Sight for Sore Eyes: 古い友人との再会と、過ぎ去った時間への寂寥感を描いたバラード。「蛍の光」のメロディが引用されているのが印象的です。
- Potter’s Field: ウェイツとボブ・アルシヴァーによる共作。殺人事件を描いた長尺の組曲で、スリリングな語りとオーケストレーションが圧巻。ウェイツのキャリアの中でも特に実験的な一曲です。
- Burma-Shave: ヒッチハイクで田舎町を旅する男女の短い物語。ロードムービーのような情景が目に浮かぶ、詩的なポエトリー・リーディング。
- Barber Shop: 軽快なラグタイム調の楽曲。床屋での他愛ない会話が、古き良きアメリカの風景を思い起こさせます。
- Foreign Affair: パリを舞台にした表題曲。異国での孤独と束の間のロマンスを、洗練されたジャジーなアレンジで描く、大人のためのバラードです。
6th: Blue Valentine (1978)
これまで多用してきたアコースティック・ピアノやストリングスを減らし、エレクトリック・ギターを前面に押し出したサウンドが特徴。
ブルース色が格段に濃くなり、よりタフでハードボイルドな世界観が展開されます。
リッキー・リー・ジョーンズとの恋愛が影響しているとも言われる、乾いた情感が漂う作品です。
- Somewhere (from “West Side Story”): ミュージカル『ウエスト・サイド物語』の名曲をカバー。壮大なストリングスをバックに、絶望的な状況の中での希望を絞り出すように歌う。意表を突く選曲とアレンジが見事です。
- Red Shoes by the Drugstore: ドラッグストアのそばにある赤い靴。少女への仄かな想いを歌った、ザラついた感触のロック・ナンバー。
- Christmas Card from a Hooker in Minneapolis: ミネアポリスの娼婦から届いたクリスマスカード、という設定で歌われる物語。幸せそうな文面の裏に隠された悲しい真実が明かされるラストは圧巻。ウェイツのストーリーテリングの極致と言える名曲です。
- Romeo Is Bleeding: 撃たれて死にゆくギャングの最期を、クールなブルース・ロックに乗せて描きます。緊迫感あふれるギターリフと生々しい歌詞が強烈です。
- $29.00: 29ドルで買われた少女の悲劇を歌う、重く引きずるようなブルース。社会の暗部をえぐるような歌詞が胸に突き刺さります。
- Wrong Side of the Road: 人生の裏街道を生きる男の覚悟を歌った、力強いロック・チューン。
- Whistlin’ Past the Graveyard: 墓場のそばを口笛を吹きながら通り過ぎる、というブルースの常套句を用いたファンキーな楽曲。不吉な状況を虚勢を張って乗り切ろうとする男の姿がユーモラスです。
- Kentucky Avenue: 幼馴染で足の不自由な少女への想いを歌った、痛切なバラード。子供の頃の思い出と、彼女を連れてここではないどこかへ行きたいという願いが胸を打ちます。
- A Sweet Little Bullet from a Pretty Blue Gun: 美しい青い銃から放たれる甘い小さな弾丸。破滅的な恋愛を歌った、退廃的で美しいバラードです。
- Blue Valentines: アルバムの最後を飾るタイトル曲。エレクトリック・ギター一本をバックに、失恋の痛みを絞り出すように歌います。孤独と絶望が滲み出る、キャリア屈指の名演です。
7th: Heartattack and Vine (1980)
アサイラム・レコードからの最後のアルバム。
前作のブルース/R&B路線をさらに推し進め、サウンドはよりラウドで荒々しくなりました。
しゃがれ声は完成の域に達し、タフなロックンローラーとしての一面と、繊細なバラード作家としての一面が同居する、アサイラム時代の集大成的な作品です。
- Heartattack and Vine: タイトル通り、心臓発作とブドウの蔓が絡みつくような、不穏でダーティなブルース・ロック。後のキャリアに繋がるサウンドの萌芽が感じられます。
- In Shades: レイ・チャールズを彷彿とさせるR&Bナンバー。オルガンとホーンがご機嫌なグルーヴを生み出しています。
- Saving All My Love for You: スタンダード・ナンバーのような風格を持つ、オーセンティックなピアノ・バラード。ストレートなラブソングは彼には珍しいですが、絶品です。
- Downtown: 都会のダウンタウンの喧騒と孤独を歌います。ミドルテンポのロックで、どこか物悲しさが漂います。
- Jersey Girl: ニュージャージーの女の子への愛を歌った、彼のキャリアで最も有名でロマンティックな曲の一つ。このアルバム発表後に結婚した妻キャスリーンに捧げた曲とも言われ、ブルース・スプリングスティーンによるカバーで広く知られるようになりました。
- ‘Til the Money Runs Out: 金が尽きるまで飲み明かそうぜ、と歌うワイルドなロックンロール。
- On the Nickel: “The Nickel” と呼ばれるロサンゼルスの貧民街に生きる人々を描いた、胸を締め付けるようなバラード。映画の主題歌にもなり、彼の優しさが滲み出る名曲です。
- Mr. Siegal: ラスベガスを舞台にした、ギャングスターについてのブルージーな楽曲。彼の描くキャラクターは常に魅力的です。
- Ruby’s Arms: 恋人が目覚める前にそっと去って行こうとしている兵士の歌。アコーディオンの音色が哀愁を誘う、アルバムの最後を飾るにふうさわしい感動的なバラードです。
3. 深みを増すトム・ウェイツ 代表曲の変遷
3-1. 傑作と名高いアルバムレイン・ドッグ
1980年代に入り、トム・ウェイツの音楽は劇的な変化を遂げます。
その象徴であり、キャリア中期以降の最高傑作と名高いのが、1985年にリリースされたアルバム『Rain Dogs』(レイン・ドッグ)です。
このアルバムは、ローリングストーン誌が選ぶ「1980年代の最も偉大なアルバム100枚」にも選出されるなど、批評的にも絶大な評価を受けました。(参照:Rolling Stone)
この変化の背景には、公私にわたるパートナーであるキャスリーン・ブレナンの存在がありました。
彼女の影響でキャプテン・ビーフハートのような前衛的な音楽に触れたウェイツは、それまでのピアノマンというイメージを自ら破壊。
ガラクタを叩くようなパーカッションやマリンバ、異国の楽器を取り入れた、実験的で摩訶不思議なサウンドを構築し始めます。
この路線は1983年の『Swordfishtrombones』から始まり、『Rain Dogs』で一つの頂点を迎えます。
『Rain Dogs』は、その実験精神がポップさと完璧に融合した奇跡的なアルバムです。
タイトルは「雨で匂いを消され、家に帰れなくなった犬たち」を意味し、ニューヨークを舞台に社会からはみ出した人々(アウトサイダー)への温かいまなざしに満ちた賛歌となっています。
多彩な楽曲が詰まった万華鏡
このアルバムには、キューバ音楽風の「Jockey Full of Bourbon」や、ニューオーリンズの葬送音楽のような「Anywhere I Lay My Head」、そしてロッド・スチュワートのカバーで大ヒットしたポップな「Downtown Train」まで、非常に多彩な楽曲が収録されています。
この一枚を聴けば、トム・ウェイツというアーティストの引き出しの多さと、音楽的冒険心の深さを体感できるはずです。
ギタリストのマーク・リボーや、ローリング・ストーンズのキース・リチャーズの参加も、アルバムに独特の質感を与えています。
『Rain Dogs』は、多くのファンが「トム・ウェイツにハマったきっかけのアルバム」として挙げる作品です。
初期の叙情的な世界とは全く異なりますが、ここから彼のより深く、混沌とした音楽の迷宮にのめり込む人も少なくありません。
3-2. 心に沁みる名バラードのタイム
実験的な楽曲が並ぶ『Rain Dogs』の中でも、ひときわ静かな輝きを放つ名バラードが「Time」(タイム)です。
この曲は、トム・ウェイツがキャリアを通じて数多くの名バラードを生み出してきた中でも、特に人気の高い一曲として知られています。
アコーディオンとピアノが奏でる物悲しくも美しいメロディに乗せて、彼は人生の儚さや、容赦なく過ぎ去っていく時間について歌います。
歌詞には、”Things are pretty lousy for the little things”(取るに足らない物事には、何もかもうんざりすることばかりだ)や “And you’re east of East St. Louis and the wind is making speeches”(君はイーストセントルイスからさらに東へ。風の音だけが、やけに雄弁に響いている)といった、彼ならではの詩的なフレーズが散りばめられています。
これらは、日常の風景に潜む哲学的な洞察を感じさせます。
この曲を聴いていると、まるで古いヨーロッパ映画のワンシーンを見ているような感覚になります。
人生の苦みと、それでもなお存在する美しさを同時に感じさせてくれる、深く、味わい豊かな楽曲です。
深夜に一人でグラスを傾けながら聴くのに、これほどふさわしい曲もありません。
「Time」は、トム・ウェイツが単なる奇人ではなく、人間の感情の機微を深く理解し、それを普遍的な歌へと昇華させることができる偉大なソングライターであることを証明しています。
彼の音楽の深淵に触れたいなら、ぜひじっくりと聴いていただきたい一曲です。
3-3. 入門に最適なベストアルバムは?
「トム・ウェイツを聴き始めたいけれど、オリジナルアルバムは数が多くて選べない。まずはベストアルバムから…」と考える方も多いかもしれません。
しかし、ここで一つ注意点があります。
実は、トム・ウェイツにはキャリア全体を網羅した決定版と呼べる公式のベストアルバムが存在しないのです。
これは、彼の音楽性が時代ごとに大きく変化するため、一枚のディスクにまとめるのが非常に難しいからだと言われています。
初期のフォーキーな楽曲と、中期の実験的なインダストリアルサウンドを並べると、同じアーティストの作品とは思えないほどの振れ幅があるのです。
非公式盤や偏った選曲盤には注意
市場にはいくつかベスト盤と銘打ったCDも出回っていますが、その多くはレーベルが独自に編集したもので、選曲に偏りがある場合があります。
特に、キャリア初期のアサイラム時代と、音楽性が激変したアイランド時代以降の楽曲が混在するベスト盤は、彼の音楽性の変遷を知らない初心者にとってはかえって混乱を招く可能性もあります。
だからこそ、多くのファンが推奨するのが、ベストアルバムではなく、彼のキャリアを代表するオリジナルアルバムから聴き始めるという方法です。
そうすることで、各時代のコンセプトや世界観を深く味わうことができます。
- 叙情的な初期が好きなら: まずは『Closing Time』や『The Heart of Saturday Night』から。
- 実験的でワイルドな中期以降に興味があれば: 『Rain Dogs』や、よりブルースに根差した『Mule Variations』がおすすめです。
このように言うと、まずは彼のキャリアのどこか一つの時代の「代表作」にじっくりと浸ってみることが、結果的にトム・ウェイツの世界を最も深く楽しむための近道となるでしょう。
3-4. ロックの殿殿堂入りした彼の現在
トム・ウェイツは、2011年にロックの殿堂入りを果たし、レジェンドとしての地位を不動のものとしました。
現在も彼はマイペースながら精力的に活動を続けています。
大規模なツアーを行うことは稀になりましたが、その創造意欲は全く衰えていません。
音楽活動としては、2011年にリリースした『Bad as Me』が、現時点での最新オリジナルアルバムです。
このアルバムは、初期のようなロックンロールやブルースに回帰した力強いサウンドが特徴で、盟友であるキース・リチャーズも参加するなど、彼のキャリアの集大成的な内容となっています。
この作品は批評家からも高く評価されました。
一方で、近年は俳優としての活動がより目立っています。
もともと数多くの映画に出演していましたが、最近でも以下のような話題作でその姿を見ることができます。
| 公開年 | 作品名 | 監督 | 役どころ |
|---|---|---|---|
| 2018 | 『バスターのバラード』 | コーエン兄弟 | 金鉱掘りの老人役でほぼ一人芝居をこなし、圧巻の演技を披露。 |
| 2019 | 『デッド・ドント・ダイ』 | ジム・ジャームッシュ | 森で暮らす謎の隠者役で、独特の存在感を放つ。 |
| 2021 | 『リコリス・ピザ』 | ポール・トーマス・アンダーソン | 往年の映画監督役で短い出演ながら、強烈なインパクトを残す。 |
新作アルバムの発表は長らくありませんが、いつサプライズが起きてもおかしくないのがトム・ウェイツです。
彼の現在の活動に注目し続けることも、ファンにとっての楽しみの一つと言えるでしょう。
公式サイトでは、彼の最新情報が随時更新されています。
4. 全スタジオ・アルバム徹底レビュー 〜アイランド・イヤーズ以降〜
8th: Swordfishtrombones (1983)
トム・ウェイツ史上、最も重要なターニングポイントとなった革命的なアルバム。
伝統的な楽器編成を放棄し、ガラクタ置き場から集めてきたような楽器や異国の民族楽器を多用。
歌詞の世界も、郊外に住む主婦や戦争で精神を病んだ帰還兵など、より奇妙で超現実的なキャラクターが登場します。
音楽の既成概念を破壊し、再構築した大傑作です。
- Underground: 地下で暮らす人々についての歌。マーチングバンドのような歪んだリズムと、金管楽器の咆哮でアルバムは衝撃的な幕開けを迎えます。
- Shore Leave: 休暇で港町に降り立った船乗りの独白。エキゾチックなパーカッションとマリンバが、異国の地の気だるい空気感を見事に表現。
- Dave the Butcher: 不気味なオルガンが響くインストゥルメンタル。短いながらもホラー映画のような強烈な印象を残します。
- Johnsburg, Illinois: 妻キャスリーンに捧げられた、わずか1分半のピアノ・バラード。アルバムの中で唯一、かつての彼を思わせる瞬間であり、その純粋さが際立ちます。
- 16 Shells From a Thirty-Ought-Six: 怒れる農夫が、喋るカラスを追いかけるブルース。鎖を引きずるようなパーカッションと唸るような歌声が暴力的。
- Town with No Cheer: 活気を失ったオーストラリアの田舎町を描いた、物悲しいアコーディオン・ワルツ。
- In the Neighborhood: 狂気じみた隣人たちを描写する、歪んだマーチングバンド・ソング。楽しげな曲調と裏腹に、歌詞の内容は不気味そのもの。
- Just Another Sucker on the Vine: カーニバルの呼び込み口上のようなインストゥルメンタル。
- Frank’s Wild Years: 飼い犬に火をつけ、家を出ていく男フランクの物語。後の舞台作品へと発展する重要な楽曲。ジャズの演奏をバックにした、ウェイツの独壇場。
- Swordfishtrombone: 戦争で片目を失った男の歌。タイトルにもなった「メカジキトロンボーン」という奇妙な楽器が登場する、幻想的な一曲。
- Down, Down, Down: 転落していく男の人生を歌った、パーカッシヴなブルース。
- Soldier’s Things: 退役軍人の遺品整理を描いた、胸を打つバラード。持ち主を失ったモノたちが、その男の人生を静かに物語る。
- Gin Soaked Boy: 酒浸りの少年。ブルージーで投げやりな雰囲気が漂う。
- Trouble’s Braids: 逃亡者の焦燥感を表現した、性急なリズムの短い曲。
- Rainbirds: アルバムの終わりを告げる、美しくも不穏なアンビエント・インストゥルメンタル。ガラスハーモニカの音が夢の世界へと誘う。
9th: Rain Dogs (1985)
『Swordfishtrombones』で始まった革命をさらに推し進め、トム・ウェイツの名声を決定づけた最高傑作。
ニューヨークを舞台に、社会からはみ出した「レイン・ドッグス(雨に匂いを消され、家に帰れなくなった犬たち)」の姿を描きます。
ギタリストのマーク・リボーが初参加し、その鋭利なギターサウンドがウェイツの世界観をさらに豊かにしました。
全19曲、捨て曲なしの奇跡的なアルバムです。
- Singapore: クルト・ヴァイル風のキャバレー音楽と船乗りの舟歌が融合したような、異国情緒あふれるオープニング。ここではないどこかへの旅立ちを宣言します。
- Clap Hands: 骸骨のようなパーカッションと不気味なベースラインが印象的な、呪術的な一曲。
- Cemetery Polka: 奇妙で不愉快な親戚一同を紹介する、狂気のポルカ。ブラックユーモアが炸裂。
- Jockey Full of Bourbon: バーボンを呷る騎手。マンボのようなリズムとマーク・リボーの神経質なギターが絡み合う、映画『ダウン・バイ・ロー』でも効果的に使われた名曲。
- Tango Till They’re Sore: 棺桶の中でタンゴを踊る男の歌。酔いどれピアノが奏でる、退廃的で美しいメロディ。
- Big Black Mariah: 囚人護送車(マライア)を歌った、力強いチェイン・ギャング・ブルース。キース・リチャーズがギターで参加。
- Diamonds & Gold: 金とダイヤモンドへの欲望を歌う、ノイジーでインダストリアルな楽曲。
- Hang Down Your Head: 亡くなった恋人への想いを歌った、カントリー調の美しいバラード。キャスリーン・ブレナンとの共作。
- Time: 人生の儚さと時間の流れを歌った、キャリア屈指の感動的なバラード。アコーディオンとピアノが静かに胸に染みる。
- Rain Dogs: アルバムのタイトル曲。都会のはぐれ者たちを歌ったアンセム。力強いビートに乗せて、彼らへの共感を叫ぶ。
- Midtown (Instrumental): 都会の喧騒を表現したかのような、フリージャズ的なインスト。
- 9th & Hennepin: ミネアポリスの交差点の汚らしい情景を、生々しく描写するポエトリー・リーディング。
- Gun Street Girl: 銃を持った女のために故郷を捨てる男の物語。バンジョーが印象的な、カントリー・ブルース。
- Union Square: ニューヨークのユニオンスクエアでの出来事を歌った、アップテンポなR&Bナンバー。
- Blind Love: 盲目的な愛を歌う、ストレートなカントリー・ソング。キース・リチャーズがボーカルでも参加。
- Walking Spanish: 死刑執行室へ向かう男の最後の歩み。緊迫感のあるリズムと鋭いギターが印象的。
- Downtown Train: 地下鉄の窓から見かける女性に恋する男の歌。彼の楽曲の中では非常にキャッチーでポップなメロディを持ち、ロッド・スチュワートのカバーで大ヒットした。
- Bride of Rain Dog (Instrumental): レイン・ドッグの花嫁。アコーディオンが主役の短いインスト。
- Anywhere I Lay My Head: ニューオーリンズの葬送音楽のようなブラスバンドをバックに、「どこでだって頭を横たえ、そこを我が家と呼ぼう」と歌う、感動的なフィナーレ。
10th: Franks Wild Years (1987)
『Swordfishtrombones』収録の楽曲から発展した同名の舞台作品の音楽をアルバム化したもの。
『Swordfishtrombones』『Rain Dogs』と本作で「フランク三部作」が完結します。
よりシアトリカル(演劇的)で、登場人物のセリフなども挿入されており、一つの物語を聴き通すような体験ができます。音楽的にもさらに自由度を増しています。
- Hang On St. Christopher: 聖クリストファーにしがみつけ、と歌う疾走感あふれるオープニング。ガラクタを叩きつけるようなパーカッションと歪んだホーンが旅の始まりを告げます。
- Straight to the Top (Rhumba): ラスベガスでの成功を夢見る男の歌。チープで猥雑なルンバのリズムが欲望を掻き立てます。
- Blow Wind Blow: 故郷を離れ、荒野をさまよう男の心情を歌うブルース。ハーモニカの音色が物悲しいです。
- Temptation: 彼の楽曲の中でも特に有名な一曲。ラテンのリズムに乗せて、抗えない誘惑について歌います。マーク・リボーのギターが妖艶です。
- Innocent When You Dream (Barroom): 酒場の喧騒の中で歌われる、本作のテーマ曲とも言える美しいワルツ。「夢を見ている時、君は無垢でいられる」という歌詞が胸を打ちます。
- I’ll Be Gone: この町を出ていく、という決意を歌う、ゴスペル風味の力強い楽曲。
- Yesterday Is Here: 過去の記憶に取り憑かれた男の歌。チェロとアコーディオンが奏でるメロディが、まるで古いヨーロッパ映画のように美しいです。
- Please Wake Me Up: 悪夢から覚めさせてくれ、と懇願する子供のような歌。オルゴールのような音色が逆に不気味です。
- Frank’s Theme: 主人公フランクのテーマ。哀愁漂うインストゥルメンタル。
- More Than Rain: 人生における絶望と、それでも残る僅かな希望を歌う壮大なバラード。
- Way Down in the Hole: 悪魔と戦うためには、穴の底まで下りていかなければならない、と歌うゴスペル・ブルース。テレビドラマ『THE WIRE/ザ・ワイヤー』の主題歌として有名です。
- Straight to the Top (Vegas): ラスベガス版。よりゴージャスで、より胡散臭いアレンジが施されています。
- I’ll Take New York: ニューヨークへの憧れと狂気を歌う、フリージャズ的なナンバー。
- Telephone Call from Istanbul: イスタンブールからの電話。スパイ映画のような緊張感が漂います。
- Cold Cold Ground: 冷たい地面の下に眠る人々への想いを歌った、アコースティックなフォーク・ソング。
- Train Song: 静かなアコースティック・ギターに乗せて、人生を列車に喩えて歌う、アルバムの最後を飾るにふさわしい内省的な曲。
- Innocent When You Dream (78): まるで古いSPレコードから流れてくるような、ノスタルジックなバージョン。物語のエンディングを静かに締めくくります。
11th: Bone Machine (1992)
5年間の沈黙を破ってリリースされた、キャリアの中で最もダークで終末的なサウンドを持つアルバム。
カリフォルニアの農場にある地下室で録音され、そのサウンドは原始的で暴力的。
パーカッションは骨や金属片を叩く音で作られ、歌詞は死、宗教、殺人といったテーマを扱います。
しかし、その中にも驚くほど美しいバラードが共存する、ウェイツの深淵を覗き込むような傑作です。
第35回グラミー賞で「最優秀オルタナティヴ・ミュージック・アルバム」を受賞しました。
- Earth Died Screaming: 地球は叫びながら死んだ、と歌うアポカリプティックなオープニング。スティックで骨を叩くようなパーカッションと、プライマス不動のベーシスト、レス・クレイプールのベースが唸ります。
- Dirt in the Ground: 死ねば誰もが土塊になるだけ、という虚無感を歌うゴスペル・ソング。彼の絞り出すようなファルセットが痛切です。
- Such a Scream: まるで壊れた機械のような、インダストリアルでノイジーなロック。
- All Stripped Down: 全てを剥ぎ取られ、本質だけが残る。ミニマルで呪術的なリズムが印象的です。
- Who Are You: 相手を詰問するような、不穏で攻撃的なブルース。
- The Ocean Doesn’t Want Us: 海さえも俺たちを受け入れてくれない、と歌う絶望的な歌。
- Jesus Gonna Be Here: もうすぐジーザスがやってくる、と信じる男の純粋な信仰心を歌うブルース。ユーモラスだが、どこか切実です。
- A Little Rain (for Clyde): 雨が降らなければ何も育たない、というシンプルな真理を歌う、アルバムの中で一筋の光のように響く美しいバラード。
- In the Colosseum: 古代ローマのコロッセウムでの殺戮ショーを描いた、狂気のマーチ。
- Goin’ Out West: 映画『ファイト・クラブ』でも使われた、暴力的でマッチョなロックンロール。ハリウッドに行ってスターになる、という野望を凶暴に歌い上げます。
- Murder in the Red Barn: 赤い納屋での殺人事件。淡々と語られる情景が逆に恐ろしい、フォーク・ブルース。
- Black Wings: 黒い翼を持つ謎の男の歌。ミステリアスな雰囲気が漂います。
- Whistle Down the Wind (for M.H.): 風に向かって口笛を吹く。友人の死を悼む、鎮魂歌のような美しいバラード。
- I Don’t Wanna Grow Up: 子供のままでいたい、という普遍的な願いをパンキッシュに歌います。ラモーンズのカバーも有名です。
- Let Me Get Up on It: 短いインストゥルメンタル。
- That Feel: キース・リチャーズとの共作・共演曲。ブルースマンとしての魂の共鳴が感じられます。
12th: The Black Rider (1993)
演出家ロバート・ウィルソン、作家ウィリアム・S・バロウズとのコラボレーションによる前衛演劇『ブラック・ライダー』のための音楽。
ドイツの民話『魔弾の射手』をベースにした物語で、音楽はクルト・ヴァイルやベルトルト・ブレヒトの影響が色濃い、悪夢のキャバレー・ミュージック。
彼の音楽の中でも最も実験的で難解とされる一枚です。
(注:本作はインストゥルメンタルや断片的な曲が多いため、主要な楽曲を抜粋してコメントします)
- The Black Rider: 悪魔(ブラック・ライダー)のテーマ。歪んだカーニバルのような音楽が不安を煽ります。
- November: 物悲しいアコーディオンが響く、晩秋のような寂寥感に満ちたバラード。ストレートに「11月」と名付けられたこの曲は、季節そのものを否定するかのような歌詞が印象的です。
- Just the Right Bullets: 望み通りの結果をもたらす「魔法の弾丸」についての歌。
- Flash Pan Hunter (Intro) / That’s the Way: ウィリアム・バロウズ自身の朗読がフィーチャーされています。
- The Briar and the Rose: イバラとバラ。対照的なものが結びつく愛を歌った、アイルランド民謡のように美しい名曲。
- Russian Dance: 文字通り、狂気のロシアの踊りのようなインストゥルメンタル。
- Gospel Train / I’ll Shoot the Moon: 救済と破滅が隣り合わせになったゴスペルと、月さえも撃ち落とすと豪語する歌。
- Lucky Day: 「今日はツイてるぜ」と歌いますが、その裏には破滅の予感が漂う。ウェイツ流のアイロニーが効いたキャバレー・ソング。
- The Last Rose of Summer: 夏の最後のバラ。過ぎ去った美しさを悼む、はかなくも美しいインスト。
- Carnival: アルバムの最後を飾る、全てが終わった後のカーニバルのようなインスト。
13th: Mule Variations (1999)
概要: 7年という長いインターバルを経て、ANTI-レーベル移籍第一弾としてリリースされた傑作。
アサイラム時代の叙情性と、アイランド時代の実験性が見事に融合し、ブルース、ゴスペル、フォークといったルーツ・ミュージックへの回帰が見られます。
家族や田舎での生活といったテーマも増え、より円熟し、人間的な深みを増した作品。グラミー賞で最優秀コンテンポラリー・フォーク・アルバムを受賞しました。
- Big in Japan: 「ここではサッパリだが、日本ではビッグなんだ」と歌う、皮肉とユーモアに満ちたオープニング。インダストリアルなビートとアジア風のメロディが混ざり合います。
- Lowside of the Road: 道の低い側を歩け、というブルージーで不穏な警告。
- Hold On: 困難な状況にある人々へ「頑張れ」と語りかける、温かくも力強い応援歌。彼の楽曲の中でも特にストレートで感動的な名曲です。
- Get Behind the Mule: 頑固なラバの後ろについていけ、というブルース。レス・クレイプールのベースが再び唸ります。
- House Where Nobody Lives: 誰も住まなくなった家。過ぎ去った日々と家族の記憶を歌う、胸を締め付けるようなピアノ・バラード。
- Cold Water: 冷たい水をくれ、と叫ぶ男の歌。カントリー・ブルース調の軽快な楽曲。
- Pony: 愛するポニー(恋人の比喩)への想いを歌う、シンプルで美しいアコースティック・バラード。
- What’s He Building?: 隣の家で、あの男はいったい何を作っているんだ?という住民の噂話をコラージュした、不気味なポエトリー・リーディング。
- Black Market Baby: ブラックマーケットで売られる赤ん坊。ファンキーでグルーヴィーなサウンドに乗せて、ダークな物語が展開されます。
- Eyeball Kid: 見世物小屋の「目玉小僧」の悲哀を歌う、ジャジーでシアトリカルな一曲。
- Picture in a Frame: 君という写真を額縁に入れて飾りたい。ストレートでロマンティックなラブソング。
- Chocolate Jesus: チョコレートのジーザスしか信じない、という少年の歌。宗教への素朴な疑問とユーモアが光ります。
- Georgia Lee: 実際にあった黒人の少女の殺人事件を元にした、悲痛なフォーク・ソング。社会の無関心さを静かに告発します。
- Filipino Box Spring Hog: フィリピン式の豚の丸焼きについての歌。プリミティブなビートと語りが狂気を帯びます。
- Take It with Me: 人生で得た全ての美しい記憶を、死ぬ時に持っていく、と歌う感動的なピアノ・バラード。究極のラブソングであり、人生賛歌です。
- Come On Up to the House: 人生の困難に打ちのめされた人々を「家へおいで」と招き入れる、力強いゴスペル・ソング。アルバムを締めくくる、魂の救済の歌です。
14th & 15th: Alice / Blood Money (2002)
いずれもロバート・ウィルソン演出の舞台音楽として作られ、長らく未発表となっていた音源を、2枚同時にリリース。
『Alice』は『不思議の国のアリス』の作者ルイス・キャロルと、彼が愛した少女アリス・リデルの秘められた関係をテーマにした、夢幻的でメランコリックな作品。
『Blood Money』はゲオルク・ビューヒナーの戯曲『ヴォイツェック』を基にした、より暴力的で不協和音に満ちた作品。
光と闇、純粋さと狂気を描いた対をなす傑作です。
Alice
- Alice: 遠い昔の恋人アリスへの想いを歌う、切なくも美しいテーマ曲。
- Everything You Can Think: 子供の夢想と大人の狂気が入り混じる、悪夢のカーニバル・ミュージック。
- Flower’s Grave: 花の墓。失われた愛を悼む、はかなく美しいワルツ。
- No One Knows I’m Gone: 私が消えたことを誰も知らない。孤独と喪失感を歌うバラード。
- Kommienezuspadt: ドイツ語で歌われる、インダストリアルで攻撃的なナンバー。
- Poor Edward: 頭の後ろにもう一つの顔を持つ男エドワードの悲劇を描いた物語。
- Table Top Joe: 生まれた時からテーブルの上で暮らす男の歌。ブルージーでどこか陽気です。
- Lost in the Harbour: 港で道に迷い、愛する人を失った男の歌。
- We’re All Mad Here: 「ここではみんな狂ってる」という『不思議の国のアリス』の有名なセリフを用いた、狂騒的なジャズ。
- I’m Still Here: 全てが過ぎ去った後も、私はまだここにいる、と歌う感動的なフィナーレ。
Blood Money
- Misery Is the River of the World: 「不幸は世界の川」と歌う、シニカルで重々しいオープニング。
- Everything Goes to Hell: 全ては地獄に堕ちる。クルト・ヴァイル風の行進曲。
- Coney Island Baby: かつての恋人を想う、甘く切ないバラード。
- All the World Is Green: 君とワインを飲んでいると、世界が緑色に見える。美しいラブソング。
- God’s Away on Business: 神は出張中。悪魔が好き放題やっている世界を歌う、本作のハイライト。しゃがれ声の説教が炸裂します。
- Another Man’s Vine: 他人のブドウの蔓。嫉妬と欲望を歌う、不穏なタンゴ。
- Knife Chase: スリリングなインストゥルメンタル。
- Lullaby: 歪んだ子守唄。安らぎではなく不安を与えます。
- Starving in the Belly of a Whale: クジラの腹の中で飢えている。絶望的な状況を歌うブルース。
- The Part You Throw Away: 人生で捨ててしまう部分にこそ価値がある、という逆説的な真理を歌います。
- A Good Man Is Hard to Find: 善人を見つけるのは難しい。第一次大戦前のキャバレーのような雰囲気を持つ曲。
16th: Real Gone (2004)
彼のキャリアの中で最も異色で過激なアルバム。
最大の特徴は、ピアノが一切使われていないこと。
そして、ドラムの代わりにウェイツ自身と息子ケイシーによるヒューマン・ビートボックス(声によるパーカッション)が多用されていることです。
サウンドは非常にプリミティブで、生々しく、荒々しい。政治的なメッセージを持つ楽曲も含まれており、ウェイツの新たな挑戦が記録されています。
- Top of the Hill: 丘の頂上から世界を見下ろす。ヒューマン・ビートボックスとマーク・リボーのギターが炸裂する、ファンキーでアグレッシブなオープニング。
- Hoist That Rag: イラク戦争への批判とも取れる、力強い反戦歌。軍隊の行進曲のようなリズムを持ちます。
- Sins of My Father: 父の罪。重く引きずるようなブルース。
- Shake It: 原始的なビートに乗せて「シェイクしろ!」と煽る、ダンス(?)ナンバー。
- Don’t Go into That Barn: あの納屋にだけは入るな。ホラー映画のような不気味さを持つ曲。
- How We Quit the Forest: 森を抜けた時のことを歌う、静かで内省的な曲。
- Metropolitan Glide: 都会の滑走。キャプテン・ビーフハートを彷彿とさせる、アヴァンギャルドなロック。
- Dead and Lovely: 死んでしまった美しい彼女。悲劇的な物語をクールに歌います。
- Circus: サーカス一座の裏側を描いた、ポエトリー・リーディング。
- Trampled Rose: 踏みにじられたバラ。女性の悲劇を歌った、ゴスペル調の美しいバラード。アリソン・クラウスとロバート・プラントがカバーしたことでも有名です。
- Green Grass: 君が緑の草の下(墓の中)に眠っていても、僕の愛は変わらない、と歌う感動的なバラード。
- Baby Gonna Leave Me: 恋人が去っていく。シンプルなブルース。
- Clang Boom Steam: 蒸気機関車のような効果音とビートが続く短い曲。
- Make It Rain: 雨を降らせてくれ、と神に願う男の歌。彼のゴスペル・ブルースの真骨頂です。
- Day After Tomorrow: 戦地にいる若い兵士が故郷に宛てた手紙の形式で歌われる、感動的な反戦歌。明日になれば帰れる、と自分に言い聞せる歌詞が胸を打ちます。
17th: Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards (2006)
概要: 未発表曲、レア音源、カバー曲などを集めた3枚組、全56曲という大ボリュームの編集盤。しかし、これは単なるアウトテイク集ではありません。
「Brawlers(喧嘩屋)」はアップテンポなブルースやロック、「Bawlers(泣き屋)」はバラード、「Bastards(私生児)」は実験的な曲や語り、というテーマに沿ってコンパイルされており、それぞれが独立したアルバムとして楽しめる構成になっています。
彼の音楽の多様性と深さを再認識させられる、ファン必携の宝箱です。
トム・ウェイツ自身の言葉:
「Orphans(孤児)とは、荒々しくも優しい曲たちのことだ。出自の怪しい歌たちが、残酷な運命から救い出され、今はただ世話されるのを待っている。怖がらずに家に連れて帰ってやってくれ。噛みついたりはしない、ただ少し構ってほしいだけなんだ」
Disc 1: Brawlers (喧嘩屋たち)
ガソリンと安物のバーボンの匂いが立ち込める、埃っぽい酒場。
それが「Brawlers」の世界です。
ここでは、ウェイツのルーツであるブルース、R&B、ロックンロールが剥き出しの形で鳴り響きます。
歪んだギター、叩きつけるようなドラム、そして獣の咆哮のようなヴォーカル。
人生のハードな側面に殴りかかるような、タフで汗臭い楽曲群が並びます。
- Lie to Me: 映画『ミステリー・メン』のサウンドトラックの別バージョンとも言われる新曲。「嘘をついてくれ、どうせ全部嘘なんだから」とシャウトする、わずか2分のロカビリー・ナンバー。性急なビートとダーティなギターが、アルバムの幕開けを宣言する完璧な狼煙です。
- LowDown: 映画『ファイト・クラブ』のサウンドトラックに提供された曲の別バージョン。地を這うようなベースラインと、唸るようなギターリフ。タイラー・ダーデンのアナーキーな哲学を体現したかのような、重くファンキーなグルーヴが体を揺さぶります。
- 2:19: ブルースマン、ジョン・ハモンドJr.のアルバム『Wicked Grin』に提供した曲のセルフカバー。列車強盗の物語で、大洪水の混乱に乗じて悪事を働く男の姿を、スライドギターが不穏に彩ります。デルタ・ブルースの亡霊が現代に蘇ったかのような一曲。
- Fish in the Jailhouse: 新曲。刑務所の中で魚を料理する、という奇妙な歌詞を持つストレートなブルース・ロック。「監獄ロック」のトム・ウェイツ版とも言える、ユーモラスで力強いナンバーです。
- Bottom of the World: ドキュメンタリー映画『Long Gone』のために書かれた曲。ホーボー(渡り労働者)の哀歌で、アコースティック・ギターとバンジョーが奏でる、シンプルで美しいメロディに乗せて、社会の底辺から世界を見つめる男の人生が歌われます。「Brawlers」の中の静かなハイライト。
- Lucinda: 新曲。ルシンダという名の女に狂わされた男の歌。ねじれたギターリフと呪術的なリズムが、破滅的な愛の物語を不気味に演出します。
- Ain’t Goin’ Down to the Well: ブルースの巨人、レッドベリーのカバー。まるで本物のフィールド・レコーディングのように、生々しくプリミティブな演奏。鎖を引きずるようなパーカッションとシャウトが、魂の渇きを歌います。
- Lord I’ve Been Changed: ジョン・ハモンドJr.に提供したゴスペル・ブルースのセルフカバー。神によって変えられた、と証しする男の歌ですが、そのサウンドは敬虔さよりも、むしろ狂信的なエネルギーに満ちています。
- Puttin’ on the Dog: 1929年のポピュラーソングのカバー。「めかしこむ」という古いスラングをタイトルにした、スウィンギーで奇妙なジャズ・ナンバー。犬の鳴き声やガラクタの音が混ざり合い、ウェイツ流の悪夢の舞踏会が繰り広げられます。
- Road to Peace: 新曲。パレスチナ問題を扱ったポリティカルな曲。実際のニュース報道から引用した生々しい歌詞で、憎しみの連鎖を描く問題作。静かで淡々としたトーンが、逆に暴力の虚しさを際立たせます。
- All the Time: 新曲。ごく初期のトム・ウェイツを思わせる、シンプルでメロウなブルース。失われた愛を静かに歌う、心の傷を癒すような一曲です。
- The Return of Jackie and Judy: パンク・ロックの伝説、ラモーンズのカバー。原曲のポップさを微塵も残さず、ヘヴィで汚らしいガレージ・ロックに再構築。ウェイツ流の解釈が爆発した、最高にクールなカバーです。
- Walk Away: 映画『デッドマン・ウォーキング』のサウンドトラックから。カントリー・ゴスペルのような荘厳さを持ちながら、人生の苦悩が滲み出るバラード。キャスリーン・ブレナンとの共作です。
- Sea of Love: フィル・フィリップスのオールディーズ名曲のカバーで、映画『シー・オブ・ラブ』主題歌。原曲の甘い雰囲気を、不気味でサスペンスフルなサウンドに一変させた名カバー。愛の海の底に潜む狂気を描きます。
- Buzz Fledderjohn: ジョン・ハモンドJr.に提供した曲のセルフカバー。近所の不気味な少年バズについての歌。犬の吠え声が入るなど、まるでポーチで録音されたかのような生々しい質感が、物語のリアリティを高めています。
- Rains on Me: ブルース・ギタリスト、チャック・E・ワイスとの共作。ウェイツのしゃがれ声と、むせび泣くようなハーモニカ、スライドギターが絡み合う、オーセンティックなブルース・ナンバー。ディスクの最後を飾るにふさわしい、雨に打たれる男の哀愁が漂います。
Disc 2: Bawlers (泣き屋たち)
「Brawlers」の喧騒が嘘のような、静かで内省的な世界。
それが「Bawlers」です。ピアノ、アコーディオン、アコースティック・ギターが奏でる美しいメロディに乗せて、愛、喪失、郷愁、そして人生の儚さが歌われます。
ウェイツのもう一つの真骨頂である、珠玉のバラード集です。
- Bend Down the Branches: 映画『シュレック2』のために書かれたが、未使用となった曲。まるで古い子守唄のような、優しくも物悲しいオープニング。子供の頃の思い出と、過ぎ去った時間への想いが歌われます。
- You Can Never Hold Back Spring: 映画『ライフ・イズ・コメディ! ピーター・セラーズの愛し方』のために書かれた曲。「冬の後には必ず春が来るように、希望を押しとどめることはできない」と歌う、感動的なワルツ。彼のキャリアの中でも屈指の美しさを誇る名曲です。
- Long Way Home: ノラ・ジョーンズに提供した楽曲のセルフカバー。どこかカントリーの香り漂う、温かいラブソング。遠回りしても、最後は君の元へ帰るという、心安らぐメッセージが込められています。
- Widow’s Grove: 新曲。未亡人の森で殺された少女の物語を歌う、アイルランド民謡風のマーダー・バラッド。美しいメロディと残酷な歌詞の対比が鮮やかです。
- Little Drop of Poison: 映画『シュレック2』のサウンドトラックに収録(エンドロールで使用)。クレズマー(東欧ユダヤの民族音楽)風の、酔いどれタンゴ。愛という名の「小さな毒の一滴」について歌う、ウェイツらしいひねくれたラブソング。
- Shiny Things: 映画『ロベルト・ベニーニのピノッキオ』の英語版に提供された曲。ピノキオの視点から、キラキラしたものへの憧れと、それがもたらす危険を歌います。おもちゃのピアノのような音が、子供の無垢さと残酷さを表現します。
- World Keeps Turning: 映画『ポロック 2人だけのアトリエ』のサウンドトラックより。失恋しても世界は回り続ける、という普遍的な真理を歌うピアノ・バラード。静かな諦念と、それでも続く人生への眼差しが胸を打ちます。
- Tell It to Me: 新曲。男女のデュエットによる、カントリー・ワルツ。愛の終わりを予感させる、切ない会話が歌われます。
- Never Let Go: 映画『アメリカン・ハート』のサウンドトラックより。決して離さない、と誓う力強い愛の歌。荘厳で、どこかゴスペルのような響きを持つバラードです。
- Fannin Street: レッドベリーの楽曲にインスパイアされた曲で、ジョン・ハモンドJr.にも提供。「ファニン通りには行くな」という母の忠告を破り、人生を誤った男の悔恨の歌。アコースティック・ギターの物悲しい響きが心に残ります。
- Little Man: プロデューサー、テディ・エドワーズへのトリビュート。息子に語りかけるような、優しくジャジーなラウンジ・ミュージック。「小さな坊や、焦ることはないよ」という歌詞が温かいです。
- It’s Over: 映画『リバティ・ハイツ』のサウンドトラックより。50年代のドゥーワップを彷彿とさせる、甘く切ない失恋ソング。ウェイツの歌声が驚くほどスイートに響きます。
- If I Have to Go: 新曲。「もし俺が先に行かなければならないなら」と、残される者への想いを歌う、死の影がちらつくラブソング。彼のしゃがれ声が、歌詞に深い説得力をもたらします。
- Goodnight Irene: レッドベリー作の有名なフォークソングのカバー。まるで酔っ払いの合唱のように、ラフで人間味あふれる演奏。哀愁と温かさが同居する、ウェイツならではの解釈です。
- The Fall of Troy: 映画『デッドマン・ウォーキング』のサウンドトラックより。古代ギリシャのトロイア戦争をモチーフに、現代の悲劇を歌う。ピアノとチェロが織りなす、荘厳で美しいバラード。
- Take Care of All My Children: ドキュメンタリー映画『Streetwise』より。路上で暮らす子供たちへの祈りを歌った、ゴスペル調の曲。救世軍のブラスバンドのようなサウンドが印象的です。
- Down There by the Train: ジョニー・キャッシュに提供した曲のセルフカバー。悪人も聖人も、全ての罪人が救われる場所が「列車のそば」にある、と歌うゴスペル。キャッシュへの深い敬意が感じられる名演です。
- Danny Says: ラモーンズのカバー。「Brawlers」でのカバーとは対照的に、こちらはアコースティックでメランコリックなアレンジ。ツアー生活の倦怠と郷愁を歌った原曲の切なさが際立ちます。
- Jayne’s Blue Wish: 新曲。ジェインという女性の青い願い。ピアノとサックスが静かに寄り添う、ジャジーで夢見心地なインストゥルメンタル。
- Young at Heart: フランク・シナトラの歌唱で有名なスタンダード曲のカバー。原曲の華やかさとは真逆の、老人の独白のような訥々とした歌唱。人生の終わりに「心は若いまま」と歌うその声は、深く胸を打ちます。
Disc 3: Bastards (私生児たち)
どの家族にも属せない、風変わりで奇妙な子供たち。
それが「Bastards」です。ここでは音楽の境界線は取り払われ、実験的なサウンドコラージュ、ポエトリー・リーディング、異色のカバー曲、そしてただの「音」が混然一体となっています。
ウェイツの最もディープで、ユーモラスで、狂気に満ちた側面が凝縮された一枚です。
- What Keeps Mankind Alive: クルト・ヴァイルとベルトルト・ブレヒト作『三文オペラ』の楽曲カバー。「人間を生かしているのは何か? 他人の犠牲だ」と歌う、痛烈な社会批判。歪んだキャバレー・ミュージックで、このディスクの方向性を決定づける強烈なオープニング。
- Children’s Story: 未発表のポエトリー・リーディング。孤児になった子供が、死に絶えた世界をさまようという、救いのない「子供の物語」。ウェイツの語りが、聴く者の想像力に直接働きかけます。
- Heigh Ho: ディズニー映画『白雪姫』の挿入歌「ハイ・ホー」のカバー。あの陽気な労働歌を、まるで地獄の工場で響くような、重くインダストリアルなサウンドにアレンジ。ユーモアと恐怖が同居する、天才的なカバーです。
- Army Ants: ポエトリー・リーディング。軍隊アリについての生態を、昆虫博士のように淡々と、しかしどこか不気味に語ります。ウェイツの知的好奇心とユーモアが窺える小品です。
- Books of Moses: スキップ・スペンスのカバー。伝説的なサイケデリック・フォークシンガーの楽曲を、バンジョーをかき鳴らしながら原始的にカバー。
- Bone Chain: インストゥルメンタル。骨と鎖がぶつかり合うような、パーカッシブで短い曲。
- Two Sisters: 伝統的なバラッドのカバー。姉が妹を殺すという残酷な物語を、ア・カペラに近い形で静かに歌います。
- First Kiss: ポエトリー・リーディング。少年時代のファーストキスについての、甘酸っぱくも少し奇妙な思い出語り。
- Dog Door: スパークルホースとの共演曲。ローファイでサイケデリックなロック。犬用のドアから出入りする男の歌です。
- Redrum: インストゥルメンタル。映画『シャイニング』の”REDRUM (MURDER)”へのオマージュ。不気味でサスペンスフルな音響がホラー映画のようです。
- Nirvana: チャールズ・ブコウスキの詩の朗読。悟り(ニルヴァーナ)を求める男の詩を、クールなジャズをバックに朗読します。ビート文学への深い愛情が感じられます。
- Home I’ll Never Be: ジャック・ケルアックの詩の朗読。ケルアックの詩に、ウェイツが即興的なメロディをつけて歌います。放浪者の魂が共鳴する瞬間です。
- Poor Little Lamb: 新曲。哀れな子羊たちの物語。ウェイツ流のゴスペル。
- Altar Boy: 新曲。かつて祭壇係だった老人の独白。酔いどれピアノに乗せた、ユーモラスで物悲しいジャズ。
- The Pontiac: ポエトリー・リーディング。古いポンティアックについての、父親との思い出語り。
- Spidey’s Wild Ride: ポエトリー・リーディング。奇妙な冒険物語を早口で語る、狂気の紙芝居。
- King Kong: 異端のシンガーソングライター、ダニエル・ジョンストンのカバー。ウェイツがア・カペラで、キングコングの悲劇を絶叫するように歌う、魂の叫びそのものです。
- On the Road: ジャック・ケルアックの詩の朗読。プライマスをバックに、ケルアックの詩をファンキーに朗読します。
- Dog Treat (Hidden Track): 隠しトラック。息子との会話を録音したホーム・レコーディング。
- Missing My Son (Hidden Track): 隠しトラック。息子が行方不明になったと悲しむ母親の電話かと思いきや…という、ブラックユーモアに満ちたオチがつくショートコント。
18th: Bad as Me (2011)
2024年現在、最新のオリジナル・スタジオ・アルバム。
比較的コンパクトな曲が多く、全体的にロックンロール色が強い、ウェイツのキャリアの集大成とも言える作品。
キース・リチャーズ、フリー(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)、マーク・リボーといった旧知のメンバーに加え、息子ケイシーも参加。
老いてなお衰えるどころか、さらに凄みを増した歌声と、バラエティに富んだ楽曲が楽しめます。
- Chicago: シカゴへ向かう列車に乗って過去を振り切る、という疾走感あふれるロックンロール。
- Raised Right Men: きちんと育てられた男たち。キース・リチャーズのギターが光る、ご機嫌なブルース。
- Talking at the Same Time: 政治家や権力者への不信感を歌った、ミドルテンポのソウルフルなナンバー。
- Get Lost: 50年代のロックンロールへのオマージュのような、シンプルで力強い曲。
- Face to the Highway: ハイウェイに顔を向け、過去を振り返らない男の歌。
- Pay Me: 金をくれ、と歌うキャバレー・ソング。哀愁漂うメロディが印象的です。
- Back in the Crowd: 群衆の中に戻っていく。スパニッシュ・フレイバー溢れる、ロマンティックなバラード。
- Bad as Me: タイトル曲。キース・リチャーズとデュエットする、荒々しいブルース・ロック。「君と同じくらいワルなのさ」と歌います。
- Kiss Me: 「キスしてくれ、まるで最後のキスみたいに」と歌う、シンプルで美しいラブソング。
- Satisfied: ローリング・ストーンズへのアンサーソングとも言われる。「ミック・ジャガーは満足できないかもしれないが、俺は満足するまで墓には行かない」とシャウトします。
- Last Leaf: 木に残った最後の一枚の葉っぱに自分を喩えた、感動的なアコースティック・バラード。キース・リチャーズが優しく寄り添います。
- Hell Broke Luce: イラク帰還兵のPTSDをテーマにした、本作で最もヘヴィで実験的な曲。兵士の行進と銃声、ウェイツの怒りのシャウトが炸裂します。
- New Year’s Eve: 大晦日の夜、一人静かに「蛍の光」を歌う。アルバムの最後を飾る、寂しくも温かい曲。
5. アクターとしての貌 – 全出演作品レビュー
トム・ウェイツの表現は音楽だけに留まりません。
彼の特異な存在感と、声に刻まれた人生の年輪は、多くの映画監督を魅了してきました。
脇役やカメオ出演が多いながらも、その一つ一つに強烈な爪痕を残しています。
彼の俳優としてのキャリアは、単なるミュージシャンの余技ではなく、彼の芸術世界を構成する重要な一部です。
【主な出演作品リスト(時系列順)】
| 公開年 | 作品名 | 監督 | 役どころ・レビュー |
|---|---|---|---|
| 1978 | パラダイス・アレイ | シルヴェスター・スタローン | ピアノ弾きマムブルス役。記念すべきデビュー作。ほとんどセリフはないが、その後のキャリアを予感させる雰囲気を醸し出しています。 |
| 1982 | ワン・フロム・ザ・ハート | フランシス・フォード・コッポラ | 音楽・歌曲を担当し、アカデミー賞にノミネート。俳優としてはトランペット奏者役でカメオ出演。 |
| 1983 | アウトサイダー | フランシス・フォード・コッポラ | ダイナーの主人バック・メリル役。短い出演ながら、若者たちの荒んだ世界のリアリティを増幅させています。 |
| 1983 | ランブルフィッシュ | フランシス・フォード・コッポラ | ビリヤード場のオーナー、ベニー役。主人公たちの兄貴分的な存在で、哲学的なセリフを呟きます。 |
| 1984 | コットンクラブ | フランシス・フォード・コッポラ | クラブのマネージャー、アーヴィング・スターク役。これまでの役柄とは一味違う、スーツを着こなすインテリな役を演じています。 |
| 1986 | ダウン・バイ・ロー | ジム・ジャームッシュ | 主演、DJのザック役。人生に敗れた男を好演し、俳優としての評価を決定づけた代表作。 |
| 1987 | アイアンウィード | ヘクトール・バベンコ | ジャック・ニコルソン演じる主人公の友人ルディ役。大恐慌時代のホームレスの絶望感を完璧に体現した見事な助演。 |
| 1989 | ミステリー・トレイン | ジム・ジャームッシュ | ラジオDJの声で出演。 |
| 1991 | フィッシャー・キング | テリー・ギリアム | 足の不自由な退役軍人役でカメオ出演。一瞬ながら強烈なインパクトを残します。 |
| 1992 | ドラキュラ | フランシス・フォード・コッポラ | 狂気のしもべレンフィールド役。虫を貪り食う怪演が絶賛されました。 |
| 1993 | ショート・カッツ | ロバート・アルトマン | リムジン運転手アール・ピゴット役。情けなくも憎めない、ごく普通の男の悲哀を見事に表現しました。 |
| 1999 | ミステリー・メン | ケンカ・アウアー | 兵器開発の博士ドクター・ヘラー役。ユーモラスな役柄。 |
| 2003 | コーヒー&シガレッツ | ジム・ジャームッシュ | 本人役でイギー・ポップと共演。二人のレジェンドが繰り広げるシュールな会話は必見です。 |
| 2009 | Dr.パルナサスの鏡 | テリー・ギリアム | 悪魔Mr.ニック役。強烈な印象を残します。 |
| 2010 | ザ・ブック・オブ・イーライ | ヒューズ兄弟 | 謎の店の店主エンジニア役。 |
| 2012 | セブン・サイコパス | マーティン・マクドナー | ウサギを抱いた男ザカリア役。その独特の語り口が物語に不気味さを与えています。 |
| 2018 | バスターのバラード | コーエン兄弟 | 金鉱掘りの老人役。ほぼ一人芝居で、その表情と佇まいだけで男の人生を物語る圧巻のパフォーマンスを披露。 |
| 2018 | さらば愛しきアウトロー | デヴィッド・ロウリー | ロバート・レッドフォード演じる主人公の強盗仲間の一人、ウォラー役。 |
| 2019 | デッド・ドント・ダイ | ジム・ジャームッシュ | 森の隠者ハーミット・ボブ役。物語の傍観者として、飄々とした魅力を発揮しています。 |
| 2021 | リコリス・ピザ | ポール・トーマス・アンダーソン | 往年の映画監督レックス・ブラウ役。短い出演ながら、その圧倒的な存在感と声で場を完全に支配します。 |
6. 結論:終わらない旅路
トム・ウェイツのキャリアを振り返ることは、まるでアメリカの裏街道を旅するような体験です。
アサイラム時代のロマンティックな敗残者たちの物語から、アイランド時代の奇妙で美しいガラクタの音楽、そしてANTI-時代に辿り着いた円熟の境地まで、彼の音楽は常に変化し続け、私たちを驚かせてきました。
ソングライターとして、彼はありふれた日常の中に潜む魔法や、社会の片隅で忘れ去られた人々の声に耳を傾け、それを唯一無二の芸術へと昇華させました。
同時に、俳優としての彼は、その特異な風貌と声をもって、スクリーンに忘れがたい刻印を残してきました。
彼が演じるのは、常にどこか世界の歯車から外れてしまったような男たち。しかし、その根底には人間への深い愛情と共感が流れています。
ソングライターと俳優、二つの顔はどちらも「トム・ウェイツ」という巨大な物語の一部です。
彼のしゃがれた声が語るのは、いつだって人生の悲哀と、それでも生きることの滑稽さ、そして美しさ。トム・ウェイツの旅はまだ終わりません。
次に彼がどんな景色を見せてくれるのか、私たちはただバーボンのグラスを傾けながら、気長に待つことにしましょう。
7. 付録
7-1. トム・ウェイツ入門におすすめのアルバム5選
どこから聴けばいいか分からない、という初心者のために、彼のキャリアの多様性がわかる5枚を選びました。
- 『Closing Time』(1973): 全ての始まり。ジャジーでロマンティックな「ピアノマン」としてのウェイツを知るには最適の一枚。メロディも親しみやすいです。
- 『Small Change』(1976): 初期アサイラム時代の頂点。歌詞の深みと「酔いどれ詩人」としての美学が極まった傑作。代表曲「Tom Traubert’s Blues」は必聴です。
- 『Rain Dogs』(1985): 彼の音楽性が爆発したアイランド時代の最高傑作。奇妙で、美しく、ロックで、バラエティ豊か。ここからウェイツにハマる人が最も多いです。
- 『Mule Variations』(1999): 円熟期の名盤。実験性と叙情性が完璧に融合し、ブルースやゴスペルに根差したサウンドは懐かしくも新しい。人間的な温かみに溢れています。
- 『Bad as Me』(2011): 現在のところ最後のオリジナル・アルバム。彼のキャリアの様々な要素がコンパクトに凝縮されており、ロックンロール色が強く聴きやすいです。
7-2. トム・ウェイツを形成したもの/トム・ウェイツが遺したもの
影響を受けたもの
- ビート文学: ジャック・ケルアック、アレン・ギンズバーグ、チャールズ・ブコウスキーなど。自由な精神、放浪、社会の周縁に生きる人々への眼差しは、彼の歌詞の世界観に直結しています。
- ブルースとジャズ: マディ・ウォーターズ、ハウリン・ウルフ、セロニアス・モンク、ルイ・アームストロングなど、アメリカ音楽の巨人たち。その魂と形式を血肉化しています。
- キャプテン・ビーフハート: 妻キャスリーンから教えられた前衛ロックの巨匠。伝統的な音楽構造を破壊する実験精神は、特にアイランド時代以降のウェイツに大きな影響を与えました。
- クルト・ヴァイル: ドイツの作曲家。キャバレー・ミュージックの退廃的でシアトリカルな作風は、ウェイツの音楽、特に舞台作品に色濃く反映されています。
影響を与えたもの
彼のユニークなスタイルは、数えきれないほどのアーティストに影響を与えています。
ブルース・スプリングスティーンやロッド・スチュワートは彼の曲をカバーし、ニック・ケイヴ、PJハーヴェイ、ザ・ブラック・キーズ、アークティック・モンキーズといったアーティストたちは、そのサウンドやアティチュードにウェイツからの影響を公言しています。
彼の存在は、メインストリームから外れた場所にも豊かな音楽が存在することを証明し、多くのオルタナティヴなアーティストたちを勇気づけてきました。
7-3. まとめ:トム・ウェイツの代表曲を聴こう
この記事では、トム・ウェイツの代表曲と、その背景にあるキャリアの変遷を解説してきました。最後に、本記事の要点をリストでまとめます。
✔︎ どの時代の代表曲から聴いても彼の世界観に深く触れられる
✔︎ トム・ウェイツは「酔いどれ詩人」と称されるアーティスト
✔︎ しゃがれた歌声と物語性の高い歌詞が大きな特徴
✔︎ キャリアは初期・中期・後期で音楽性が大きく異なる
✔︎ 初期の代表作はデビュー盤のクロージング タイム
✔︎ Ol’ ’55やMarthaは初期の不朽の名曲
✔︎ 人気のセカンド・アルバムはジャジーな「土曜日の夜」
✔︎ 「Tom Traubert’s Blues」は初期キャリアの最高傑作の一つ
✔︎ キャリアの転換点となったのは傑作アルバムのレイン・ドッグ
✔︎ 心に沁みる名バラードとしてタイムも非常に人気が高い
✔︎ 多くの名曲はYouTubeの公式音源で聴くことが可能
✔︎ 入門にはベストアルバムよりオリジナル盤から入るのがおすすめ
✔︎ 2011年にはロックの殿堂入りを果たしている
✔︎ 現在も俳優として第一線で活躍中
✔︎ 音楽性は常に変化し続けてきた唯一無二の存在
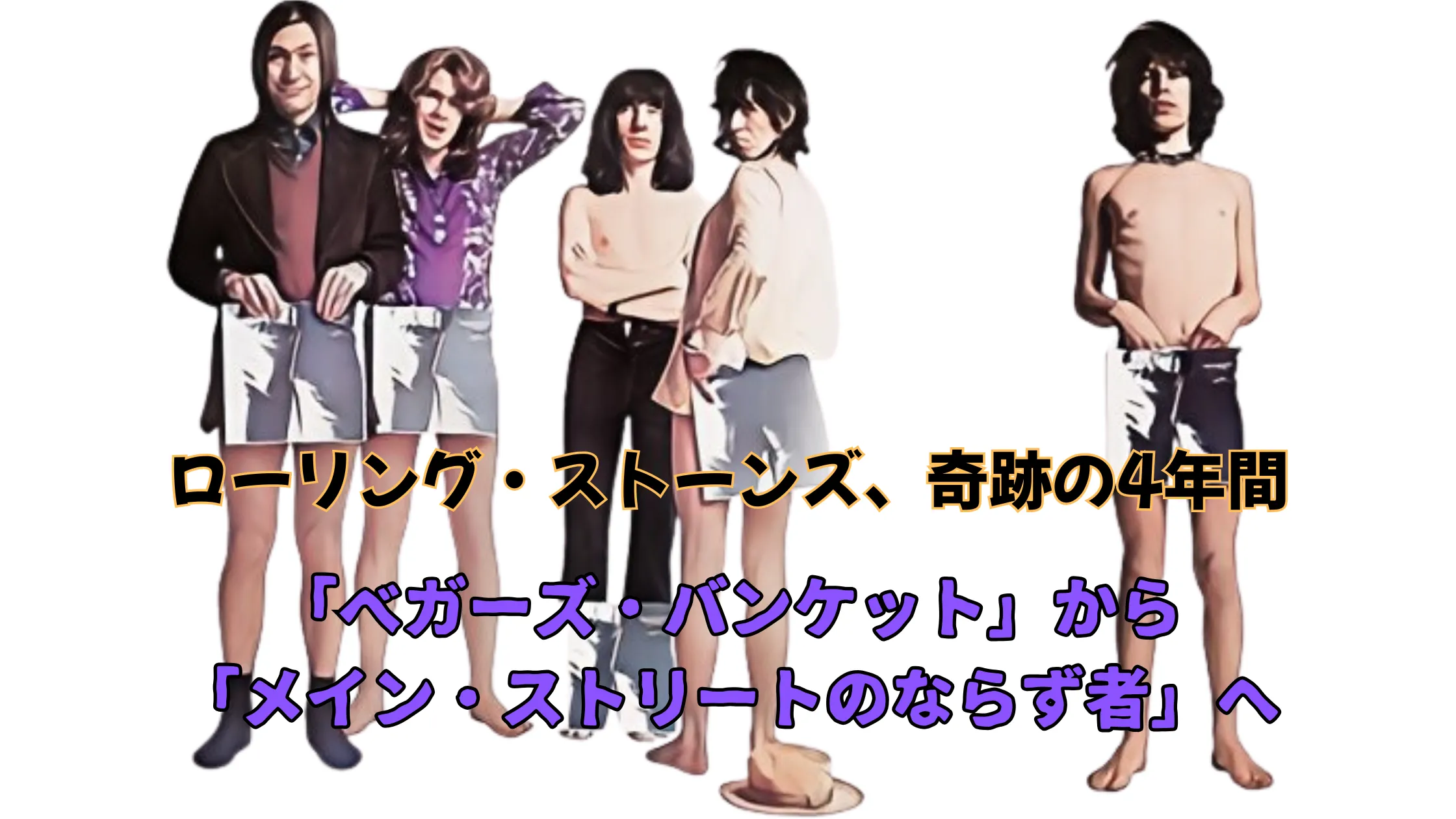
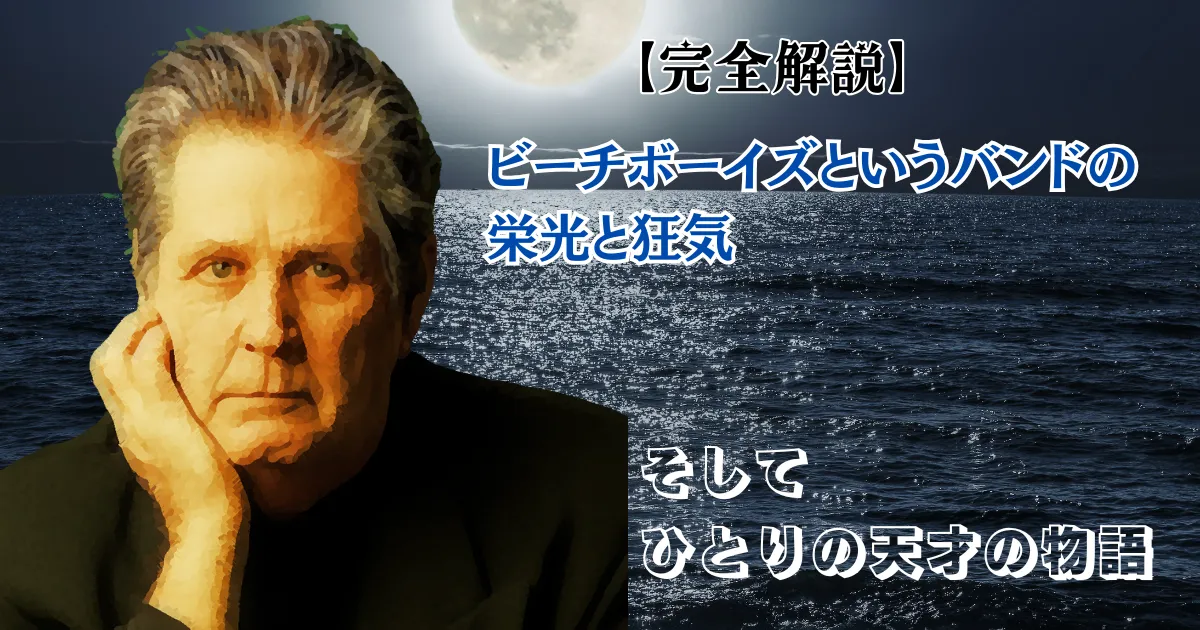

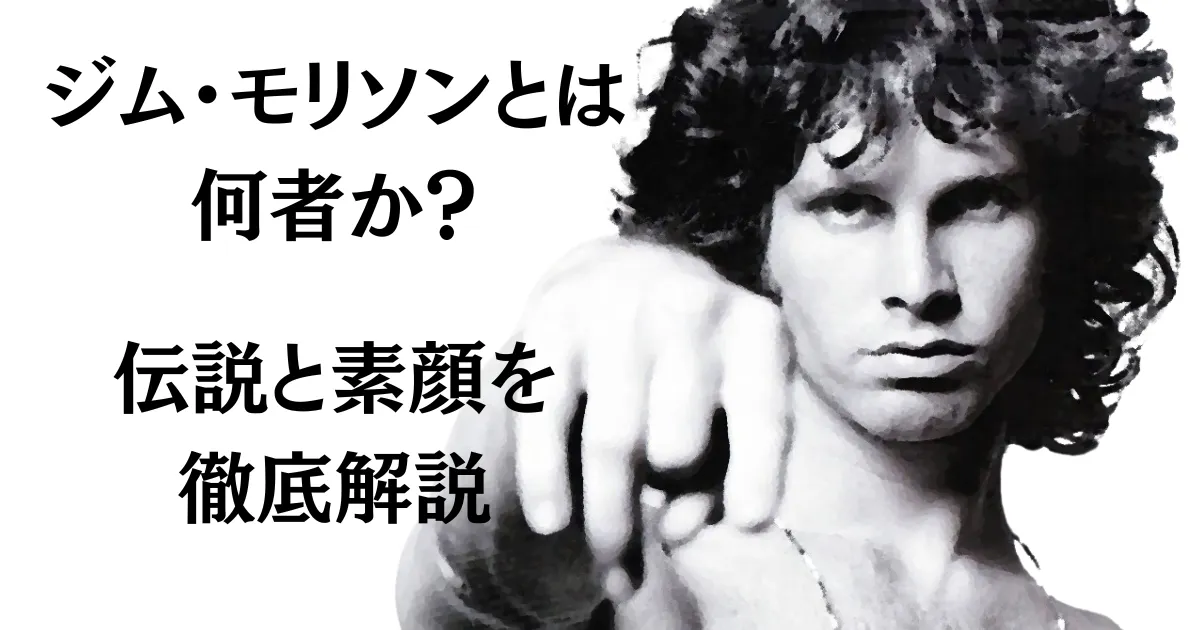

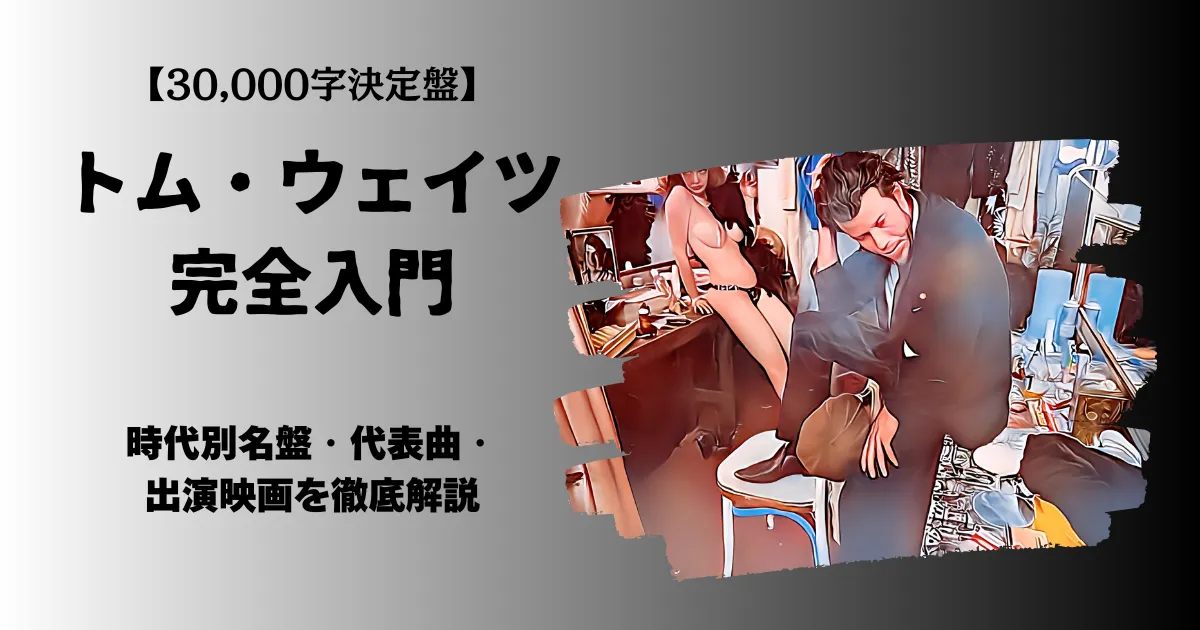

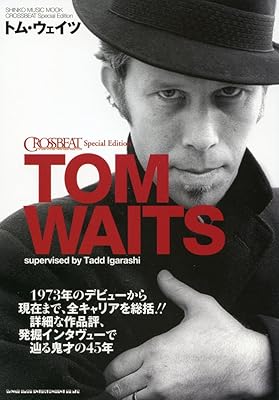

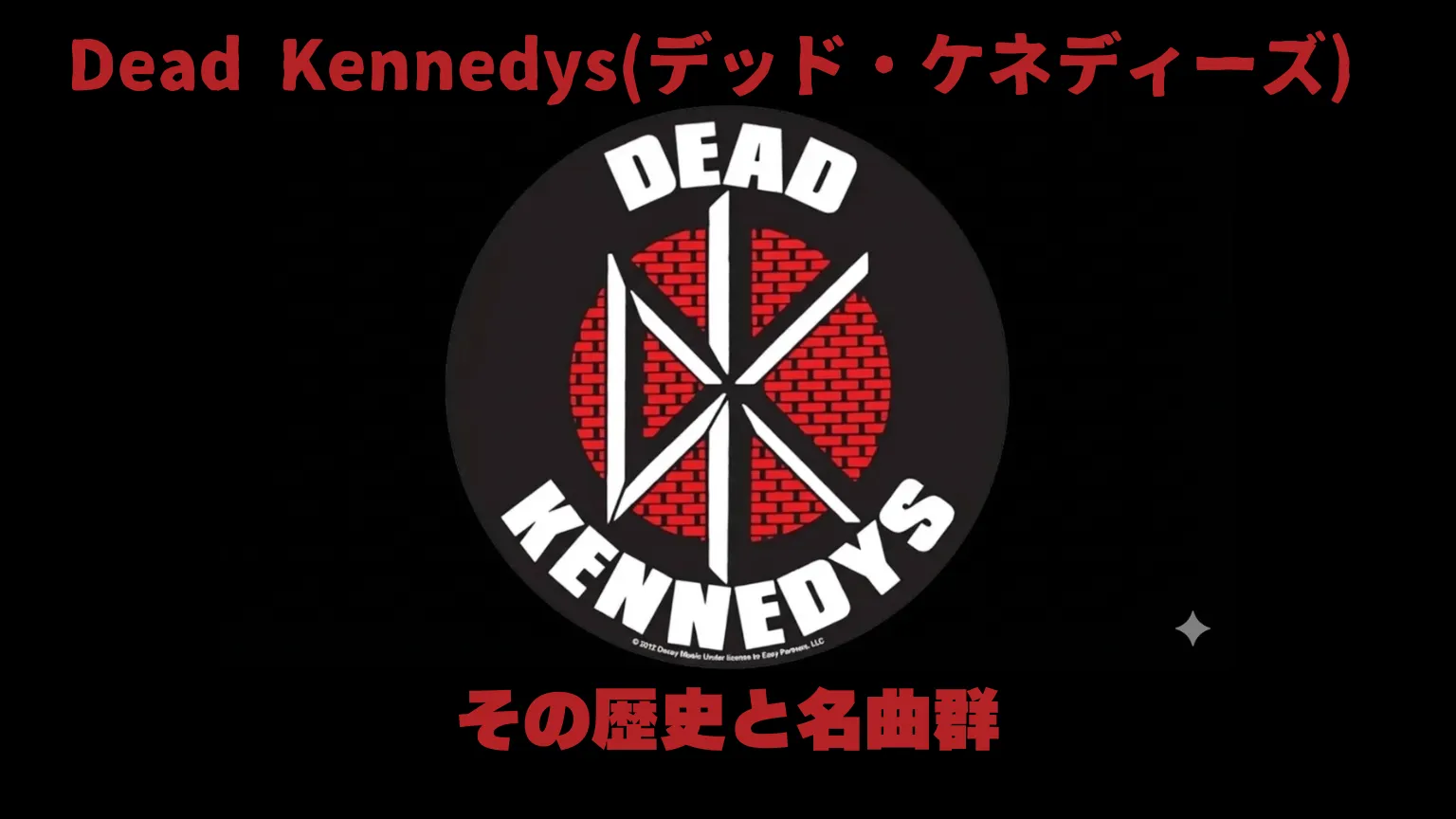
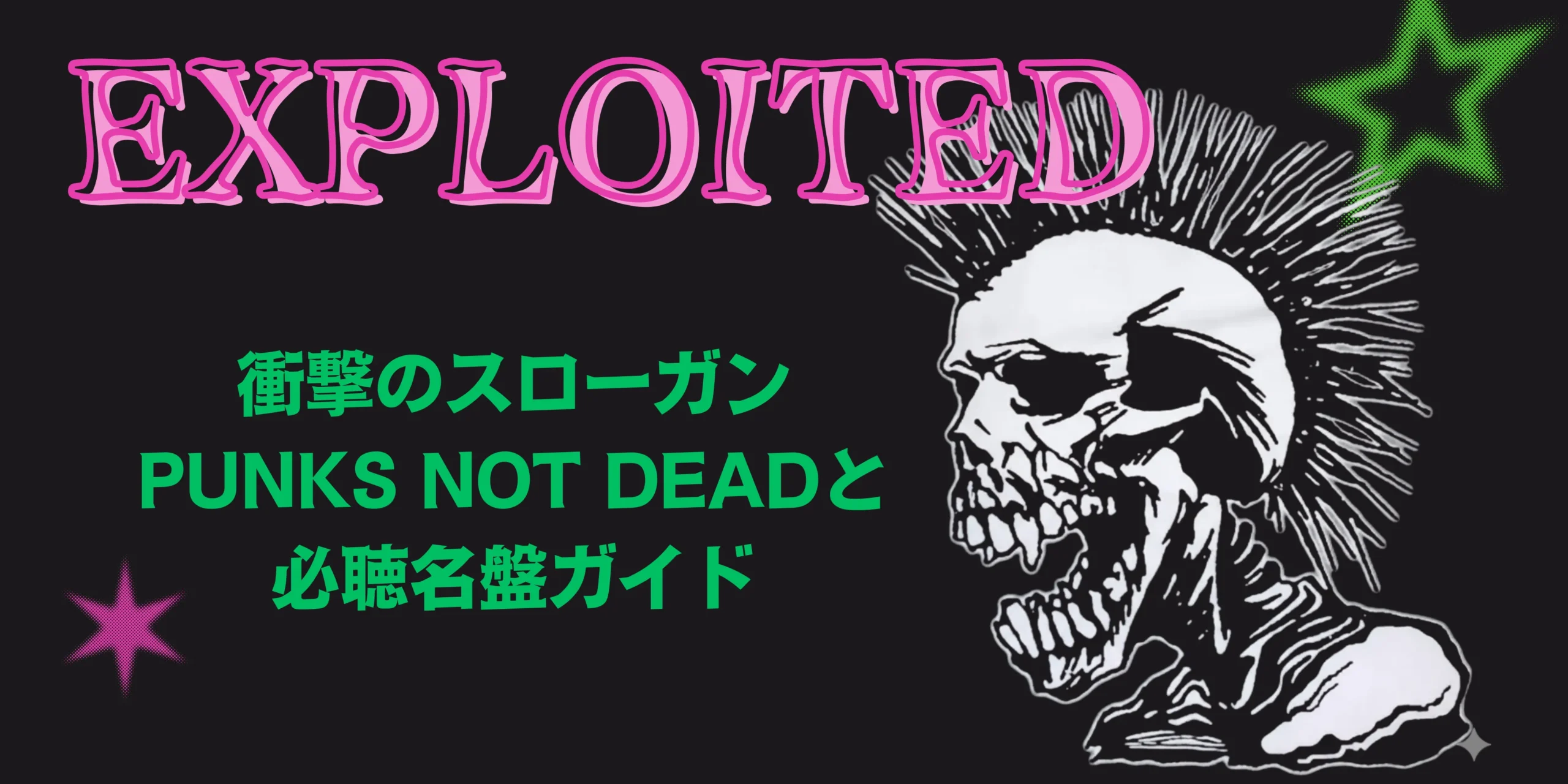



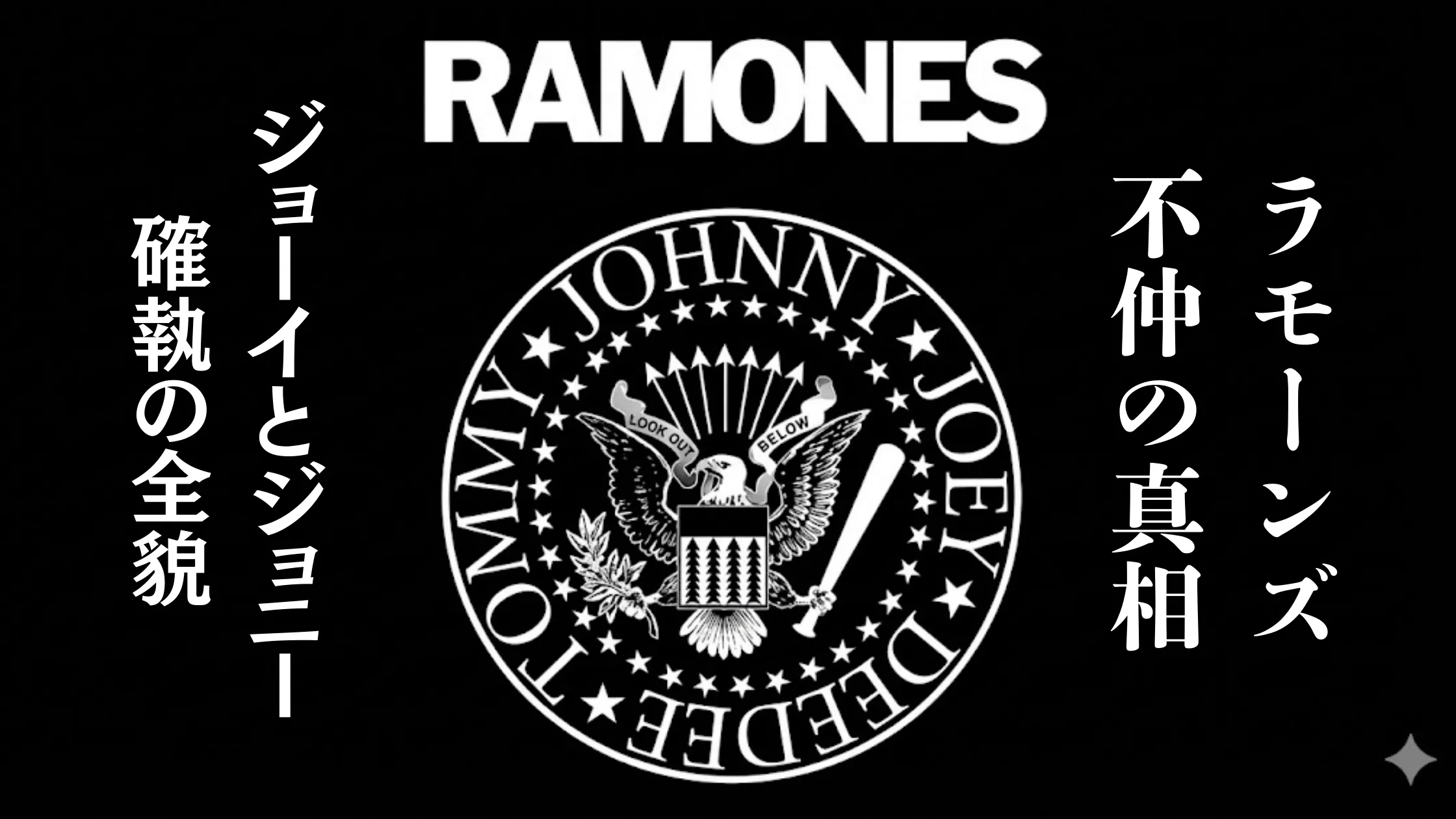
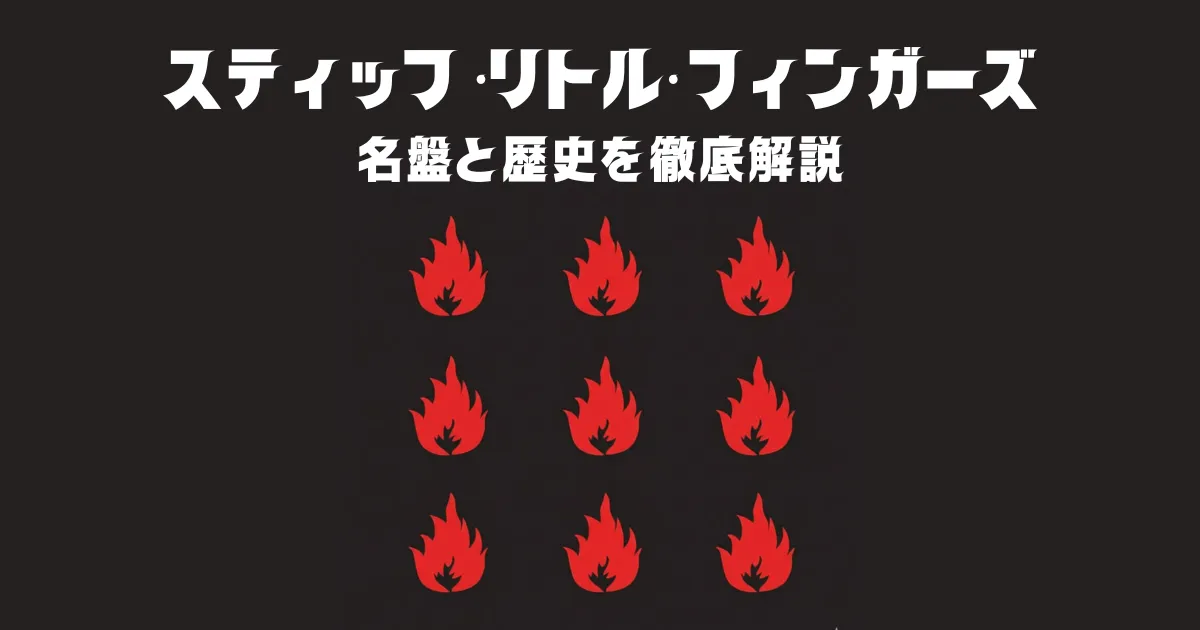






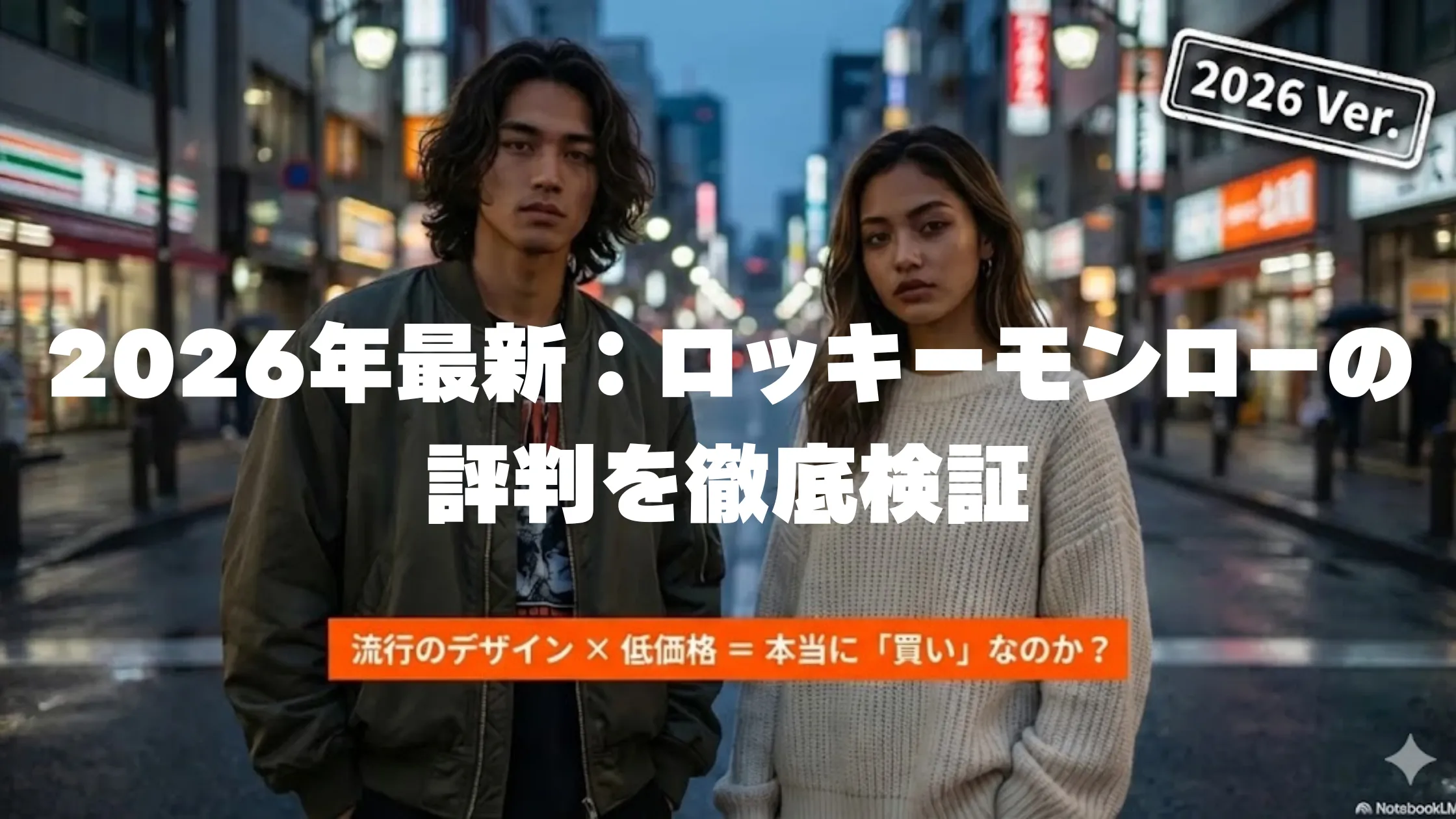
コメント
コメント一覧 (3件)
[…] […]
[…] […]
[…] […]