マンチェスターパンクの黎明期を駆け抜け、後世に多大な影響を与えた伝説のバンド、スローター・アンド・ザ・ドッグスについて、その全貌を深く知りたいと思っていませんか。
彼らの印象的なバンド名がミック・ロンソンの名盤『Slaughter on 10th Avenue』に由来すること、そしてグラムロックの煌めきをパンクの衝動へと昇華させた中心人物、ウェイン・バレットのカリスマ性。
さらに、「Cranked Up Really High」や「Boston Babies」といったアンセムの誕生背景には、一筋縄ではいかないドラマティックな物語が隠されています。
この記事では、彼らの代表曲やアルバムを網羅的に解説するのはもちろん、コレクター垂涎の『Do It Dog Style』のOriginal Vinylや希少なシングル「Situations」、さらにはdiscogsを駆使したレコード探しの具体的なヒントまで、あらゆる角度から徹底的に掘り下げていきます。
パンカビリーにも通じる彼ら独自の音楽性の本質から、分裂を経た現在の複雑なTour情報まで、スローター・アンド・ザ・ドッグスの魅力を余すところなくお届けします。
- バンドの結成から現在に至るまでの詳細な歴史
- 代表的なアルバムやシングルの音楽的な特徴と背景
- バンド名の由来やメンバーに関する興味深いエピソード
- 分裂後の現在の活動状況や今後のツアー情報

1. スローター・アンド・ザ・ドッグスの結成と歴史
- 「Slaughter on 10th Avenue」がバンド名の由来
- 中心人物ウェイン・バレットとバンドの歩み
- 名曲「Cranked Up Really High」の衝撃
- ライブで人気の高い「Boston Babies」
- パンカビリーにも通じる音楽スタイル
1-1. 「Slaughter on 10th Avenue」がバンド名の由来
スローター・アンド・ザ・ドッグスという、一度聴いたら忘れられない過激で詩的なバンド名は、彼らが単なるパンクバンドではないことを雄弁に物語っています。
この名前は、ヴォーカルのウェイン・バレットが初期のギグの前にベッドで思いついたもので、70年代グラムロックシーンを象徴する二人の巨匠の作品から直接的なインスピレーションを得て生み出されました。
具体的には、デヴィッド・ボウイの右腕として「ジギー・スターダスト」の世界観を構築した天才ギタリスト、ミック・ロンソンの初ソロアルバム『SLAUGHTER ON 10TH AVENUE (虐殺の10番街)』と、デヴィッド・ボウイ自身が発表した退廃的で近未来的な名盤『DIAMOND DOGS』。
この二つのタイトルを融合させたのです。
この事実は、彼らが1974年から75年にかけて結成され、1976年のパンクムーブメントが爆発する以前から活動していた生粋のロックンロール-バンドであり、そのDNAがパンクではなく、むしろ煌びやかで演劇的なグラムロックに深く根差していたことを示す、何よりの証拠と言えるでしょう。
当初のバンド名候補と芸術的志向
ちなみに、さらに彼らのグラム志向を物語るエピソードとして、一時期は「ウェイン・バレット・アンド・ザ-マイム・トゥループ」というバンド名が真剣に検討されていました。
これは、ヴォーカルのウェインが、デヴィッド・ボウイの師としても知られる伝説的パントマイム・アーティスト、リンゼイ・ケンプから強い影響を受け、ステージでパントマイムを取り入れていたことに由来します。
パンクが標榜した「反芸術」「シンプルさ」とは対極にある、こうした芸術的でシアトリカルな野心こそが、彼らの初期のアイデンティティだったのです。
このように、バンド名自体が彼らの音楽的バックボーンを象徴しており、初期のライブではヴェルヴェット・アンダーグラウンドのルー・リードやデヴィッド・ボウイの楽曲をカバーしていました。
後にマンチェスター・パンクの先駆者として認知される彼らですが、その根底には常に、華やかで危険な香りのするグラムロックの精神が脈々と流れているのです。
1-2. 中心人物ウェイン・バレットとバンドの歩み
スローター・アンド・ザ・ドッグスの波乱に満ちた物語は、二人の若者の運命的な出会いから始まります。
その中心にいたのが、カリスマ的なフロントマンのウェイン・バレットと、独創的なギタリストのミック・ロッシです。
1974年、マンチェスター南部に広がる広大な公営住宅地ウィゼンショウに建つシャーストン高校で彼らは出会い、バンドの中核を形成しました。
彼らが育ったウィゼンショウは、当時のイギリス社会の縮図のような場所でした。
「北部のスキンヘッドの首都」と悪名高く、タフであることが求められる労働者階級の街。
この荒々しい環境がバンドの「気骨ある態度」を育み、バレットが後に「憎しみが生まれた場所」と語ったように、彼らの音楽に込められた怒りとフラストレーションの源泉となりました。
この労働者階級出身というリアルな背景は、多くのパンクバンドが後から取ってつけたような「ストリート」の信頼性を、彼らに生まれながらにして持っていました。
でも、彼らの心はグラムロックの幻想的な世界にありました。この矛盾こそが、彼らを唯一無二の存在にしたのです。
パンクへの劇的な転身
彼らのキャリアにおける最大のターニングポイントは、英国音楽史の伝説として語り継がれる一夜、1976年7月20日に訪れます。バズコックスが主催したセックス・ピストルズのマンチェスター公演で、彼らはマネージャーの交渉術によってサポートアクトの座を射止めました。しかし、長髪にサテンの衣装、ミック・ロンソン風のギターポーズというグラムロック然とした姿でステージに上がった彼らは、新しい時代の到来を告げる観客やプレスから「時代遅れ」と酷評されてしまいます。
当時の音楽誌『サウンズ』に掲載されたジョン・インガムによるレビューでは、彼らが「ピストルズによって引かれつつある境界線の遥か外側」にいると断じられました。
この手厳しい評価こそが、彼らにとってのインスピレーションとなったのです。
ピストルズの生々しい暴力性とサウンドの衝撃を目の当たりにした彼らは、即座に自分たちの進むべき道を悟りました。
ギグの後、彼らは髪を切り、服装を改め、サウンドをより速く、より攻撃的なものへと変化させたのです。
まさにこのギグが、グラムロックバンドを正真正銘のパンクバンド、スローター・アンド・ザ・ドッグスとして生まれ変わらせた瞬間でした。
レッサー・フリー・トレード・ホールのギグの歴史的重要性
この歴史的なギグの観客席には、後のジョイ・ディヴィジョン/ニュー・オーダーのメンバー、ザ・フォールのマーク・E・スミス、そしてザ・スミスのモリッシーといった、マンチェスターの音楽シーンを根底から変えることになる若者たちがいました。当初のスタイルこそシーンとは異質でしたが、この「事件現場」に当事者として居合わせたという事実が、彼らにマンチェスターパンクの創生神話における、揺るぎない地位を永遠に与えることになったのです。
1-3. 名曲「Cranked Up Really High」の衝撃
「Cranked Up Really High」は、スローター・アンド・ザ・ドッグスを象徴するアンセムであり、英国パンク史、特にロンドン以外の地方都市におけるパンクの勃興を語る上で絶対に欠かせない一曲です。
この曲のリリースは、マンチェスターの音楽シーンに革命的な衝撃を与えました。
1977年6月、設立されたばかりのインディペンデント・レーベル「ラビッド・レコード(Rabid Records)」からリリースされたこの7インチシングルは、記録上、マンチェスターのパンクバンドによってリリースされた初のインディシングルとなりました。
当時、音楽産業もメディアもロンドンに一極集中していた状況で、マンチェスターからの狼煙(のろし)となったこの一枚の持つ意味は計り知れません。
この歴史的なシングルの誕生には、後のマンチェスターシーンを形作ることになる二人の重要人物が深く関わっています。
- ロブ・グレットン:当時、バンド専門のファンジン『Manchester Rains』を発行するほどの熱心なファンだった彼は、後にジョイ・ディヴィジョンやニュー・オーダーの伝説的なマネージャーとなります。彼は自らの資金を投じて、このシングルのレコーディングとリリースを全面的にバックアップしました。
- マーティン・ハネット:こちらも後にジョイ・ディヴィジョンやハッピー・マンデーズを手掛け、ファクトリー・レコードのサウンドを定義する鬼才プロデューサー。彼の初期の仕事の一つであるこの曲では、バンドの持つ生々しいエネルギーを損なうことなく、緊張感と鋭利さをサウンドに与えることに成功しています。
この曲の普遍的な評価は、英国の権威ある音楽雑誌MOJOが企画した「100 Punk Scorchers」で史上最高のパンクシングルの一つに選出されるなど、数々のメディアで証明されています。
シンプルながらも一度聴いたら耳から離れない衝動的なギターリフと、ウェイン・バレットの投げ捨てるような気だるいヴォーカルは、まさにクラシック・パンク・アンセムと呼ぶにふさわしい完成度を誇ります。
この一曲のインディーズでの成功が、彼らをメジャーレーベルであるデッカ・レコードとの契約へと導きました。
しかし、皮肉なことに、このメジャー契約という「成功」が、後のバンドの創造性を削ぎ、最初の解散へと向かわせる大きな一因となってしまうのです。
1-4. ライブで人気の高いBoston Babies
「Boston Babies」は、スローター・アンド・ザ・ドッグスの初期レパートリーの中でも、特にライブでの爆発力と人気において際立った存在の一曲です。
この曲は、彼らのストレートでエネルギッシュなロックンロールの真髄を凝縮したようなナンバーであり、パンクムーブメントの初期衝動を見事に捉えています。
この楽曲が初めて公式に音源として世に出たのは、1977年6月にハーヴェスト-レコードからリリースされた、歴史的なライブ・コンピレーション-アルバム『Live at the Roxy WC2』でした。
ロンドンのコヴェント・ガーデンにあった伝説的なパンク-クラブ「ロキシー・クラブ」での100日間のライブ音源を収録したこのアルバムに、「Runaway」と共に彼らの生々しい演奏が収められています。
このアルバムは全英アルバムチャートで24位を記録し、地方都市マンチェスターのバンドだった彼らの名を全国区に知らしめるきっかけとなりました。
ロキシー・クラブは、ダムド、ザ・クラッシュ、ジェネレーションX、スリッツといった、まさに初期ロンドンパンクを代表するバンドが連夜ステージに立っていた聖地中の聖地。
そこでライブ音源が公式盤としてリリースされたことは、マンチェスター出身の彼らがロンドンのシーンでも高く評価され、受け入れられていた何よりの証拠と言えるでしょう。
「Boston Babies」の抗いがたい魅力は、そのシンプルで中毒性の高いギターリフと、オーディエンスが拳を突き上げながら一体となってシンガロングできるキャッチーなコーラスにあります。
ライブでは、バンドの演奏がスタジオ音源以上に熱を帯び、観客を興奮の渦に巻き込む必殺のキラーチューンとして、長年にわたり機能してきました。
さらに、この曲はレゲエDJであり映画監督のドン・レッツが撮影したドキュメンタリー映画『The Punk Rock Movie』でも、ロキシー・クラブでの彼らの貴重なライブシーンと共にフィーチャーされています。
これにより、当時のバンドの荒々しい勢いとパフォーマンスを映像で確認することができます。
現在に至るまで、彼らのライブセットリストに欠かせない、ファンにとって最も重要なレパートリーの一つであり続けています。
また、この「Boston Babies」が後世のパンクシーンに与えた影響は大きく、特にイギリスのハードコア・パンクバンドであるG.B.H.がカバーしていることでも知られています。
G.B.H.によるカバーは、オリジナルが持つ初期衝動をさらに激しく、アグレッシブに解釈したもので、この曲がジャンルを超えていかに多くのバンドに影響を与え続けているかを示す象徴的な例と言えるでしょう。
このカバーによって、新たな世代のパンクファンにもその魅力が伝わり、楽曲の普遍的なパワーが再認識されることにも繋がりました。
1-5. パンカビリーにも通じる音楽スタイル
スローター・アンド・ザ・ドッグスの音楽性を、単に「77年型パンク」という枠だけで語るのは、彼らの本質を見誤る可能性があります。
彼らのサウンドには、パンクの持つ性急な攻撃性に加えて、グラムロック由来の華やかさ、そして50年代のルーツ-ロックンロールへの深い憧憬が色濃く反映されています。
そのユニークなスタイルは、後にパンカビリーと呼ばれるようになるジャンルの先駆けとも言える側面を持っていました。
パンカビリーとは、パンクのスピード感とDIY精神に、ロカビリーの軽快なシャッフル・リズムや特徴的なギターフレーズ、そして時にホラーやB級映画のテイストを融合させた音楽ジャンルです。
彼らの楽曲、特にギタリスト、ミック・ロッシのギタープレイには、チャック・ベリー直系の躍動感あふれるリフや、ミック・ロンソンの構築美を感じさせるフレーズが散見され、単なる3コードのパンクロックとは一線を画す、ロックンロールの「粋」や「華」が込められています。
多様な音楽性のハイブリッド
彼らのサウンドは、主に以下の要素が複雑に絡み合い、唯一無二のハイブリッド-サウンドを形成しています。
- グラムロック:デヴィッド・ボウイ、Tレックス、モット-・ザ・フープルからの影響。キャッチーなメロディラインと、派手でシアトリカルなステージングの基盤。
- パンクロック:セックス・ピストルズやニューヨーク・ドールズから受けた衝撃。サウンドのスピード感、攻撃性、そして歌詞の反抗的なテーマ。
- パブ・ロック/R&B:ドクター・フィールグッドのようなパブ・ロックバンドや、ローリング・ストーンズに通じる、骨太でブルージーなロックンロールの感覚。
この多様な音楽性を示す最も象徴的な例が、彼らの代表曲の一つ「Where Have All The Boot Boys Gone?」です。
この曲は、当時の英国社会問題であったスキンヘッズやフットボール・フーリガンといったギャング文化を教訓的に描いたものですが、そのサビのテラス・チャント(サッカースタジアムでの応援歌)のような高揚感あふれるコーラスから、バンドの本来の意図とは別に、後に勃興するOi!/ストリート-パンクシーンのゴッドファーザーとして崇められる原因となりました。
グラムロックに影響を受けたバンドが、全く意図せずして、より硬派で労働者階級のアイデンティティを前面に押し出したOi!ムーブメントのアンセムを書いてしまったという事実は、彼らの音楽が持つ一筋縄ではいかない魅力と、サブカルチャーにおける意味の流転を物語る、非常に興味深いケーススタディと言えるでしょう。
2. スローター・アンド・ザ・ドッグスの作品と現在
- デビュー盤「Do It Dog Style 」の魅力
- 彼らの全曲とアルバムを紹介
- シングル「Situations」などの希少性
- Discogsでコレクションをコンプリート
- 最新のTour情報と今後の活動
- レコードで聴きたいスローター・アンド・ザ・ドッグス
2-1. デビュー盤「Do It Dog Style」の魅力
1978年5月、大手デッカ・レコードからリリースされた『Do It Dog Style』は、スローター・アンド・ザ・ドッグスにとって最初で最後となったオリジナルラインナップでのスタジオアルバムです。
このアルバムは、バンドが内包していたエネルギー、音楽的な背景、そして時代の空気が奇跡的に結晶化した、英国パンクの金字塔として今なお高く評価されています。
このアルバム最大の魅力は、パンクロックが持つ性急なスピード感と、彼らの音楽的ルーツであるグラムロックの華やかさ(彼らが言うところの “swagger”)が見事に融合している点にあります。
ミック-ロッシのギターは鋭利なリフを刻みながらも歌心にあふれ、ウェイン・バレットのヴォーカルは反抗的でありながらどこかグラマラスな響きを持っています。
この絶妙なバランスが生み出すサウンドは、アナログレコードで聴くことでその真価を最大限に発揮します。
当時のレコーディングが持つ生々しい空気感、ラウドなギターサウンドの壁のような質感、そしてステレオの左右に振り分けられた楽器の定位など、制作者の意図をよりダイレクトに感じ取ることができるでしょう。
ヒーロー、ミック・ロンソンのゲスト参加
このアルバムを語る上で絶対に欠かせないのが、バンドにとって神のような存在であったヒーロー、ミック・ロンソンが2曲でゲスト参加しているという事実です。
先行シングルにもなったザ・スプートニクスのカバー「Quick Joey Small」で聴ける、彼のむせび泣くようなスライドギターはまさに圧巻の一言。
自分たちのアイドルとスタジオで共演するという、バンドにとって最大の夢が叶った瞬間でもありました。
しかし、この歴史的名盤には、あまりにも悲しい運命が待ち受けていました。
度重なるリリースの遅延、そして大手レーベルとのプロモーション方針を巡る根深い確執から、バンドはアルバムがレコード店の棚に並ぶ数日前に、あっけなく解散してしまいます。
ツアーやメディア露出といったプロモーションを行うバンド本体が存在しない状況では、アルバムが正当な評価を得ることは難しく、商業的にも成功を収めることはできませんでした。
とはいえ、時代が経つにつれて口コミでその評価は着実に高まり、後年になって再評価が進みました。
現在ではマンチェスターパンクを代表する必聴盤の一枚として、世界中のロックファンに愛され続けています。
特に、英国オリジナルの初版レコードは、その音質の良さと希少性から、コレクターズアイテムとして常に高値で取引されています。
2-2. 彼らの全曲とアルバムを紹介
スローター・アンド・ザ・ドッグスのキャリアは、度重なる解散と再結成、メンバーチェンジに彩られた複雑なものですが、その中で数多くの印象的でパワフルな曲とアルバムを世に送り出してきました。
ここでは、彼らの主要なディスコグラフィーをスタジオアルバムと代表的なシングルに分けて、その変遷と共に紹介します。
スタジオ・アルバム
彼らの音楽性の進化、あるいは変化を時系列で辿ることができるスタジオアルバムは、バンドを深く理解するための必須アイテムです。
| アルバム-タイトル | リリース年 | レーベル | 備考 |
|---|---|---|---|
| Do It Dog Style | 1978 | Decca | パンクの衝動とグラムの華やかさが融合した記念碑的デビューアルバム。ミック-ロンソンが2曲に参加。 |
| Bite Back | 1980 | DJM | バンド名を「Slaughter」に短縮。ヴォーカルに元ノーズブリーズのエディ-ギャリティを迎え、よりハードロック色の強いサウンドに変化。 |
| Shocking | 1991 | Receiver | 約10年の長い沈黙を破ってリリースされた復活作。80年代のハードロックやメタルの影響も感じさせるサウンド。 |
| Beware Of… | 2001 | Captain Oi! | 21世紀に入り、原点回帰ともいえるストレートなパンクロックを展開した力作。 |
| Vicious | 2016 | Cleopatra | オリジナルラインナップ再結成の流れで制作されたアルバム。往年の勢いと円熟味を兼ね備える。 |
| Il Tradimento Silenzioso | 2022 | Contra | イタリア語で「静かなる裏切り」を意味するタイトルが印象的な最新作。ウェイン・バレット主導で制作された。 |
主要シングル
時代を象徴するアンセムから、コレクター泣かせのレア盤まで、彼らの7インチシングルはパンクの初期衝動そのものであり、まさにパンクロックの魅力に溢れています。
- Cranked Up Really High / The Bitch (1977): マンチェスター初のインディ・パンク・シングルにして、永遠のクラシック。
- Where Have All The Boot Boys Gone? / You’re a Bore (1977): 意図せずOi!パンクのアンセムとして後世に語り継がれることになった問題作。
- Dame To Blame / Johnny T (1977): メジャーからの第2弾シングル。キャッチーなメロディが光る。
- Quick Joey Small / Come On Back (1978): ミック・ロンソンがギターで全面参加した、バンドの夢が結実した一枚。
- You’re Ready Now / Runaway (1979): 最初の再結成時にDJMレコードからリリースされた、ポップな魅力を持つシングル。
これらの作品群を聴けば、彼らが単なる77年パンクの一発屋ではなく、時代と共にサウンドを変化させながらも、常に独自のロックンロールを追求し続けた、誠実で不器用なバンドであったことが理解できるはずです。
2-3. シングル「Situations」などの希少性
スローター・アンド・ザ・ドッグスのディスコグラフィーには、アルバムには収録されなかった楽曲や、ごく少数プレスのみでリリースされたシングルが数多く存在し、世界中の熱心なレコードコレクターたちの探求心を絶えずくすぐり続けています。
中でも、2015年にリリースされたシングル「Situations」は、彼らのキャリア後期にあたる比較的新しい作品でありながら、その希少性から注目を集めている一枚です。
このシングルは、アメリカのインディペンデント・レーベル「Brass City Boss Sounds」から、こだわりの7インチ・アナログ盤としてリリースされました。
B面には、彼らのヒーローであるミック・ロンソンが参加した名カバー曲「Quick Joey Small」が収録されており、新旧のファン双方にとって非常に魅力的なカップリングとなっています。
レーベルの性格上、生産枚数が限られており、現在では市場で見つけることがやや困難になりつつあるアイテムです。
コレクターズアイテムとして価値の高いシングル群
「Situations」以外にも、以下のようなシングルはコレクター市場で特に人気があり、高値で取引される傾向にあります。
- You’re Ready Now / Runaway (1979): 最初の再結成時にDJMレコードからリリースされたシングル。バンドのメンバー構成が非常に流動的だった混乱期の貴重な音源であり、当時の英国盤ピクチャースリーブ付きは特に珍重されます。
- It’s Alright EP (1979): TJMレコードからリリースされた4曲入りEP盤。「Edgar Allan Poe」など、初期のデモ音源に近く、パンクというよりもグラムロックやハードロック色が強く残ったサウンドが特徴で、バンドのルーツを知る上で欠かせません。
- Half Alive E.P. (1983): バンドが長い活動休止期間に入っていた時期に、Thrush Recordsから突如リリースされた、ライブ音源とスタジオ音源の混合EP。正規の活動がなかった時期の音源だけに、資料的価値も高い一枚です。
これらのシングルは、単なる楽曲の記録というだけでなく、バンドの歴史の重要な節目や、音楽性の変化をリアルタイムで捉えた貴重なドキュメントと言えます。
特に70年代後半から80年代初頭にかけてのオリジナル盤は、パンクムーブメントの熱気と混沌としたエネルギーを、ジャケットのアートワークや盤面の質感ごとパッケージした、タイムカプセルのような存在です。
こうした希少なシングルを一枚一枚探し出し、コレクションに加えていくのも、スローター・アンド・ザ・ドッグスという奥深いバンドを最大限に楽しむための一つの方法と言えるでしょう。
2-4. Discogsでコレクションをコンプリート
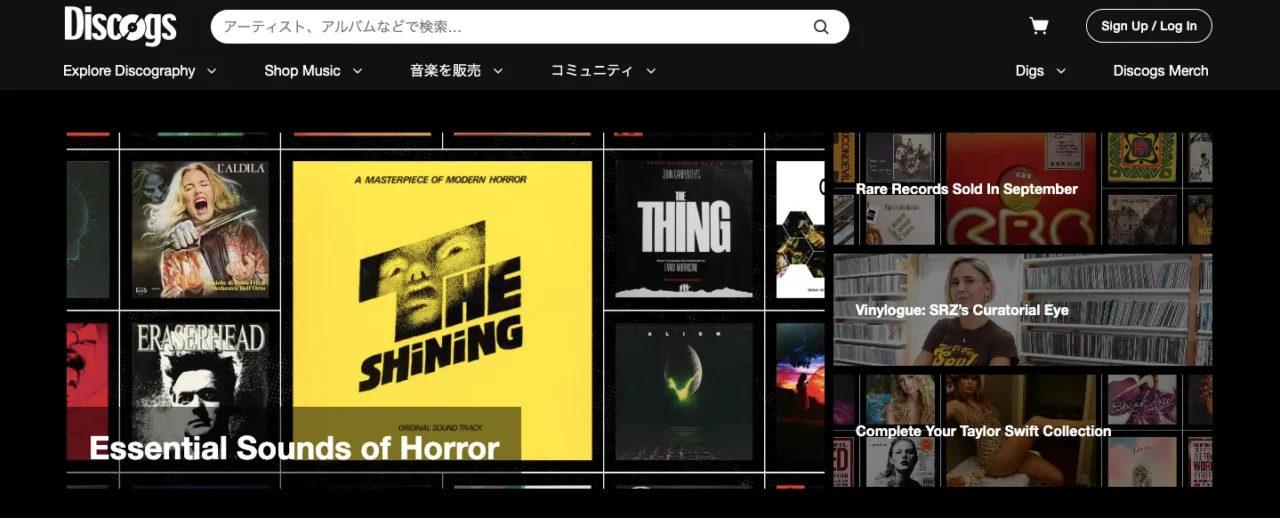
スローター・アンド・ザ・ドッグスのオリジナル盤レコードや、今では廃盤になってしまったCDを探し求めているなら、オンラインの巨大音楽データベース兼マーケットプレイスであるDiscogs(ディスコグス)の利用が、現在考えられる最も有効かつ確実な手段です。
世界中のレコードセラーや個人コレクターが数百万点以上のアイテムを出品しているため、地元のレコード店を何年もかけて探し回っても見つからなかったような、希少なアイテムに巡り会える可能性が非常に高まります。
Discogsを利用する最大のメリットは、その圧倒的な情報量とデータベースとしての正確性にあります。
単にレコードを売買するだけでなく、各リリースの詳細な情報を正確に確認できるのが最大の特徴です。
コレクションをコンプリートしたいヘビーなファンはもちろん、「まずは代表作のアナログ盤を聴いてみたい」という入門者にとっても、Discogsは強力な味方となってくれます。
日本からDiscogsを利用する簡単ガイド
もちろん、Discogsは日本からでも全く問題なく利用できます。
サイトは基本的に英語ですが、簡単な手順で世界中のレコードを購入することが可能です。
公式サイトにアクセスし、メールアドレスとパスワードを設定するだけで簡単に登録できます。
欲しいアーティスト名「Slaughter and the Dogs」やアルバム名「Do It Dog Style」で検索します。
商品ページで最も重要なのが出品者の情報です。「Ships from:」が出品国、「Ships to:」が発送対応国です。必ず「Japan」へ発送してくれる出品者かを確認しましょう。また、「Shipping」の項目で日本への送料がいくらかも必ず確認してください。
多くの出品者がPayPalでの支払いに対応しています。事前にPayPalアカウントを作成しておくと、決済が非常にスムーズです。
海外からの購入に関する注意点
Discogsでの購入は個人輸入にあたるため、いくつか注意点があります。
- 出品者の評価: トラブルを避けるため、購入前には必ず出品者の評価(Feedback)を確認し、評価の高い(99%以上が目安)出品者から購入することをおすすめします。
- 関税・消費税: 商品価格と送料の合計額が一定額(一般的に16,666円)を超えると、日本の税関で関税と消費税が課せられる場合があります。これは商品到着時に配達員から請求されることが一般的です。(参照:税関「個人輸入通関手続」)
これらの点に注意すれば、Discogsはあなたのレコードコレクションを飛躍的に充実させてくれる素晴らしいツールです。
お目当てのレコードを探すだけでなく、自分が持っているコレクションを登録して管理したり、「Wantlist」機能を使って探しているアイテムが出品された際に通知を受け取ったりと、音楽コレクターにとって夢のような機能が満載です。
2-5. 最新のTour情報と今後の活動
スローター・アンド・ザ・ドッグスの現在の活動状況は、長年のファンにとっても少々複雑で、心を痛める様相を呈しています。
数十年にわたるキャリアの中で、メンバー間の人間関係や音楽性の違いは少しずつ変化し、近年、バンド名の所有権を巡る法的な争いにまで発展してしまいました。
その結果、現在は二つの異なるバージョンのバンドが、それぞれ「スローター・アンド・ザ・ドッグス」を名乗り、並行して活動するという異例の状況が生まれています。
この問題は、2018年にヴォーカリストのウェイン・バレットが単独で英国の商標を登録したことに端を発します。
これに対し、他のオリジナルメンバーが異議を申し立て、法廷闘争へと発展。
最終的に英国知的財産庁はバレットの単独登録を無効と判断しましたが、両者の間の溝は埋まらず、分裂は決定的となりました。
二つの「スローター・アンド・ザ・ドッグス」
チケットを購入する際はメンバーの確認が必須
現在、Tourやライブ活動を行っているのは、主に以下の二組です。どちらのバンドのパフォーマンスを観たいのか、ライブ告知の際に発表されるメンバー構成をよく確認することを強くお勧めします。
- Wayne Barrett’s Slaughter & the Dogs™
バンドの創設者であり、象徴的な「声」を持つオリジナル・ヴォーカリスト、ウェイン・バレットが率いるバージョンです。彼はフランスとアメリカを拠点とする新しいラインナップ(長年ベースを弾いてきたジャン=ピエール・ソレなど)と共に、ヨーロッパやアメリカを中心に精力的にツアーを続けています。2025年には活動に一区切りをつけるファイナルショーを計画しているとの情報もあります。 - Slaughter & The Dogs (Original Members)
バンドの音楽的な核を担ってきたギタリストのミック・ロッシ、ベーシストのハワード・ベイツ、ドラマーのブライアン・グランサムといったオリジナルメンバーが中心となったバージョンです。こちらも「オリジナル」を冠して、主にイギリス国内のフェスティバルなどでライブ活動を行っており、同じく2025年までの活動を告知しています。
この分裂はファンにとって悲しい出来事ではありますが、両者がそれぞれの形でバンドの偉大なレガシーを守り、楽曲を未来に伝えようとしていると捉えることもできます。
一方はオリジナルの「声とカリスマ」を、もう一方はオリジナルの「サウンドとグルーヴ」を継承していると言えるかもしれません。
最新のtour情報については、それぞれのバンドが運営する公式サイトや公式SNSアカウントを直接フォローし、確認するのが最も確実です。
伝説のバンドのパフォーマンスを直接体験できる貴重な機会ですので、情報をこまめにチェックしてみてはいかがでしょうか。
2-6.レコードで聴きたいスローター・アンド・ザ・ドッグス
この記事では、マンチェスターが生んだ偉大なパンクロック・バンド、スローター・アンド・ザ・ドッグスの多岐にわたる魅力と、その波乱に満ちた歴史を深く掘り下げてきました。
最後に、彼らのキャリアを総括する上で重要なポイントを、改めてリスト形式でまとめます。
- バンド名はミック・ロンソンの『Slaughter on 10th Avenue』とデヴィッド・ボウイの『Diamond Dogs』が由来
- その音楽的ルーツは77年パンク以前のグラムロックに深く根差している
- 中心メンバーはヴォーカルのウェイン・バレットとギターのミック・ロッシという二人の強烈な個性
- 出身地である労働者階級の街ウィゼンショウの荒々しい空気が音楽性に色濃く反映された
- 1976年のセックス・ピストルズの歴史的ギグを体験し、グラムからパンクへと劇的な転身を遂げた
- 名曲「Cranked Up Really High」はマンチェスター初のインディ・パンク・シングルという記念碑的作品
- マーティン・ハネットやロブ・グレットンといった後のマンチェスターシーンの重要人物に早くから才能を見出されていた
- デビューアルバム「Do It Dog Style」にはバンドのヒーローであるミック・ロンソンがゲスト参加している
- しかしアルバムリリース直前に解散するという商業的には不運なスタートを切った
- ライブアンセム「Boston Babies」は伝説の『Live at the Roxy WC2』に収録され名を上げた
- その音楽性は単なるパンクに留まらず、パンカビリーや後のOi!パンクにも通じる幅広さを持つ
- キャリアを通じて解散と再結成を繰り返し、その歴史は複雑を極める
- Discogsのようなマーケットプレイスは彼らの希少なレコードを探す上で最適なツールである
- シングル「Situations」など、後年にリリースされた作品にもコレクターズアイテムが多数存在する
- 現在はバンドが分裂状態にあり、二つのバージョンがそれぞれTourなどの活動を行っている
彼らの音楽が持つ、荒々しくもキャッチーで、どこか切ないロックンロールの魅力は、便利なデジタル音源で楽しむのも良いですが、ぜひ一度、アナログレコードに針を落とし、そのサウンドの真髄に全身で触れてみてください。
そこには、時代を超えて輝き続ける本物の衝動が刻み込まれているはずです。

【人生の初期衝動】
「彼らは体制を拒否した。しかし、現実の生活は続く。『反体制』を貫くための現実的な財産形成はこちらで確認できます。」
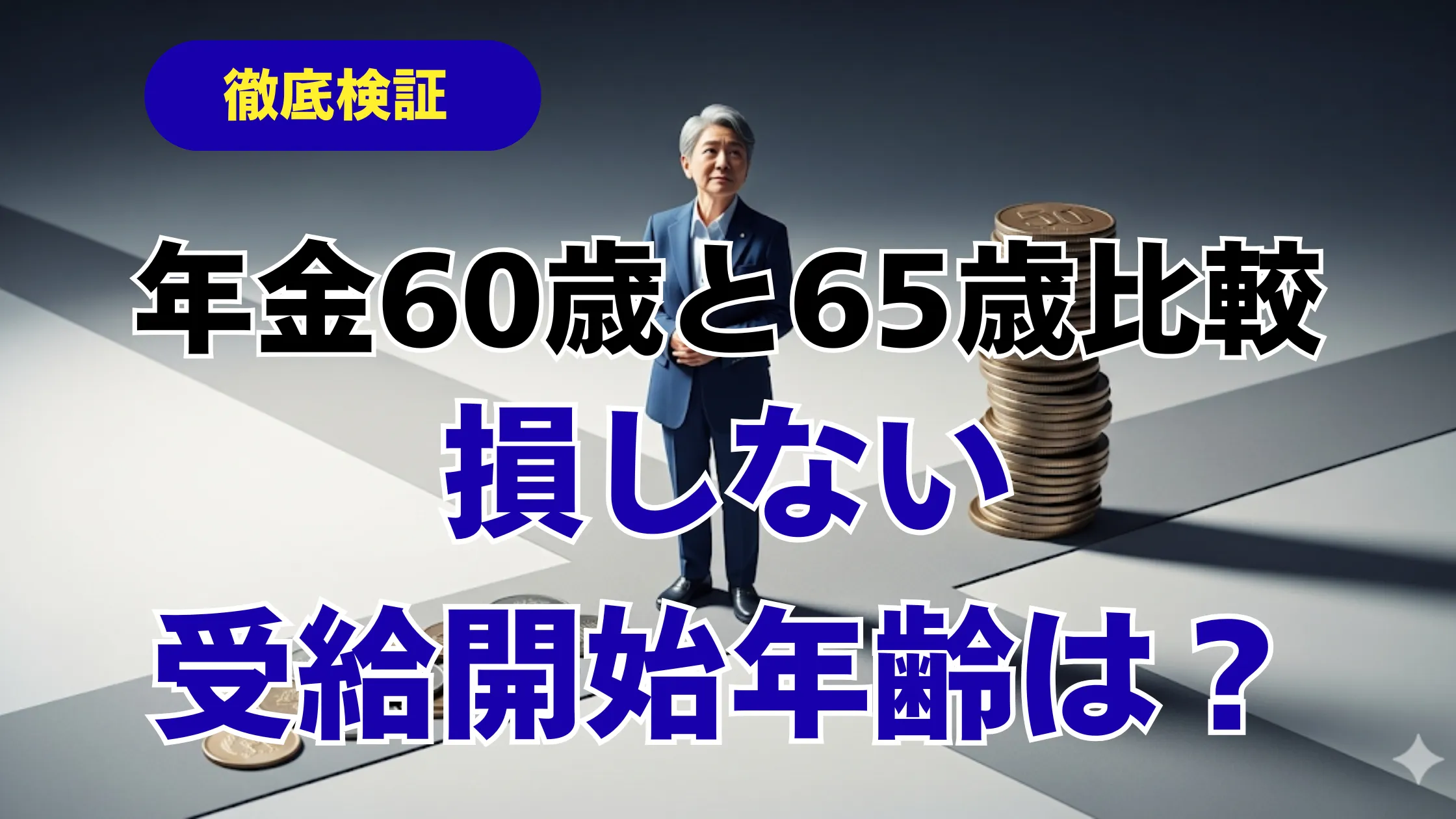

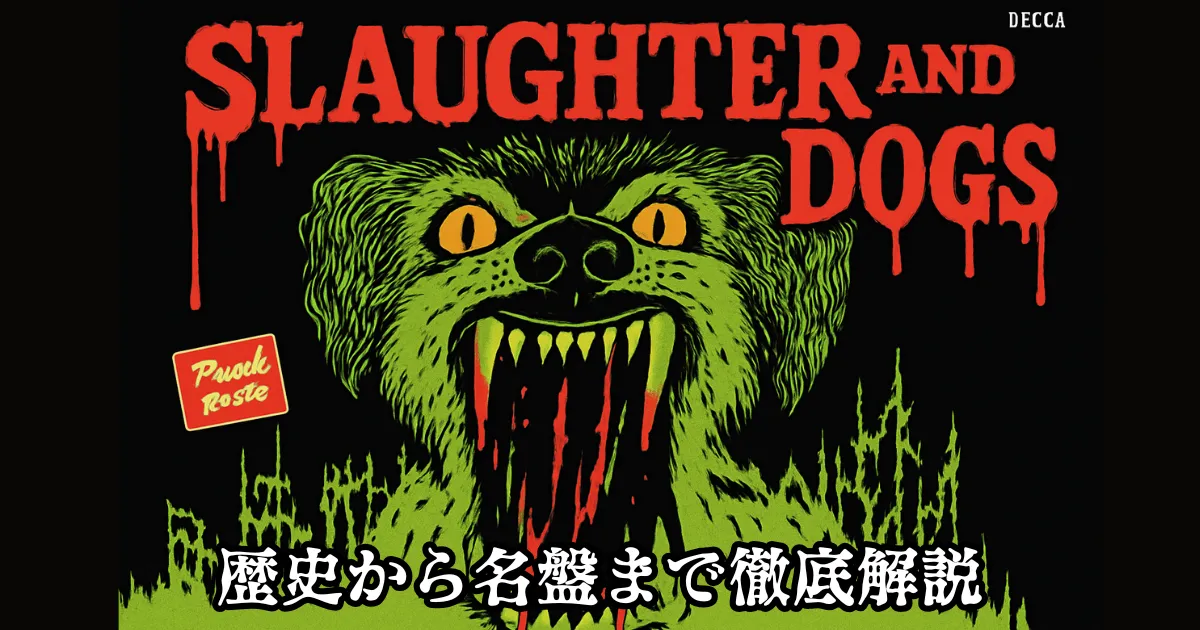



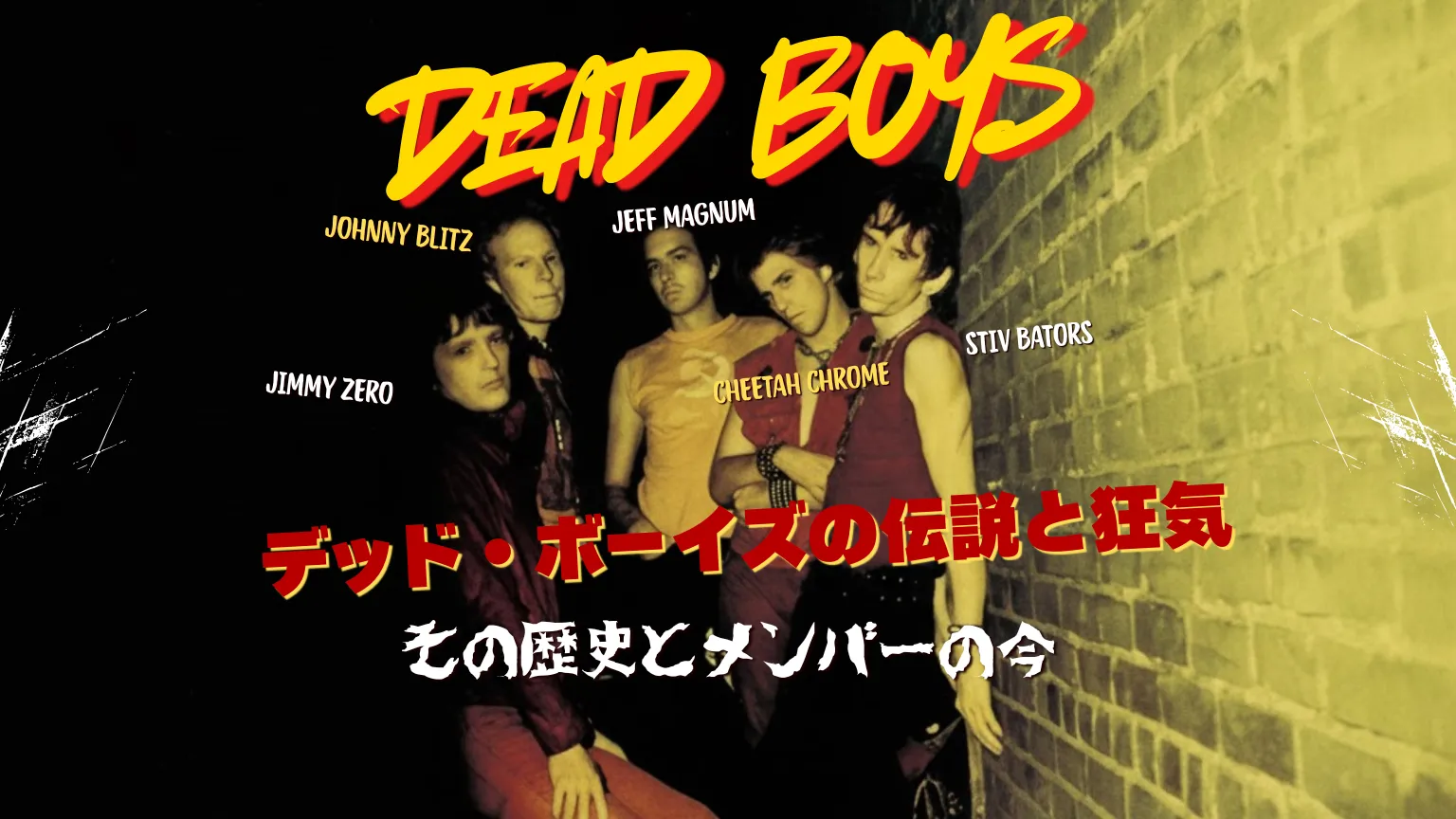



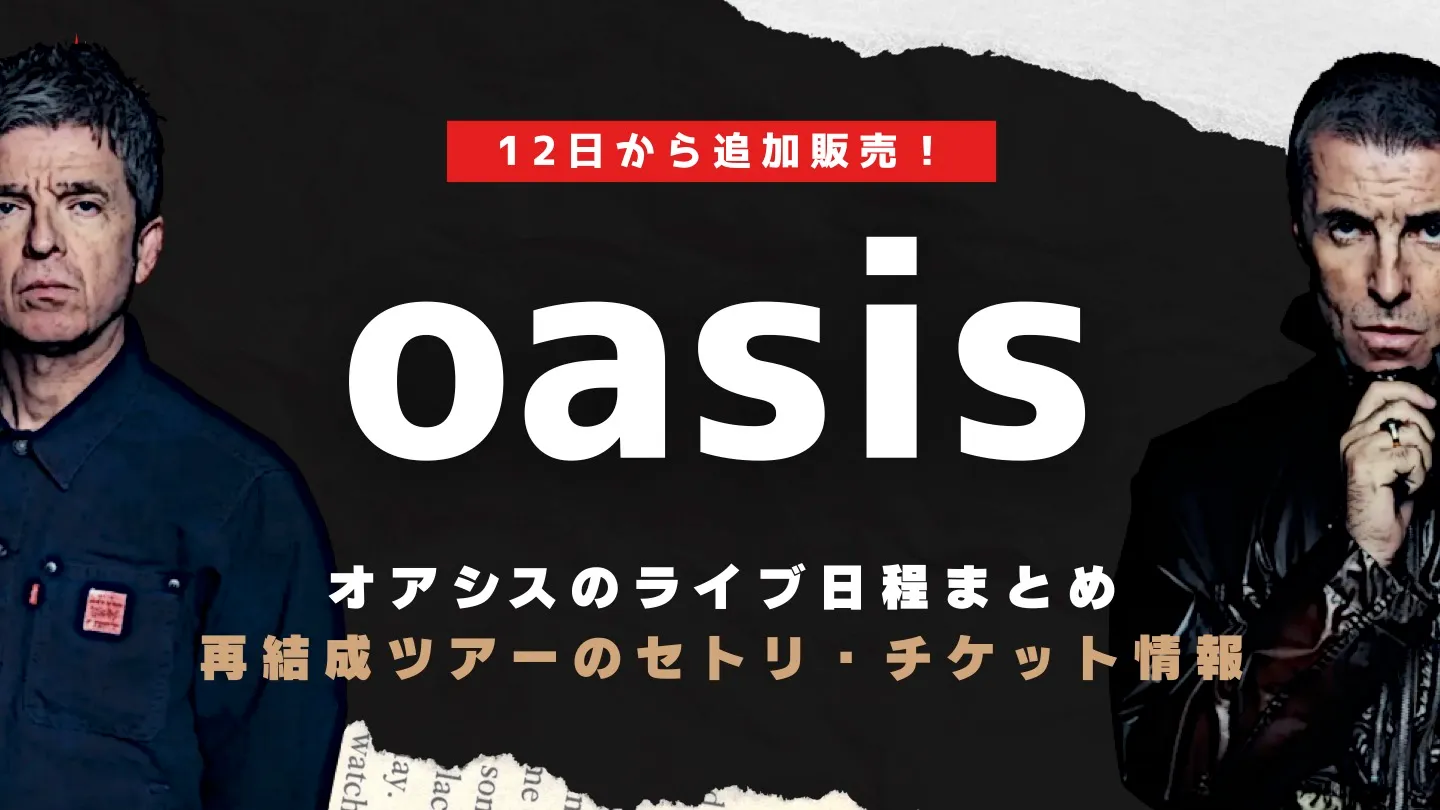
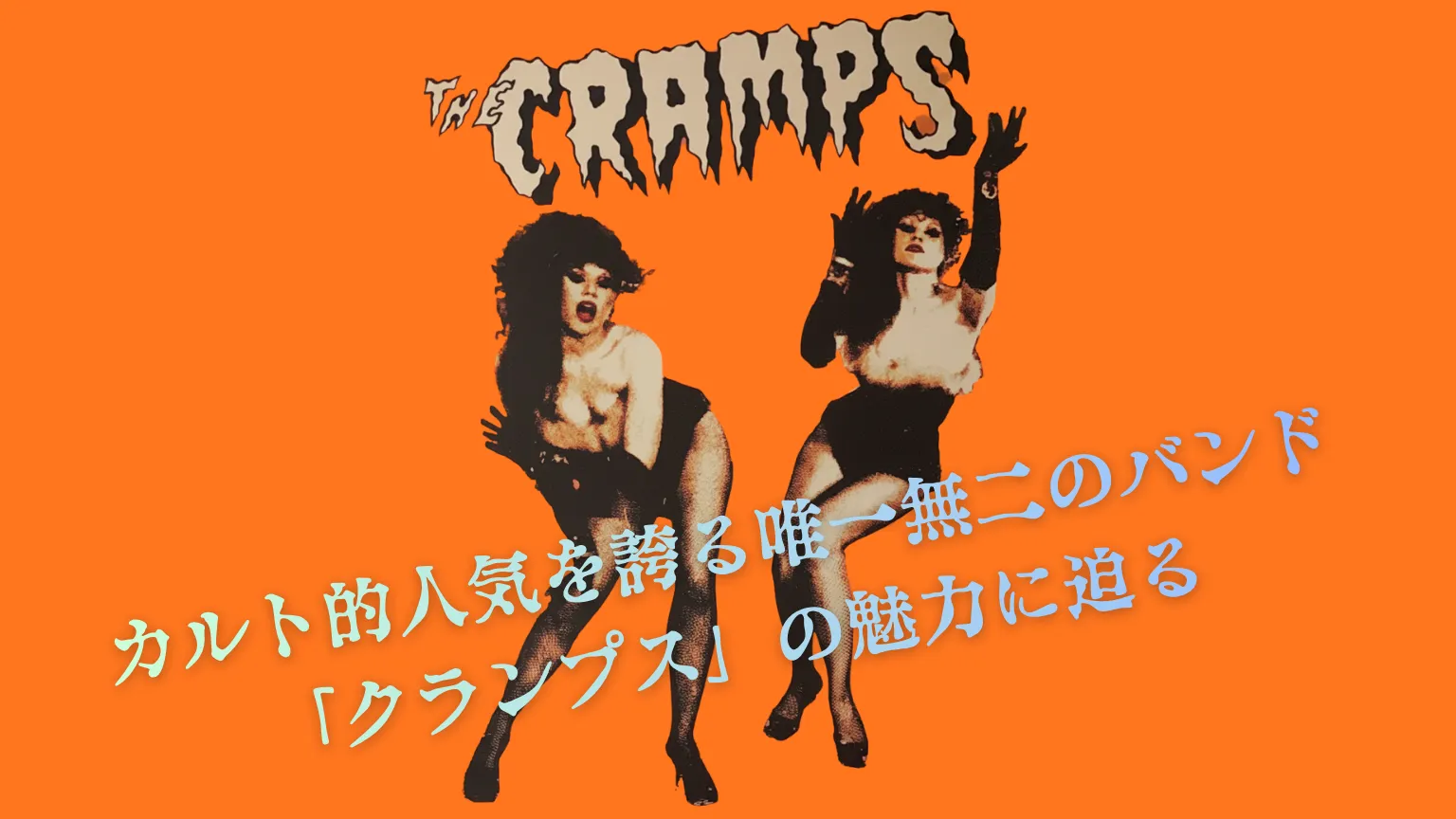






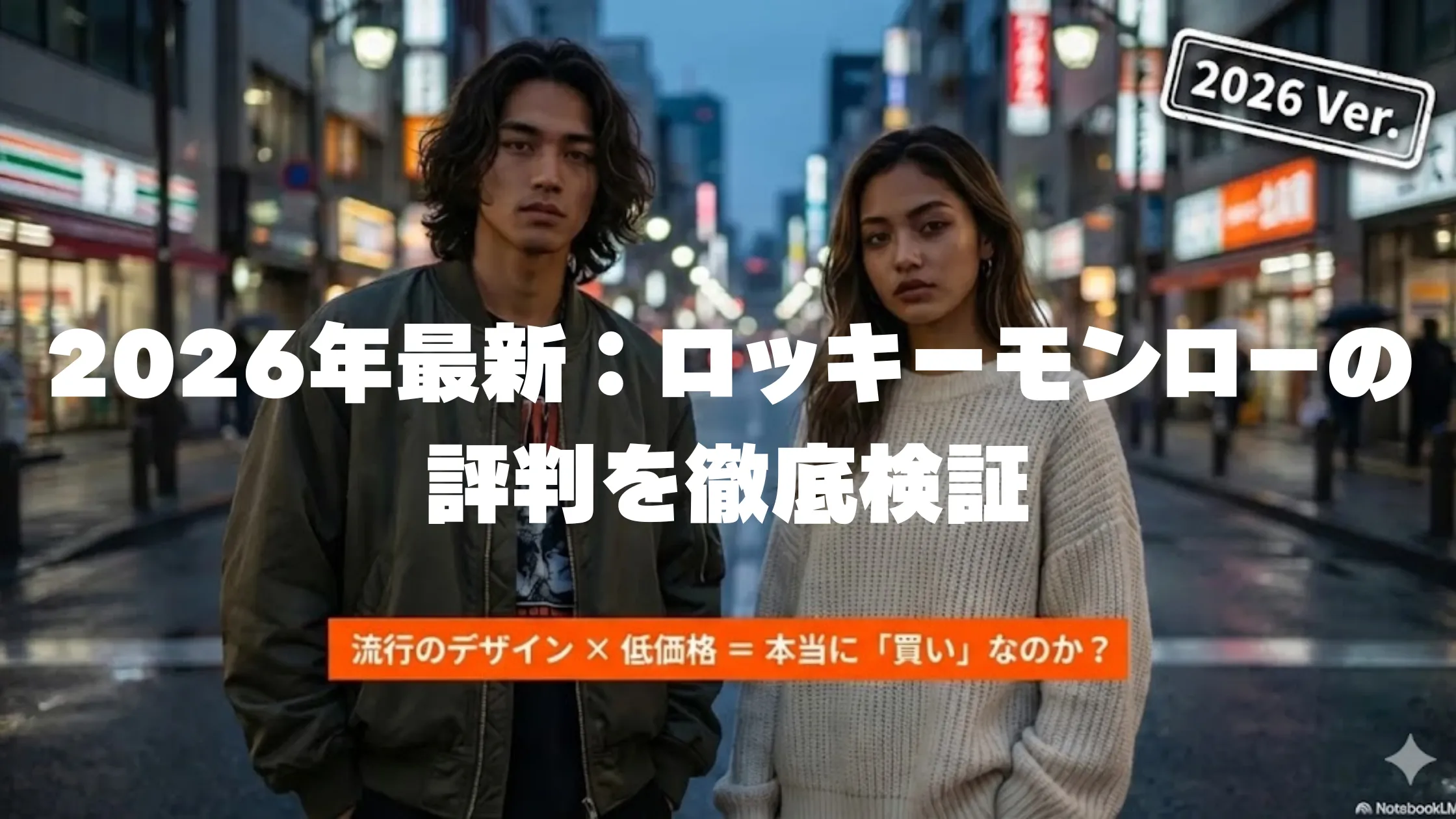
コメント