こんにちは。ジェネレーションB、運営者のTAKUです。
今回は、gang of four entertainmentというキーワードで検索してきたあなたに向けて、ポストパンクの金字塔アルバム『Entertainment!』と、その周辺情報をまるっと整理していきます。
Gang of Fourというバンドのこと、『Entertainment!』がどんなポストパンクアルバムなのか、Full Albumをどこで聴けるのか、SpotifyやYouTube、さらにはLPやCD、Discogsの情報、海外Reviewや批評家評価、Wikiやlyricsとの関係まで、検索してもバラバラにしか出てこなくて「結局どこから押さえればいいの?」と感じている人も多いはずです。
実際、『Entertainment!』はリリースから40年以上たっても海外のReviewサイトや音楽メディアで繰り返し取り上げられていて、DiscogsではさまざまなReissueやRemasterの盤が登録されていますし、SpotifyのOfficial AlbumページやYouTubeのFull Albumプレイリストも乱立しています。
さらに、Gang of Four Entertainment LLCのような名前のビジネス実体も検索結果に混ざるので、「これはバンドのこと?会社のこと?」と混乱しやすいポイントでもあります。
加えて、当時のイギリス社会の空気や、同時代に並走していたポストパンクバンドたちの動きまで含めて理解しようとすると、情報のボリュームが一気に跳ね上がります。
パンク、ポストパンク、オルタナ、インディ、さらには現代のポストパンク・リバイバルまで、Gang of Fourの影響があまりに広範囲なので、「どこまで追いかけるべきか」で迷う人もいると思うんですよね。
そこでこの記事では、私が長年聴き込んできた経験も交えながら、『Entertainment!』というアルバムの成り立ちや意味、代表曲、lyricsの読み解き方、VinylやCDを探すときのDiscogs活用法、Spotifyや他ストリーミングでFull Albumを楽しむコツまで、gang of four entertainmentまわりの情報を一気に整理していきます。
ここ、かなりややこしいところも多いので、一緒にゆっくりほどいていきましょう。
- 『Entertainment!』がポストパンク史でどんな位置づけのアルバムなのかがわかる
- 代表曲の特徴や歌詞の意味をざっくり把握して、歌詞カードを読む楽しみが増える
- SpotifyやYouTube、VinylやCD、Discogsを使って自分に合う聴き方を選べるようになる
- wikiやGang of Four Entertainment LLCとの違いを理解して、検索で迷子になりにくくなる
1. Gang of Four 『Entertainment!』解説
ここでは、Gang of Fourのデビューアルバム『Entertainment!』がどんな作品なのか、ざっくり全体像をつかめるように整理していきます。
時代背景の中でのポジション、Tracklistと代表曲、Lyricsの意味、海外Reviewや評価、そして現代的なFull Albumの聴き方まで、まずは入り口として押さえておきたいポイントをまとめます。
ここを押さえておくと、後半のディープな話も一気に理解しやすくなりますよ。
1-1. デビューAlbumとしての位置

『Entertainment!』は、1979年にリリースされたGang of FourのデビューAlbumです。
場所でいうとイギリスのリーズ発、時間でいうとパンクの爆発が一段落して、ポストパンクが一気に立ち上がってきたタイミングですね。
セックス・ピストルズやクラッシュがぶち抜いたドアの先で、「ロックをどう再構築するか?」を試行錯誤していた時代です。
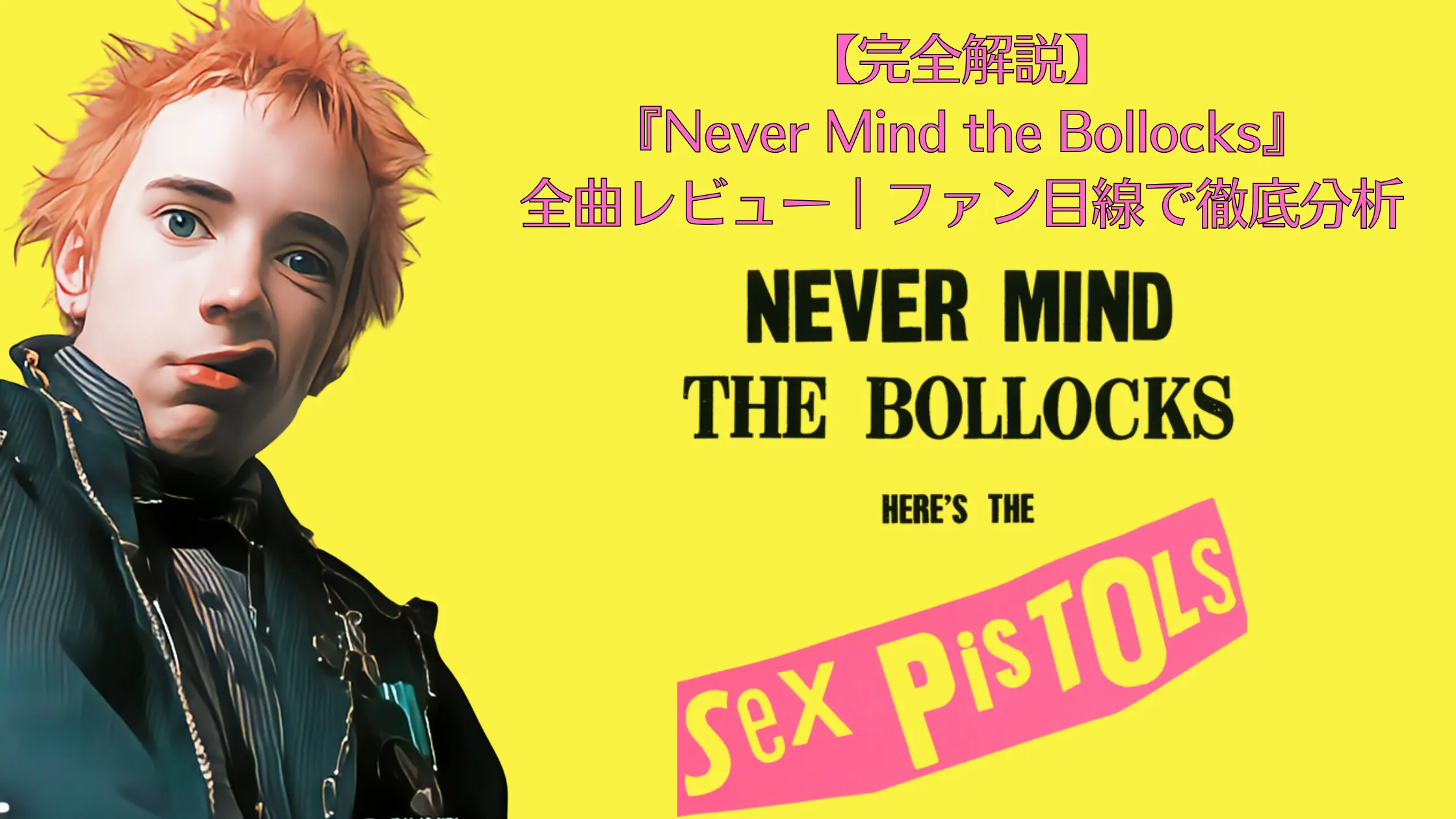
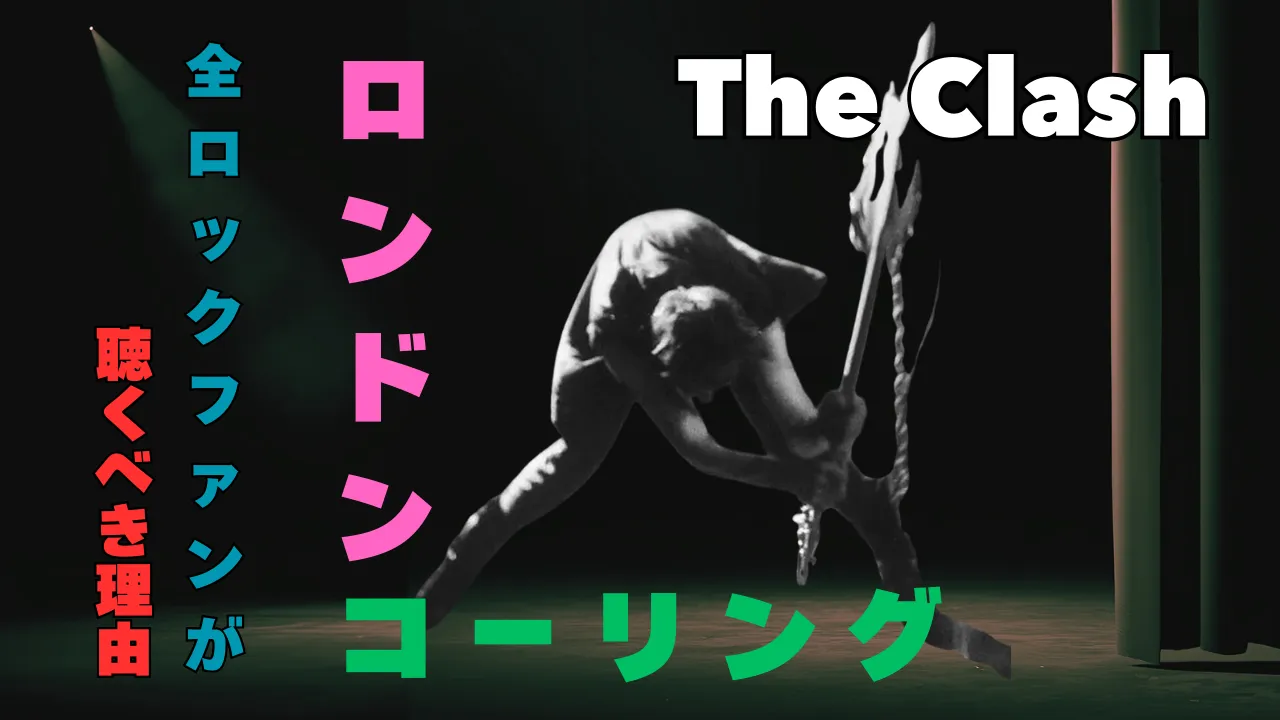
同じポストパンク勢でいうと、Public Image Ltd.やThe Pop Groupの初期作品と近い空気をまとっていて、セックス・ピストルズ的なストレートなパンクから、「じゃあこの先どうする?」と考え始めた世代の代表格というイメージです。

ただ、Gang of Fourはアートスクール的な理屈っぽさと、ダンスミュージック的なグルーヴを強烈に結びつけた、かなり特殊な立ち位置にいます。
『Entertainment!』が面白いのは、単なる「パンクの続き」ではなく、ファンクやダブのリズム感を強く取り入れているところ。
ギターはカラッカラのノイズ寄り、ベースとドラムは完全にダンスグルーヴ志向という、かなり変わったバランスで成立しているアルバムなんですよね。
ギターが「メロディ」ではなく「リズムとノイズのパーツ」として扱われている感じが、当時としてもかなりラディカルでした。
社会背景をざっくり言うと、イギリスでは失業率の上昇や労働争議が相次いでいて、労働市場の緊張感が日常レベルで可視化されていた時期です。
今でもイギリスの雇用・失業に関する統計は国家統計局(ONS)が継続的に公表していて、当時から現在までの推移を追うと、「音楽が生まれた空気」がより立体的に見えてきます(出典:Office for National Statistics「Employment and labour market」)。
リリース当時のUKチャート的にはそこまで派手なヒットではないものの、後のオルタナ/インディ界隈への影響はとんでもなく大きくて、Nirvana、R.E.M.、Red Hot Chili Peppersあたりがこぞって名前を挙げているのも有名な話です。
さらに、2000年代以降のFranz FerdinandやBloc Partyなど、ポストパンク・リバイバル勢のギター・リフやリズム構造にも、明らかに『Entertainment!』由来のDNAが見えます。
結果的に、『Entertainment!』は「ポストパンクを象徴する1枚」として、多くのメディアで必ず名前が出てくる存在になりました。
老舗音楽誌のオールタイム・ベスト企画にもたびたび登場しますし、「ポストパンク入門10選」みたいな記事では、もはや定番中の定番。
そういう意味で、このアルバムを押さえておくことは、ジャンル全体を理解するうえでの大きなショートカットにもなると思います。
ポストパンク全体の流れをざっくりつかみたいなら、Public Image Ltd.を掘るのもかなりおすすめです。
同じジェネレーションB内のPublic Image Ltd徹底解説ガイドも、合わせて読むと時代の空気がつながって見えてくるはずです。
Gang of FourとPILを行き来しながら聴くと、「パンクの後にロックはどこへ向かったのか?」という大きな流れがかなりくっきり見えてきますよ。
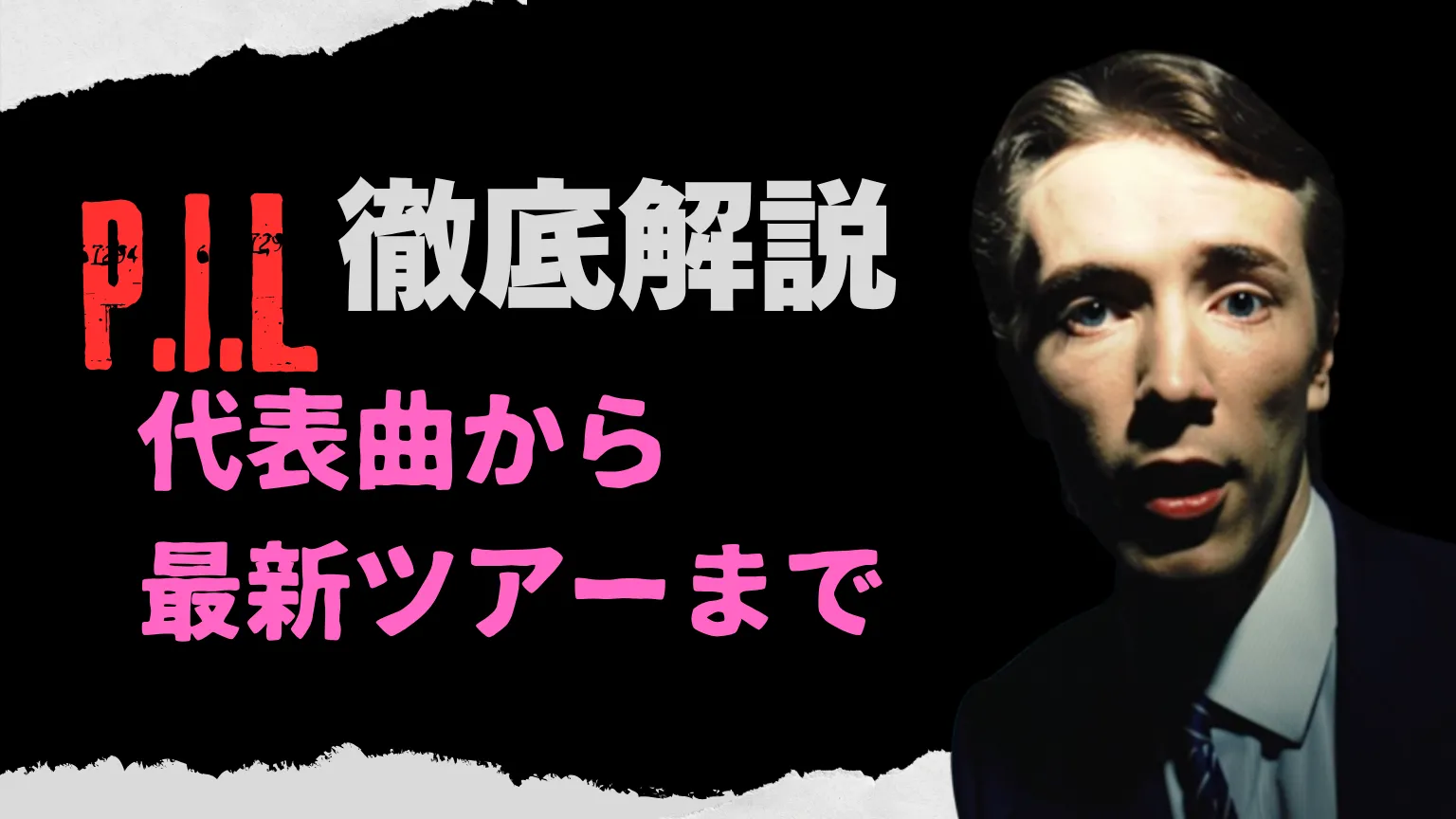
1-2. Tracklistと代表曲解説
『Entertainment!』のTracklistは全12曲。
テンション感は一貫しているのに、一曲ごとにテーマや角度がかなり違うのがこのアルバムの妙なところです。
「全部同じようにカラカラしてるのに、なぜか飽きない」という不思議なバランスで成り立っています。
ここでは、まず全体像をざっくり見つつ、その中でもキーになってくる曲をピックアップして解説していきます。
| トラック | タイトル | ざっくりテーマ |
|---|---|---|
| 1 | Ether | 北アイルランド紛争、国家暴力 |
| 2 | Natural’s Not in It | レジャーと消費、身体の商品化 |
| 3 | Not Great Men | 英雄史観批判、歴史の構造 |
| 4 | Damaged Goods | 恋愛と商品の交換価値 |
| 5 | Return the Gift | 消費社会と空虚な報酬 |
| 6 | Guns Before Butter | 軍事優先とメディアの物語 |
| 7 | I Found That Essence Rare | 広告と核時代の不安 |
| 8 | Glass | 脆さと透明性、不安 |
| 9 | Contract | 結婚制度と経済 |
| 10 | At Home He’s a Tourist | 家庭内疎外、検閲 |
| 11 | 5.45 | テレビニュースと暴力の消費 |
| 12 | Love Like Anthrax | ラブソング批判、恋愛の病理 |
ざっくりテーマを頭に入れてから聴くと、「この曲、こんなこと歌ってたのか」と気づきが増えるはずです。
序盤で世界観を叩き込む3曲
アルバム冒頭の「Ether」は、北アイルランド紛争や拷問の問題を、不穏なギターとリズムで描く1曲。
いきなりニュース映像みたいな世界に放り込まれる感じで、「このバンド、ただのロックじゃないぞ」という空気を一発で伝えてきます。
歌詞に出てくる「Long Kesh」や「Rockall」といった固有名詞は、当時の英国政治をめぐる具体的な地名・施設名で、そこまで追いかけると一気にドキュメンタリー性が増してきます。
続く「Natural’s Not in It」は、レジャーと消費社会をテーマにした名曲。
ハイハットが刻むディスコ的なノリと、鋭いカッティングギターがぶつかり合う感じが最高で、のちにCMや映画にも使われまくることになります。
アップテンポでキャッチーなので、「とりあえず1曲聴いてみたい」という人にも推しやすい入り口ですね。
「Not Great Men」では、いわゆる「偉人が歴史を作る」という考え方をひっくり返す歌詞が乗ってきて、ここで一気にバンドの思想的な芯も見えてくる、という流れです。
サウンド的にはダンサブルなのに、歌っている内容はかなりシニカル。この「ノレるのにスッキリさせてくれない」感じが、アルバム全体のトーンを象徴しています。
アルバムの象徴「Damaged Goods」
『Entertainment!』の中で一番有名な曲を1つ挙げるなら、やっぱり「Damaged Goods」でしょう。
恋愛の終わりを「返品処理」になぞらえる歌詞と、ファンク寄りのベースライン、カミソリみたいなギターが完璧に噛み合っています。
イントロのリフが鳴った瞬間、「あ、これだ」と分かるタイプのキラーチューンです。
「傷物になったから返す」「お釣り(change)が君のためになる」という比喩は、初めて聞くとちょっと冷たすぎて笑ってしまうんですが、何度も聴いていると、そこにある違和感や残酷さこそがこのバンドの本質だな、と感じるようになるはずです。
恋愛を「感情のやり取り」ではなく「取引」として描くことで、人間関係の裏側にある経済的なロジックを浮かび上がらせているわけですね。
ライブ音源やカバーもかなり多くて、Red Hot Chili PeppersやIDLESなど、世代もジャンルも違うバンドが取り上げています。
オリジナルとカバーを聴き比べると、『Entertainment!』がどれだけ多くのアーティストにとっての土台になっているかが、耳で実感できると思いますよ。
後半で一気に深度を増す楽曲群
後半に入ると、「5.45」や「Love Like Anthrax」のような、より実験的で重たい曲が増えていきます。
テレビニュースを見ながらお茶をすする感覚を描いた「5.45」は、現代にも直結するメディア消費の問題を突いていますし、「Love Like Anthrax」では「愛」を炭疽菌になぞらえつつ、左右チャンネルで別々の声が同時に流れるという超変則的な構成を取っています。
たとえば、片方のチャンネルでは普通のラブソング的な歌詞が進行しているのに、もう片方では「ラブソングという形式そのもの」への批評が語られている。
ヘッドホンでじっくり聴くと、「この人たち、ここまでやるのか…」とちょっと笑ってしまうレベルの実験です。
Tracklist全体で見ると、「踊れるけど全然安心させてくれないアルバム」というのが『Entertainment!』の正体かなと思います。
リズムはノれるのに、歌詞とサウンドが常に足を引っ張ってくる感じですね。
この「違和感をあえて残しておく」美学がハマると、抜け出せなくなります。
1-3. Lyricsと意味を読む
Gang of Fourの魅力は、サウンドだけじゃなくLyricsの鋭さにあります。『Entertainment!』の歌詞は、恋愛、レジャー、家族、労働、戦争といった身近なテーマを通して、資本主義社会の構造やメディアの欺瞞をえぐり出しているんですよね。
いかにも「政治的ロックです!」と叫ぶのではなく、日常会話レベルの言葉でサラッと批評を差し込んでくるスタイルが、本当にいやらしくて最高です。
レジャーと消費の関係
「Natural’s Not in It」の「The problem of leisure, what to do for pleasure?」というフレーズは、表面的には「暇なとき何して遊ぶ?」という軽い問いかけに見えます。
でも、その裏には「そもそもレジャーって誰がどう設計してるの?」「本当に自分の選択?」という疑問が潜んでいます。
休日の過ごし方、買い物、旅行、エンタメ…いわゆる「楽しみ」がパッケージとして売られている現代に、そのまま突き刺さるテーマですよね。
自分がやっていることが、自発的な選択なのか、広告や社会のムードに乗せられているのか。
そういうモヤモヤを、踊れるトラックに乗せて投げつけてくるのが、この曲の怖いところです。
「身体はビジネスだ」というラインは、欲望やセクシュアリティが市場に組み込まれている現実を、これ以上なくストレートに言い切っていると言っていいでしょう。
今のSNS文化やフィットネスブーム、インフルエンサー経済なんかを思い浮かべながら聴くと、「1979年のアルバムが、普通に2020年代の話をしているな…」とゾッとするかもしれません。
恋愛=取引という視点
「Damaged Goods」では、恋愛やセックスが、商品の売買や返品にたとえられています。
「君は傷物だから返品する」「お釣りが君のためになる」というフレーズは、一歩間違えばただの悪趣味ですが、そこに「市場のロジックが人間関係に浸食している」という冷静な観察が乗ることで、鋭い批評になっています。
あなた自身の経験を少し重ねてみると、「あ、これ分かるかも…」という瞬間が一つ二つ出てくるかもしれません。
恋人を選ぶときの条件、別れるときの言い訳、SNSでの「いいね」の数。
どこまでが感情で、どこからが損得勘定なのか。
その境界線がどんどん曖昧になっている現代に、この曲はかなりエグい鏡を突きつけてきます。
歌詞カードと対訳の楽しみ方
英語にそこまで自信がなくても、歌詞カードと対訳を手元に置いてじっくり向き合うだけで、このアルバムの見え方はガラッと変わります。
大事なのは、単語の意味を機械的に追うことよりも、「この一行はどんな場面を切り取っているのか?」という状況ごとイメージしながら読むことです。
流れとしては、最初に日本語対訳だけをざっと読んで世界観をざっくりつかむ、そのうえで英語の歌詞を実際の音源と一緒に追いかけてみる、最後に引っかかったフレーズだけ辞書やネットで掘り下げる、という順番にするとかなりスムーズに入ってきます。
いきなり一語一句を完璧に理解しようとするより、「空気ごと受け取ってから細部を詰める」くらいの感覚の方が、ストレスが少なくて続けやすいんですよね。
あとは、SpotifyやCDで何度かアルバムを通し聴きしてから、気になった曲のLyricsを集中的に読む→もう一度Full Albumで聴き直す、という往復もかなり効きます。
歌詞カードと音源を行ったり来たりしているうちに、「この一行、やっぱり刺さるな…」というフレーズが何本も見つかってきて、自然と沼にハマっていくはずです。
1-4. 海外Reviewと批評家評価
『Entertainment!』は、発売当初から「ラジカルなポップミュージック」として高く評価されてきましたが、面白いのは時代が進むごとに評価がじわじわ上がっていったタイプのアルバムだということです。
「当時の名盤」というより、「今もアップデートされ続けている古典」に近い扱いを受けています。
いわゆる老舗音楽誌のオールタイム・ベスト企画では、たいてい「歴代アルバム500選」といったランキングに名前が入っていますし、ポストパンク特集や「70年代後半の名盤」企画でも、かなり高い位置に置かれることが多いです。
再発やリマスターのタイミングで大手サイトが大きなReviewを出すことも多く、「聴くべき理由」が何度も書き換えられている珍しい作品でもあります。
海外のReviewをざっと読むと、よく出てくるキーワードはこんな感じです。
- Angular(角張った)ギターサウンド
- FunkとPunkのハイブリッドなグルーヴ
- マルクス主義的な視点を持ったLyrics
- ダンスフロアでも機能する政治的ロック
- 「楽しさ」と「不安」が同居するサウンドデザイン
特に面白いのは、「聴きやすいとは言えないのに、何度も聴きたくなる」「40年以上前のアルバムなのに、今のニュースにそのまま接続できる」という声が多いところ。
これは、サウンドの新しさだけじゃなくて、歌詞が扱っているテーマが、いまも全然古くなっていないからだと思います。
また、ミュージシャンからの評価もかなり熱くて、さっき名前を出したNirvanaやR.E.M.、Red Hot Chili Peppersはもちろん、最近だとIDLESやSavages、Fontaines D.C.あたりも、インタビューの中で『Entertainment!』の影響を語ることがあります。
そういう発言を追いかけていくと、「このバンドのこの曲は、『Entertainment!』のこの要素を引き継いでいるな」といった楽しみ方もできるようになりますよ。
海外ブログやレビューサイトでは、しっかりした長文レビューも多いので、英語に抵抗がなければチェックしてみると、新しい聴き方のヒントがたくさん見つかります。
特に、音響面(ギターの音作り、ベースとドラムの関係性)にフォーカスしたレビューは、日本語圏にはまだ少ないので、英語圏のテキストがかなり参考になります。
1-5. Full AlbumとSpotify視聴
今、『Entertainment!』を聴く一番手軽な方法は、やっぱりSpotifyなどのストリーミングサービスでFull Albumを再生することかなと思います。
公式アルバムとして配信されているので、検索バーに「Gang of Four Entertainment」あたりを入れればすぐ出てきます。
サブスクに加入しているなら、まずはこれでOKです。
配信の場合のメリットは、なんと言っても「再生環境を選ばない」「すぐに他のアルバムに飛べる」こと。
『Entertainment!』を聴き終わったら、そのまま2ndアルバムやライブ盤、さらには関連アーティストのプレイリストにどんどん飛んでいけるので、沼に落ちるスピードが爆速です。笑
他にも、YouTubeにはFull Album形式のプレイリストや、ライブ映像、個別曲の公式アップロードなどがいろいろ転がっています。
まずはSpotifyで通しで聴きつつ、「この曲もっと聴きたいな」というものがあればYouTubeでライブVer.を探してみる、という使い方も楽しいですね。
特に「At Home He’s a Tourist」や「Damaged Goods」は、ライブ映像で観るとバンドの緊張感が倍増します。
配信状況や収録曲、クレジット表記などは、サービスごと・時期ごとに変わる可能性があります。
ここで触れている内容はあくまで一般的な目安なので、正確な情報は各ストリーミングサービスの公式ページで必ず確認してください。
音質や契約内容、利用料金などに不安がある場合は、オーディオショップや配信サービスのサポート、もしくは音楽配信に詳しい専門家に相談してから最終的な判断をするのがおすすめです。
ストリーミングで気に入ったら、後で紹介するVinylやCDにステップアップするのも良い流れです。
いきなり高価な盤に手を出すより、まずは配信で「これは長く付き合えそうだ」と感じてからフィジカルで投資する方が、財布にも優しいかなと思います。
通勤中や作業中に何度か流して、「あ、これは人生のBGMにしてもいいな」と思えたら、フィジカル購入のタイミングですね。
2. Gang of Four 『Entertainment!』再考
ここからは、もう一歩踏み込んでGang of Four 『Entertainment!』を「再考」していきます。
Wiki的な基本情報から押さえるバンド史、Lyricsに込められた政治性、VinylやCDとDiscogsでの情報収集、再発盤やRemasterの選び方、そして最終的な総括まで、よりコアな視点で楽しみたいあなた向けのパートです。
ここまで読んで「もう少し深く行ってみたいな」と思ったら、そのまま一緒に潜っていきましょう。
2-1. Wikiで押さえるバンド史

まずは、ざっくりGang of Fourというバンドの歴史を整理しておきましょう。
メンバーは、ジョン・キング(Vo)、アンディ・ギル(Gt)、デイヴ・アレン(Ba)、ヒューゴ・バーナム(Dr)の4人。
美術大学や文芸畑出身のメンバーが多くて、「ロックバンドだけど、バックグラウンドは完全にアカデミック寄り」という珍しいタイプです。
いわゆる美大バンド的なセンスと、パンクの衝動ががっつり噛み合っているイメージですね。
彼らの出発点は、70年代後半のイギリス・リーズ。
ロンドンほど華やかでもなく、地方都市ならではの閉塞感と、工業都市としての荒々しさが同居している街です。
失業率の高さや労働争議、極右勢力の台頭など、政治的にも社会的にもかなりピリついた空気の中で、パンク以降の表現を模索していた若者たちの一群から生まれてきた存在です。
バンド名の「Gang of Four」は、中国の四人組(文化大革命期の政治グループ)から取られていますが、これは単純なイデオロギーの表明というより、「権力闘争」や「陰謀」を想起させる響きを意識したネーミングだと私は感じています。
実際のインタビューでも、彼らは特定のイデオロギーに忠誠を誓うというより、「どう権力が働いているか」を観察し続けるスタンスを強調しています。
Wikiのバンドページでは、結成からメンバーチェンジ、レーベル移籍、解散と再結成、メンバーの死去に至るまでの大まかな流れがまとまっているので、「まず履歴だけざっと追いたい」というときには便利です。
特に、アンディ・ギルの逝去後に行われたトリビュート・プロジェクトについても触れられていることが多く、『Entertainment!』以降の話を知るうえでも役立ちます。
Wikiのバンドページは、メンバーの出入りやディスコグラフィを一覧で確認するのに便利です。
ただし、編集状況によって情報が変わることもあるので、気になる部分があれば公式アナウンスやインタビュー記事など、複数ソースを照らし合わせるのが安全です。
特にリリース年やメンバー構成などは、盤によってクレジットが微妙に違うこともあるので、レコード/CDの現物と照合するのがいちばん確実ですよ。
検索結果に出てくる「Gang of Four Entertainment LLC」のような法人名は、主に権利管理やビジネス面の実体を指すことが多くて、バンド史そのものというより、「作品の裏側にある会社の話」と考えると整理しやすいかなと思います。
著作権やライセンスの管理のために、バンド名に近い名称の会社が作られることはよくあるので、「これは別の企業?」と混乱しなくて大丈夫です。
2-2. Lyricsから読む政治性
『Entertainment!』が今でも語り継がれている理由のひとつが、Lyricsに込められた政治性の描き方です。
ただし、ここでいう政治性は「特定の政党やスローガンを応援する」という意味ではなく、もっと日常レベルのミクロな政治を描くという意味に近いです。
ニュースの中の「大文字の政治」よりも、日々の生活の中で感じるモヤモヤや違和感にフォーカスしているんですよね。
ニュースの向こう側にある感情
「Ether」や「5.45」のような曲では、ニュース映像やラジオ報道がそのまま歌詞に入り込んできますが、重要なのは「それを見ている/聞いている人」の感情まで含めて描いているところ。
戦争や拷問、暴力のニュースが流れていても、家では普通に夕食をとっている──このギャップにこそ政治がある、という視点を突きつけてきます。
「5.45」の「どうやってお茶を飲んでいられるんだ?」という問いは、現代にもまったく通じますよね。
SNSで流れてくる悲惨なニュースをスクロールで流しながら、同じ画面で猫動画を見て笑っている私たち。
その感覚を40年以上前にすでに歌っている、という事実がまずすごいです。
家庭・恋愛・レジャーの中の権力
「Damaged Goods」や「Contract」、「Natural’s Not in It」といった曲では、恋人同士や夫婦関係、休日の過ごし方といった、一見「私的」な領域の話をしているようでいて、実はその中に埋め込まれた経済構造や権力関係を描いています。
家族の役割分担、家計の管理、消費行動…そういうところにこそ、イデオロギーが入り込んでいるという感覚です。
「家族」「恋愛」「レジャー」が、いつのまにか市場や広告のロジックに乗っ取られていないか? という問いが、アルバム全体を通して静かに流れている感じですね。
歌詞の中にさりげなく出てくる「広告コピーっぽい言い回し」にも注目してみると、よりはっきり見えてきます。
他のポストパンクとの比較で見えるもの
同時期のポストパンクバンドであるThe Pop GroupやPublic Image Ltd.と比べると、Gang of Fourはスローガンを叫ぶというより、「ツッコミの鋭い社会学者」みたいなスタンスで歌詞を書いている印象があります。
叫ぶのではなく、皮肉や比喩でじわっと効かせてくるタイプです。
たとえばThe Pop Groupは、もっと情緒的でカオス寄りの表現が多く、Public Image Ltd.は内面の分裂やアイデンティティの揺れを前面に出すことが多いですが、Gang of Fourは「社会構造を冷静に分析しているけど、ちゃんと踊れる曲にしてくる」あたりが独特です。
この違いを意識しながら聴き比べると、それぞれのバンドの個性が一気に立体的に見えてきますよ。
ポストパンク全体の中での位置づけを知りたいなら、The Pop Groupを取り上げたThe Pop Group完全ガイドも合わせて読むと、各バンドの「政治性」の違いがかなりクリアに見えてくるはずです。
「どこまでが怒りで、どこからが分析なのか」という線引きが、それぞれ全然違います。

2-3. アートワークの謎:「カウボーイとインディアン」の意味とは
アルバム『Entertainment!』を語るうえで、ジャケットに描かれた「カウボーイとインディアン」の握手シーンは外せないポイントです。
一見すると、西部劇によくある「和解」とか「友情」の瞬間を切り取ったポップなビジュアルに見えますよね。
でも、このアートワークはただのレトロな映画スチルではなく、かなり緻密に仕掛けられた政治的ジョークになっています。
まず、この画像の元ネタは、ドイツの作家カール・マイ原作の西ドイツ映画『Winnetou(ヴィネトゥ)』シリーズのスチール写真だと言われています。
ヴィネトゥは、西部劇でありながら「高潔なインディアン」と「理解ある白人」の友情を描いた作品として、東側の社会主義圏でも人気を集めた、ちょっと特殊なコンテンツなんですよね。
資本主義国・西ドイツの映画なのに、東ドイツでは「搾取や植民地主義を批判する読み替え」が行われていた、という二重の文脈を持っています。
Gang of Fourは、この微妙なポジションの西部劇イメージをそのまま使うのではなく、そこにテキストを重ねることで意味をひっくり返しています。
周囲に配置された文章はだいたいこんな内容です。
「インディアンは微笑んでいる。彼はカウボーイが友達だと思っている。カウボーイも微笑んでいる。インディアンが騙されていることを喜んでいる。これで彼を搾取できる。」──つまり、握手という「友好のジェスチャー」が、実は一方的な搾取の入り口でしかない、ということを露骨に暴いているわけです。
このやり方は、状況主義(シチュアシオニズム)がよく使った「転用(détournement)」という手法そのものです。
本来は別の意味や用途を持っていたイメージに、テキストや配置を足すことで、資本主義やメディアの嘘を暴くメッセージへと再利用してしまう。
Gang of Fourは、ポスターやアートブックではなく、ロックのアルバムジャケットというフォーマットでこれを実践しているんですよね。
面白いのは、この一枚のカバーが、アルバム全体のテーマをそのまま象徴しているところです。
「Damaged Goods」で描かれる「恋愛関係=取引」や、「Natural’s Not in It」の「レジャー=商品」、「Contract」の「結婚=契約」といったモチーフは、どれも「友好的な装いの裏側で進む搾取」という構図でまとめることができます。
握手を交わすカウボーイとインディアンは、恋人、夫婦、企業と消費者、国家と市民…いろんな関係のメタファーとして読み替えられるわけです。
つまり、あのカバーは「西部劇っぽくてカッコいいから使った」わけではまったくなくて、
1) 東西冷戦下で二重の意味を持った映画イメージを引用し、
2) 転用(détournement)的なテキストで植民地主義と搾取をあぶり出し、
3) アルバム全体のテーマを視覚的に一枚に圧縮した、コンセプチュアルな装置
として機能している、という感じです。
ジャケットをもう一度じっくり眺めてみると、顔のないインディアンとカウボーイは決して「完全なハッピーエンド」という感じではなく、どこかぎこちなく、フレームの外側に不穏な空気が漂っているようにも見えてきます。
その違和感に気づいた瞬間、ただのレコードの表紙だったものが、社会批評のパネルに変わる。その感覚こそが、Gang of Fourが仕込んだ「アートワークの謎」なんだと思います。
2-4. VinylやCDとDiscogs情報

ここからは、フィジカル派のあなた向け。『Entertainment!』のVinylやCDを集めたい場合、Discogsはほぼ必須ツールと言っていいです。
オリジナル盤から各種Reissue、Remaster、国別のプレス違いまで、膨大な情報が並んでいます。
検索窓に「Gang Of Four – Entertainment!」と入れると、ズラッとリリース一覧が出てきて、「こんなに種類があるのか…」と軽くめまいがするかもしれません。
主なフォーマットのざっくり整理
- オリジナルUK盤LP(EMIレーベル/黄色いジャケットが目印)
- US盤LP(Warner Bros.)
- 後年のCD再発(ボーナストラック付き、解説ブックレット付きのものも)
- リマスター盤LP/CD(年ごとに音の傾向が微妙に違う)
- 限定カラーVinylやRecord Store Day限定盤などのスペシャル仕様
コレクター的な視点だと「どの国の初版か」「ジャケットの印刷や帯の有無」「マトリクス刻印」なども重要になってきますが、単純に音源を楽しむだけなら、自分の予算と機材環境に合わせて、そこまで神経質にならなくても大丈夫です。
「音の好み」と「所有する喜び」のバランスをどこに置くか、ですね。
中古市場の価格は、状態やタイミングによって大きく変動します。
ここで触れているのはあくまで一般的な傾向であり、具体的な価格や在庫状況はレコードショップや通販サイト、Discogsの最新情報を必ず確認してください。
高額なVinylを購入する場合は、信頼できるショップや専門業者に状態確認を相談してから決めると安心です。
ジャケットのスレや盤のソリなど、写真だけでは判断しづらいポイントも多いので、最終的な判断は慎重にいきましょう。
Discogsの活用ポイント
Discogsでは、特定のリリースページで「Have」「Want」の数や、平均的な取引価格の目安がチェックできます。
これを眺めるだけでも、「どの盤が人気なのか」「どのくらいレアなのか」がなんとなく見えてくるので、眺めているだけでも楽しいです。
「Want」がやたら多いのに出品が少ない盤は、大体レアで高額です。
また、自分のコレクションを管理する用途としても優秀なので、『Entertainment!』を皮切りに、他のパンク/ポストパンク盤も一緒に管理していくと、気づいたら沼にハマっている…かもしれません。
自分の棚をそのままデータベース化できる感覚は、一度体験するとやみつきになりますよ。
個人的なおすすめとしては、「最初の1枚」はあまり難しく考えず、状態の良い一般的な再発盤LPかCDから入ること。
そのうえで、「このアルバムは一生付き合う」と確信が持てたら、改めてオリジナル盤や別マスタリング盤を探す、という二段構えがいいかなと思います。
2-5. 再発盤やRemasterの聴き方
🎶オリジナル🎶
🎶2021リマスター🎶
『Entertainment!』は、リリースからの年月が長いこともあって、再発盤やRemasterがかなりのバリエーションで存在します。
ここがまた、初心者を迷わせるポイントなんですよね。「どれを買えばいいの?」問題は、ロックの名盤あるあるです。
音圧高めのModern Remasterか、オリジナル寄りか
ざっくりいうと、近年のRemasterは音圧が高くて「現代の耳」に合わせたバランスになっていることが多く、一方で古い盤やオリジナルに近いマスタリングは、ダイナミクスが広くて余白の多い鳴り方をします。
特に『Entertainment!』の場合、ドライでスカスカに聞こえるくらいのバランスがむしろ「正解」だったりするので、Modern Remasterだと少し詰まって感じることもあります。
Gang of Fourに関しては、あのカラッとしたドライな質感が魅力のひとつなので、個人的には「やや余白多め」のマスタリングの方が好きですが、これは完全に好みの話です。
環境によっても印象が変わるので、スマホ+ワイヤレスイヤホンか、アンプ+スピーカーかでも評価はかなり変わります。
聴き比べのコツ
もし複数の版を聴ける環境があるなら、「Damaged Goods」や「Natural’s Not in It」のような、リズムとギターのぶつかり合いが分かりやすい曲で聴き比べてみるのがおすすめです。
キックとベースの出方、ギターの角の立ち具合、ボーカルの前後感あたりに注目すると、違いが掴みやすくなります。
また、同じ音量に揃えたうえで聞き比べるのも大事なポイントです。
音圧が高い方が最初は「迫力があって良く聞こえる」ことが多いので、事前に音量を揃えてから比較した方が、公平に判断しやすいですよ。
マスタリングや音質の評価は、再生環境や好みに大きく左右されるので、「この版が絶対正解」というものはありません。
レビューやSNSの意見はあくまで参考にしつつ、最終的には自分の耳と予算に相談して決めるのがいちばんです。
高額なオリジナル盤だけが正義ではなく、「自分の部屋で一番気持ちよく鳴る盤」があなたにとっての正解です。
ジェネレーションBでは、他にもパンク/ポストパンクの名盤を多く取り上げています。
例えば、時代の橋渡し的な名作としてはBuzzcocksの代表曲と名盤解説もかなり相性が良いので、合わせてチェックしてみてください。
メロディ・センスの塊みたいなBuzzcocksと、鋭角なGang of Fourをセットで聴くと、「UKパンク〜ポストパンクの懐の深さ」がよく分かるはずです。
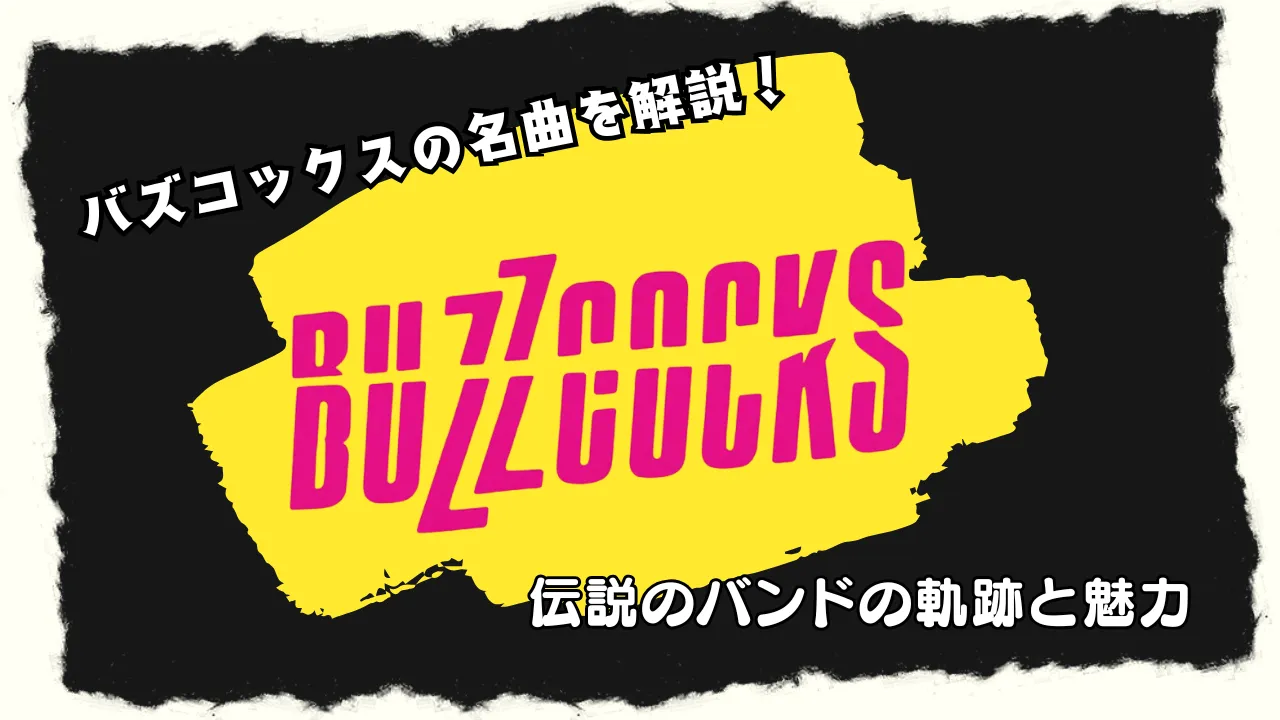
2-6. Gang of Four 『Entertainment!』総括
最後に、Gang of Four 『Entertainment!』をどう捉えるか、改めてまとめておきます。
『Entertainment!』は、「ポストパンクの名盤」という肩書きだけでは収まりきらないアルバムです。
パンクのエネルギー、ファンク/ディスコのグルーヴ、アートスクール出身ならではのコンセプチュアルな思考、そして日常の中の政治をえぐるLyrics。
それらがすべて混ざり合って、いまだに誰も完全には真似できていない独自のサウンドを形作っています。
検索でgang of four entertainmentと打ち込むと、アルバム『Entertainment!』の情報、Gang of Fourというバンドの歴史、DiscogsやSpotifyのデータ、さらにはGang of Four Entertainment LLCのようなビジネス実体まで、さまざまな断片が一気に表示されます。
この記事が、そのバラバラな情報をひとつの流れとしてつなげて、「まず何から聴けばいいか」「どこまで深掘りするか」を決めるガイドになっていたら嬉しいです。
もしまだFull Albumを通して聴いたことがないなら、ぜひ一度、時間をとって頭から最後まで通しで聴いてみてください。
最初は「なんだこのカラカラの音…」と思っても、数回聴くうちに、ギターの隙間、ベースのうねり、歌詞のフレーズが、じわじわと頭から離れなくなってくるはずです。
その瞬間に、このアルバムがただの「過去の名盤」ではなく、今と地続きの作品なんだと実感できると思います。
音源の入手方法や機材選び、価格などについては、ここで書いた内容はあくまで一般的な目安です。
正確な情報は各レーベルやショップ、ストリーミングサービスの公式サイトを確認しつつ、必要に応じてオーディオショップや販売店、オーディオの専門家などに相談しながら、最終的な判断をしてもらえればと思います。
大事なのは、「自分が無理なく楽しめる環境をつくること」なので、その軸だけは忘れずに選んでみてください。
あなたがGang of Four 『Entertainment!』をきっかけに、ポストパンクやその周辺のディープな世界に足を踏み入れてくれたら、音楽好きとしてこれ以上うれしいことはありません。
気になったら、ぜひコメントやSNSで感想を教えてください。
あなたがどの曲にハマったのか、すごく知りたいです。
💿 アナログ盤で味わう“生のGang of Four”

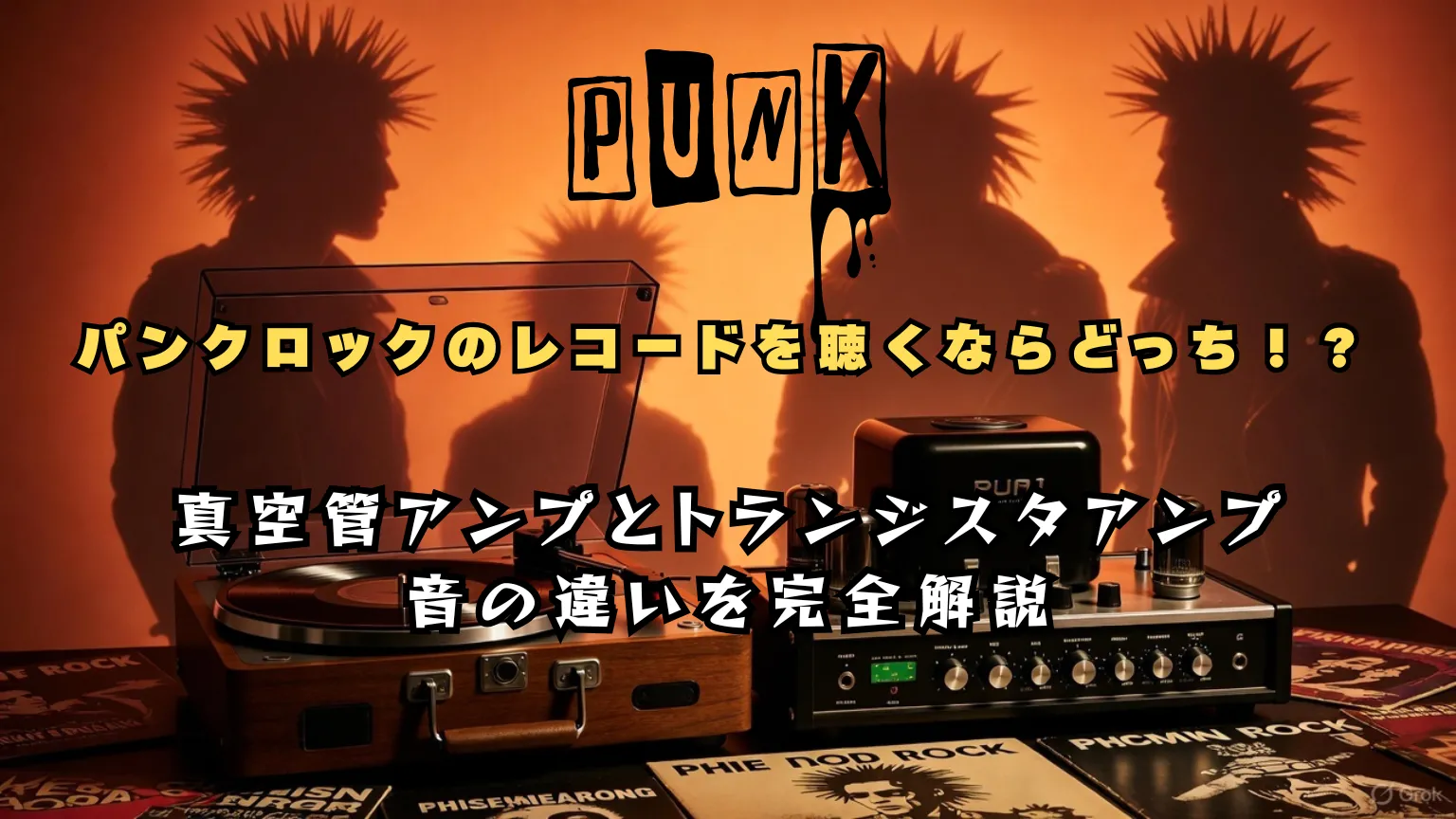

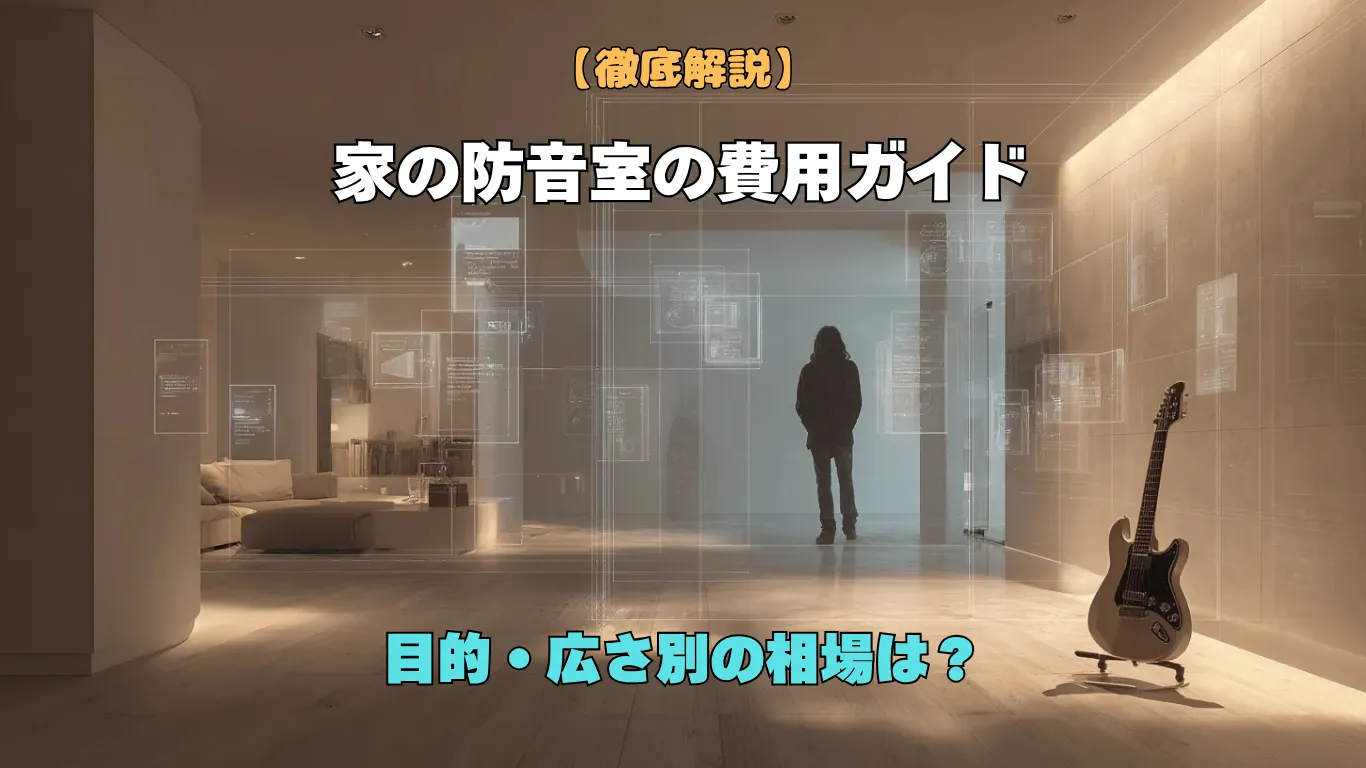
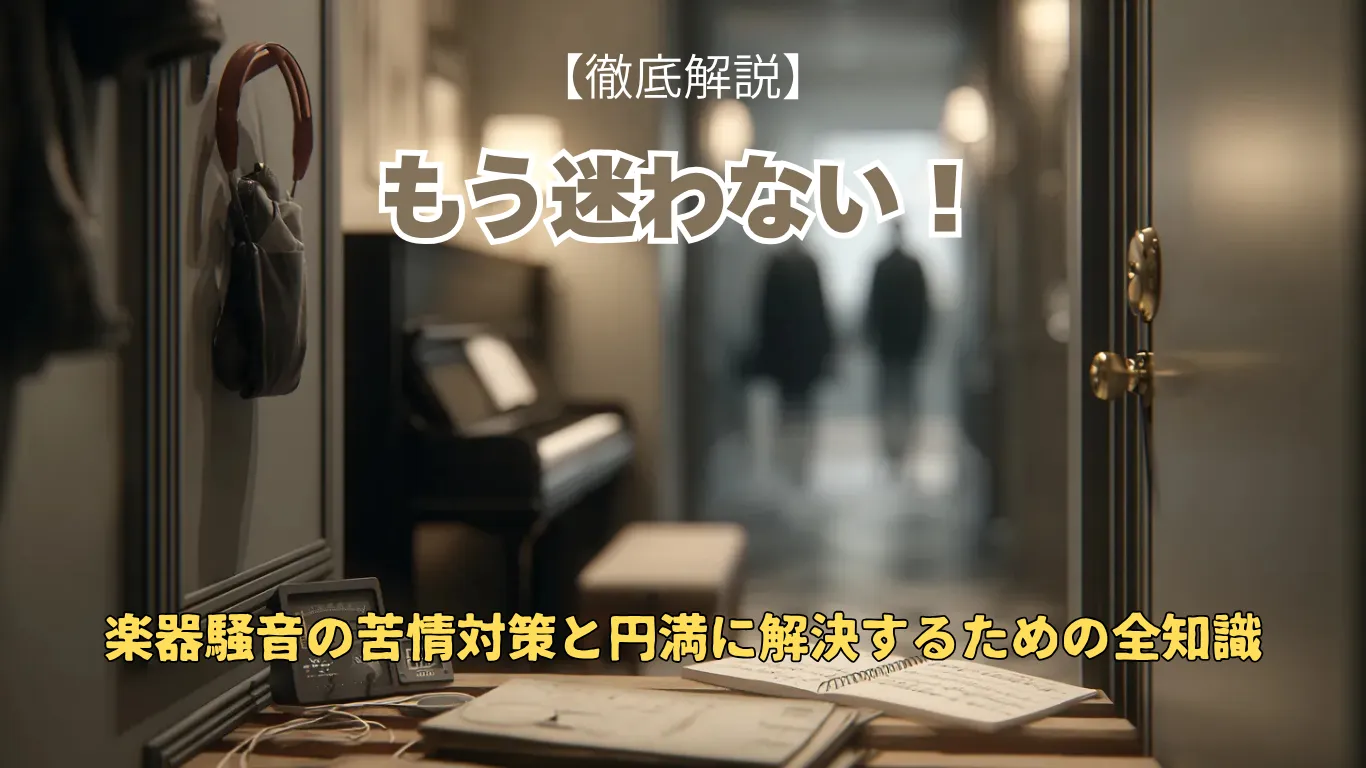
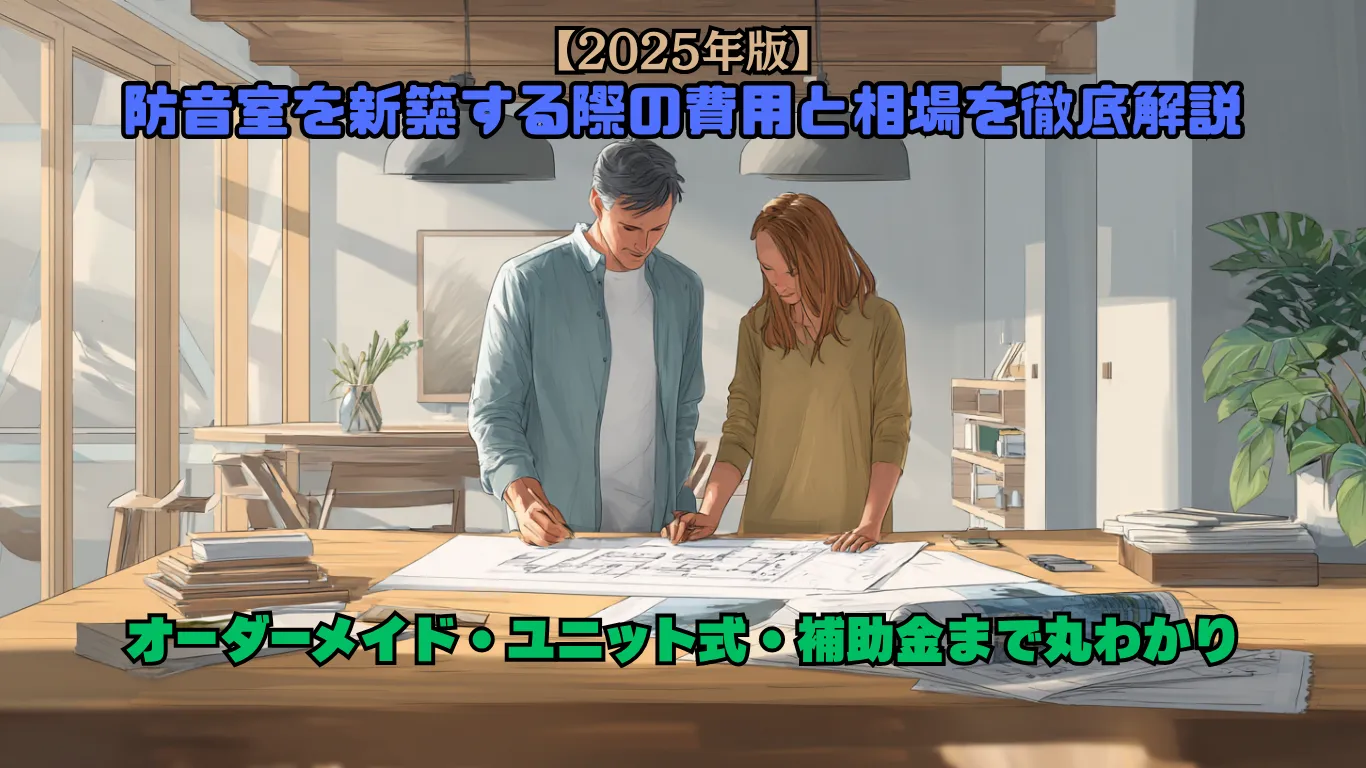



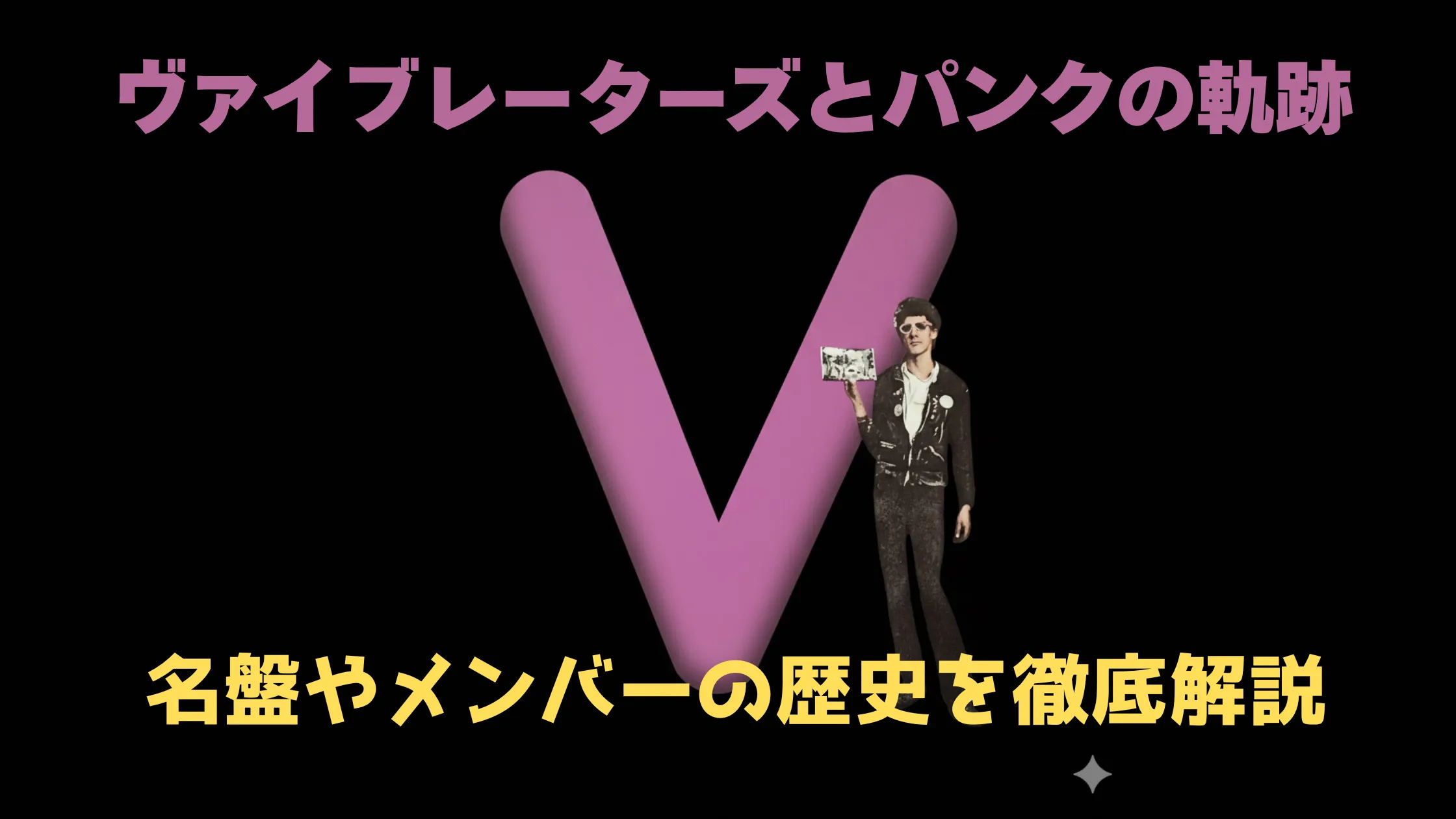
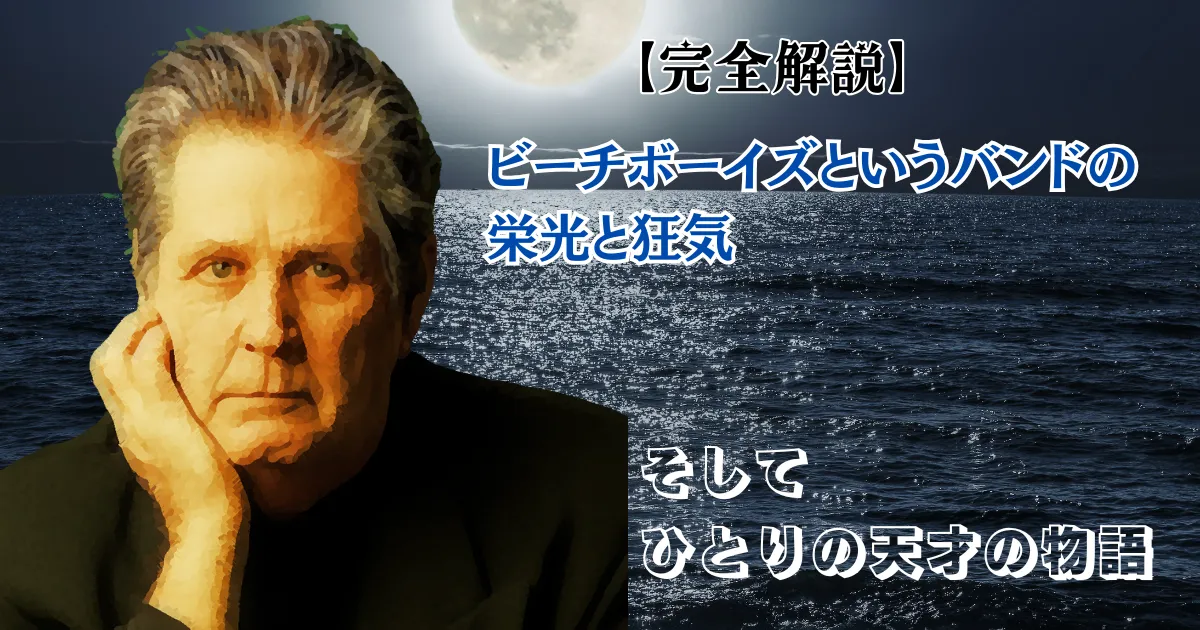
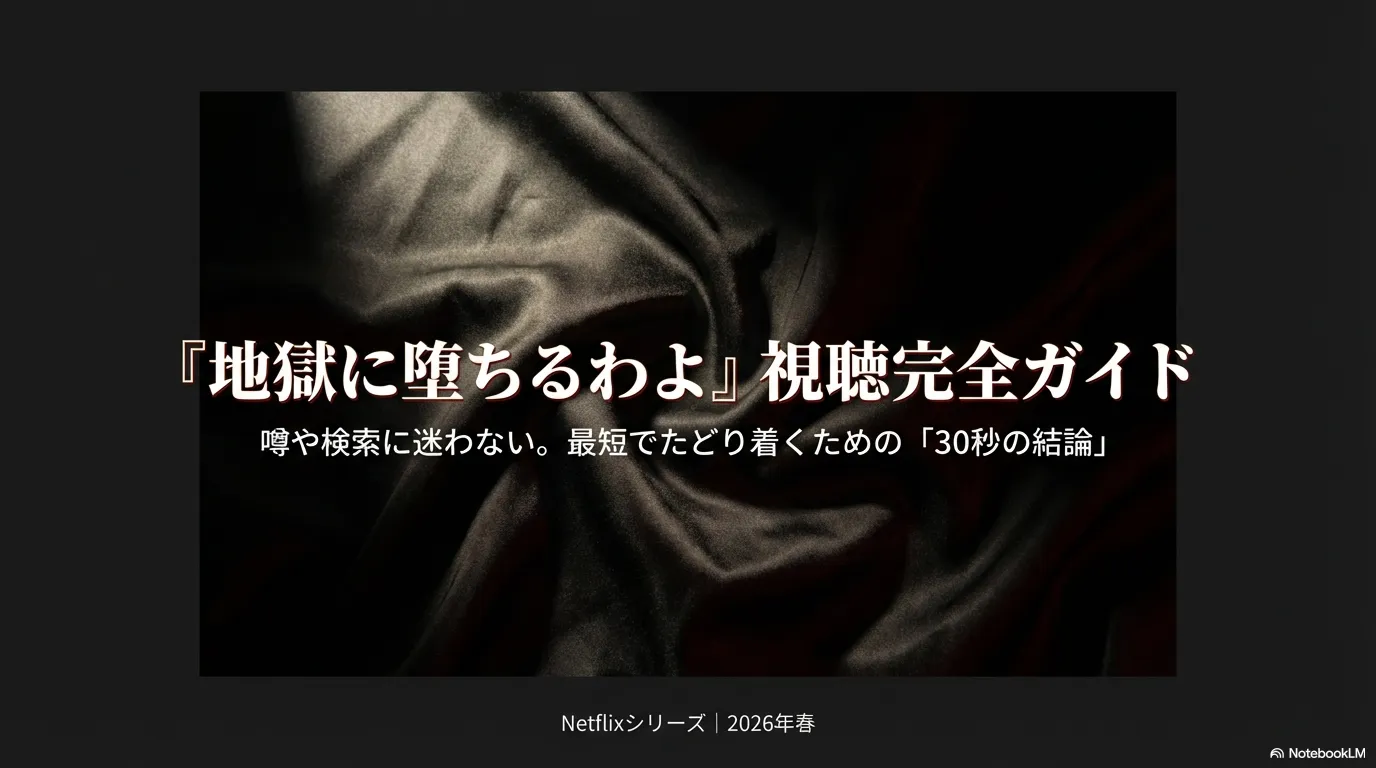

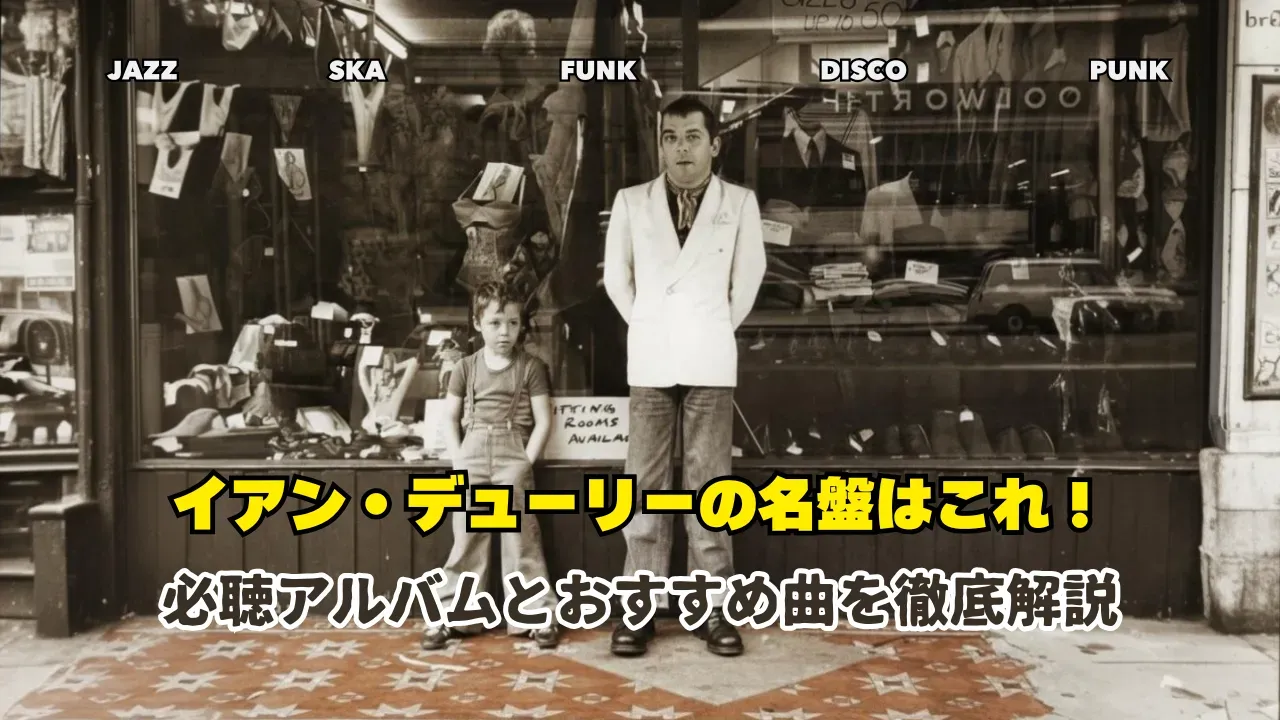
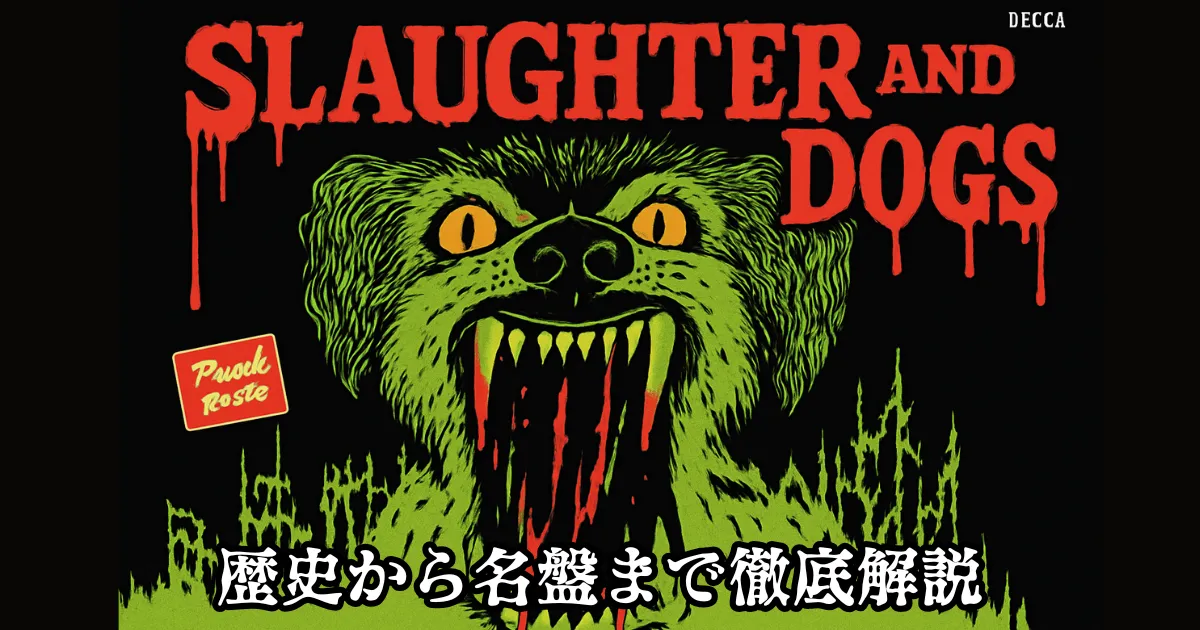
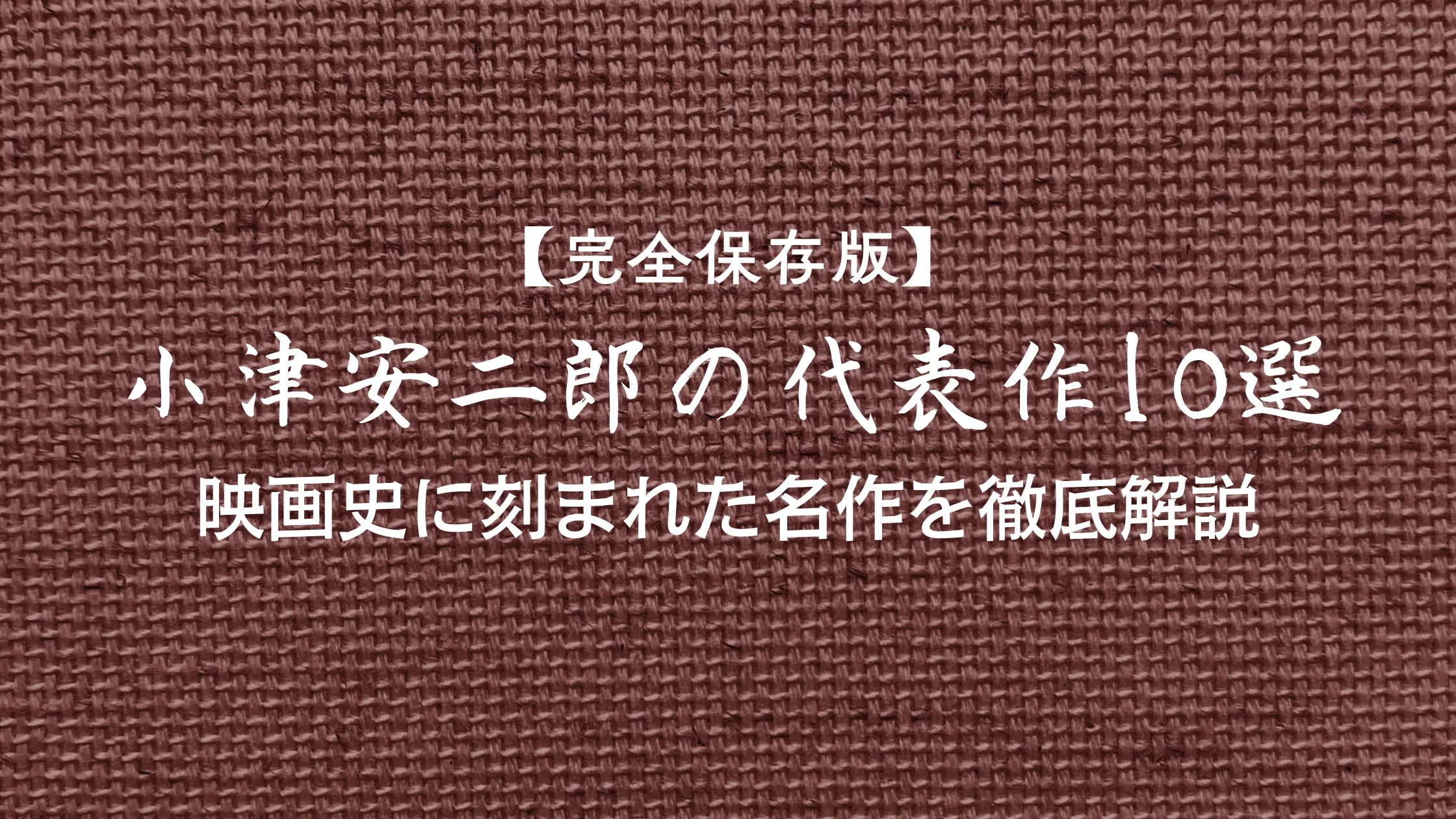
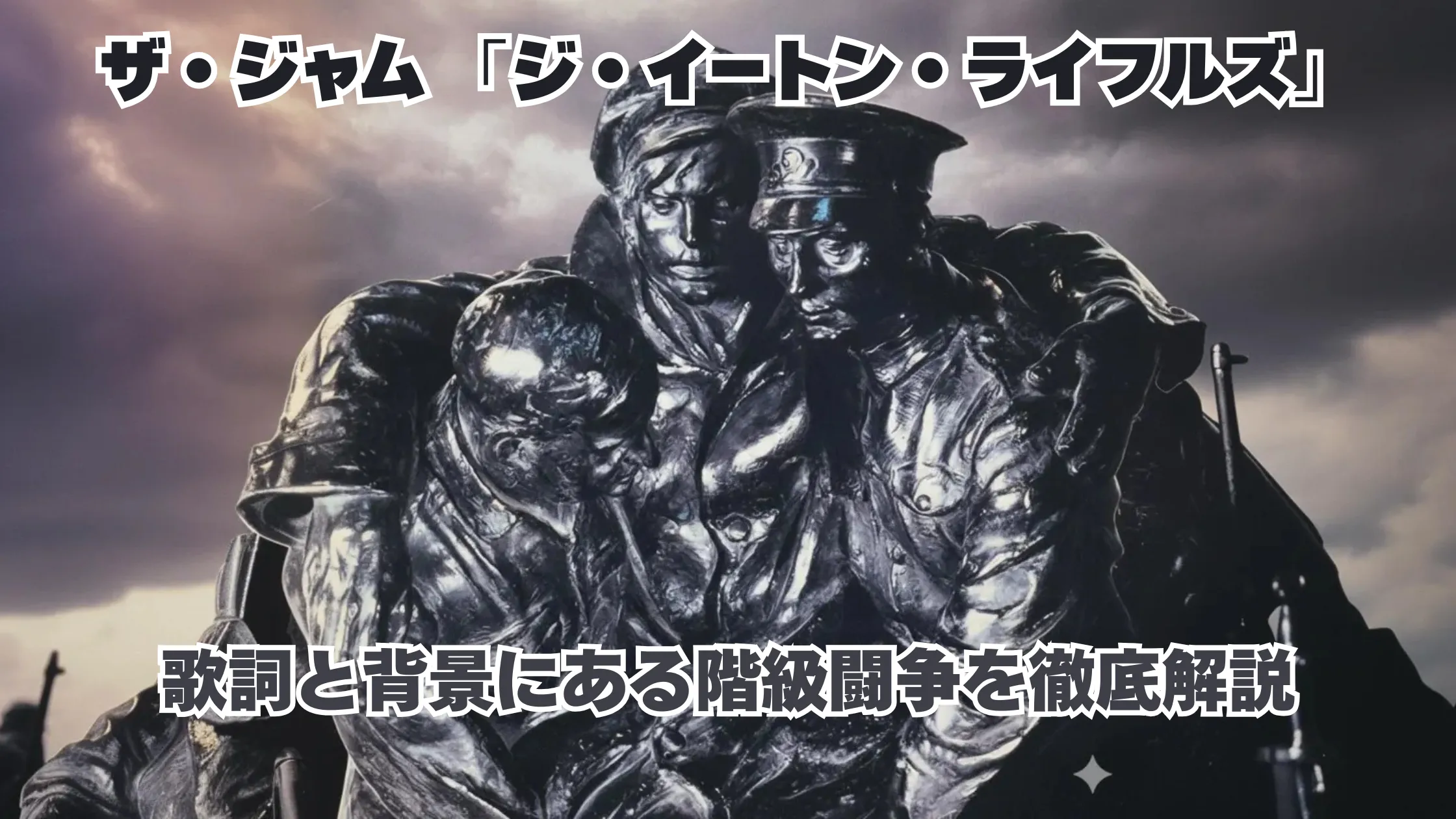





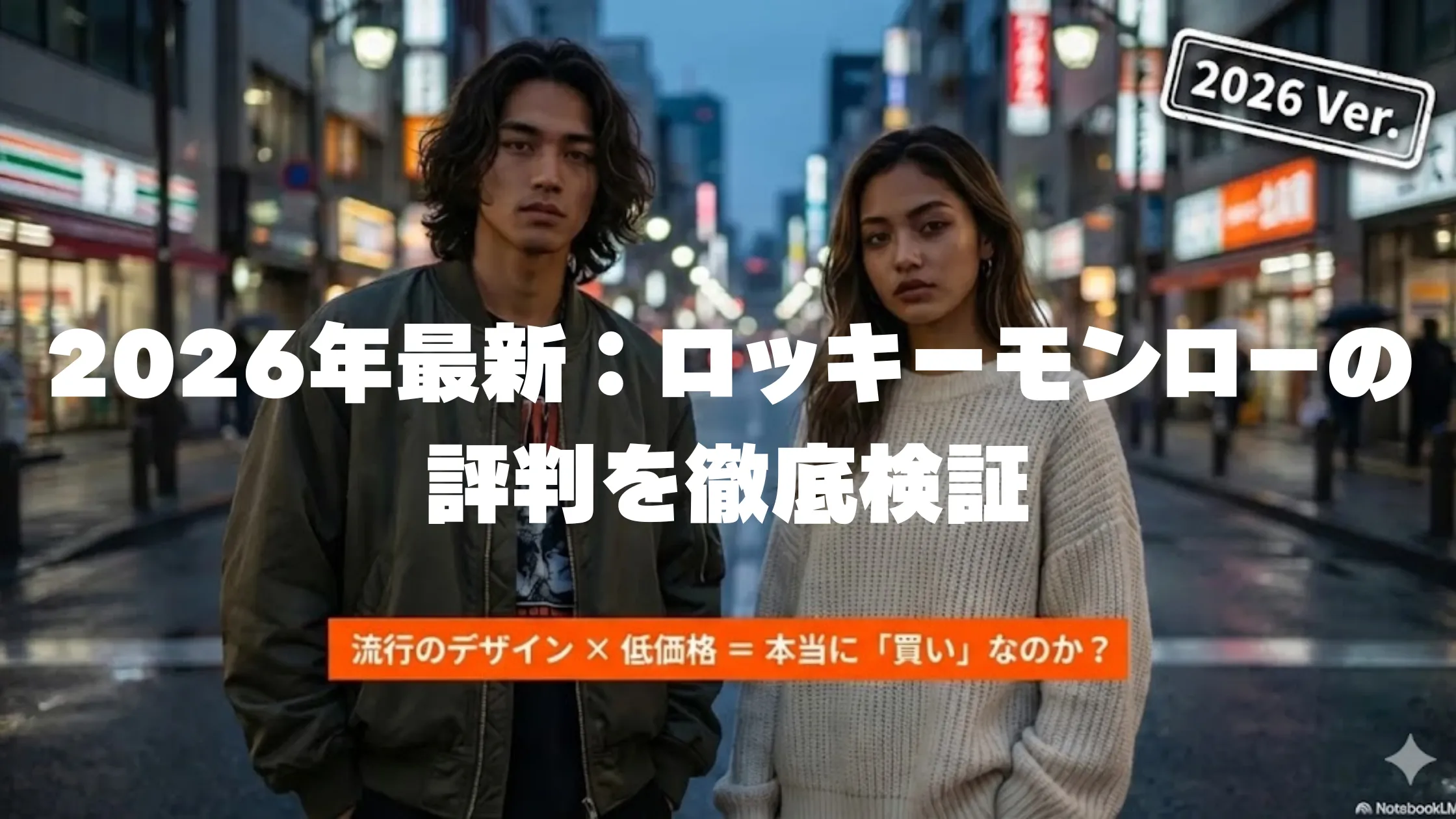
コメント