こんにちは。ジェネレーションB、運営者の「TAKU」です。
「ラモーンズ 不仲」というキーワードで検索をかけてこの記事に辿り着いたあなたは、きっとあの完璧なユニフォームと爆音の裏側に隠された、あまりにも人間臭いドラマの真相を知りたいのだと思います。
世界中のキッズを熱狂させた「ワン・ツー・スリー・フォー!」のカウント。
その背後で、メンバー同士が口もきかないほどの冷戦状態にあったなんて、にわかには信じがたい話ですよね。
映画『エンド・オブ・ザ・センチュリー』でも赤裸々に語られましたが、彼らの関係は単なる「性格の不一致」などという生易しい言葉では片付けられません。
政治思想の決定的な対立、ひとりの女性を巡る泥沼の三角関係、そして当時はまだ理解が浅かった強迫性障害という病の問題。
これらが22年間という長い活動期間の中で複雑に絡み合い、修復不可能な断絶を生んでしまったのです。
この記事では、いちファンとして、そしてバンドマンとしての視点も交えながら、ラモーンズの不仲がいかにして伝説となり、そしてなぜ彼らが最後まで解散せずにステージに立ち続けられたのか、その深層に迫っていきたいと思います。
この記事でわかること
- 22年間も口をきかなかったジョーイとジョニーの決定的な対立原因
- 名曲「The KKK Took My Baby Away」に隠された切ない三角関係の真実
- ツアー中のバンやガソリンスタンドで起きた衝撃的な不仲エピソード
- なぜ彼らは憎しみ合いながらも解散せず最高の音楽を生み出せたのか
1. ラモーンズが不仲に陥った根本的な原因
ラモーンズの不仲を語る上で避けて通れないのが、バンドの二大巨頭であるジョーイ・ラモーンとジョニー・ラモーンの関係性です。
結論から言ってしまうと、この二人の対立構造こそがラモーンズというバンドを前進させる「エンジン」であり、同時にメンバーを苦しめ続けた「呪い」でもありました。
ここでは、なぜ彼らの溝がこれほどまでに深まってしまったのか、その構造的な原因を徹底的に掘り下げていきます。
1-1. ジョニーとジョーイの絶望的な性格不一致
まず大前提として理解しておかなければならないのは、この二人は水と油……いや、それ以上に「混ぜると爆発する危険物」同士のような存在だったということです。
ギターのジョニー・ラモーン(本名ジョン・カミングス)は、厳格な父親に育てられ、軍学校に2年間在籍していた経歴を持っています。
彼の性格はまさに「軍隊の司令官」そのもの。
バンドをひとつのビジネスとして成功させることに異常なまでに執着し、遅刻や怠慢、予算の無駄遣いを一切許さない規律の鬼でした。
彼にとってバンド活動は「仕事」であり、メンバーは部下だったのです。
一方でボーカルのジョーイ・ラモーン(本名ジェフリー・ハイマン)は、内向的で繊細、そして独自のファンタジーワールドを持つ「夢想家のアーティスト」でした。
彼はヒッピー的な自由さを愛し、感情の赴くままに行動するタイプ。
ジョニーの管理的なやり方や高圧的な態度には、常に息苦しさと反発を感じていました。
結成当初から、この「支配する者(ジョニー)」と「支配される者(ジョーイ)」という非対称な力関係が、バンド内に張り詰めた空気を作り出していました。
ジョニーにとってジョーイのルーズな振る舞いは「甘え」や「プロ意識の欠如」にしか見えず、ジョーイにとってジョニーは自分の自由を奪う「冷酷な独裁者」に映っていたのでしょう。
お互いにリスペクトはあれど、友情が育つ土壌は最初から枯れ果てていたのです。
1-2. リンダ・ダニエルを巡る泥沼の三角関係
ラモーンズの歴史において、最も決定的かつ修復不可能な亀裂を生んでしまったのが、ファンの間でも語り草となっている「リンダ略奪事件」です。
リンダ・ダニエル(後のリンダ・ラモーン)は、もともとジョーイの恋人でした。
二人は約3年間にわたって交際しており、ジョーイにとっては心の支えとも言える存在でした。
しかし1980年代初頭、あろうことかバンドメイトであるジョニーが彼女と親密になり、最終的に彼女を奪い去ってしまったのです。
しかも、ただの浮気では終わらず、ジョニーとリンダはその後結婚し、ジョニーが亡くなるまで添い遂げることになります。
バンド内恋愛のタブーと裏切り
想像してみてください。毎日同じ狭いバンに乗り、同じ楽屋を使い、同じステージに立つメンバーに、最愛の恋人を奪われる状況を。ジョーイにとって、これがどれほどの地獄だったか。精神的な拷問と言っても過言ではありません。
リンダ側の証言によれば、ジョーイとの生活は彼の精神的な問題や衛生観念の欠如(後述するOCDの影響もあり)によって破綻しかけていたとも言われています。
彼女がジョニーの強さや頼り甲斐に惹かれた側面もあったのでしょう。
ジョニー自身も後に「恋に落ちてしまったのだから仕方がない」と開き直るような発言を残していますが、ジョーイにとってこれは究極の裏切り行為でした。
この事件以降、二人はバンドの業務連絡以外で一切口をきかなくなりました。
ステージ上では隣同士で演奏しながら、楽屋では目も合わせない。
まさに「冷戦」状態が解散まで続くことになったのです。
1-3. 名曲KKKに隠された歌詞の意味と噂
ラモーンズのファンなら誰もが知る名曲「The KKK Took My Baby Away」(アルバム『Pleasant Dreams』収録)。
この曲の歌詞には、ジョーイの悲痛な叫びとジョニーへの強烈な皮肉が込められているという説が、まことしやかに囁かれ続けています。
歌詞の内容は「KKK(クー・クラックス・クラン)が俺の彼女を連れ去ってしまった」という奇想天外なものですが、多くのファンや関係者はこれをダブルミーニングだと解釈しました。
KKKは誰を指すのか?有力な説
一方で、これには異説も存在します。
ジョーイの弟であるミッキー・リーや元ドラマーのマーキー・ラモーンらは、この曲はジョーイが精神病院に入院していた時代に出会った黒人女性(ウィルナ)との悲恋を歌ったものだと示唆しています。
彼女の親が人種差別的な理由で交際に反対し、引き裂かれたことを「KKKに連れ去られた」と表現したというのです。
また、ジョニー自身も自伝の中で「この曲はリンダ事件の前に書かれたものだ」と否定し、むしろ「アルバムの中で一番気に入っている曲」だと公言していました。
真実は藪の中ですが、ライブでジョーイがジョニーの隣に立ち、恨めしそうにこの曲を歌う姿は、バンド内の倒錯した緊張感を可視化する儀式として機能していました。
1-4. 強迫性障害への無理解とメンバーの孤立
ジョーイとジョニーの溝を決定的なものにしたもう一つの要因は、ジョーイが抱えていた深刻な強迫性障害(OCD)です。
ジョーイのOCDの症状は非常に重く、日常生活に支障をきたすレベルでした。
例えば、ドアの鍵を何度も何度も確認しないと気が済まない、特定の順序で物に触れないと前に進めない、歩道を行ったり来たりを繰り返すといった行動が頻繁に見られました。
また、入浴することに極度の恐怖や抵抗を感じる時期もあり、これが体臭や水虫などの衛生問題を引き起こしていました。
1970年代から80年代にかけては、メンタルヘルスに対する社会的な理解が現在ほど進んでいませんでした。
特に軍隊的な規律を重んじるジョニーにとって、ジョーイのこうした病的な行動は単なる「遅刻」「怠慢」「だらしなさ」としか映りませんでした。
ジョニーはジョーイに対して「いい加減にしろ」「早くしろ」「ふざけるな」と怒鳴り散らし、時には暴力的な威圧を加えることもあったと言われています。
ジョーイにとって、自分の意志では制御できない脳の誤作動を「性格の問題」として責められることは、深い絶望と孤独感を生んだはずです。(出典:National Institute of Mental Health『Obsessive-Compulsive Disorder』)
1-5. 映画で語られた政治思想の決定的な対立
ドキュメンタリー映画『エンド・オブ・ザ・センチュリー』でも描かれていますが、二人の対立は個人的な感情だけでなく、政治的なイデオロギーの違いによっても深まっていきました。
ジョニーはロックミュージシャンには極めて珍しい熱烈な共和党支持者であり、保守主義者でした。
彼はロナルド・レーガン大統領を崇拝し、「強いアメリカ」や資本主義の成功を信奉していました。
一方のジョーイは典型的なリベラル派であり、人権問題や反戦運動に関心を持つヒューマニストでした。
この対立が爆発したのが、1985年の「ビットブルク事件」です。
レーガン大統領がナチス親衛隊も埋葬されているドイツのビットブルク墓地を訪問した際、ジョーイはこれに抗議して「Bonzo Goes to Bitburg(ボンゾ、ビットブルクへ行く)」という痛烈な批判曲を書きました。
ジョニーはこの曲に激怒しました。
「俺のヒーローである大統領を侮辱するな」というだけでなく、政治的なメッセージでファンを分断することはビジネス上のリスクだと考えたのです。
結果として、ジョニーの圧力によりアルバム収録時にはタイトルが『My Brain Is Hanging Upside Down』に変更されました(ただし、ファンは元のタイトルで記憶しています)。
音楽性だけでなく、世界を見るレンズそのものが正反対だった二人。
それでもバンドを続けた彼らのプロ意識には、ある種の狂気すら感じます。
2. ラモーンズの不仲を象徴する衝撃エピソード
ここからは、そんな険悪な関係のまま22年間走り続けた彼らの、信じられないような不仲エピソードを紹介していきます。
笑っていいのか泣いていいのか分からない、これぞラモーンズという逸話ばかりです。
2-1. 移動車内での沈黙と厳格な座席ルール
ラモーンズは世界的な成功を収めた後も、豪華なツアーバスではなく、機材車も兼ねた狭いバン(フォードのエコノラインなど)で移動を続けていました。
この狭い密室こそが、彼らの不仲を象徴する現場であり、逃げ場のない監獄でした。
長年ツアーマネージャーを務めたモンテ・メルニックの著書や証言によると、バンの中での座席位置は絶対的なルールとして固定されていたそうです。
- 運転席:モンテ・メルニック(マネージャー兼運転手兼ベビーシッター)
- 助手席:ジョニー・ラモーン(司令官席。エアコンの温度調節とカーステレオの選曲権を独占)
- 後部座席:ジョーイ、ディー・ディー、ドラマー(それぞれのテリトリーに引きこもり、沈黙を守る)
驚くべき事実は、何時間、時には何十時間にも及ぶ移動中、メンバー間で一言も会話がなかったということです。
彼らは互いに干渉せず、視線も合わせず、ただひたすら沈黙を守り続けていました。
これは「仲が悪い」というレベルを超え、不用意な発言が喧嘩の引き金になることを避けるための、生存本能に基づいた「休戦協定」だったのです。
2-2. ガソリンスタンドへの置き去り事件の真相
ファンの間で最も有名な都市伝説の一つが、「ジョーイ置き去り事件」です。
これは単なる噂ではなく、実際に起きた出来事として複数の関係者が証言しています。
ある雪の降る日、ツアーの移動中に一行はガソリンスタンドに立ち寄りました。
メンバーはトイレ休憩や軽食の購入のために車を降りましたが、OCDの影響で行動が緩慢だったジョーイは、用事を済ませて車に戻るのが遅れてしまいました。
時間に厳格で、ジョーイの「遅刻」に常々苛立っていたジョニーは、戻ってこないジョーイに腹を立て、運転手のモンテにこう命令しました。
「出発しろ!」。
モンテは躊躇しましたが、ジョニーの剣幕に押され、本当にジョーイを雪の中に置き去りにしてバンを出してしまったのです。
冗談のような話ですが、これは彼らの関係性が限界に達していたことを示す悲しいエピソードです。
後になって戻って拾ったとも、ジョーイが自力で次の会場まで来たとも言われていますが、いずれにせよジョニーの冷徹さと、それを黙認せざるを得なかったバンド内の異常な力学が浮き彫りになっています。
2-3. 殿堂入りスピーチで起きた最後の波紋
2002年、ラモーンズは念願のロックの殿堂入りを果たしました。
パンクロックの始祖として歴史に名を刻んだ瞬間でしたが、この式典はジョーイがリンパ腫で亡くなった約1年後に行われました。
壇上でスピーチを行ったジョニーは、マネージャーや妻リンダへの感謝を淡々と述べた後、スピーチの締めくくりにこう言い放ちました。
「ジョージ・W・ブッシュ大統領とアメリカに神の祝福を(God bless President Bush, and God bless America)」
9.11テロ直後の愛国的な空気があったとはいえ、リベラルなロック界、そして何より徹底したリベラルであり反戦主義者だった亡きジョーイの追悼の場でもある式典で、あえて自分の支持する共和党大統領を称える発言をしたのです。
これには会場も凍りつき、多くのファンが困惑しました。
ジョニーはジョーイへの直接的な追悼の言葉をほとんど口にしませんでした(友人のエディ・ヴェダーにその役を譲った形になりました)。
最後まで自分のスタンスを曲げず、ジョーイに媚びるような「偽善」を拒否したジョニーの姿は、ある意味で彼らしい、残酷なまでの誠実さだったのかもしれません。
2-4. 死の直前まで拒絶された和解の電話
2001年4月、ジョーイ・ラモーンがリンパ腫で死の床についていた時、弟のミッキー・リーや元メンバーのマーキー・ラモーンなど周囲の人々は、ジョニーに連絡を取りました。
「ジョーイの具合が悪い。電話をしてやってほしい」「見舞いに行ってほしい」と懇願したのです。
しかし、ジョニーはこれを頑なに拒否しました。
ジョニーの言い分はこうでした。
「俺たちは友達じゃなかった。もし俺が死にかけているとして、嫌いな奴から電話がかかってきたら迷惑だ。だから俺もしない」。
彼は、死の間際になって急に取り繕うような「お涙頂戴の和解劇」を嫌ったのです。
最後まで「ビジネスパートナー」という距離感を崩しませんでした。
それでも、ジョーイが亡くなった後、ジョニーはインタビューで「一週間ずっと落ち込んでいた」と告白しています。
また、「ジョーイ以外のシンガーとは演奏しない。彼は俺のシンガーだ」と公言し、ラモーンズの再結成の可能性を完全に否定しました。
言葉や態度には出さなくとも、そこには22年間背中を預け合った戦友だけが知る、愛憎を超越した深い絆があったのだと私は信じたいです。
2-5. 結論:ラモーンズの不仲が産んだ奇跡の音楽
ラモーンズの物語は、ジョーイの死だけでは終わりませんでした。
「不仲」という呪縛から解き放たれるかのように、あるいは後を追うかのように、残されたメンバーたちもまた、次々とこの世を去っていきました。
ここでは、ジョーイ以後の彼らの最期について触れておかなければなりません。
ディー・ディー・ラモーンの孤独な退場
2002年6月5日、ジョーイの死からわずか1年後、そしてロックの殿堂入りのわずか2ヶ月後、ベーシストであり主要ソングライターだったディー・ディー・ラモーンが、ロサンゼルスの自宅で亡くなっているのが発見されました。
死因はヘロインのオーバードーズ。享年50歳でした。
殿堂入りのスピーチで「自分自身に感謝したい。ありがとう、ディー・ディー」と語り、会場の笑いを誘った彼でしたが、長年苦しんだ薬物依存との戦いには勝てませんでした。
バンドを脱退し、ラップに挑戦し、世界中を放浪してもなお、彼は「ラモーンズ」という重圧と、自身の繊細な精神との折り合いをつけられなかったのかもしれません。
ジョニー・ラモーン、不屈の男の最期
ディー・ディーの後を追うように、2004年9月15日、ジョニー・ラモーンが前立腺癌により55歳で死去しました。
彼は死の直前、「癌が俺を少し柔らかくした」と語っていたと言われていますが、最後までジョーイに対する後悔の言葉を公にすることはありませんでした。
彼はロサンゼルスのハリウッド・フォーエバー墓地に、自身の銅像を建て、そこで眠っています。
その像は、ギターを低く構えたあの「ジョニー・ラモーン」の姿そのものです。
最後まで強く、揺るがない男として、彼は自分の人生を完結させました。
トミー・ラモーン、最後の生き証人の旅立ち
そして2014年7月11日、オリジナルメンバーで唯一生き残っていたトミー・ラモーンが、胆管癌により65歳で亡くなりました。
彼はバンドのコンセプトを作り上げた「建築家」であり、初期の不仲なメンバー間を取り持とうとした唯一の理知的な存在でした。
こうして、オリジナル・ラモーンズの4人は全員、鬼籍に入りました。
彼らの歴史を振り返ると、「ラモーンズ 不仲」という事実は、バンドにとってマイナス要素ではなく、むしろあの驚異的なスピードと緊張感を生み出すための必要不可欠な要素だったように思えてきます。
仲良しこよしではなく、互いに憎しみ合い、軽蔑し合いながらも、「ラモーンズ」という共通の目的のためにステージに立ち続けた男たち。
その歪で純粋なエネルギーこそが、今もなお世界中のパンクスを魅了し続けるラモーンズの魔法なのです。
彼らの不仲は、悲劇ではなく、奇跡のスパイスだったと言えるでしょう。

💿 アナログ盤で味わう“生のラモーンズ”



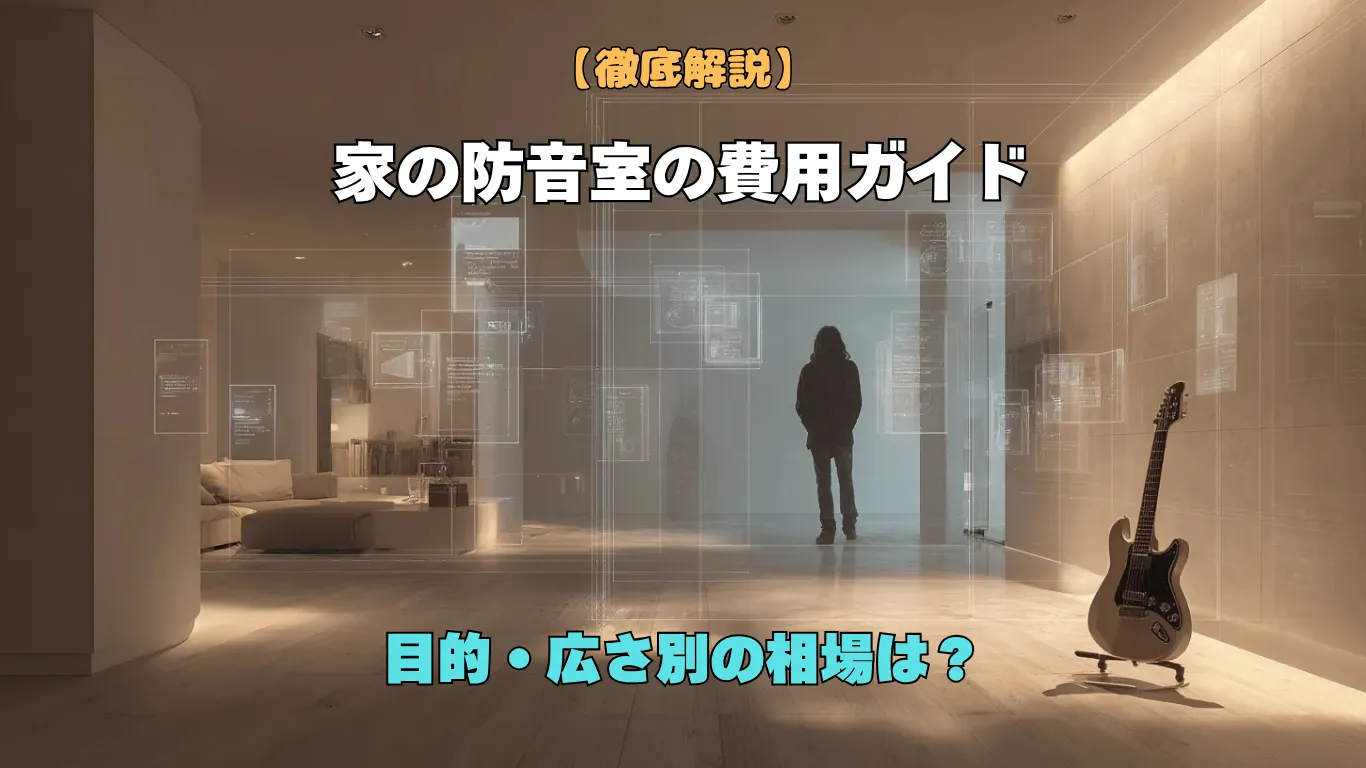
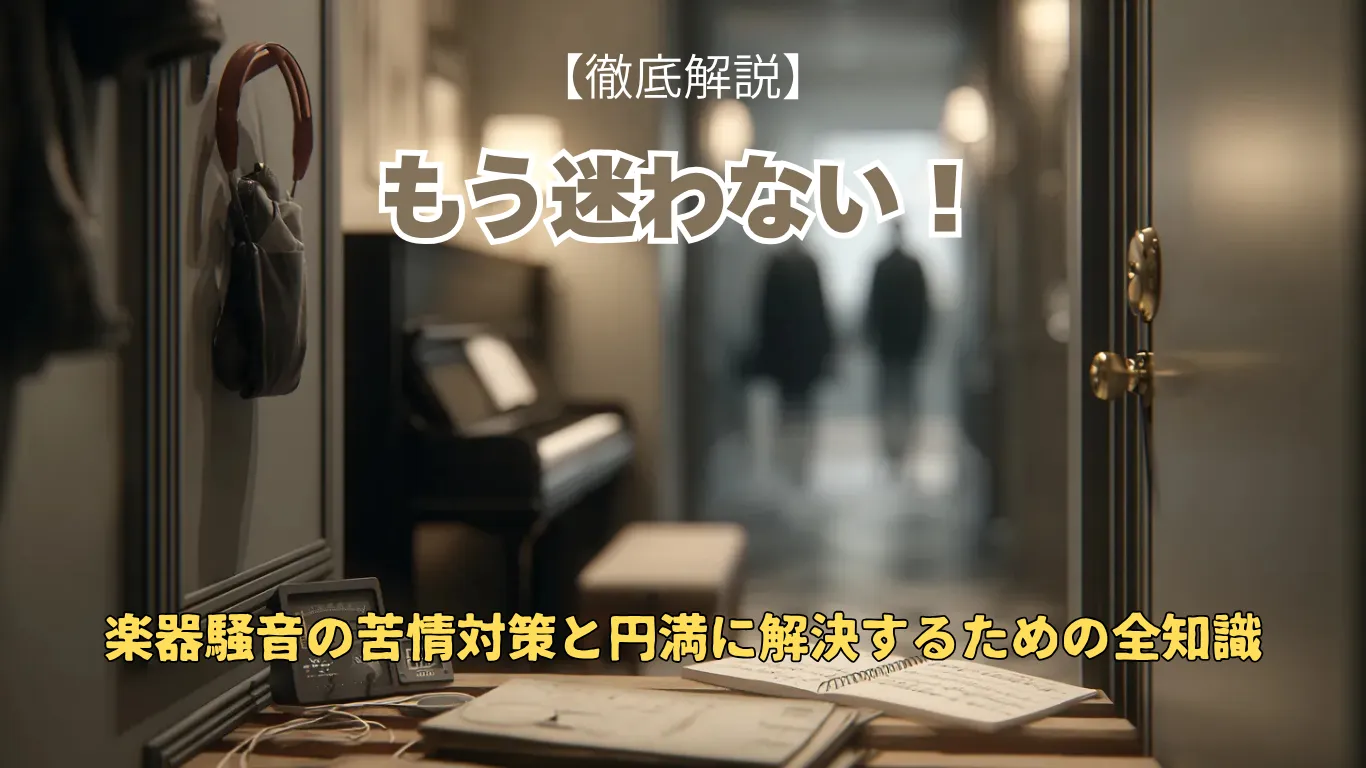
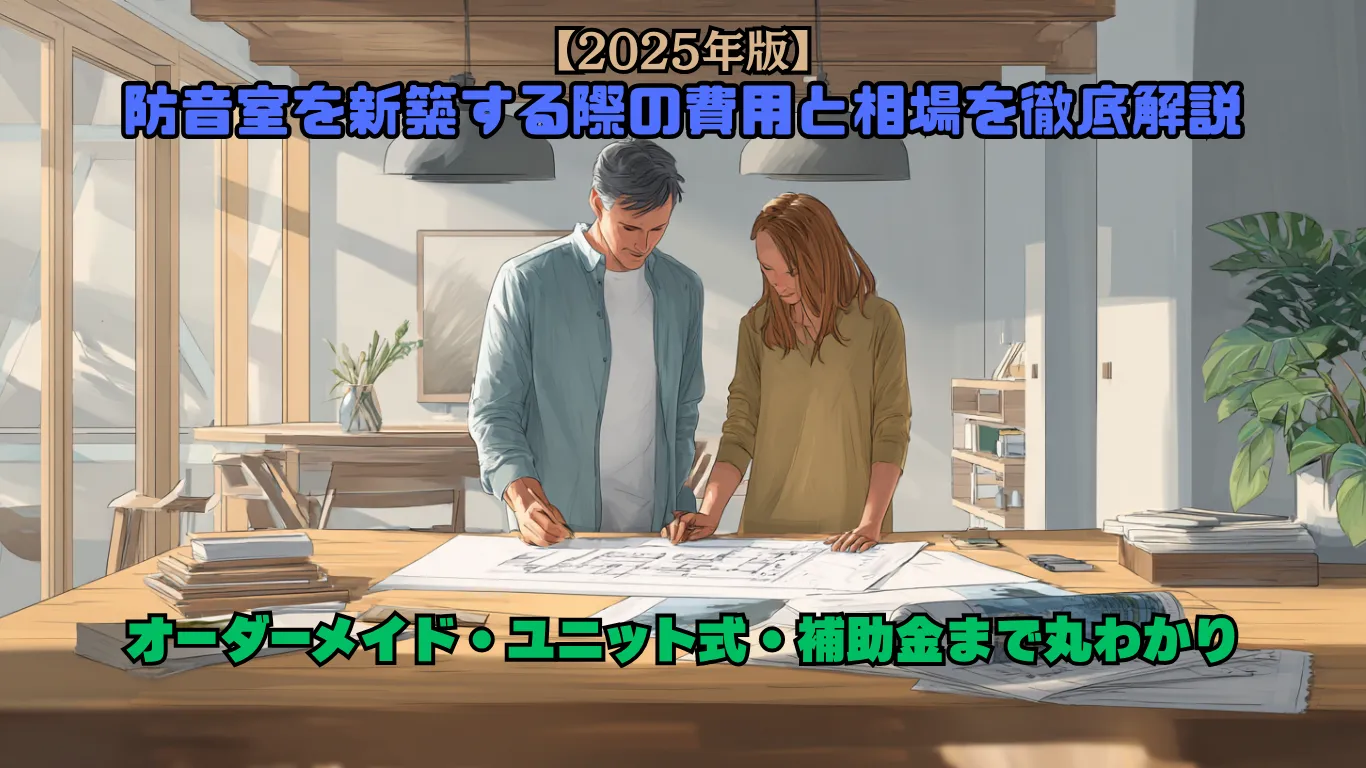







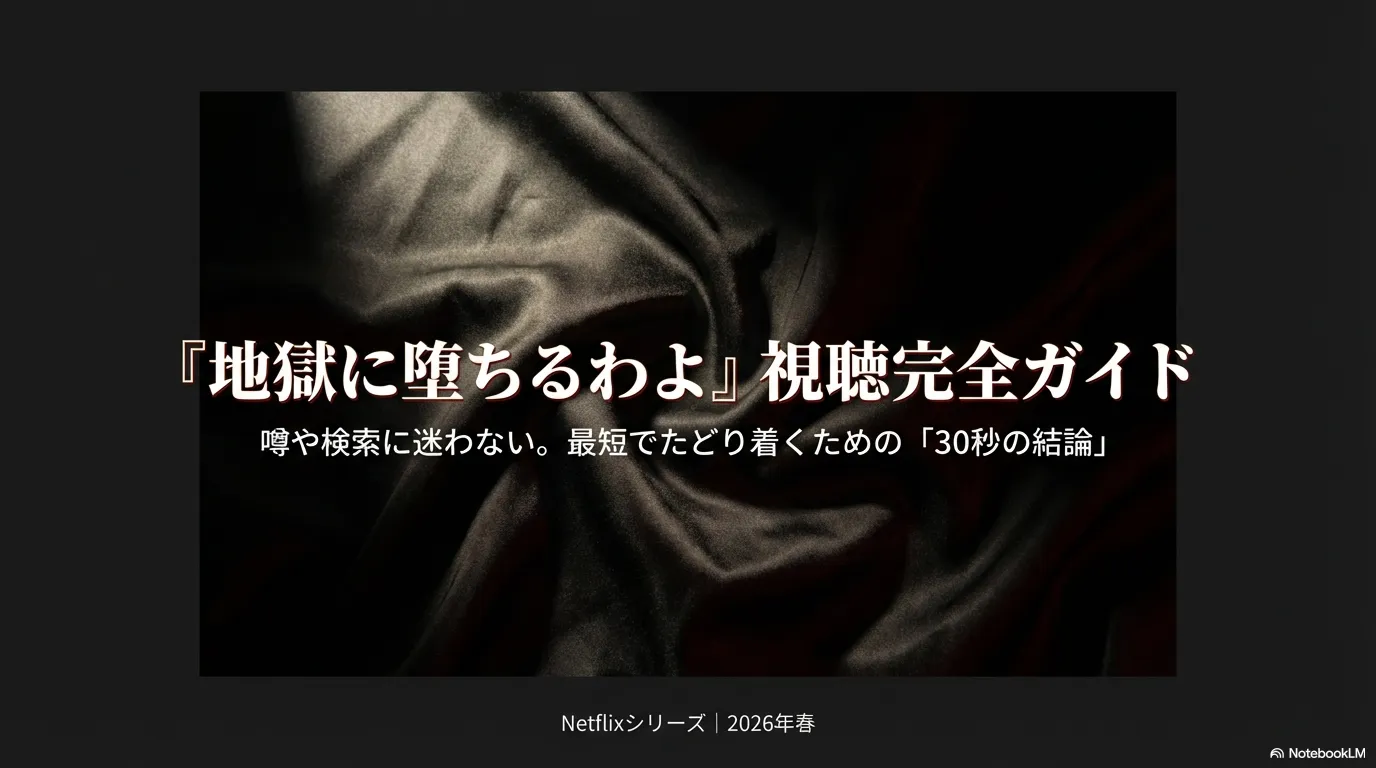







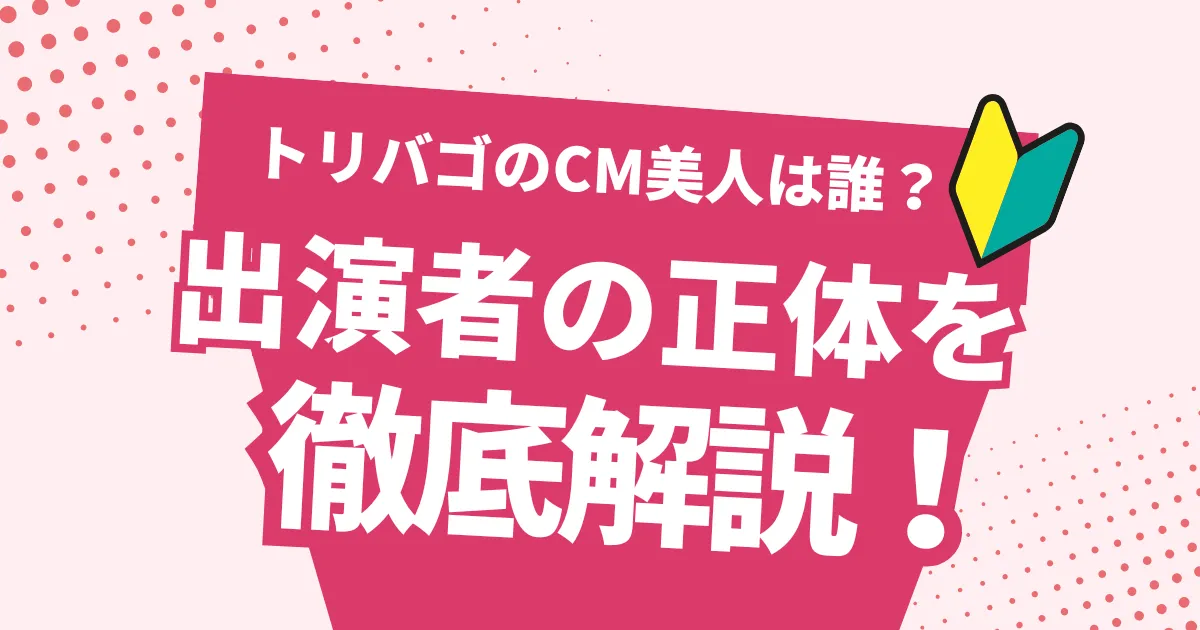




コメント