全国でクマの出没と人身被害が相次ぐ中、その背景には人々の無理解がある可能性が指摘されています。
一方で、クマの生態を正しく学び、安全に共存しようとする動きも広まっています。
「なぜ凶暴化?」専門家が指摘する“餌付け”の危険性
北海道羅臼岳で登山者がヒグマに襲われ死亡した事件で、加害グマは、普段は「岩尾別の母さん」とあだ名がつけられるほどおとなしいメスグマだったことが判明しました。
専門家は、このようなクマが凶暴化する理由として、人間の食べ物の味を覚え、人間への恐怖心が薄れてしまう「餌付け」の危険性を指摘。
知床では、車内からヒグマにスナック菓子を与える観光客が目撃されるなど、無責任な行動がクマを人里へ引き寄せ、最終的に悲劇的な事故につながっている可能性があるとしています。
また、知床国立公園では、近年外国人観光客が急増しており、マナーに関する問題が浮上。
一部の観光客による不法投棄や餌やり行為がクマの行動変化を促し、人間とクマの共存に大きな課題を突きつけています。
“死んだふり”は危険!クマとの正しい向き合い方
クマの脅威が身近になる中、安全に共存するための学習会も各地で開かれています。
島根県では、冬眠を前にクマが栄養を蓄える時期であることから、吉田小学校でクマの生態や対処法を学ぶ学習会が開催されました。
講師は、クマと遭遇した際には「静かに後ずさりするか、うつ伏せになって首やお腹を守る姿勢をとる」などの対処法を説明。
一方で、専門家の中には、「クマは感情で人を追うのではなく、食べ物を得られる場所だと記憶している」とし、もし襲われた場合は「死んだふり」は効果が薄いと警告する声もあります。
クマによる被害を防ぐには、クマ鈴やラジオなどで事前に人間の存在を知らせる、家の近くに餌となる柿や栗などを放置しないといった、地道な対策が最も重要です。
また、専門家からは、クマが人を襲う理由として「驚き」「空腹」「子グマを守るための防衛行動」の3つが挙げられており、これらの行動原理を理解した上で、冷静に対応することが求められています。





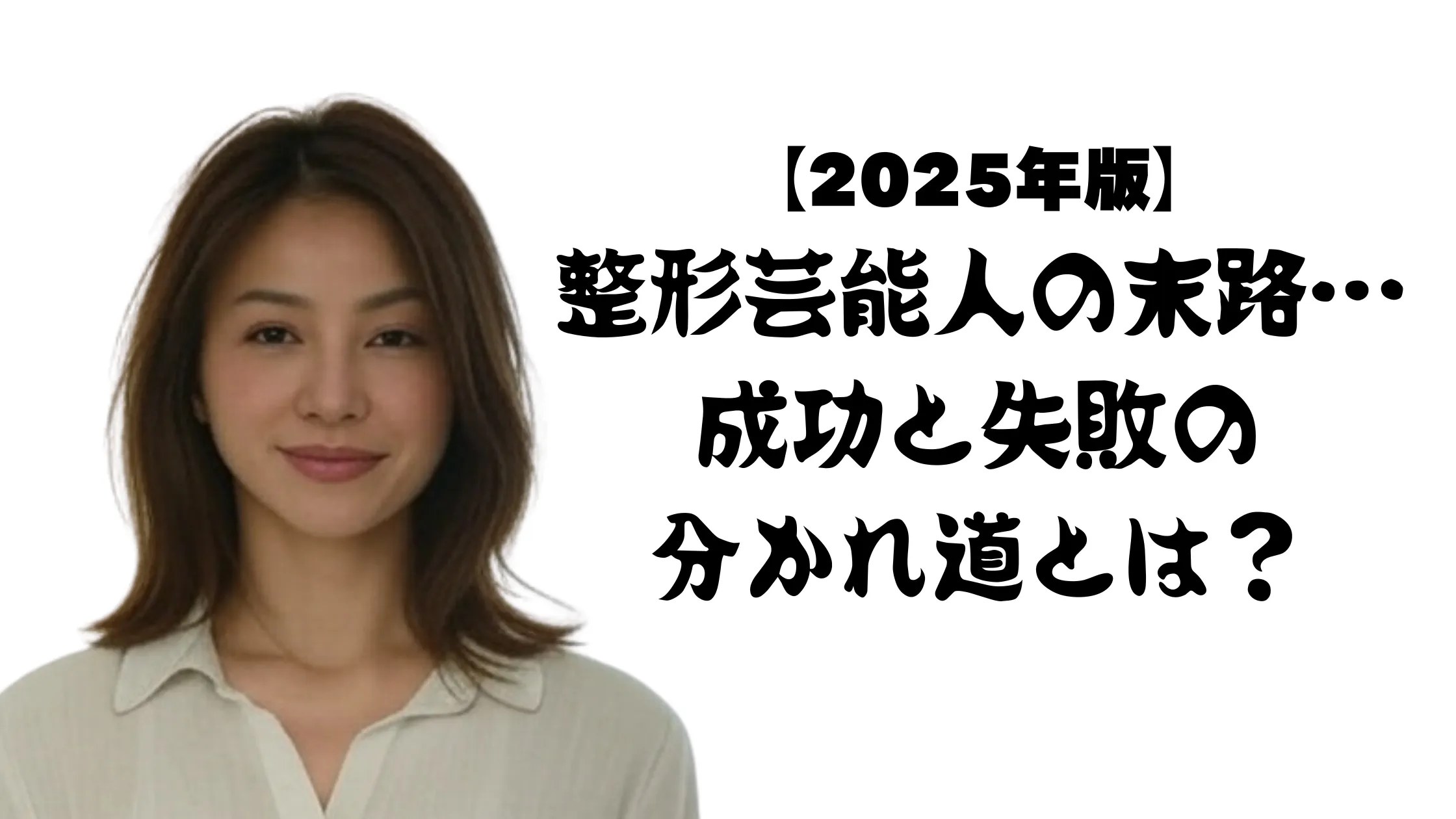





コメント