羅臼岳での死亡事故から本州での人身被害まで、クマによる被害が全国で急増しています。
こうした現状を受け、専門家は従来の対策に疑問を投げかけ、新たな提言を打ち出しています。
「クマよけスプレーは無力」専門家が語る本当の対処法
夏山シーズンに多くの観光客が訪れる北海道羅臼岳で、20代の登山者がヒグマに襲われ死亡しました。
その後、襲撃した個体が駆除されましたが、この悲劇はクマとの共存のあり方を改めて問い直すきっかけとなっています。
北海道野生動物研究所の門崎允昭氏は、行政が推奨する「クマよけスプレー」や「地面に伏せる」といった対処法を「本気で襲ってくるクマには全く無意味」と断言。
クマに襲われて生還した多くの人は、刃物などで反撃していたと指摘します。
門崎氏が推奨する必須アイテムは、ホイッスルとナタの2つ。
ホイッスルで自分の存在を知らせ、万が一の際にはナタで反撃し、出血させることで攻撃を止めさせるという、厳しい現実に基づいた対策を提唱しています。
「駆除」を巡る深刻な溝とハンターの苦悩
クマによる被害が続く中、世論は「駆除」へと傾いています。
ある調査では、8割以上の人々がクマ対策として「ハンターによる駆除」を支持しています。
しかし、現場ではその溝が浮き彫りになっています。9月1日から、市町村の判断で市街地でのクマ駆除が可能になりますが、北海道猟友会は「ハンターが責任を負うリスクが拭えない」として、安全に疑念がある場合はハンター自身が発砲を中止できるという見解をまとめました。
命がけで任務にあたるハンターと、リスクを負わせることになる行政との間で、責任の所在を巡る問題が深刻化しています。
止まらない「クマの街化」、地域経済にも打撃
クマはもはや山の中だけの存在ではありません。
函館市では体長1.5メートルほどのクマが道路を横断する姿が目撃され、近くのトウモロコシ畑の食害との関連が調べられています。
また、青森県弘前市では出没件数が前年比2倍となり、商業施設近くでも目撃情報が相次いでいます。
この事態を受け、弘前市は一部の公共施設を一時休業にすることを決定。
地域住民だけでなく、観光客にも影響が出ており、クマの問題が地域経済にまで打撃を与え始めています。
専門家は、クマが増加した背景に「銃声への慣れ」や「人里との境界線の不明確化」を挙げ、行政に対し、有刺鉄線の柵を設置するなど根本的な対策を急ぐよう提言しています。





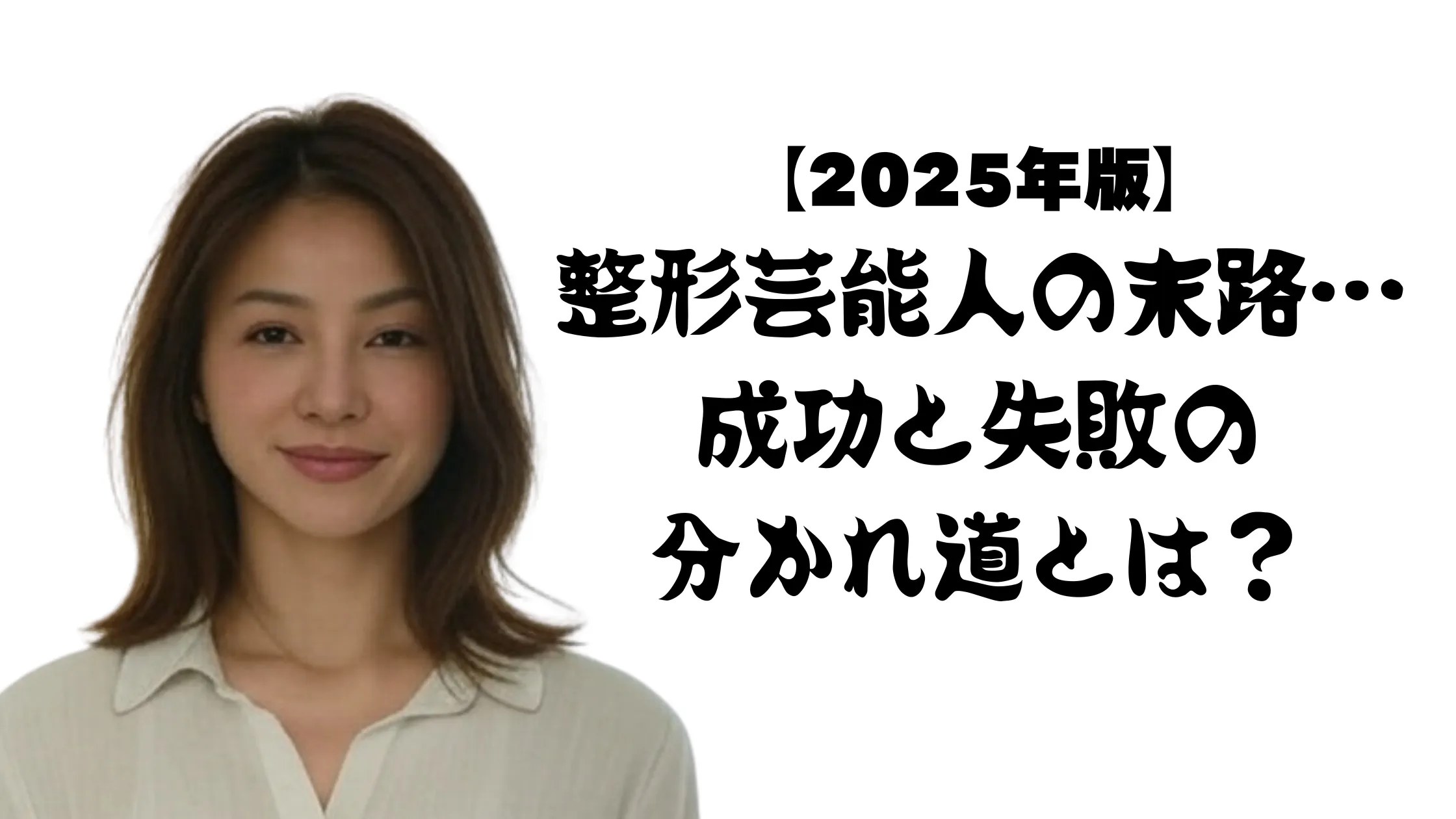





コメント