「匂い」に誘われ人里へ—専門家が語るクマの生態と対策
北海道をはじめ全国でクマの市街地への出没が相次いでいます。
酪農学園大学の佐藤喜和教授は、この時期の出没増加の理由を「山の中に食べ物が少ない時期だから」と解説します。
特に8月は、森の草が硬くなり、木の実が熟すにはまだ早いため、嗅覚が鋭いクマは畑の農作物や生ゴミの「匂い」に誘われて人里に降りてきてしまうといいます。
道南で出没が多発する理由については、もともとの生息密度が高いことに加え、山と海岸線が近く、人間の生活圏とクマの生息圏が隣接している地形的要因を挙げています。
佐藤教授は「クマを生活圏に入れない」ためのゾーニング計画が重要だと強調。
草刈りや適切に設置された電気柵、そして収集日の朝にゴミを出すといった基本的な対策が、クマの誘引を防ぐ上で最も重要だと訴えています。
「なぜ殺した」抗議電話、そしてデマの拡散—現実と乖離する議論
羅臼岳での死亡事故後、現場でクマが駆除されたことに対し、町役場には100件を超える抗議電話が殺到。
「なぜクマを殺したのか」「クマのいる場所に行くのが間違い」といった意見が寄せられています。
しかし、クマの駆除を担うハンターは、日当8,000円、労災なしという過酷な状況で活動しています。
中には猟銃の所持許可を取り消されるリスクに直面する人もおり、命がけの活動に対する社会の理解が追いついていない現状が浮き彫りになりました。
また、SNSでは「知床のクマは皆耳にタグがあるから、どのクマが駆除されたか分かる」というデマが拡散。
知床財団は「物理的に不可能」と否定する事態になっています。
クマの脅威という現実が迫る一方で、感情的な議論や誤った情報が人々の間に混乱を生んでいます。
人里への出没は止まらない—福島でも親子グマが路上に
クマの出没は全国で続いています。
20日夜には、福島県喜多方市の主要地方道で、体長1.5メートルの親グマと子グマ2頭の親子連れが目撃されました。
幸い人的被害はありませんでしたが、夜間の路上という人通りがある場所での出没に、警察が警戒を強めています。
ベテランハンターは、クマと遭遇した際には「おーい」などと声を出すと、クマを興奮させてしまうため逆効果だと指摘。
「いなくなれー」など人間の言葉で追い払うことが重要だと語っています。
これらの事例は、クマ対策が単なる「自然保護」ではなく、専門家、行政、ハンター、住民が連携し、科学的根拠に基づいた現実的な対応を講じるべき社会問題であることを改めて示しています。





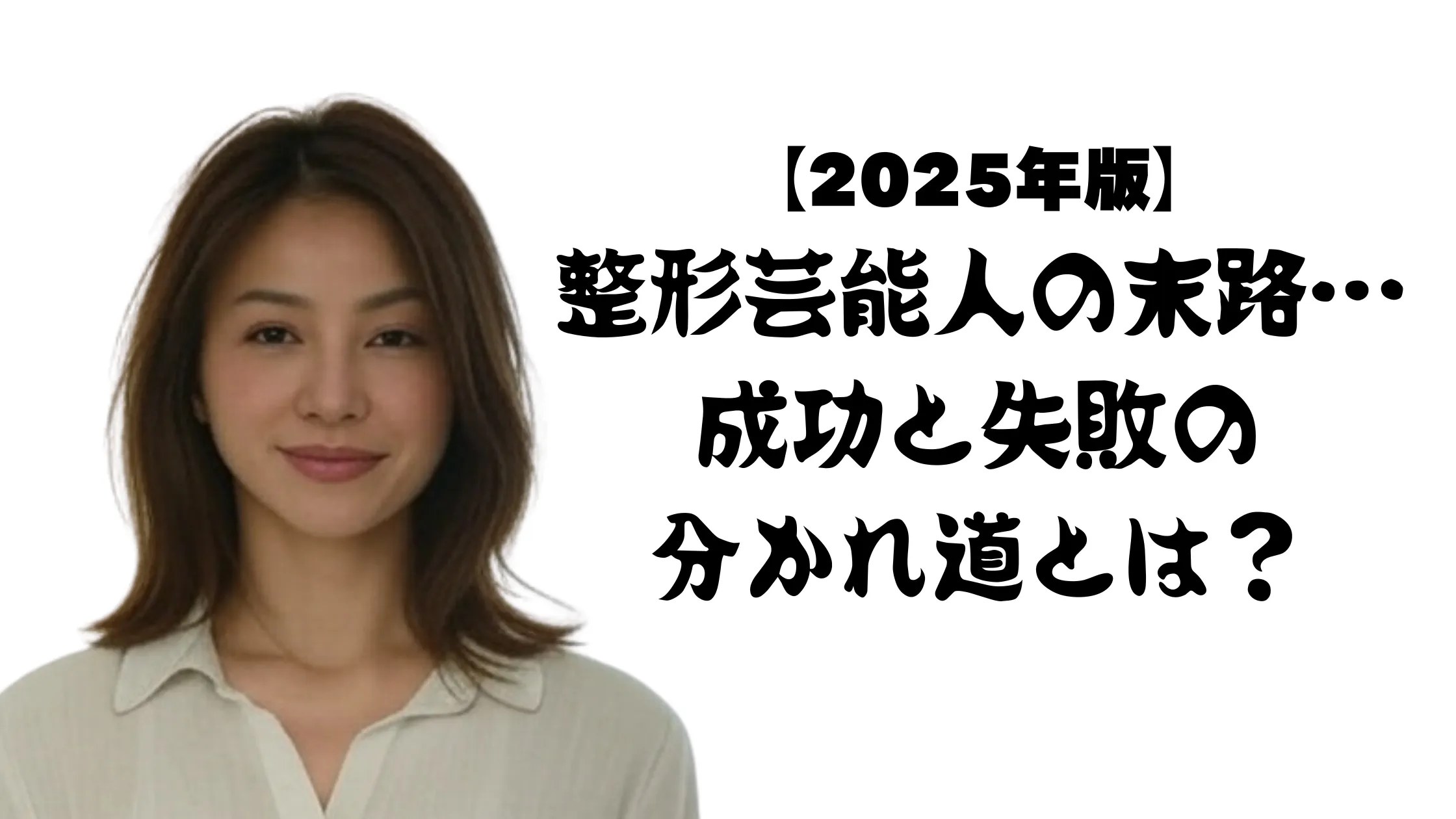





コメント